 過去放送した番組
過去放送した番組
NONFIX 2006年オンエア作品
生きる力 授けます~マラソン幼稚園の教え~
2006年12月21日 (木) 02:28~03:28

ガンコ園長と“スーパー園児”たちの1年間
様々な問題がつきない教育現場…
そんな中、周囲の逆風を受けながら、独特の教育哲学を実践する園長と伸び伸びとフルマラソンを完走する園児たちに、1年間密着取材。
「学力偏重」「知的教育」に異議を唱える幼稚園の姿を通して、我々が失いかけている「大切なもの」を見つめ直す。
来日少年はなぜ非行に走ったのか?~密着・久里浜少年院「国際科」~
2006年12月14日 (木) 02:28~03:23

湘南の海を臨む神奈川県横須賀市の久里浜少年院。
ここでは93年に初めて国際科を設け、外国籍の少年たちを受け入れている。
現在はブラジル人17名、ボリビア、フィリピン、中国各1名の計20名が在籍する。
親との住まいは愛知、群馬、静岡などの工業地帯、いわゆる「ブラジル人町」から来た日系3、4世が多数を占める。
なぜ彼らは犯罪や非行に走ったのか?
その背景には、移民にとって厳しい日本社会の構図が見えてくる。
あぁ!哀愁の喫煙者!(再)
2006年12月7日 (木) 02:28~03:23
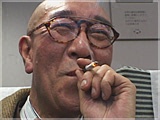
日本中を急激な勢いで席巻する禁煙化の流れ。タバコ価格も急騰。追いやられ、追いやられて、タバコを吸う場所も無い。
そう、タバコが体に悪いことは百も承知。副流煙が他人の健康までも奪っていることも知っている。今の時代、タバコは完全な悪者だ。
しかし、5年前はどうだっただろうか? 10年前は? そして20年前は…
大人が作る“子供のための”遊び場(再)
2006年11月30日 (木) 02:28~03:28

最近、外で泥んこになって遊んでいる子どもの姿を見かけなくなったと思いませんか?
連れ去り事件の多発や不審者の続出など、子どもを取り巻く環境は「危険」が多く、「安心」して「安全」に遊べる場所が減ってきている。
では、今どきの子ども達は、一体どこで遊んでいるのか?
人気の遊び場や秘密基地など、現代の子どもの遊び場最新事情に迫ります。
何を求める風の中ゆく~平成のお遍路さん~(再)
2006年11月23日 (木) 02:28~03:23

四国遍路が静かなブームを呼んでいる。この秋には、遍路に歩く女子高生をモチーフにした映画「ロード88」が封切られ、漫画誌では二度に渡る遍路行を遂げた俳人、種田山頭火を描いた「まっすぐな道でさみしい」が人気を集めている。現地ではバスツアーで札所を回る中高年、バックパックで歩く若者たちの姿が目立ち、遍路の年間総数は15万人を超えるという。
従来、巡礼の道として、宗教的な空間だった遍路は、今や誰もが手軽に目指すことが可能になった。“癒し”を求めて、余暇の過ごし方を探る現代人に、遍路体験は何を与えてくれるのか。当代遍路事情を取材する。
男一代菩薩道~インド仏教の頂点に立つ男~(再)
2006年11月16日 (木) 02:28~03:23
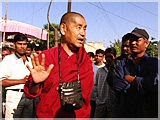
10億人以上の民を抱える悠久の国インド。その8割はヒンズー教徒であるが、そこはまた仏教発祥の地でもある。 佐々井秀嶺(69歳)インド名アーリア・ナーガルジュンは、インドの仏教徒が最も尊敬する僧侶である。 昨年、インド政府が代表を任命する少数委員会の仏教代表に選ばれ、インド仏教の世界で名実ともにその象徴として活躍している。 番組では一ヶ月間インドロケを敢行。彼が導師を務める100万人のインド仏教徒による「大改宗式典」を軸に、佐々井秀嶺とインド仏教の現状に迫る。
日本で“難民”になる方法(再)
2006年11月9日 (木) 02:28~03:23

1980年、日本は難民条約に加盟。迫害などを受けて自国で暮らせない『難民』を受け入れなければならない。しかし、2003年の日本での受け入れは、申請者300人中、わずか10人。命からがら逃れてきた人でも、受け入れを拒否されれば、不法入国者として国外退去となってしまう。では、どうしたら平和な日本で『難民』として滞在することができるのか。
ジョンスの青春~海外初“韓国徴兵制”密着取材
2006年11月2日 (木) 02:43~03:43

徴兵制をとる韓国では、成年男子は必ず兵役に就かなければならない。
18歳になると徴兵検査を受け、等級に応じて兵役が課せられる。陸軍は26ヶ月、空軍は30ヶ月。原則的に免除はなく、たとえ軍務に適さないと認定されても公益勤務、義務警察、戦闘警察などの代替勤務に服さなくてはならない。
今も戦時にある韓国での兵役は過酷で、毎年100名余が自殺し、200名強が訓練事故で亡くなっている。
海外メディア初のTVカメラ取材により、韓国の若者たちにとって、また韓国社会にとって、徴兵制度はどういう意味を持つのか、徴兵制度に対する韓国の若者たちの価値観の変遷も浮き彫りにする。
プロゲーマーをめざす若者たち(再)
2006年10月26日 (木) 02:58~03:58

いま、アメリカや欧州など世界中で流行するコンピューターゲームの大会。それはインターネットやLANを介し、人間同士が対戦するゲームである。コンピューターのプログラムを相手にするのでなく、生身の人間同士がぶつかりあうゲーム。それはいつしかeスポーツと呼ばれるようになった。対戦ゲームを未来のスポーツとして市民権を得たいというゲーマーたちの想いからであろうか。スポーツ競技さながらに、ゲーマーたちはチームを組み、大会の実況中継でゲームを熱く語り始めた。そして、世界各地の大会で賞金を稼ぎ、スポンサーを獲得するプロのゲーマーまで誕生した。
ぼくらに遊び場はありますか? 日本初!難病児のキャンプ場を作れ
2006年10月19日 (木) 02:58~03:58

病気や障害のある子供たちは通常の遊びを楽しむことが難しいと言われています。
なぜなら、病気でない子供が転んで出血しても大事に至るケースはほとんどありませんが、病気の子供の場合、些細なことが命に関わる危険があるからです。
「施設的にバリアフリー化するだけでなく、どんな時でも即座に対応できる医療スタッフと医療設備の整ったサポート体制があれば、子供たちは安心して自然とふれあうことができる…」
アメリカには毎年難病の子供およそ1000人が無料で参加できるキャンプがあります。
しかし日本にはそうした施設がないのが現状です。そしてその現状すら知らない人も多く存在します。
この番組では「病気と闘う子供たちのために国内で初めて常設のキャンプ場(そらぷちキッズキャンプ)を作ろうとしているある団体」の活動を通し、『障害や病気と供に生きる子供や家族の願い』そして、それを取り巻く『日本の現状』を描き出します。
「介護シリーズ」理想の介護を目指して~認知症 特別養護老人ホームの1年
2006年9月14日 (木) 02:28~03:28

取材対象者は、天野里美ケアマネージャー(38歳)。50人(認知症患者だけではない)のケアプランを担当。かつて瀬戸内の小さな島をひとりで守り続けたバイタリティーあふれるナース。「認知症高齢者グループホーム管理者」の資格を取得し、このホームの介護のリーダー的存在となっている。
天野さんの現在の悩みは、施設に入った入所者の容態が、在宅時以上に悪化してしまうケースがあること。天野さんは言う。「佐柳島には、“認知症”“寝たきり”という言葉さえなく、みな元気だった。しかし、設備の整った介護施設の入所者の認知症がさらに悪化するのはなぜなのか? 介護の仕方に問題があるのか? 悩んでいます。」
「介護シリーズ」誰にもせかされずに私は死にたい~在宅ホスピスという選択~
2006年9月7日 (木) 02:28~03:28

1960年代まで、日本人は自宅で死を迎えることが一般的でした。
しかし1977年を境に病院で亡くなる人が在宅死の数を抜き、今や自宅で死ぬ人は、1割程度です。自宅から病院へと死に場所が移行するなかで、延命治療を中心とした医療への反省がなされ、在宅死の意義が浮上してきました。
川越厚さん(58歳)は16年前から「在宅ホスピスケア」の先駆者として挑戦を続けている医師です。「在宅ホスピスケア」とは末期癌などで間もなく死を迎える人の、最期まで自宅で、自分らしく生活し続けるということを支援する医療です。治療の主眼は、末期癌特有の痛みを緩和すること。痛みをコントロールすることで、その人の望む過ごし方を可能にすることができると考えています。
一般病院で行なわれている医療が「治す医療」であるなら、在宅ホスピスケアは「癒す医療」であるという考えのもと、川越先生は今まで500人以上の人たちの最期の時を看取ってきました。
「介護シリーズ」消え行く記憶~若年認知症を生きる~
2006年8月31日 (木) 02:28~03:28

65歳以下で発病するいわゆる「若年認知症」の患者は全国で10万人といわれる。その半数以上は「アルツハイマー型」といわれるものだ。現在の医学では、原因も、根本的な治療法も見つかっていない。認知症に対する大きな誤解のひとつに「介護する家族は大変だが、患者本人は呆(ほう)けているから何もわかっていない」というものがあるが、実際の患者さんは、非常な不安感、焦り、屈辱感などに押しつぶされそうになって生きている。
思い出せないことがどんどん増え、今までできていたことができなくなり、症状は進行してゆく一方なのに特効薬もない。その絶望と、患者は、そして支える家族は、どう折り合って生きているのだろうか。私たちは、患者本人と介護する家族に密着し、「記憶をなくす」ことが人間にとって何なのかを見つめたい。
巨大魚に魅せられた男たち
2006年8月24日 (木) 02:28~03:28

現在、2000万人と言われる釣人口。週末にもなると、日本全国の漁港は釣り人達で活気に満ち溢れている。
映画「釣りバカ日誌」は毎年公開され、釣りは海に囲まれている日本人にとって、趣味、娯楽の王道として認識されている。
そんな釣りの世界にもカリスマと呼ばれる人間がいる。
中村 透(51才)
彼は釣り業界、特に大物釣り師のカリスマと呼ばれている。
日本サブカル秘史~ビートルズと女スパイ~
2006年8月17日 (木) 02:38~03:38
今でも広い世代に支持されているビートルズ。
彼らが40年前に来日した。その時のハッピ姿の映像は10代の若者でも知っている。しかし、その来日の裏舞台ではどのような事があったかはあまり知られていない。
日中宇宙バトル“神舟”に隠された戦略
2006年8月3日 (木) 02:28~03:28

2005年10月17日、小泉首相が靖国神社に参拝して平和を祈念した朝、隣の中国は熱狂に包まれていた。有人宇宙飛行を実現させた「神舟6号」が、飛行士の聶海勝(41)と費俊竜(40)を乗せ、無事帰還したのだった。
一昨年、「神舟5号」が初めて有人宇宙飛行に成功した時、日本の科学者・技術者の中には「ロシアのソユーズを模倣したもので、大した成果ではない」と、過小評価する姿勢が見られた。しかし…。
「司法シリーズ」裁判員制度
2006年7月20日 (木) 02:28~03:28
刑事裁判の審理に一般市民が参加する裁判員制度が、2009年5月までに導入される。
原則としてくじびきで選ばれた6人の裁判員と職業裁判官3人で構成され、有罪・無罪や有罪の場合はどの程度の刑にすべきか(量刑)を多数決で決める。
対象となるのは殺人や放火、強盗傷害などの重大事件で年間約3,000件の見通し。
「司法シリーズ」死刑廃止への旅~被害者家族と加害者家族のテキサス17日間~
2006年7月13日 (木) 02:33~03:33

世界は今、死刑廃止の潮流にある。先進国中、死刑制度を存置している国は日本とアメリカだけ。そのアメリカも50州中23州が法律上、又は事実上、死刑を廃止している。一方で、日本人の世論調査では、8割が死刑に賛成している。
その理由として、“法の甘さ”や“確立されていない被害者支援”などが挙げられるとみる専門家も多い。
「司法シリーズ」ロースクールの挑戦~激動の司法改革の中で~
2006年7月6日 (木) 02:28~03:28

僕はドキュメンタリー番組を制作するディレクター。1年前、39歳になる兄が突然、大学院に進学した。それも法科大学院。いわゆるロースクールだ。兄は昼間は出版社で働き、夜は毎日法律家になるための勉強をしている。
兄はなぜ突然ロースクールに通いはじめたのだろう。そしてロースクールって一体どんなところなんだろう。取材がはじまった。その中で見つけたのは激動のさなかにある日本の司法の現状と、普段は酒ばかり飲んでいる(と思っていた)兄の意外な一面だった。
間違いだらけの「ボランティア」-他人を助けるホントの意味-(再)
2006年6月29日 (木) 02:28~03:28

昨今、「ボランティア」という言葉が新聞やニュースに出てこない日はない。
ある統計によれば、日本人の3人に1人はボランティア経験があるという。
NPO法にボランティア休暇、都立高校の奉仕活動必修化など、行政や一般企業、教育現場でもボランティアの導入が進んでいる。
そう、時代はボランティア万歳!
でも、ちょっと待って。
「ボランティア」って、どういう行為なの?
貧困に翻弄された女たち~チェチェン・自爆テロリストの告白(再)
2006年6月22日 (木) 02:28~03:28

94年にロシアからの独立を目指して始まったチェチェン紛争。すでに10年の内戦状態は泥沼化し、自爆テロを行った女性は42人に上る。
「なぜチェチェン女性が自爆テロリストになるのか?」
自爆未遂した女性の極秘インタビューが、知られざる彼女たちの素顔を明らかにする。
告白するのはザレマ・ムジャーホエワ(25歳)、現在はロシア国内の収容所に暮らす、生き残った元自爆テロリストである。
東京ニューシネマパラダイス(再)
2006年6月15日 (木) 02:28~03:28

近年日本映画は斜陽産業の文脈だけで語られて来た。しかしハリウッドへの進出、興行収入の記録まだまだその魅力を失っていない。番組では映画を支え、愛して来た人の物語を広い集めてみた。
ノーエクスキューズ~車椅子バスケ・俺たちに言い訳なし!~(再)
2006年6月8日 (木) 02:28~03:28

障害者スポーツ界の格闘技、それが車椅子バスケットボール。
車椅子を操り、パスをし、シュートをする。転倒やケガは当たり前、その迫力と魅力は、「障害者・健常者」という枠を越え、近年、ファン層を拡大し続けている。
この番組では、及川さんが所属するチーム「ノーエクスキューズ」に密着し、障害者の現実と、生きることに邁進する彼らに迫った。
あぁ!哀愁の喫煙者!(再)
2006年6月1日 (木) 02:28~03:28
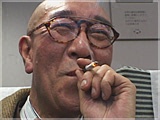
日本中を急激な勢いで席巻する禁煙化の流れ。タバコ価格も急騰。追いやられ、追いやられて、タバコを吸う場所も無い。
そう、タバコが体に悪いことは百も承知。副流煙が他人の健康までも奪っていることも知っている。今の時代、タバコは完全な悪者だ。
しかし、5年前はどうだっただろうか? 10年前は? そして20年前は…
子供たちを救え!小学生がタバコを吸う時代(再)
2006年5月25日 (木) 02:28~03:28
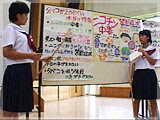
子供たちのタバコ観は、昔と比べてどう変わってきているのか?
喫煙の低年齢化に歯止めをかけることが出来るのか?
なぜ、子供たちはタバコに手をだしていくのか。
その現状を様々な視点から検証していく。最新子供タバコ事情を追う!
ドクターストップ~K-1・PRIDEを支える命の番人~(再)
2006年5月11日 (木) 02:28~03:28

K-1、PRIDEを始めとする昨今の格闘技ブーム。
その人気の大きな要因の一つが『ガチンコ勝負』。
つまり、手抜きや八百長無しの本気勝負。選手と選手がマジに激突するその迫力に会場に詰めかけた観客は惜しむことのない拍手を送る。
しかし、そのボルテージが上がり、本気になればなるほど増えるのが“選手のケガ”。
リング上でのケガは大きな事故につながるケースがあり、時には死につながるケースもある。
そんなことの起こらないように、冷静な視線で試合を見つめる男達がいる。
リングドクター、格闘医師軍団である。
プロゲーマーをめざす若者たち
2006年5月4日 (木) 02:28~03:28

いま、アメリカや欧州など世界中で流行するコンピューターゲームの大会。それはインターネットやLANを介し、人間同士が対戦するゲームである。コンピューターのプログラムを相手にするのでなく、生身の人間同士がぶつかりあうゲーム。それはいつしかeスポーツと呼ばれるようになった。対戦ゲームを未来のスポーツとして市民権を得たいというゲーマーたちの想いからであろうか。スポーツ競技さながらに、ゲーマーたちはチームを組み、大会の実況中継でゲームを熱く語り始めた。そして、世界各地の大会で賞金を稼ぎ、スポンサーを獲得するプロのゲーマーまで誕生した。
大人が作る“子どものための”遊び場(再)
2006年4月27日 (木) 02:28~03:28

最近、外で泥んこになって遊んでいる子どもの姿を見かけなくなったと思いませんか?
連れ去り事件の多発や不審者の続出など、子どもを取り巻く環境は「危険」が多く、「安心」して「安全」に遊べる場所が減ってきている。
では、今どきの子ども達は、一体どこで遊んでいるのか?
人気の遊び場や秘密基地など、現代の子どもの遊び場最新事情に迫ります。
家族たちの一年~尼崎列車事故あれから1年~
2006年4月20日 (木) 02:28~03:28
昨年4月25日、JR福知山線の脱線事故で、106人の乗客の尊い命が奪われ、また助かった方々の多くは心や体に深い傷を負いました。
あれから1年…
亡くなった方々のご遺族は、いまこの時期、どんな思いを抱え、どんな日々をすごしていらっしゃるのか。そして、未来に向けてあの悲しい出来事をどう自分の中で整理していこうとされているのか。
私たちは、いくつかの家族からお話をうかがい、そして日々の生活を取材させていただきました。
男一代菩薩道~インド仏教の頂点に立つ男~(再)
2006年4月6日 (木) 02:35~03:30
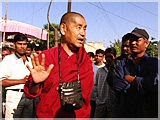
10億人以上の民を抱える悠久の国インド。その8割はヒンズー教徒であるが、そこはまた仏教発祥の地でもある。
佐々井秀嶺(69歳)インド名アーリア・ナーガルジュンは、インドの仏教徒が最も尊敬する僧侶である。
昨年、インド政府が代表を任命する少数委員会の仏教代表に選ばれ、インド仏教の世界で名実ともにその象徴として活躍している。
番組では一ヶ月間インドロケを敢行。彼が導師を務める100万人のインド仏教徒による「大改宗式典」を軸に、佐々井秀嶺とインド仏教の現状に迫る。
路上の未来~「ビッグイシュー」とホームレスライフ(再)
2006年4月4日 (火) 02:35~03:30

東京・新宿。絶えることなく人が行き交うビジネス街。その流れを邪魔せぬよう、けれども存在をアピールするかのような力強い声が聞こえる。
「ビッグ・イシューいかがですか!」
2003年9月に大阪で発刊された雑誌「ビッグイシュー」の販売員である。その販売員には共通していることがある。彼らは皆ホームレスだということ。
犯罪とガラスの進化論
2006年4月1日 (土) 02:20~03:30
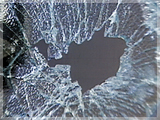
年々巧妙化、凶悪化する犯罪手口。一時期、ピッキングやサムターン回しなど鍵を狙った手口が横行していたが、最近では、窓ガラスを破って侵入する空き巣が急増、各メーカーではこぞって強力な防犯ガラスを製造しつつある。
実は、犯罪の変化が、日本のガラス技術の進化に少なからぬ影響を与えてきた側面もあった…。
この番組では、人類史にガラスが誕生してから現在に至るまでの過程と、犯罪の手口・質の変容ぶりを照らし合わせ、いかに互いに影響を与えてきたかを検証するとともに、治安悪化の一途をたどる市民生活への警鐘を鳴らす。
また、そこからは、改めて人類の生活にとっての〝ガラスの意味〟も浮き彫りになっていく。
開戦60年企画・ザ・ウィンズ・オブ・ゴッド~フィリピン人が愛した神風(再)
2006年3月15日 (水) 02:33~03:28

太平洋戦争から60年、日本では「戦争」そのものが風化しつつある今日、未だにその記憶を引き継ぎ、大切にしている人々が異国の地に存在する。場所はフィリピン・マバラカット市。
昭和19年10月25日、マバラカットより神風特攻隊の第一陣が初出撃を行った。
1571年のスペイン統治から始まり、1898年のアメリカ統治、と他国に支配されてきたフィリピン。それは蹂躙の歴史でもあった。
しかし、1942年に始まった日本軍の軍政は違い、マバラカットの人々は尊重され、子供などは特攻隊員に非常に可愛がられた、とディソン氏は語る。そのディソン氏は15歳のときに大西中将・関大尉に可愛がられた思い出を持つ。特攻隊員たちは「死」から逃れられない運命を享受しつつ、生活を共にすることになったフィリピン・マバラカットの人々を守ることにも力を注いだのだと。マバラカットの人々にとって彼らは英雄であった。
懲役のない刑務所~フィリピンの日本人死刑囚~(再)
2006年3月5日 (日) 02:40~03:40

「6人に1人」。これ、何のことかわかりますか?
実は外国に出かけた日本人の海外トラブル経験者数です(2003年2月外務省による世論調査)。年間1700万人が海外に出かけ、90万人が海外で暮らす今、日本人がトラブルに巻き込まれる件数は想像を遥かに越えています。たいていが不注意から生じる、スリ、置き引き、強盗などの被害が、中には逆に、加害者となってしまうケースの被害もあります。
ここにひとりの日本人死刑囚がいます。1994年12月7日、麻薬不法所持でフィリピン初の日本人死刑囚となった男。男の名は鈴木英司(スズキヒデシ)。しかし男は無罪を主張。彼に突然おとずれた転落の人生とは? そして彼が目にした驚くべきフィリピンの刑務所の実態とは? この話を他人事だと思っているあなた!
あなたのすぐ後ろにも魔の手は忍びよっているのです!!
答え。~千原Jr.の答えを探す旅~(再)
2006年2月22日 (日) 03:03~03:58

深夜に1時間。「女」に興味のある人々に…
この番組は、千原Jr.が、正解のない定義「女とは?」の答えの、実像に実際に会って答えを探す旅の記録。
出会って話を聞いた全ての女との記念写真を、ケータイにおさめ、旅の思い出とする。
世の中のいろんな女と出会って別れて、Jrが導く答えとは???
もしかしたら、答えは出ないかもしない。
でも、Jr.が訪ね歩いて出会う人は今を生きる「女」。
これは、今の時代を切り取った、まぎれもない「女」のカタログになる。
千原浩史と一緒に「女」を旅してみませんか?
迷宮ゴールデン街 ~新人ディレクター漂流記~(再)
2006年2月19日 (日) 02:40~03:40

新宿・歌舞伎町1丁目。ここに「ゴールデン街」という名称の飲み屋街がある。
かつてこの街は、60年代後半から作家、演劇人、映画人など文化人や安保闘争に明け暮れていた学生たちのたまり場となっていたという。そしてそこでは毎夜、酒を飲みながらの議論やけんかが繰り広げられていた…。
フラメンコに宿る魔力 ~日本人100年目の奇跡~(再)
2006年2月12日 (日) 02:40~03:40

スペインについで世界で第一位のフラメンコ人口を誇る日本。
踊りの練習生だけでも10万人以上。観客動員数は40万人を越えるというその熱い日本のフラメンコはこの春、フラメンコのメッカ、アンダルシアのヘレスフェスティバルにて世界初、外国人としての公演を行った。題目は日本の古典、『曽根崎心中』。
全編を通して日本語で歌われる歌詞を阿木燿子が、そして音楽を宇崎竜童が担当。
日本のフラメンコは本場ヘレスの地元の人々たちに受け入れられるのか? 日本を代表するフラメンコアーティスト、鍵田真由美、佐藤浩希の挑戦を軸に、なぜ日本人にフラメンコが愛されるのか? その謎に迫ります。
日本で“難民”になる方法(再)
2006年2月8日 (水) 02:33~03:28

1980年、日本は難民条約に加盟。迫害などを受けて自国で暮らせない『難民』を受け入れなければならない。しかし、2003年の日本での受け入れは、申請者300人中、わずか10人。命からがら逃れてきた人でも、受け入れを拒否されれば、不法入国者として国外退去となってしまう。では、どうしたら平和な日本で『難民』として滞在することができるのか。
だから、私は歌い継ぐ -アイヌのウポポ、八重山の島唄-(再)
2006年2月5日 (日) 02:55~03:55

音楽には、そこで暮らす人々の感じ方、考え方、暮らし方が色濃く刻みこまれている。人々の感じ方、考え方、暮らし方が変われば音楽も変化するように、音楽の変遷を辿ればその土地の歴史が浮かび上がってくる。
北はアイヌ、南は沖縄・八重山列島。ともに悲しい歴史をもつ民族・地域の音楽に焦点を当て、その地に広がる豊かな音楽世界を見つめていく。
<日本>でありながら<本土・日本>ではない、辺境の音楽(マージナル・ミュージック)。
人間の営みの記憶や生命力を映し出す“音楽”の核に迫る。
東京ニューシネマパラダイス(再)
2006年1月29日 (日) 02:40~03:40

近年日本映画は斜陽産業の文脈だけで語られて来た。しかしハリウッドへの進出、興行収入の記録まだまだその魅力を失っていない。番組では映画を支え、愛して来た人の物語を広い集めてみた。
間違いだらけの「ボランティア」-他人を助けるホントの意味-(再)
2006年1月22日 (日) 03:05~04:05

昨今、「ボランティア」という言葉が新聞やニュースに出てこない日はない。
ある統計によれば、日本人の3人に1人はボランティア経験があるという。
NPO法にボランティア休暇、都立高校の奉仕活動必修化など、行政や一般企業、教育現場でもボランティアの導入が進んでいる。
そう、時代はボランティア万歳!
でも、ちょっと待って。
「ボランティア」って、どういう行為なの?
韓国における日本文学のあいまいな軽さ(再)
2006年1月15日 (日) 03:10~04:10
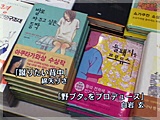
日本の小説にはまる韓国人が急増している。日本の小説は、1999年には年間219作品が翻訳され、それが04年には364作品に増え、05年になると、ベストセラー50位で日本の小説の占める割合が初めて韓国の小説を抜いた。
なぜ今、韓国で日本の小説がうけるのか。