フジテレビジュツのスタッフ
美術プロデューサー
番組制作側とやりとり、交渉をして、
美術セットの制作に関する予算を管理するアートプロデューサー(AP)。
インタビュー
※所属・肩書きはインタビュー当時のものです

株式会社フジアール
メディア事業部
メディア事業課課長
小林 大輔さん
2007年 (株)フジアール入社
2016年4月から美術プロデューサー(10年目)
主な担当番組:フジテレビ『続・続・最後から二番目の恋』『アイシー』『絶対零度』『おじゃマップ』
Netflix『御手洗家、炎上する』『The Days』『金魚妻』
Abema TV『7.2 新しい別の窓』『1000万円シリーズ』『72時間ホンネテレビ』 他多数

ーメディア事業部には美術プロデューサーは何人いますか?
小林
13人です。それとフジテレビから5人が兼務出向しています。主に番組など映像コンテンツを担当していて、イベント関係はイベント事業部になります。結果的に番組・イベントの両方やっている人もいます。
ー美術プロデューサーになる前はどんな仕事でしたか?
小林
2007年に新卒入社して研修が2年、イベントの美術プロデューサーを3年、その後番組のアートコーディネーター(美術進行)を4年やりました。
ーフジアールへ入ろうと思ったきっかけは?
小林
学生時代にお世話になった美容師さんが、番組のヘアメイクも兼務されている方で、その方から「美術進行」という仕事があると教えてもらったのがきっかけです。それまではハウスメーカーへの就職を考えていて、家や店舗の内装に興味があったのですが、番組のセットにも同じような関心を持つようになりました。その後実際に番組の現場を見学できる機会があって、美術進行という仕事を目の当たりにしたんです。図面を描くというよりは、現場を仕切り、管理し、監督していく立場に魅力を感じて、この仕事を目指したいと思うようになりました。その延長線上で、現在は美術プロデューサーとしての仕事に携わっています。
ーアートコーディネーターも美術プロデューサーも両方経験した訳ですが、また現場の美術進行に戻りたいと思ったりしますか?
ずっと現場での仕事にこだわっている人もいますよね。
小林
アートコーディネーターはずっと現場にいる分、熱量が高くて、それがすごく伝わってきます。打ち上げや現場で盛り上がっている様子を見ると、少し羨ましく感じて、「また現場に戻りたいな」と思うこともあります。
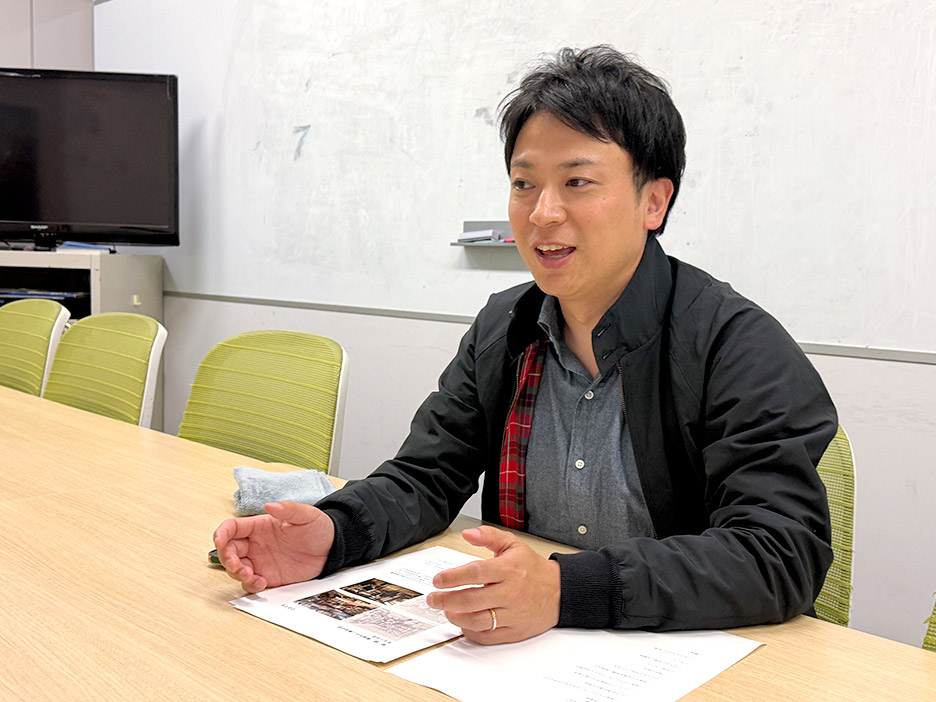
ー美術プロデューサーの場合は、同時期に何本も掛け持ちになりますか?アートコーディネーターは特にドラマに関わると兼務は難しいと思うのですが。
小林
そうですね、ドラマも何本か掛け持ちしますし、同時にバラエティー番組、CM・MV撮影もやります。幅広く仕事がやれるという意味では、美術プロデューサーの方が面白い面もあります。
ー美術プロデューサーの仕事も、人によって重きを置くポイントが違うことがありますか?
小林
予算の使い方やスタッフへの関わり方には、その人の個性が強く表れると感じています。例えば、全体のバランスを慎重に取りながら予算を配分する人もいれば、ここぞという勝負どころで思い切って予算をかけることで、作品のクオリティを高める人もいます。また、ロケ地で目に見えない部分の養生までしっかり対応しようとするような配慮をする人もいます。そういった判断の仕方や考え方には、その人ならではの価値観が表れていると感じます。さらに、スタッフとのコミュニケーションの取り方にも個性が出ます。近況をこまめに共有し合ったり、問題が起きる前に予防的に対処しておいたりと、人によってアプローチは様々です。そうした“さじ加減”にも、それぞれのスタイルや経験が反映されているように思います。
ー制作のプロデューサーとの相性で「合う、合わない」がありそうですね。
小林
そうですね、確かにあると思います。制作プロデューサーの中には、「とにかく費用をうまくコントロールしてくれる美術プロデューサーがいい」という人もいれば、「現場をうまくまとめてくれる美術プロデューサーがいい」という人もいます。そのあたりに制作プロデューサー自身の個性が表れますし、相性が出てくる部分だと感じています。現場では、美術スタッフの皆さんの話を聞いたり、トラブルが起きたときに間に入って場を収めたりする、いわば“はけ口”になるような役割も大切だと思っています。ただ、それをどこまで積極的にやるかは、人によって違います。私はどちらかというと、そういう話をスタッフから言われやすいタイプなのか、「もうやってられませんよ!」といった、結構ストレートなことを言われることもあります(笑)。「いやいや、別のあの人が美術プロデューサーだったら、そんなこと言わないでしょ」と思うことも、正直あります(笑)。でも、本音をぶつけてもらったうえで、最後に「また頑張ります」と言ってもらえるのは、本当にありがたいなと感じています。
ーなるほど、でも現場からしたら言いやすい方がいいですよ(笑)。
小林
そうですね、私自身もそう思っています。「言いやすい」というか、「言われやすい」というか…。子どもの頃から、なんとなくそういうタイプだったように思います。とはいえ、なるべく美術スタッフの話をしっかり聞きつつ、美術以外のスタッフの声にも耳を傾けて、状況を俯瞰的に見られるよう心がけています。現場のいざこざにわざわざ首を突っ込むのは、「余計なこと」と思われているかもしれませんが、そういう考え方も含めて “個性”なのだと思います。
ースタッフの気持ちも含めて、現場がうまく回る環境を作ることも、美術プロデューサーの仕事として大切だということですか?
小林
はい、私はそういう考え方でやっています。まだまだ半人前ですが、ありがたいことに、これまで様々な経験をさせてもらいました。その中で特に意識しているのは、人間関係やスタッフの気持ちの起伏に気を配り、問題が起きそうなポイントに事前に目を向けて、火種は小さいうちに解決しておくこと、つまり大事になる前に配慮を尽くすことの大切さです。そういった対応がうまくいき、現場がスムーズに回ったときは、とてもうれしく感じますし、大きなやりがいにもなっています。とはいえ、まだまだ思うようにいかないことも多く、日々試行錯誤の連続です。

ー美術プロデューサーになりたい人に、必要な知識などはありますか?
小林
入社する段階では「これは身につけておいた方がいい」という明確な条件は、あまりないと思っています。私自身、大学は理工学部で、この業界のことはまったく知りませんでした。今実際に使っている知識は、すべて入社してからの経験で身につけたものばかりです。現在の仕事で役立っているのは、知識というよりも、経験から得たことを応用する力です。特に大切だと感じているのは、状況を先読みして「これから何が起こるか」を予測し、先手を打って対応すること。そのためには、感性と、それに対応するための“引き出し”の多さが必要だと思っています。これからもその“引き出し”を増やし、経験を柔軟に生かしていけるよう努力していきたいと考えています。
ー必要なのは知識というよりは、適性ということでしょうか?
小林
そうですね。知識があることは、打ち合わせをより早く、深く進められるという点で、とても大切だと思います。一方で、経験に基づいた対応力も同じくらい重要だと感じています。専門的な知識は、それぞれの分野のスタッフがしっかり持っているので、むしろそのスタッフたちが気持ちよく、スムーズに動けるように配慮することのほうが、今の自分にとっては大事だと感じています。…とはいえ、このあたりの考え方はまだ自分の中でも少しフワッとしていて、模索している部分でもあります。
ーアートコーディネーター(美術進行)の中には、前職が設計者やイラストレーターなど色々な経歴の人がいますし、その個人の特徴が仕事に生きている場合があるなと感じるのですが、美術プロデューサーの場合は持っていた方がいい知識や技術があるのかな?と思っての質問でした。持っていた方がいいのは運転免許くらいでしょうか(笑)。
小林
あとは、地味ですが、日頃から世の中の状況を把握しておくことの大切さを、最近ますます痛感しています。近年、特にコロナ禍では、流通の停滞や木材不足といった影響があり、通常よりも早めの発注が必要になりました。また、物価の上昇を見越した対応や、金属類の供給不足への対策など、世の中の動きがそのまま美術の現場にも影響してくると実感しています。「ニュースって軽視できないな」と感じる場面が増えました。社会の動向を把握し、自分の仕事にどのような影響が出るのかを考えること。車両や貨物の動き、物流全体の流れまで意識を広げることで、ようやく先手を打てることも多くあります。この仕事は現場対応力が求められますが、そのための“予測力”は、日常的な情報の積み重ねから得られるものだと、最近特に実感しています。
ーどんな人が美術プロデューサーに向いていますか?
小林
「打たれ強い人」だと思います。くじけないこと、そして“打たれ慣れる”こと(笑)。これは本当に大切だと感じています。たとえば学生の人が、自分は打たれ強いと思っていたとしても、実際に入社してみると、想像以上に厳しい場面もあります。そこから立ち上がり、さらに打たれ強くなっていけるかどうか。最初から強い必要はなくて、「くじけない覚悟」がある人が向いていると感じます。これはきっとどの職業でも、普遍的なことのように思います。中には、もはや“打たれている”という感覚すらなくなって……もう仙人のような域に達している先輩もいます(笑)。もうひとつ大切なのは、俯瞰で状況を見られることです。様々な立場の意見を整理し、全員が納得できる“落としどころ”を見つけていく。そのためには、時には誰かにとっての“悪者”にならなければならないこともあります。全員にいい顔をし続けることはできません。そういう時に腹をくくれるかどうか、それも大切な資質の一つだと思います。
ー美術プロデューサーに大事なのは「度胸」があるかどうかだとも思いますが、いかがでしょう?
小林
そうですね、その通りだと思います。何かを決断しなければならない場面では、度胸があるかどうかで、現場の動きも結果も大きく変わってきます。あまりにも守りに入ると、結局何もできなくなってしまう。だからこそ、「自分が腹をくくって音頭を取る」という覚悟が必要です。もしうまくいかなかったとしても、「やり切った」とスタッフを労い、責任は自分が取るという姿勢。これこそが、美術プロデューサーにとって欠かせないものだと思っています。

ー美術プロデューサーをやっていて困ったこととか、普段からの悩みはありますか?
小林
「予算が足りない!人が足りない!」です。最近は、ネット配信や地上波以外のチャンネルも増え、それぞれが多くの作品を制作するようになってきました。その結果、番組コンテンツの本数自体はどんどん増えているのですが、1本あたりの制作予算は下がっているというのが現状です。一方で、働き方改革によって一人あたりの労働時間に制限があるため、「少人数で長時間働く」というやり方ができなくなりました。結果として、一つの番組に必要なスタッフの数は増えているにもかかわらず、全体の数も増えているので、圧倒的に“人”が足りないのです。スタッフの確保には本当に苦労していて、それが現場全体に大きな影響を与えていると感じています。
ー各美術協力会社もスタッフ確保に苦労していると聞きます。どんどん若者が志望して参入してほしいですね。最初の入り口はアルバイトでも何でもいろんな働き方があると思いますけれど。
小林
そうですね、やはり近年は少子化の影響も大きいと感じます。一方で、番組側としては「人が足りないからぜひ来てほしい」という状況なのですが、それに見合った予算が用意できないというジレンマも抱えています。また、美術業界全体で見ると、男性の応募が劇的に減っているという現状があります。逆に、女性の応募は増えていて、そこは非常に助かっているのですが、全体として男性が少なくなってきているというのは実感しています。もちろん「男性がいい」「女性がいい」といった話ではなく、多様な人がバランスよく関わってくれることが理想的だと思っています。だからこそ、そのバランスをどう保っていくかというのも、今後の課題の一つだと感じています。
ー今までで、失敗したと思ったことを教えてください。
小林
それはもう、山ほどあります(笑)。同年代の仕事仲間に話を聞いても、恥ずかしい話ばかり。バッキバキに怒られましたし、当時持っていた自信やプライドはもう…粉々になってさようなら、って感じでした(笑)。たとえば、数を間違えて発注してしまって、予算がオーバーしそうになったこととか、連絡が一人に漏れてしまっていたこととか…。正直、そんな“小さいけど重大なミス”は、数え切れないほどあります。でもまあ、今となっては「かわいいもんだな」って思えますけど(笑)。ただ、今でもずっと心配し続けていることがあります。それは、初回の「美打ち(美術打合せ)」で、本当に全スタッフがちゃんと来てくれるかどうかということです。ドラマの現場で、美術スタッフを調整して集めて、最初の美打ちを迎えるとき、当然「全員揃うはず」なのですが、当日まで本当に全員来るのか、実はずっと不安です。いくら事前に確認していても、これはもう性格というか、定年までずっと心配し続けるだろうなと覚悟しています。というのも、過去に一度、本当に来なかったセクションがありました。その時は、該当のジャンルの話が一切できず、大変なことになりました。欠席が事前にわかっていればまだ対応できるのですが、連絡の漏れや日程の誤伝達、単なる失念など、原因は様々です。でも、こうした初回の打ち合わせでスタッフが揃わないというミスは、美術プロデューサーとしての信頼に直結するので、本当にゾッとします。スタッフから「え?私そんなの聞いてないんですけど?」なんてことが絶対に起きないように、とにかく確認です。一度、顔合わせが済んでスタッフ同士がつながってしまえば、ある程度安心できるのですが、最初の段階の調整ミスだけは絶対に避けなければいけない。こればかりは、今も昔も、ずっと緊張感をもって向き合っているところです。
ーやりがいを感じるのはどんな時ですか?
小林
一つは、大変だった現場が無事に終わり、撮影が完了して、最後の撤去まで安全に終わった時。その瞬間は、「やり切った」という達成感があります。もう一つは、映画やドラマの作品として完成し、テレビやスクリーンで放送・上映されて、エンドロールが流れているのを見た時。自分の名前が出て、それを見た家族や昔からの友達から「見たよ!頑張ってるね」と連絡をもらったりすると、この仕事をやってきてよかったな、と実感します。よく学生の人にも伝えるのですが、やりがいを感じる瞬間は、そんなに多くありません。私の場合は、たまに、ほんの一瞬です。普段は、地道で大変なことや苦労の連続。でも、その“一瞬”が本当に大きい。他の仕事では味わえないような、充実感があります。
ー自分の関わった作品がヒットして成功することもあると思いますが、そういう作品への評価が自分のやりがいには影響しますか?
小林
私にとって、作品の評価は“おまけ”のようなものだと考えています。まずは「現場を成立させること」が最優先です。スジュール通りに、安全に、無事に終えられること。そのうえで、クオリティを上げる努力をして、それが実現できたときには、自分の仕事としては“成功”だと感じます。その後に、作品としての評判がよければ、それは“ご褒美”のようなもの。もちろん、うれしいですし、それがさらなるやりがいにもつながります。完成した作品が評価されれば、その瞬間に感じた充実感が後から増加する、そんな感覚があります。
ー仕事をやるうえで大事にしていることは?
小林
入社するまでに特別なスキルや知識が必要だとはあまり思っていません。だからこそ、どの学部からでも入ってこられるし、「やろう」と思えば誰にでもできる仕事だと思っています。特別な資格が必要なわけではないし、門戸が広い分、誰でも挑戦できる仕事です。だからこそ、「小林(自分)にやってもらってよかった」と言われるような価値を、自分の立ち回りで作らなければいけないと考えています。たとえば、「スタッフ同士が円滑に動けるように配慮する」「現場が動きやすくなるように事前に根回しをしておく」「スタッフが信頼されるような印象を持ってもらうよう気を配る」などなど。こうした小さな積み重ねを通じて、自分が“間に入る”意味や存在価値を少しでも高めたいと常に考えながら行動しています。
ー今回初めて一緒に仕事(『続・続・最後から二番目の恋』)をさせてもらいましたが、非常にやりやすかったです。
(注) 聞き手は美術デザイナー
小林
そう言ってもらえることが、一番うれしいです(笑)。本当に。
ーテレビ番組以外でもこれからやってみたい仕事はありますか?
小林
実は、Netflixの作品にはこれまでに3本関わらせてもらいました(笑)。規模が大きい現場が続くので、プレッシャーはある分、やりがいも大きくて、すごく楽しいです。一つ一つの現場が刺激的で、関わるたびに自分の経験値が上がっていくのを感じていますし、入社した時に憧れていたことが、今まさに自分の仕事になっています。当時は、「いつか美術プロデューサーになって、月9ドラマをやりたい」「大きなバラエティー番組を担当したい」なんて夢を描いていました。それが今、現実のものとなっています。これからの目標は、その実績をもっと積み重ねていくこと。あと5年、10年と続けることで、いろいろな作品に携わることがとても楽しみですし、自分自身の成長も実感できるはずです。
ー最後に趣味を教えて下さい。
小林
無趣味なんです。祖父もそんなことを言っていました。こだわっていることがあまりなくて。ただその代わりに、「これ面白いよ」と誰かにすすめられたものは、とりあえずやってみようという気持ちはあって、何でも広く浅く試してきました。一つのことに深くのめり込むというよりは、いろんな世界をちょっとずつのぞいてみるような感覚を楽しんでいます。
ー最近だとどんなことに興味を持ちましたか?
小林
最近はゴルフに誘っていただく機会が増えてきて、少しずつ頑張り始めています。正直、技術的にはまだまだ“ド下手”なんですが(笑)、それでも楽しさを感じる場面が増えてきました。特にハマっているのは、クラブなどの道具選びです。性能はもちろんなんですが、「自分に合っているか」「どんな特徴があるのか」などを調べるのがけっこう面白いです。今のところ、ゴルフが一番、これから趣味になりそうな予感がしています。
ー物が好きなタイプですか?
小林
物は好きですね。普段はなるべく物を集めないように心がけているんですけど、実は物で溢れた生活がしたいっていうのが根底にはあります(笑)。コレクター魂というか、本当は収集癖がすごくあるんです。でも、実際やってしまうと大変なことになるし、物が溢れてしまうことが嫌な部分もあって、今は頑張って一切買わないようにしています。
ーどうしても欲しいと思ったものはないんですか?
小林
くだらないんですが、ゴジラの模型とかドラゴンボールの悟空がカメハメ波打ってるフィギュアとか、浮いているデロリアンとか、ああいうのは本当は欲しくて並べたいんですけどキリがないので、一つも持ってないです。
ー家族に怒られるから?
小林
怒られるからもあります(笑)。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のデロリアンはパート3まで何台も並べたいんですけど、置く場所の問題もそうですし(笑)。
ー車やバイクとかは?
小林
趣味としては今のところなくて、程よいサイズで移動できればいい感じです。でも、カーシェアとかではなくて、所有欲からか、自分の車の方がいいです。まとめると無趣味ってことです(笑)。
ー仕事が趣味という感じですか?例えば休みの日でも会社に来てしまうみたいな?
小林
ここ最近は、ほとんど仕事が生活の中心になっていました。誰かに感謝されるのが、うれしかったり楽しかったりで。仕事でそれを味わえることが充実感だったように思います。これが趣味かと言われると・・・わかりません。

ー忙しくても自分の時間を取れることに喜びを感じるのに対して、仕事が忙しいことに喜びを感じるのが、仕事が趣味という人だと思うのですが、小林さんはどうですか?
小林
忙しい自分がうれしいって・・・でも、そうかもしれません。誰かに頼られたり、感謝されたりすることは、とてもうれしいので、つまりは忙しい自分がうれしいような。気持ち悪いですね。そういう意味では、信用を得るのが好きだということかもしれないです。スタッフからの信用を得るために頑張りたいですし、仕事に限らず、人との関わりを丁寧に、充実させていきたい。それが、自分にとって一番大事なことかもしれません。
ーありがとうございました。
(2025年9月)

株式会社フジテレビジョン
美術制作センター局次長職 兼部長
株式会社フジアール
執行役員部長 エグゼクティブ・アート・プロデューサー
三竹 寛典さん
入社29年目
ー美術プロデューサーとはどのような仕事ですか?
三竹
まずは予算管理。ドラマの場合は美術スタッフを決定するのも仕事です。
あとは安全管理、スタッフの労務管理といったところですね。
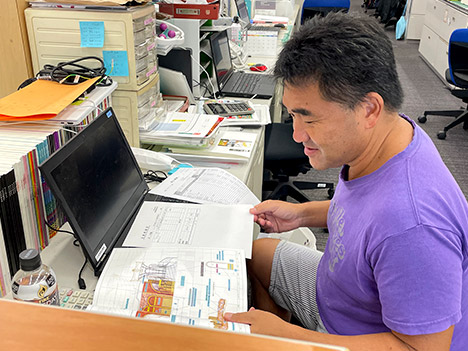
ー予算管理の業務はどのような内容ですか?
三竹
番組では大体予算が決まっているのですが、美術制作関連の内容を確認した上で、内容に見合った額を制作プロデューサーに投げて美術予算を交渉します。合わない場合は、内容をこうしたらどうか、こうして欲しい、など話合いをします。
番組のやりたいことと、それにかかる美術費用を調整する仕事ですね。
ー番組の安全管理とはどういう内容ですか?
三竹
最近は減ってきたのですが、ゲームの多いバラエティー番組では、打ち合わせの段階で制作側のやりたい企画内容を聞いて、「そのままでは危ないので、もう少し角度をこうしよう」だとか、「マット設置するとか、こういう安全対策をしなければいけない」という提案や確認をします。また、「事前シミュレーションは絶対必要だからやりましょう」ということを確認して準備し、現場で実行していきます。安全にかかる費用は削減できないので、「やるのであればちゃんと予算をかけないとダメだ」ということも制作側と事前に話し合います。
あとは、建て込みの時間の確保ですね。美術の細かいスケジュールはアートコーディネーターが作るのですが、その前に、例えば「スタジオにこのくらいの空き時間がないと、その収録時間には始められないから開始時間をずらして欲しい」などと要求することもあります。スタジオの空き状況と、セットを建てるのに美術が必要とする時間と、番組制作全体のスケジュールとの調整を制作側と行います。
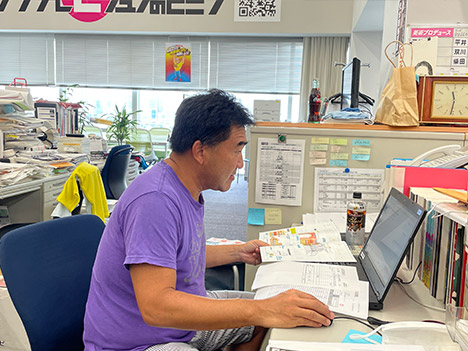
ー美術プロデューサーの担当番組はどのように決まりますか?
三竹
デザイナーも同じだと思うのですが、過去に担当した時と同じスタッフがやる番組であれば、その組というか流れで決まることが多いですね。
また、制作プロデューサーやディレクターからの希望で決める場合もあります。美術デザイナーの方が先に決まっていて、そのデザイナーから一緒にやってくれませんかというリクエストで決める場合もあります。最終的には部長の承認で決定するのですが、現場の希望をひっくり返すことはあまりないですね。
あとは個々の美術プロデューサーが、オーバーワークにならないように調整するということでしょうか。
ー美術プロデューサーに向いているのは、どんな人でしょう?
三竹
色んな人がいていいと思っています。デザイナー出身の美術プロデューサーは、美術のことを細かいところまでよく知っているので、そういう人もいいと思いますし、美術以外の部署を経験してきている美術プロデューサーの場合は、前に所属していた部署とのつながりが強く、交渉などがやりやすかったりするので、いいと思います。
資質という面では、共通して言えるのはバランス感覚のある人ですよね。まあ、美術プロデューサーに限らず、求められる資質はどの部署でも一緒なのかもしれませんけれども(笑)。
それから美術でなくとも、ある程度マスコミ人というか、会社や社会での経験を積んでる人の方がいいと思うので、新入社員でいきなり美術プロデューサーというのは難しいかなあ。番組の美術全体を俯瞰で見る仕事だと思うので。
ー仕事をやるうえで大事にしていることは?
三竹
昔からいろんな番組を担当してきました。深夜の小さな番組から大型の特番まで大小様々な番組があるわけですが、各番組における美術スタッフは、その番組においてベストなスタッフだなと信じてやるようにしています。「人を信頼する」ということを大事にしています。
ー一人で何本かの番組を担当していると思いますが、番組数に比べて美術プロデューサーの人数は足りてますか?
三竹
今は丁度いいバランスだと思います。
ー美術プロデューサーを目指したい人は、どうすればいいのでしょうか?
三竹
一つはフジアールのような美術会社に入ることですね。フジアールは美術総合職といって、新入社員でも研修が終われば美術プロデューサーになれるっていえばなれるんですよ。ただフジアールに入ったにしても、現場を経験しておかないと言うことに説得力がありませんから、現場の人が動いてくれなかったりすることもあるので、いきなりだと大変だと思います。
ーフジアールでは、デザイナー志望と美術プロデューサー志望では募集が違うのですか?
三竹
確か美術プロデューサー、デザイナー、アートコーディネーター、イベント事業などと志望別で募集していると思います。

ー美術が関わっている番組で、デザイナーがいないケースはありますが、美術プロデューサーがいない番組はありませんね。
三竹
最近予算が少なくなってきたせいか、デザイナーがつかないオールロケの番組が増えていますね。ただロケ先での飾りだとか、ドッキリみたいな新しい装置の仕組みを考えるとか、セットがなくても美術デザイナーが必要な番組もあります。
ーオールロケなど、番組が多様化していく時代に合わせて、美術プロデューサーも色んなタイプの人がいるといいですね。
三竹
そうですね、色んな人がいればやり方も増えるのでいいと思います。
ーありがとうございました。
(2023年6月)

