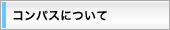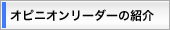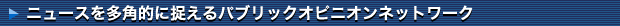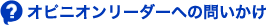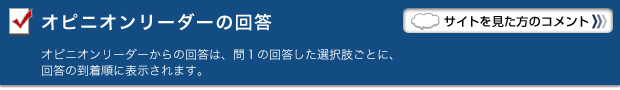社会・公共
復興予算の正しい使い方
東日本大震災のための復興予算が、「防災」を名目に全国の官庁施設
約100カ所の耐震補強に使われたほか「水産業の復旧支援」として
南極海での調査捕鯨に対する反捕鯨団体の妨害活動への対策費と
しても使われていたことが明らかになりました。
これを受けて、政府は、東日本大震災の復興予算を使った事業について、
その使途が適切であったかを今後、調査することを検討していると
伝えられています。
政府は、東日本大震災からの復興に向けて5年間で19兆円規模の予算を充てる
ことになっており、財源は増税によって賄われる方針です。約10兆円については、
復興財源確保法(2011年12月2日公布)に基づく2つの臨時増税を以て調達することに
なっています。ひとつは来年1月以降、25年間に渡り納税額が2.1%上乗せ徴税
される所得税の増税、もうひとつは個人住民税の均等割を年1000円増額することを
10年間行う増税です。すでに、復興関係費として、2011年度に約15兆円が
予算として計上され、復興が進められています。
しかし、復興予算に関しては、①被災地に復興予算が行き渡っていないという問題、
②復興予算が使い残されている問題(8月時点で、5.8兆円が未消化)、
③先述した、被災地以外の事案に復興予算が使われているという問題などが
指摘されています。
2:番組として (our aim)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
東日本大震災からの復興では、被災地域の復旧復興が大前提となります。
一方、政府方針を見ると、「被災地域の復興は、活力ある日本の再生の先導的役割を
担うものであり、また、日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はないとの
認識を共有する。」が謳われており、日本経済全体の活性化も復興予算の使い道に
含まれているようです。
また、「復興の基本方針」に示されている実施する施策の中には、「東日本大震災を
教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等の
ための施策」という記述があり、被災地以外でも復興予算を耐震化などに使えることに
なっています。
復興予算は、使い道の範囲や審査の仕方などが整理されないままになっており、
優先順位が多くの国民からよく見えない状態となっているようです。
そこで番組では、復興予算がどのような用途に使われるべきか、国民が納得できる
復興予算の優先順位の付け方とは、どのようなものであるかについて、オピニオン
リーダーの皆さまからさまざまなご意見をいただき、番組視聴者、ユーザーとともに
議論したいと考えました。
コンパス・オピニオンリーダーの皆さまには、被災地復興に直接関わっていらっしゃる方、
視察やボランティアを行っている方がいらっしゃいます。また、被災地復興は、皆さまの専門分野
にどこかで関連する大きなテーマであると思われます。
それぞれの専門分野、ご見識に基づく幅広いご意見をお待ちしております。
《参考資料》
復興予算の政府の考え方の背景にある資料をこちらのpdfファイルにて
ご覧いただけます。
『東日本大震災からの復興の基本方針』
www.reconstruction.go.jp/topics/doc/20110729houshin.pdf
『復興構想7原則』
www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou4/7gensoku.pdf
約100カ所の耐震補強に使われたほか「水産業の復旧支援」として
南極海での調査捕鯨に対する反捕鯨団体の妨害活動への対策費と
しても使われていたことが明らかになりました。
これを受けて、政府は、東日本大震災の復興予算を使った事業について、
その使途が適切であったかを今後、調査することを検討していると
伝えられています。
政府は、東日本大震災からの復興に向けて5年間で19兆円規模の予算を充てる
ことになっており、財源は増税によって賄われる方針です。約10兆円については、
復興財源確保法(2011年12月2日公布)に基づく2つの臨時増税を以て調達することに
なっています。ひとつは来年1月以降、25年間に渡り納税額が2.1%上乗せ徴税
される所得税の増税、もうひとつは個人住民税の均等割を年1000円増額することを
10年間行う増税です。すでに、復興関係費として、2011年度に約15兆円が
予算として計上され、復興が進められています。
しかし、復興予算に関しては、①被災地に復興予算が行き渡っていないという問題、
②復興予算が使い残されている問題(8月時点で、5.8兆円が未消化)、
③先述した、被災地以外の事案に復興予算が使われているという問題などが
指摘されています。
2:番組として (our aim)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
東日本大震災からの復興では、被災地域の復旧復興が大前提となります。
一方、政府方針を見ると、「被災地域の復興は、活力ある日本の再生の先導的役割を
担うものであり、また、日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はないとの
認識を共有する。」が謳われており、日本経済全体の活性化も復興予算の使い道に
含まれているようです。
また、「復興の基本方針」に示されている実施する施策の中には、「東日本大震災を
教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等の
ための施策」という記述があり、被災地以外でも復興予算を耐震化などに使えることに
なっています。
復興予算は、使い道の範囲や審査の仕方などが整理されないままになっており、
優先順位が多くの国民からよく見えない状態となっているようです。
そこで番組では、復興予算がどのような用途に使われるべきか、国民が納得できる
復興予算の優先順位の付け方とは、どのようなものであるかについて、オピニオン
リーダーの皆さまからさまざまなご意見をいただき、番組視聴者、ユーザーとともに
議論したいと考えました。
コンパス・オピニオンリーダーの皆さまには、被災地復興に直接関わっていらっしゃる方、
視察やボランティアを行っている方がいらっしゃいます。また、被災地復興は、皆さまの専門分野
にどこかで関連する大きなテーマであると思われます。
それぞれの専門分野、ご見識に基づく幅広いご意見をお待ちしております。
《参考資料》
復興予算の政府の考え方の背景にある資料をこちらのpdfファイルにて
ご覧いただけます。
『東日本大震災からの復興の基本方針』
www.reconstruction.go.jp/topics/doc/20110729houshin.pdf
『復興構想7原則』
www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou4/7gensoku.pdf
Q1:あなたが復興予算を使って「是非行うべきと考えること」は何でしょうか?ご意見をお聞かせください。
| 1.回答する(問2でコメント) | |
| 2.回答を控える |
Q2:復興予算の具体的な使い道について、お聞かせください。
(複数でも結構です。)
(複数でも結構です。)
Q3:復興予算の優先順位をどうつけるべきか? また、限りある復興予算の対象となる範囲はどこまでとすべきか? 復興予算の「使い方に関する考え方」について、ご意見をお聞かせください。
1. 回答する(問2でコメント)
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
被災地域において、事業活動や普通の生活を軌道に乗せるための緊急性の高いものを優先することは当然だが、どのような形で再生するのか、それぞれの地域における全体的な計画に基づいて配分をしていく必要がある。
被災地域において、事業活動や普通の生活を軌道に乗せるための緊急性の高いものを優先することは当然だが、どのような形で再生するのか、それぞれの地域における全体的な計画に基づいて配分をしていく必要がある。
特に被災者の人たちが働ける場を整備して、衣食住を確保できる場を整備することが重要。農業、漁業、工業などが行えるようにするための環境整備や生活支援が特に求められる。
ただ、いつまでもきりのない支援は困難であり、一時的なことに終始するとか、無駄になったりしないように、将来の自立を促すようにする必要もある。
『東日本大震災からの復興の基本方針』や7原則は、一応もっともなことばかり書いてあるが、その具体的な適用において拡大解釈や復興予算の本来の趣旨から逸脱できるような「きれいな言葉」につけこまれるようなことがないようにする必要がある。そのためには、事前に支出をチェックする部署なり委員会などがあってしかるべきだが、それが機能していないのか?
特に被災者の人たちが働ける場を整備して、衣食住を確保できる場を整備することが重要。農業、漁業、工業などが行えるようにするための環境整備や生活支援が特に求められる。
ただ、いつまでもきりのない支援は困難であり、一時的なことに終始するとか、無駄になったりしないように、将来の自立を促すようにする必要もある。
『東日本大震災からの復興の基本方針』や7原則は、一応もっともなことばかり書いてあるが、その具体的な適用において拡大解釈や復興予算の本来の趣旨から逸脱できるような「きれいな言葉」につけこまれるようなことがないようにする必要がある。そのためには、事前に支出をチェックする部署なり委員会などがあってしかるべきだが、それが機能していないのか?
Q3. 回答する
緊急性のほか、復興予算を投入することによる効果・効率の高いものを優先すること。
基本的に「被災地域」から離れている地域の事業に復興予算を使うべきではないだろう。その意味で、耐震のための修理などというのは、全国どこでも当てはまる話なので、復興とは無関係。
したがって、復興予算は、東日本の甚大な被災地域に限定すべきだろう。復興と無関係ないし関係の薄いものに復興予算を使うのは筋違い。
基本的に「被災地域」から離れている地域の事業に復興予算を使うべきではないだろう。その意味で、耐震のための修理などというのは、全国どこでも当てはまる話なので、復興とは無関係。
したがって、復興予算は、東日本の甚大な被災地域に限定すべきだろう。復興と無関係ないし関係の薄いものに復興予算を使うのは筋違い。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
こうなったら問題点は明らかだ!賊省、奸僚の悪事をあばく一大国家的プロジェクトを直ちに実行してほしい!予算を役人から取り戻すのだ!
賊省、奸僚の悪事を過去50年にわたって解明し、その損害を賠償するプロジェクトをまず立ち上げてほしい。例えば保養施設グリーンピアなどの計画や予算がいったいだれによってどのように立案され配分されたのか、私が死ぬまでにはなんとか明らかにしてほしい大疑惑だ。そうでもしなければ砂漠に水を灌ぐがごとく、予算はいくらあっても足りない。「役所のための、役所による、役所の予算」である限り、何においても有効に活用することなど絶対にできない。この点、今後社会は、日本国民は、絶対に一歩無譲ってはならない。予算を役人から取り戻そう!
Q3. 回答する
霞が関の近くに映画「大魔神」に出てくる「魔人像」を造るのはどうか。理不尽で無慈悲で私利私欲なヤクニンを懲らしめてくれるよう、お参りする人が絶えないようになるだろう。
毎日心臓の手術を行っている私にとって、そんな公共の予算がどのように使われているのか、そしてどうあるべきか、実は具体的にはよく知らない。そもそもお金とは自分で汗水たらしてせっせと稼ぐものだ。政府がもったいぶってばらまくお金など、不浄極まりないものではないのか。
それよりも地域限定の条例や法律を制定して「地域差」を出すべきではないだろうか。
こうも言える。ヤクニンが庶民からひとたび税金を搾り取ったなら、それはもう奴らのものだ。お遊びに使おうが恥さらしの「プロジェクトNG」に使おうが誰もコントロールできない。民をこれ以上苦しめず、あまり恥をかかない程度にせいぜい遊んでくれたらいい。魔人様が動き出したら大変だぞ!
毎日心臓の手術を行っている私にとって、そんな公共の予算がどのように使われているのか、そしてどうあるべきか、実は具体的にはよく知らない。そもそもお金とは自分で汗水たらしてせっせと稼ぐものだ。政府がもったいぶってばらまくお金など、不浄極まりないものではないのか。
それよりも地域限定の条例や法律を制定して「地域差」を出すべきではないだろうか。
こうも言える。ヤクニンが庶民からひとたび税金を搾り取ったなら、それはもう奴らのものだ。お遊びに使おうが恥さらしの「プロジェクトNG」に使おうが誰もコントロールできない。民をこれ以上苦しめず、あまり恥をかかない程度にせいぜい遊んでくれたらいい。魔人様が動き出したら大変だぞ!
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
復興予算は、高齢化が進む被災地を、大震災前の状態に元通りに戻すのではなく、被災地を居心地の良い街に新生するために用られるのが望ましいと考えます。
被災地の東日本大震災直前の状況に鑑みれば、復興予算を、大震災前の元の姿に復元しようとするに形で用いないことが重要です。被災地は、大震災前の時点で、高齢化が進んでいる上、中には「シャッター通り」のごとく中心市街地が衰退していたところもありました。
真に被災者と被災地のことを考えれば、大震災前の元の姿にほぼ完全に復元からといって今後の繁栄が約束されているわけではありません。むしろ、これからの被災地で生活される方々にとって居心地の良い街を(ある意味で理想を追求するように)新たに築くという意気込みで復興することを考えた方が有意義でしょう。多少時間がかかるとしても、高台移転を進めて再び悲惨な被害を受けないようにすることも一案でそう。
また、被災地の産業構造を思い切って転換するような発想も必要になってくるでしょう。大震災直前の産業構造を前提とした復興や地場産業支援では、結局は衰退の趨勢から抜け出せずに、収益や雇用の確保が長続きしない恐れがあります。その意味では、より多くの収益が上げられる産業を被災地で新たに起こすことも検討するとよいでしょう。復興予算は、それを支援するために用いられれば有意義です。
このように、復興予算は、「元通りに戻す」ためではなく、被災地を居心地の良い街に新生するために用いることが有益だと考えます。
真に被災者と被災地のことを考えれば、大震災前の元の姿にほぼ完全に復元からといって今後の繁栄が約束されているわけではありません。むしろ、これからの被災地で生活される方々にとって居心地の良い街を(ある意味で理想を追求するように)新たに築くという意気込みで復興することを考えた方が有意義でしょう。多少時間がかかるとしても、高台移転を進めて再び悲惨な被害を受けないようにすることも一案でそう。
また、被災地の産業構造を思い切って転換するような発想も必要になってくるでしょう。大震災直前の産業構造を前提とした復興や地場産業支援では、結局は衰退の趨勢から抜け出せずに、収益や雇用の確保が長続きしない恐れがあります。その意味では、より多くの収益が上げられる産業を被災地で新たに起こすことも検討するとよいでしょう。復興予算は、それを支援するために用いられれば有意義です。
このように、復興予算は、「元通りに戻す」ためではなく、被災地を居心地の良い街に新生するために用いることが有益だと考えます。
Q3. 回答する
最も避けなければならないことは、景気対策を混在させないことです。復興予算を、景況の悪化につけこんで、景気対策にからめて行おうとする恐れがあります。復興事業は、決して無意味なバラマキ財政支出であってはならず、真に被災者や被災地のために役立つものでなければなりません。単に支出先が被災地であるというだけで、必ずしも被災者が早急に求めているものでないものに支出は、復興予算の対象とすべきではありません。景況の悪化予想により、復興事業に景気対策的な意味合いを持たせたがる圧力がかかってくる恐れがありますが、早期に被災者の生活と被災地の経済が立ち直るようにするには、景気対策的な色彩を排除して、真に復興事業といえるものに限定しなければなりません。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
阪神大震災復興では、事業費約16兆3000億円の半分以上の8兆3000億円が、神戸空港や新長田再開発など被災地支援とは直接関係ない大型公共事業に充てられた。今回最優先で行うべきことは、被災地支援と「直接」関係ない分野への支出。予算を食い荒らす愚は避けるべき。
95年1月に発生した阪神大震災の復興では、事業費約16兆3000億円の半分以上の8兆3000億円が、神戸空港や新長田の再開発など被災地支援とは直接関係ない大型公共事業に充てられ、地域の被災地への恩恵が少ないうえに、そのツケが現在地元住民に回ろうとする事態となっている。
今回行うべきは、国民から広く集めた血税を食い荒らす愚を避けること。復興の基本方針の文言を操作し、被災地支援と「直接」関係ない分野へ支出する体質は、まさに官尊民卑と経済界の社会貢献意識の乏しさを際立たせている。
日本政府や官僚、経済界に対する国民の信頼感が薄れるばかりで残念無念の事態だ。
今回行うべきは、国民から広く集めた血税を食い荒らす愚を避けること。復興の基本方針の文言を操作し、被災地支援と「直接」関係ない分野へ支出する体質は、まさに官尊民卑と経済界の社会貢献意識の乏しさを際立たせている。
日本政府や官僚、経済界に対する国民の信頼感が薄れるばかりで残念無念の事態だ。
Q3. 回答する
何といっても被災地住民の日々の衣食住にかかわる部分、さらに被災地住民の職を確保するために出されている要望を最優先すべき。加えて医療や福祉関連への配分を惜しむべきではない。被災地医療機関(個人開業医師•歯科医師含め)の中には、不十分な予算で医療提供を断念(廃業含め)する事態も相次いでいるようだ。
国民は被災後の義援金等寄付金が、その後どのように使われたかについても強い関心を持っている。復興予算にしても寄付金にしても、国民の感情に訴えて集めた金の使途を明確に情報公開する責任が政治家にはある。ぜひ今後も復興予算や寄付金の使い道をメディアが暴いて明らかにして欲しい。その積み重ねが国民が政治を信じるために必要最低条件だ。
国民は被災後の義援金等寄付金が、その後どのように使われたかについても強い関心を持っている。復興予算にしても寄付金にしても、国民の感情に訴えて集めた金の使途を明確に情報公開する責任が政治家にはある。ぜひ今後も復興予算や寄付金の使い道をメディアが暴いて明らかにして欲しい。その積み重ねが国民が政治を信じるために必要最低条件だ。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
復興予算の使い方はすでに十分な議論をふまえて復興構想会議が「復興への提言」を昨年6月に取りまとめている。被災者の方の生活をできるだけもとにもどすとともに高台移転など防災に配慮しながら復興を果たすなどこの提言にそって復興を実現するために予算を使うべき。
http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/
http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/
Q3. 回答する
復興予算は被災地域の復興に直接役立つものに限って使うべきである。
関係ない地域における防災などについては通常の予算で申請すべきである。各省庁がいろいろな理屈をつけて復興予算の枠で要求をしているのは想像に難くない。問題は査定庁である財務省の姿勢である。5年で19兆という数字にとらわれ、財務省を含め、各省とも予算消化に躍起となっているのかもしれない。しかし、そもそも復興に必要な額というのは十分な議論を経て決まったものではない。従って、この数字のとらわれる必要はなく、必要ならこれより増やせばよいし、不要であれば削ればよいという性格のものである。
財務省は厳しく査定するべきで、例に挙げられているような予算を認めているのであれば、査定庁としての役割を十分果たしているとはいいがたい。もちろん一部(不合理と思われる)予算には政治家の働きかけがあるのかもしれない。このような形で査定しているのであれば、査定プロセスにも行政刷新会議の事業仕分けのような手法を導入してはどうか。そうすれば、各省も申請内容を一層精査するであろうし、財務省もより国民の目を意識して査定するであろう。
関係ない地域における防災などについては通常の予算で申請すべきである。各省庁がいろいろな理屈をつけて復興予算の枠で要求をしているのは想像に難くない。問題は査定庁である財務省の姿勢である。5年で19兆という数字にとらわれ、財務省を含め、各省とも予算消化に躍起となっているのかもしれない。しかし、そもそも復興に必要な額というのは十分な議論を経て決まったものではない。従って、この数字のとらわれる必要はなく、必要ならこれより増やせばよいし、不要であれば削ればよいという性格のものである。
財務省は厳しく査定するべきで、例に挙げられているような予算を認めているのであれば、査定庁としての役割を十分果たしているとはいいがたい。もちろん一部(不合理と思われる)予算には政治家の働きかけがあるのかもしれない。このような形で査定しているのであれば、査定プロセスにも行政刷新会議の事業仕分けのような手法を導入してはどうか。そうすれば、各省も申請内容を一層精査するであろうし、財務省もより国民の目を意識して査定するであろう。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
1.被災した人々(家族)に直接お金を配ること。
2.被災地に職を作ること、職を作っている企業に直接補助金を現金給付すること
2.被災地に職を作ること、職を作っている企業に直接補助金を現金給付すること
1.被災した人々(家族)に直接お金を配ること。
そして、その人々自由な判断で、その将来を決めてもらうこと。
2.被災地に職を作ること、職を作っている企業(商店なども含む)に直接補助金を現金給付すること
そして、その人々自由な判断で、その将来を決めてもらうこと。
2.被災地に職を作ること、職を作っている企業(商店なども含む)に直接補助金を現金給付すること
Q3. 回答する
復興予算は、被災者に直接配る、もしくは直接恩恵がある(被災者に直接サービスや職を提供する企業や団体など)ものに限定する。
復興に関係が少しでもあれば、復興予算として認められるというのなら、理屈は何でもつく。そのようなものは、通常予算で査定すればよい。
復興に関係が少しでもあれば、復興予算として認められるというのなら、理屈は何でもつく。そのようなものは、通常予算で査定すればよい。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
被災地での瓦礫処理や原発事故に伴う除染、壊れた社会基盤や産業の復旧・復興に特化し、余った予算は復興債返済に充て、復興増税の負担を軽減する。
被災地での瓦礫処理や原発事故に伴う除染、壊れた社会基盤や産業の復旧・復興に特化し、余った予算は復興債返済に充て、復興増税の負担を軽減する。
Q3. 回答する
被災地で必要な資金が不足する一方で他地域の事業が進むのでは復興予算の意味がない。
被災地に予算が優先的に回る仕組みを構築する一方で復興計画を見直し、必要ない事業は中止すべき。
そもそも、赤字国債発行を伴わず復興増税中心に財源がまかなわれているため、予算の上限が設けられず、放漫財政になっていることが根底にある。
一刻も早く予算の検証を行って編成を見直してほしい。
被災地に予算が優先的に回る仕組みを構築する一方で復興計画を見直し、必要ない事業は中止すべき。
そもそも、赤字国債発行を伴わず復興増税中心に財源がまかなわれているため、予算の上限が設けられず、放漫財政になっていることが根底にある。
一刻も早く予算の検証を行って編成を見直してほしい。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
復興予算を被災地に絞り込むことはごく当たり前の話だ。インフラ整備、住宅の供給、教育・訓練向け施設の再建と人材の投入。これらをワンパッケージでそれぞれの自治体に浸透させていかねばならない。
復興予算の執行を実施する前に、まずは政局の不安定さ、不透明さを払拭する必要がある。次に、従来の経済政策で対応できる内容と、被災地の復興を目指す内容を区別する必要がある。追加金融緩和が矢継ぎ早に実施されてきたにもかかわらず、デフレから脱却できずにいる。その元凶は言うまでもなく円高。政府高官は断固とした措置を講じると繰り返すが、現状の水準を維持するだけで精一杯。円安に誘導できないでいる。1ドル100円に固定(ペッグ)するといった荒治療が必要で、円高が被災地にも負の影響を及ぼしていることを政府・日銀関係者は再度、肝に銘じてほしい。ただし、円高阻止・円安誘導を所与の条件としても、日本企業には内需を掘り起こす努力が必要だろう。その標的市場はシルバー市場。シルバー層を標的とする新製品を世に送り出して欲しい。
以上が復興予算執行の大前提条件である。そのうえで提言したい。復興予算の対象を被災地に絞り込むべきであることは論を待たない。政治家、官僚、地元有力者といったあらゆる層の利権が絡むから復興予算が悪用される。この際、既得権益層を壊滅しておく必要がある。規制があるところには必ずや既得権がある。徹底的な規制撤廃で既得権益層を破壊しなければならない。そうでないと、効率的な資源配分は不可能だ。日本は外国にパッケージ型のインフラ輸出を今後増やしていく。この手法を被災地でも適用すべきだろう。ライフラインを含むインフラ整備がまずは重要だ。そして、衣食住。政府の仕事は割安な住宅を供給することにある。次に、教育・訓練。教育・訓練施設の再建と人材の投入に復興予算を充当することはきわめて重要である。被災地での人材育成が今後の日本経済の試金石となる。
以上が復興予算執行の大前提条件である。そのうえで提言したい。復興予算の対象を被災地に絞り込むべきであることは論を待たない。政治家、官僚、地元有力者といったあらゆる層の利権が絡むから復興予算が悪用される。この際、既得権益層を壊滅しておく必要がある。規制があるところには必ずや既得権がある。徹底的な規制撤廃で既得権益層を破壊しなければならない。そうでないと、効率的な資源配分は不可能だ。日本は外国にパッケージ型のインフラ輸出を今後増やしていく。この手法を被災地でも適用すべきだろう。ライフラインを含むインフラ整備がまずは重要だ。そして、衣食住。政府の仕事は割安な住宅を供給することにある。次に、教育・訓練。教育・訓練施設の再建と人材の投入に復興予算を充当することはきわめて重要である。被災地での人材育成が今後の日本経済の試金石となる。
Q3. 回答する
復興予算の対象は被災地に絞り込むことが何よりも重要である。そのほかの地域では従来の経済政策を充当すればよい。被災地の中でも地域によって被害状況やニーズが異なるが、その共通因数はインフラ整備、住宅供給、教育・訓練施設の再建であることは言うまでもないだろう。全体のニーズから各地域のニーズという発想が必要だと思う。各地域のニーズが先行すると意見対立が先鋭化して、復興が進展しないだろう。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
多くの被災地の首長や議員から「何より人手が足りない、資材も不足している」との声を聞く。人やモノの手当ては急務の課題。予算執行には、そうした着意が必要ではないだろうか。もっと、被災地の声やニーズを反映させるべき。
Q3. 回答する
防衛省が計上した「戦闘機の操縦士訓練教育費」も槍玉にあがるが、津波で水没した松島基地のF2戦闘機は教育用の機種(複座)。必ずしも「復興と無縁」ではない。他も、何らかの理由あっての計上では。いずれにせよ優先順位をつけるのは政治の責任。国会も開かず、閉会中審査も行なわないのは責任放棄に等しい。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
アジアの若者研究家として、他の方にない意見を呈示させて頂く、
という立場で今回は回答させて頂きます。
復興予算の中から使われるべきかは議論の余地が大いにあるかと思いますが、
私は復興予算の中から、東北の名産品などのPRの予算を組み入れるべきだと
思います。
復興支援の予算を純粋な復興だけに使い、東北の街並みが仮に10年・20年かけて
震災前の姿に戻ったとしても、現在既に超高齢社会の日本ですから、その頃には
更に高齢化が進んでいて、復興前よりも人口やGDPは低下しています。
ですから、経済的な観点から言えば、「元通りにする」という発想では、元通りに
ならないのが現実で、もう少し「攻め」の姿勢を持つ必要があると思います。
確実に経済成長していくアジアに対して、東北の名産物のPRをしていくなどの
「攻めの施策」を取ることで初めて、経済的に震災前の状況に元通りにできる
可能性が出てくると思います。
ちなみに、私は今、親日で知られる台湾の台北で、たくさんの若者たちに
インタビューをしている最中ですが、あれだけ震災後にたくさんの義援金が日本に
送られた超親日エリアの台湾でさえ、20代半ばより上の世代は大変親日ですが、
10代や20代前半の若い世代は、韓流ブームの真っただ中に育ち、日本よりも韓国に
影響を受けている人の方が多くいます。
日本のプレゼンスの低下は、台湾だけの話ではありません。アジア全域で
起こっていることで、超親日エリアである台湾ですら、そういう状況であることを
日本人はかなり深刻に受け入れる必要があると感じています。
という立場で今回は回答させて頂きます。
復興予算の中から使われるべきかは議論の余地が大いにあるかと思いますが、
私は復興予算の中から、東北の名産品などのPRの予算を組み入れるべきだと
思います。
復興支援の予算を純粋な復興だけに使い、東北の街並みが仮に10年・20年かけて
震災前の姿に戻ったとしても、現在既に超高齢社会の日本ですから、その頃には
更に高齢化が進んでいて、復興前よりも人口やGDPは低下しています。
ですから、経済的な観点から言えば、「元通りにする」という発想では、元通りに
ならないのが現実で、もう少し「攻め」の姿勢を持つ必要があると思います。
確実に経済成長していくアジアに対して、東北の名産物のPRをしていくなどの
「攻めの施策」を取ることで初めて、経済的に震災前の状況に元通りにできる
可能性が出てくると思います。
ちなみに、私は今、親日で知られる台湾の台北で、たくさんの若者たちに
インタビューをしている最中ですが、あれだけ震災後にたくさんの義援金が日本に
送られた超親日エリアの台湾でさえ、20代半ばより上の世代は大変親日ですが、
10代や20代前半の若い世代は、韓流ブームの真っただ中に育ち、日本よりも韓国に
影響を受けている人の方が多くいます。
日本のプレゼンスの低下は、台湾だけの話ではありません。アジア全域で
起こっていることで、超親日エリアである台湾ですら、そういう状況であることを
日本人はかなり深刻に受け入れる必要があると感じています。
Q3. 回答しない
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
常識的に考えて、復興とある程度、明確な関連がある内容に限られるのは当然であろう。
シーシェパード対策や国立競技場の補修に復興予算が使われるのは、明らかに常識の範囲を逸脱している。
シーシェパード対策や国立競技場の補修に復興予算が使われるのは、明らかに常識の範囲を逸脱している。
Q3. 回答する
被災地の方々の生活再建を最優先すべきだ。わが国では、補正予算は総じて
議会やマスコミのチェックが甘くなりがちであるが、そのことを悪用すべきではない。
議会やマスコミのチェックが甘くなりがちであるが、そのことを悪用すべきではない。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
事前査定より事後審査を厳しく
この問題の原因の一つは、震災後の熱気を帯びた中で決められた基本方針・原則が、1年半たった今、あらためて読み返してみると、現状に即していないという点に原因がある、と思う。
平成23年5月10日に決められた、東日本大震災復興構想会議決定の復興構想7原則では、
「原則5:被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。」と記されており、役所はそれをうまく利用しながら拡大解釈し、予算要求をしていったということではないか。
今日的な目で見ると、我々の税金で行われる復興事業なので、使途を被災地に限定し、効果の高いものに思い切って予算を付けることが必要だ。具体的には、雇用効果の高い立地補助金、中小企業の共同施設(倉庫等)の立ち上げ資金を補助するグループ補助金などであろう。
平成23年5月10日に決められた、東日本大震災復興構想会議決定の復興構想7原則では、
「原則5:被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。」と記されており、役所はそれをうまく利用しながら拡大解釈し、予算要求をしていったということではないか。
今日的な目で見ると、我々の税金で行われる復興事業なので、使途を被災地に限定し、効果の高いものに思い切って予算を付けることが必要だ。具体的には、雇用効果の高い立地補助金、中小企業の共同施設(倉庫等)の立ち上げ資金を補助するグループ補助金などであろう。
Q3. 回答する
復興予算のように、19兆という枠がまず決められ、そのもとで各省が予算要求するというやり方では、(積み上げ予算ではないので)どうしても査定が甘くなる。早い者勝ち、アイデアを出したものが勝ち、ということになる。
実は、わが国の補正予算も、景気対策としてまず総額が決まり、その中で各省要求が行われるため、どうしても使い方がルーズになってきた。これが今日の財政悪化を招いた要因の一つである。
わが国の財政状況は、このようなことを容認する余裕はない。厳しい「事後審査体制」を作り上げるべきだ。
事前のチェックより事後チェックというように方針を変え、事後審査で不適切な使い方の予算を要求した官庁の責任を問う(たとえば、各省の一般予算をその分削減する)というような厳しい姿勢で臨むしか方法はないのではないか。
実は、わが国の補正予算も、景気対策としてまず総額が決まり、その中で各省要求が行われるため、どうしても使い方がルーズになってきた。これが今日の財政悪化を招いた要因の一つである。
わが国の財政状況は、このようなことを容認する余裕はない。厳しい「事後審査体制」を作り上げるべきだ。
事前のチェックより事後チェックというように方針を変え、事後審査で不適切な使い方の予算を要求した官庁の責任を問う(たとえば、各省の一般予算をその分削減する)というような厳しい姿勢で臨むしか方法はないのではないか。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
以下の5点を重点柱とする。(1は緊急、2,3は地域の本質的基盤、4,5は未来への道筋)
1三陸鉄道(被災者の生活の足)をはじめとする、被災地の人々の生活インフラの整備が最優先
2そのうえで、産業が復興しなければ、雇用を生まず、地域内での資金循環が起こらず、人口は益々流出する。そこで地域への波及効果の大きい産業、事業、地域に絞って重点支援を行う(特に内陸部の東北自動道沿いの製造業集積地)。
3沿岸部の復興のプライオリティは水産業。拠点漁港の整備と水産加工業の誘致への集中投資によって一挙に国際競争力のある漁業をめざす。その際、ノルウェイーの養殖漁業も参考に。
被災地は農業地域でもあることから、単なる原状回復ではなく、大胆な集約化による大規模農業経営に持っていく機会ととらえて、そのための資金投入を行う。その際、国際競争力のあるオランダの先進的ハウス栽培も参考に。いわば今後の日本全体の農業再生のモデルになることを目指す事業への集中投資。
4地域の強みを生かして、エネルギー先進地域にする取り組みも必要。
具体的には、風力、地熱の開発支援(被災地への重点支援として)、北海道から関東圏に至る超電導による送電網の整備。サハリンからの天然ガスパイプラインの敷設。これらは喫緊の課題である、日本のエネルギー安全保障にも資する。
5高齢化社会対応型の先進医療システムを整備して、社会実験の拠点とする(一応特区にはなっているが、資金投入ももっと大胆に)。
1三陸鉄道(被災者の生活の足)をはじめとする、被災地の人々の生活インフラの整備が最優先
2そのうえで、産業が復興しなければ、雇用を生まず、地域内での資金循環が起こらず、人口は益々流出する。そこで地域への波及効果の大きい産業、事業、地域に絞って重点支援を行う(特に内陸部の東北自動道沿いの製造業集積地)。
3沿岸部の復興のプライオリティは水産業。拠点漁港の整備と水産加工業の誘致への集中投資によって一挙に国際競争力のある漁業をめざす。その際、ノルウェイーの養殖漁業も参考に。
被災地は農業地域でもあることから、単なる原状回復ではなく、大胆な集約化による大規模農業経営に持っていく機会ととらえて、そのための資金投入を行う。その際、国際競争力のあるオランダの先進的ハウス栽培も参考に。いわば今後の日本全体の農業再生のモデルになることを目指す事業への集中投資。
4地域の強みを生かして、エネルギー先進地域にする取り組みも必要。
具体的には、風力、地熱の開発支援(被災地への重点支援として)、北海道から関東圏に至る超電導による送電網の整備。サハリンからの天然ガスパイプラインの敷設。これらは喫緊の課題である、日本のエネルギー安全保障にも資する。
5高齢化社会対応型の先進医療システムを整備して、社会実験の拠点とする(一応特区にはなっているが、資金投入ももっと大胆に)。
Q3. 回答する
1あくまで復興予算は被災地を対象としたものに限るべき。もちろん防災強化のための全国的な取り組みや日本経済全体の活性化も政策としては大事だが、それは復興予算とは別に、明示的に項目を立てて取り組むべき性格のもの。またそれが被災者の心情にも寄り添うことになる。
復興予算を大きく見せたい政治的思惑が官僚による便乗予算を誘発している。見え方、見栄えにしか関心がないのは、「原発ゼロ」の文言が入ることに拘ったのと同根の、この政権の性癖か。
2問2の具体的な使い道のうち、1から5までの順での優先順位。
今回の被災は広範囲であることから、波及効果の高いものから支援を行うとの原則が大事。
復興予算を大きく見せたい政治的思惑が官僚による便乗予算を誘発している。見え方、見栄えにしか関心がないのは、「原発ゼロ」の文言が入ることに拘ったのと同根の、この政権の性癖か。
2問2の具体的な使い道のうち、1から5までの順での優先順位。
今回の被災は広範囲であることから、波及効果の高いものから支援を行うとの原則が大事。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
東日本大震災に見舞われた各都市・町村における早急の復興復旧に向けて直接必要なことに至急使われることが当然である。まずは、それにとこんとん充当されるべきである。それに当てられて余れば、他への流用もできなくはないが、余るはずはなく本来の復興復旧だけですべて使われるはずである。仮に、余ることになれば、復興復旧に使うということで、特別増税を許したものだから、それは一種の詐欺まがいである。
また、そもそも流用等を許せば、各官庁・役所はその使途につきルーズとなり、本来の復旧・復活とはおよそ言い難い科目に使われることが必然である。
また、そもそも流用等を許せば、各官庁・役所はその使途につきルーズとなり、本来の復旧・復活とはおよそ言い難い科目に使われることが必然である。
Q3. 回答する
復興復旧に直接必要なものに限る。復興復旧の中での優先順位は、十分な議論・検討をして速やかに決定・実施(予算執行)する。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
問題の原点は、我が国の財政支出に対する国民からの負託に合致した監視体制が薄弱であることの認識がないことである。先進諸外国ではこれら公(政府)監査のシステムが確立している。故に、先進国のような復興の趣旨、意図に合致した歳出のための会計・評価・公監査制度の法的確立が急務である。
1.問題の原点は、我が国の財政支出に対する国民からの負託に合致した外部独立的監視・監査・評価体制が薄弱であることの認識がないことである。
2.先進諸外国ではこれら公(政府)監査・監察のシステムが確立している。
3.アメリカの例では、カトリーナ台風の復興歳出が不適切になされた経験から、その後の財政危機の際の復興歳出については、不適切支出法を強化し、1ドル以上歳出の法規準拠性・有効性の事前・事後の監査・監察制度を強化して効率的・効果的運営がなされた。
4.現在の国・自治体の財政の無駄の増大の根源はここにある。
5.故に、復興の趣旨、意図に合致した歳出のための会計・評価・公監査制度の法的確立が急務であり、これがなされなければ、現在の国民・市民の政治・行政への期待ギャップは埋まらない。
2.先進諸外国ではこれら公(政府)監査・監察のシステムが確立している。
3.アメリカの例では、カトリーナ台風の復興歳出が不適切になされた経験から、その後の財政危機の際の復興歳出については、不適切支出法を強化し、1ドル以上歳出の法規準拠性・有効性の事前・事後の監査・監察制度を強化して効率的・効果的運営がなされた。
4.現在の国・自治体の財政の無駄の増大の根源はここにある。
5.故に、復興の趣旨、意図に合致した歳出のための会計・評価・公監査制度の法的確立が急務であり、これがなされなければ、現在の国民・市民の政治・行政への期待ギャップは埋まらない。
Q3. 回答する
財政資金の歳出の優先度は、
1.被災地の復興予算のための資金
2.被災地の復興のための経済、行政政策の実施資金
3.1・2のための全国的な経済活性・福祉の政策資金
4.今後の防災のための国土的政策資金
5.今後の防災のための自治体地域的政策的資金
これらを支出するためには問1の制度・仕組みを構築するための立法がまずやらなければならない。これがなされなければ、無駄・不適切支出がまた繰り返されることははっきりしていると思う。
1.被災地の復興予算のための資金
2.被災地の復興のための経済、行政政策の実施資金
3.1・2のための全国的な経済活性・福祉の政策資金
4.今後の防災のための国土的政策資金
5.今後の防災のための自治体地域的政策的資金
これらを支出するためには問1の制度・仕組みを構築するための立法がまずやらなければならない。これがなされなければ、無駄・不適切支出がまた繰り返されることははっきりしていると思う。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
作るべきもの。
それは学校である。
復興開発の基盤は学校
それは学校である。
復興開発の基盤は学校
以下は私が 2011年3月中旬、震災直後に書いたものである。Voice 2011年5月号に掲載された 東日本復興開発銀行という論文に掲載もされている。
作るべきもの。
それは学校である。
復興開発の基盤は学校
今後の東日本を支える人材を今こそ作らなくてはならない。それには学校が必要だ。具体的には、工業高等専門学校と類似の農業、林業、漁業高等専門学校、そして看護大学を設立する。これと連携する大学院も設立する。
復興によりいち早く日常に戻らなければならないのは学生である。勉学こそ最優先に復帰させるものである。学校は全寮制にし、学費も住居費も食費も無料とする。人材は、これまでの農業高校などの教員や、大学、大学院の農学部の教員などを結集する。東日本の大学そのものの全面協力も得る。看護については医学部や大学病院の支援を得る。農業などに関連する官公庁、研究所の職員、研究者も協力する。今、この震災の姿を忘れられない学生、子供たちの意欲を活かし、東日本を支えるために、今こそ徹底した教育を行う。学生たちは、実習(インターンシップ)によって給料も得ることになる。そして、そのインターンを行う現場、農場、病院こそ、復興開発銀行でプロジェクトファイナンスをして設立する。学生達はそこの実習から給料を得る。そして実際に農産品や医療サービスは提供され、東日本の重要な産業となっていく。
このプランを受け入れる、既存の学校、病院などは、公募をする。彼らは自治体と共同で立候補することになる。復興開発銀行は複数の立候補者の中から、最も地域にふさわしいものを選ぶ。
作るべきもの。
それは学校である。
復興開発の基盤は学校
今後の東日本を支える人材を今こそ作らなくてはならない。それには学校が必要だ。具体的には、工業高等専門学校と類似の農業、林業、漁業高等専門学校、そして看護大学を設立する。これと連携する大学院も設立する。
復興によりいち早く日常に戻らなければならないのは学生である。勉学こそ最優先に復帰させるものである。学校は全寮制にし、学費も住居費も食費も無料とする。人材は、これまでの農業高校などの教員や、大学、大学院の農学部の教員などを結集する。東日本の大学そのものの全面協力も得る。看護については医学部や大学病院の支援を得る。農業などに関連する官公庁、研究所の職員、研究者も協力する。今、この震災の姿を忘れられない学生、子供たちの意欲を活かし、東日本を支えるために、今こそ徹底した教育を行う。学生たちは、実習(インターンシップ)によって給料も得ることになる。そして、そのインターンを行う現場、農場、病院こそ、復興開発銀行でプロジェクトファイナンスをして設立する。学生達はそこの実習から給料を得る。そして実際に農産品や医療サービスは提供され、東日本の重要な産業となっていく。
このプランを受け入れる、既存の学校、病院などは、公募をする。彼らは自治体と共同で立候補することになる。復興開発銀行は複数の立候補者の中から、最も地域にふさわしいものを選ぶ。
Q3. 回答する
決定主体が誰か、という問題がある。したがって、公的機関であり、政府、地方自治体からも独立した、東日本復興開発銀行というものをつくり、そこに決定させるべきであった。『voice』2011年5月号「「東日本復興開発銀行」参照
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
従来から大規模災害発生時は、予備費などから特別枠の災害復旧事業予算が組まれてきた。その都度、各省庁などから様々な名目の便乗予算要求が行われてきたが、それらは限られた範囲でしかなかった。しかし、今回の震災復興予算規模は膨大なため、便乗内容は多岐にわたり大胆かつあきれるものも多い。
被害の規模と内容が広範多岐にわたる広域複合大災害にもかかわらず、「東日本大震災からの復興の基本方針」「復興構想7原則」などが短時日で概要策定されたため、対象範囲などの細部規定や具体的枠決めが精査されないまま、被災自治体及び各省庁からの要求額を性急に積み上げ復興予算とした。その結果、細部に目の届かないアバウト予算にならざるを得なかった。加えて、各省庁からの便乗事業や復興とは無関係事業などをを割り込ませないための客観的検証システムを設けなかったこと。予算と税金の使途審議という国会議員の最大責務が果たされず、「復興予算のあり方審議委員会」も頻繁に開かない政府や国会にも責任がある。
復興予算範囲は本来「被災地の復興・被災者生活再建に限る」とすべきを「全国的に・・・防災・減災等の施策」というあいまい表現の復興方針を国会が認めたことがこうした問題を引き起こしている。それを奇貨とし、過度の事業仕分けや予算削減で積み残されていた事案を処理するため、一部省庁で拡大解釈され被災地復興とかけ離れた事業に流用されている。これらは被災地・被災者に対し厳に恥ずべき行為である。
言うまでもないが、増税という過大な国民負担によって賄われる貴重な復興予算は、被災者支援や被災地復興の他に流用すべきではない。政府は再度予算内容精査を即時実施するとともに、各省庁に猛省を促すべきである。また、そうした火事場泥棒が横行することを想定せず、ただただ「急げ、急げ」と言ってきた私自身反省しつつ忸怩たる思いである。
被害の規模と内容が広範多岐にわたる広域複合大災害にもかかわらず、「東日本大震災からの復興の基本方針」「復興構想7原則」などが短時日で概要策定されたため、対象範囲などの細部規定や具体的枠決めが精査されないまま、被災自治体及び各省庁からの要求額を性急に積み上げ復興予算とした。その結果、細部に目の届かないアバウト予算にならざるを得なかった。加えて、各省庁からの便乗事業や復興とは無関係事業などをを割り込ませないための客観的検証システムを設けなかったこと。予算と税金の使途審議という国会議員の最大責務が果たされず、「復興予算のあり方審議委員会」も頻繁に開かない政府や国会にも責任がある。
復興予算範囲は本来「被災地の復興・被災者生活再建に限る」とすべきを「全国的に・・・防災・減災等の施策」というあいまい表現の復興方針を国会が認めたことがこうした問題を引き起こしている。それを奇貨とし、過度の事業仕分けや予算削減で積み残されていた事案を処理するため、一部省庁で拡大解釈され被災地復興とかけ離れた事業に流用されている。これらは被災地・被災者に対し厳に恥ずべき行為である。
言うまでもないが、増税という過大な国民負担によって賄われる貴重な復興予算は、被災者支援や被災地復興の他に流用すべきではない。政府は再度予算内容精査を即時実施するとともに、各省庁に猛省を促すべきである。また、そうした火事場泥棒が横行することを想定せず、ただただ「急げ、急げ」と言ってきた私自身反省しつつ忸怩たる思いである。
Q3. 回答する
復興予算の使い道は、被災地域・被災者にかかわることに限定すべきである。
執行の優先順位は
1、被災者の生活再建にかかわること
2、被災地インフラ復旧にかかわること
3、被災地の農・漁・商工業など産業復興にかかわること
4、災害に強い街づくりにかかわること
で、さらに①緊急度②重要度③結果の重大性等を勘案して優先順位基準を設ける。
復興といっても、本来短期事業、長期事業があるが、復興事業となると短期の期限内で完了することが求められている。しかし、県、市町村とも多岐にわたる復興事業を短期間に消化するための人材が不足しており、すでに各所でオーバーワークに陥っている。緊急性の低い復興事業は柔軟性のある期限を設けることも必要。
そして、適正・迅速執行を推進するための客観的でかつ一定権限を持たせた第三者で構成する「復興予算執行監視オンプズマン」制度を設け、執行状況を一定期間ごとに国会に報告開示せしめる必要がある。
そのほかの全国的に緊急を要する防災・減災等に資する事業は、堂々と別途予算要求してよいのではなかろうか。必要であれば、その受け皿として特定地域に限らず全国を対象とした「国民の安全に資する防災・減災にかかわる特別措置法」制定も検討すべきである。その内容と支える原資を考える「国民会議」を設置する必要がある。
執行の優先順位は
1、被災者の生活再建にかかわること
2、被災地インフラ復旧にかかわること
3、被災地の農・漁・商工業など産業復興にかかわること
4、災害に強い街づくりにかかわること
で、さらに①緊急度②重要度③結果の重大性等を勘案して優先順位基準を設ける。
復興といっても、本来短期事業、長期事業があるが、復興事業となると短期の期限内で完了することが求められている。しかし、県、市町村とも多岐にわたる復興事業を短期間に消化するための人材が不足しており、すでに各所でオーバーワークに陥っている。緊急性の低い復興事業は柔軟性のある期限を設けることも必要。
そして、適正・迅速執行を推進するための客観的でかつ一定権限を持たせた第三者で構成する「復興予算執行監視オンプズマン」制度を設け、執行状況を一定期間ごとに国会に報告開示せしめる必要がある。
そのほかの全国的に緊急を要する防災・減災等に資する事業は、堂々と別途予算要求してよいのではなかろうか。必要であれば、その受け皿として特定地域に限らず全国を対象とした「国民の安全に資する防災・減災にかかわる特別措置法」制定も検討すべきである。その内容と支える原資を考える「国民会議」を設置する必要がある。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
各方面の要望をまとめた案ではなく、復興支援、災害対策を念頭に置いた構想をトップダウンで大胆に推進すべし。災害時に活躍する病院船建造のチャンスではないか。
具体的には、次の3つである。
第一に、大地震、津波に襲われても、その地域の住民の生活条件が一変してしまうことがないような環境作りをするために、予算を支出すべき。再利用可能エネルギー活用のための投資に使う。原子力発電に多くのことを期待できないことを考えると、風力発電、太陽光の大規模な施設を東北地方に展開する。陸上にはそのスペースがないのであれば、浮きドック式の再利用可能エネルギー活用施設を海上に造る。再利用可能エネルギー設備であれば、他の方式でもよい。津波に遭遇して原発施設の危機という事態にならないための施設であるから、復興予算の使途としてふさわしい。そして、日常の電力不足解消への一助になる。そのために5兆円を使う。その設計、建設は経営が苦しい日本の企業に発注する。
第二に、被災者を救出して医療を迅速に施すための病院船を5隻建造する。震災のとき、震災地域の近くに停泊してけが人を治療したり、船舶を緊急の宿泊施設にしたりする。戦前、日本は病院船を持っていたが、いま海上自衛隊には専用病院船が一隻もない。1万5千トン級で、緊急時には1隻で5千人は収容できるようにする。すると、5隻で2万5千人が宿泊できる。航空母艦は一隻あたり5千人以上が乗艦しており、その程度の人数の収容は可能だろう。そのための医療システムを確保する。医師、看護士らの確保には莫大なコストがかかるので、その育成のための経費も確保する。また、緊急時の医療活動だけのための病院船にするとコストがかかるので、米軍の方式に学んで普段は輸送艦や揚陸艦として離島防衛にも活用できるような構造にする。だから海上自衛隊が運用する。ヘリ空母としての機能も必要になるが、主な任務は医療活動であるので、手術室や医療機材を積んである艦船をイメージしていただきたい。その建造費と運用経費にはいくらかかるだろうか。一般的な病院船は一隻220億円程度というが、揚陸艦としても併用する軍艦としての頑丈な作りをするため、余分の予算が必要になる。1隻が3千億円。5隻で1兆5千億円。ちなみに航空母艦は5千億円程度かかる。病院船は海外の災害時にも治療支援のために派遣する。平和維持活動に利用できるので、日本の国際貢献の活動に使える。したがって病院船には常に医療チームが乗り組み、ヘリコプターを持っていることが必要になる。病院船で働くお医者さんをたくさん育ててゆく必要があるので、東北地方の優秀な若者で学費が足りない学生のための医学奨学金を設ける。防衛医科大学の定員を増やしても良い。医科大学を大幅拡充して医療システムをトータルに整備するために3千億円。
第三に、大地震に強い工業団地を東北地方の各県に造成する。リアス式海岸は津波に弱いのであれば、リアス式海岸を埋め立ててしまって、直線の海岸にする。風光明媚なリアス式海岸の風景が失われてしまうことへの反対は起きるが、背に腹は換えられない。災害復興と今後の対策のためだ。そこには新しい土地が生まれる。韓国のインチョンや中国の天津の埋め立て工業団地がモデルになる。そこには高い防波堤が必要になる。職住近接の大規模団地である。精密機械の工業団地にして、日本の輸出産業復興の一助にするために、輸出産業を誘致する。既存のインフラも活用するために、すでに完成している高速道路と地方空港にアクセスしやすいところに造成する。輸送路は大事だ。この新規工業団地には、海外の日系企業の工場を日本に呼び戻す。中国から引き揚げてくるであろう日本企業の工場をここに誘致する。これは被災地の産業起こしのための経費として使用することになるので、復興予算の正しい使い方である。このために5兆円。
いかがでしょうか。
第一に、大地震、津波に襲われても、その地域の住民の生活条件が一変してしまうことがないような環境作りをするために、予算を支出すべき。再利用可能エネルギー活用のための投資に使う。原子力発電に多くのことを期待できないことを考えると、風力発電、太陽光の大規模な施設を東北地方に展開する。陸上にはそのスペースがないのであれば、浮きドック式の再利用可能エネルギー活用施設を海上に造る。再利用可能エネルギー設備であれば、他の方式でもよい。津波に遭遇して原発施設の危機という事態にならないための施設であるから、復興予算の使途としてふさわしい。そして、日常の電力不足解消への一助になる。そのために5兆円を使う。その設計、建設は経営が苦しい日本の企業に発注する。
第二に、被災者を救出して医療を迅速に施すための病院船を5隻建造する。震災のとき、震災地域の近くに停泊してけが人を治療したり、船舶を緊急の宿泊施設にしたりする。戦前、日本は病院船を持っていたが、いま海上自衛隊には専用病院船が一隻もない。1万5千トン級で、緊急時には1隻で5千人は収容できるようにする。すると、5隻で2万5千人が宿泊できる。航空母艦は一隻あたり5千人以上が乗艦しており、その程度の人数の収容は可能だろう。そのための医療システムを確保する。医師、看護士らの確保には莫大なコストがかかるので、その育成のための経費も確保する。また、緊急時の医療活動だけのための病院船にするとコストがかかるので、米軍の方式に学んで普段は輸送艦や揚陸艦として離島防衛にも活用できるような構造にする。だから海上自衛隊が運用する。ヘリ空母としての機能も必要になるが、主な任務は医療活動であるので、手術室や医療機材を積んである艦船をイメージしていただきたい。その建造費と運用経費にはいくらかかるだろうか。一般的な病院船は一隻220億円程度というが、揚陸艦としても併用する軍艦としての頑丈な作りをするため、余分の予算が必要になる。1隻が3千億円。5隻で1兆5千億円。ちなみに航空母艦は5千億円程度かかる。病院船は海外の災害時にも治療支援のために派遣する。平和維持活動に利用できるので、日本の国際貢献の活動に使える。したがって病院船には常に医療チームが乗り組み、ヘリコプターを持っていることが必要になる。病院船で働くお医者さんをたくさん育ててゆく必要があるので、東北地方の優秀な若者で学費が足りない学生のための医学奨学金を設ける。防衛医科大学の定員を増やしても良い。医科大学を大幅拡充して医療システムをトータルに整備するために3千億円。
第三に、大地震に強い工業団地を東北地方の各県に造成する。リアス式海岸は津波に弱いのであれば、リアス式海岸を埋め立ててしまって、直線の海岸にする。風光明媚なリアス式海岸の風景が失われてしまうことへの反対は起きるが、背に腹は換えられない。災害復興と今後の対策のためだ。そこには新しい土地が生まれる。韓国のインチョンや中国の天津の埋め立て工業団地がモデルになる。そこには高い防波堤が必要になる。職住近接の大規模団地である。精密機械の工業団地にして、日本の輸出産業復興の一助にするために、輸出産業を誘致する。既存のインフラも活用するために、すでに完成している高速道路と地方空港にアクセスしやすいところに造成する。輸送路は大事だ。この新規工業団地には、海外の日系企業の工場を日本に呼び戻す。中国から引き揚げてくるであろう日本企業の工場をここに誘致する。これは被災地の産業起こしのための経費として使用することになるので、復興予算の正しい使い方である。このために5兆円。
いかがでしょうか。
Q3. 回答する
復興予算として5年間で19兆円規模の予算が予定されている。これは大変な金額だ。それが被災地に復興予算が行き渡っていないと聞くと、もう少し詳しく知りたくなる。すると「復興予算が使い残されており、8月時点で、5.8兆円が未消化だ」と言う。それに被災地以外の事案に復興予算が使われているという話を聞くと、「本来の予算の趣旨とは違うのではないか」と国民は思うだろう。政府方針が「被災地域の復興は、活力ある日本の再生の先導的役割を担うものであり、また、日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はないとの認識を共有する」ことなので、「日本経済全体の活性化も復興予算の使い道に含まれている」という説明が出てきた。これは拡大解釈だ。
復興予算の使い方の指針は次の3つ。(1)被災地域の東北地方が力強い産業活動をするためのインフラ改善(2)今後の震災に際して、危機管理、人命救助、医療活動に役立つ装備の導入、制度の設立、施設の建設に経費を使う。(3)また、緊縮財政のおり、1つの目的にしか使用できないものに税金を投入するのではなくて、複数の目的に同時に活用できるものに投資する。例えば、海上自衛隊の病院船建造は、救難救助、海外平和協力活動、離島防衛の3つに役立つ。
復興予算の使い方の指針は次の3つ。(1)被災地域の東北地方が力強い産業活動をするためのインフラ改善(2)今後の震災に際して、危機管理、人命救助、医療活動に役立つ装備の導入、制度の設立、施設の建設に経費を使う。(3)また、緊縮財政のおり、1つの目的にしか使用できないものに税金を投入するのではなくて、複数の目的に同時に活用できるものに投資する。例えば、海上自衛隊の病院船建造は、救難救助、海外平和協力活動、離島防衛の3つに役立つ。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
復興予算はあくまでも被災地域の復興のために使われるべきもの。当たり前です。
『復興予算はあくまでも被災地域の復興のために使われるべきもの』。当たり前です。
少なくとも、被災地以外のあちこちにある、特に国の出先機関と含む官公庁の新築・改築には使うべきでない。調査捕鯨の関連にも使うべきではない。
こんなことをして、小学生・中学生の「社会科」で『復興予算はこんな使われ方をしています』って説明出来ますか?
子供たちに説明のしようのない使い方を考え出した官僚1人、1人に被災地に1か月ほど入って、1年7か月経った被災地の状況をじっくりと見てきたらいい。
これは、結局は、与野党含む国会議員が予算は成立させても、その使われ方についてはまるでノーチェックで、朝から晩まで政争・政局に明け暮れているから、頭のいい官僚がその隙をついた、ということだろうか。
少なくとも、被災地以外のあちこちにある、特に国の出先機関と含む官公庁の新築・改築には使うべきでない。調査捕鯨の関連にも使うべきではない。
こんなことをして、小学生・中学生の「社会科」で『復興予算はこんな使われ方をしています』って説明出来ますか?
子供たちに説明のしようのない使い方を考え出した官僚1人、1人に被災地に1か月ほど入って、1年7か月経った被災地の状況をじっくりと見てきたらいい。
これは、結局は、与野党含む国会議員が予算は成立させても、その使われ方についてはまるでノーチェックで、朝から晩まで政争・政局に明け暮れているから、頭のいい官僚がその隙をついた、ということだろうか。
Q3. 回答する
壊れたビル、がれきの山、跡形もなくなった住宅地、住み慣れた家は残ってても、眼には見えない『モノ』が覆っていて住めない、いや、行くこともできない地域。まだ帰ってこない父・母・わが子・親戚縁者・・・。地域で採れた食料品は大都会では買ってくれない。がれきはどこも受け入れてくれない。
そんな状況がずっと続いているのに、『復興予算はあくまでも被災地域の復興のために使われるべきもの』。当たり前です。
住まいを優先するか、子供のための学校なり、遊び場を優先するのか、医療施設を優先するのか、市役所・町役場の改築・新築を優先するのか、漁港を含めた地場産業基盤を優先するのか、除染を優先するのか、町そのものの高台への移転を優先するのか、がれきの撤去を優先するのか・・・などなどは、『その地域の住民(被災者)が決めればいい』。
東京の真ん中で、高価な洋服・和服を着て、普段と変わらない生活をしている学者・評論家とか医者・弁護士・ジャーナリストらが決めることではない。
そんな状況がずっと続いているのに、『復興予算はあくまでも被災地域の復興のために使われるべきもの』。当たり前です。
住まいを優先するか、子供のための学校なり、遊び場を優先するのか、医療施設を優先するのか、市役所・町役場の改築・新築を優先するのか、漁港を含めた地場産業基盤を優先するのか、除染を優先するのか、町そのものの高台への移転を優先するのか、がれきの撤去を優先するのか・・・などなどは、『その地域の住民(被災者)が決めればいい』。
東京の真ん中で、高価な洋服・和服を着て、普段と変わらない生活をしている学者・評論家とか医者・弁護士・ジャーナリストらが決めることではない。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
良心的な範囲での復興ということを考えるべきです。正直言ってそれらの境界にまで目を光らせなくてはならないというのは妙になさけない。
誠に信用おけないという感じがします。
誠に信用おけないという感じがします。
Q3. 回答する
復興支援ということなら税金を取り上げやすいと考えたとしか思えない。
少なくとも調査捕鯨などについての対策費は?です。
純粋に復興に優先されるべきです。
少なくとも調査捕鯨などについての対策費は?です。
純粋に復興に優先されるべきです。
Q2. 「1 - 回答する(問2でコメント)」の回答理由
評価の主体、評価の方法、評価結果の予算編成、政策形成への反映の仕方に
大きな問題がありそうです。
大きな問題がありそうです。
今回の「復興予算の使い方」を、その「復興予算」用途の「適切・不適切」、「けしからん」の議論に
閉じてはいけないと思います。
国家の政策サイクル(企画立案、実施、評価、反映)、予算執行行政
(予算編成、財源確保、執行、予算評価、修正)のどこに問題があるのかを指摘、
あるべき姿の共有をしなければ各論的一過性の議論になるのではないでしょうか。
企業経営にあてはまれば至極あたりまえの予算取り扱いのルールが、
国においてはなされていないのでは、というあたりまえの疑問が持ちます。
政府の予算編成は各府省を中心に展開しており、予算編成・執行に重要な影響を
与える制度、組織としては政策評価と総務省行政成果局があるようです。
また財務 省主計局では 財政全体の制約を踏まえながら主計官が政策の優先順位や
執行手段の適否などを通じて評価する、とされています。
政策評価制度は政策評価法にもとづいて導入されており、各府省の評価委員会、
さらに全体を横断的な視野で評価を行う総務省評価委員会の二重構造があります。
まず、ここからも分かるように予算執行、政策評価を行う主体があまり多岐に渡り、
また横断的評価を行う総務省評価委員会の提言効力が保証されていないのも問題のようです。
また政策評価の考え方は、「合理的形成仮設」と「組織的形成仮設」、前者は
定量的で評価結果が政策形成にに反映され、後者は極めて情報共有を目的に
予算編成・政策形成には影響なし、という実にわかりづらい評価方法が用いられています。
さて、今回の予算執行の問題点が、そのどこに問題があるのか、
評価の主体、評価の方法、評価結果の予算編成、政策形成への反映の仕方に
大きな問題がありそうです。
閉じてはいけないと思います。
国家の政策サイクル(企画立案、実施、評価、反映)、予算執行行政
(予算編成、財源確保、執行、予算評価、修正)のどこに問題があるのかを指摘、
あるべき姿の共有をしなければ各論的一過性の議論になるのではないでしょうか。
企業経営にあてはまれば至極あたりまえの予算取り扱いのルールが、
国においてはなされていないのでは、というあたりまえの疑問が持ちます。
政府の予算編成は各府省を中心に展開しており、予算編成・執行に重要な影響を
与える制度、組織としては政策評価と総務省行政成果局があるようです。
また財務 省主計局では 財政全体の制約を踏まえながら主計官が政策の優先順位や
執行手段の適否などを通じて評価する、とされています。
政策評価制度は政策評価法にもとづいて導入されており、各府省の評価委員会、
さらに全体を横断的な視野で評価を行う総務省評価委員会の二重構造があります。
まず、ここからも分かるように予算執行、政策評価を行う主体があまり多岐に渡り、
また横断的評価を行う総務省評価委員会の提言効力が保証されていないのも問題のようです。
また政策評価の考え方は、「合理的形成仮設」と「組織的形成仮設」、前者は
定量的で評価結果が政策形成にに反映され、後者は極めて情報共有を目的に
予算編成・政策形成には影響なし、という実にわかりづらい評価方法が用いられています。
さて、今回の予算執行の問題点が、そのどこに問題があるのか、
評価の主体、評価の方法、評価結果の予算編成、政策形成への反映の仕方に
大きな問題がありそうです。
Q3. 回答しない
2. 回答を控える
該当する回答がありません

※ご入力いただいた情報の取り扱いについては、『利用目的』をご覧下さい。
また、メッセージを送信される前には『フジテレビホームページをご利用される方へ』を必ずお読み下さい。
※送信内容に個人情報は記載しないようお願いします。
※投稿する際は、件名を編集しないでください。
また、メッセージを送信される前には『フジテレビホームページをご利用される方へ』を必ずお読み下さい。
※送信内容に個人情報は記載しないようお願いします。
※投稿する際は、件名を編集しないでください。

コメントはありません