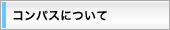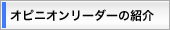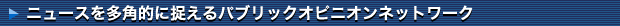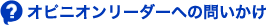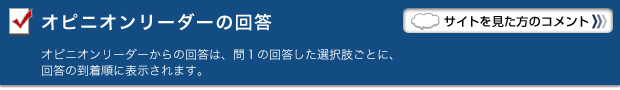社会・公共
日本に国会議員って何人必要?
1:設問テーマの背景(facts)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8月27日、自民党、公明党は今週29日水曜日に野田首相への問責決議案を参議院に共同提出する方針を決めました。問責決議案の提出後は、審議拒否の構えを示しており、事実上、国会が空転したまま閉会予定の9月8日を迎える可能性が高まっています。
終盤国会を迎え、衆院選挙制度改革は、各党からさまざまな提案がありながらも8月27日、衆院政治倫理確立・公職選挙法改正特別委員会で野党欠席のまま民主党が、自らの案(主な内容は、
〈1〉5県で小選挙区を1減する「0増5減」〈2〉小選挙区比例代表連用制の一部導入〈3〉比例定数の40削減)を
単独で強行採決、可決しました。しかし、野党側の反対もあり、今国会での成立は困難な情勢です。
選挙制度改革法案は、2つの意味で極めて重要な法案となっています。ひとつは、社会保障・税一体改革を進めるにあたり、野田総理は議員定数削減を「身を切る改革」の目玉として位置づけているためで、この点については自民党、公明党は同調の姿勢を見せています。
もうひとつは、一票の格差の問題からです。
2009年の衆議院選挙は、一票の格差が最大2.3倍であったことから、最高裁が法の下の平等を保障した憲法に反するとして違憲状態と判断しており、この状況の改善がなされないまま次の選挙が行われた場合、最高裁が、選挙無効判決を出す可能性も指摘されています。
こうした国会の動きの一方で、8月26日、大阪維新の会代表の橋下徹大阪市長は、国は権限と財源を地方に移譲して外交や社会保障などに専念すべきという主張とともに、「国全体の仕事を絞り込めば480なんて数はいらない。維新として半減ということをしっかり出す」と述べ、次期衆院選の公約「維新八策」に衆院定数の半減を盛り込むことを明言しました。維新八策には、すでに参院の廃止も視野に入れた二院制の見直しも盛り込まれており、国会議員の人数を大きく削減する内容となる見通しです。
2:番組として(ouraim)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
国会議員の定数をどのように考えるかについての議論は、議席数が具体的でありながらもその論拠、論点については十分に整理されていないと思われます。
加えて、前述のように、定数是正の議論には、一票の格差問題、財政状況を踏まえた歳費削減や、国会議員の活動内容とそのための適正費用の問題などが混在しています。
そこで、今回、「ザ・コンパス」では、そもそも「日本に国会議員は何人必要か」についての考察から出発することで、国会議員の定数に関わるいくつかの論点を整理して考えることができればと思います。
(参考情報)
・国会議員の定数:衆議院480人 参議院242人
・国会議員一人あたりの歳費(議員給与):月129万4千円
(歳費法より、但し2012年5月から二年間は、年額270万円を
「身を切る改革」の一環として削減)
・国会議員一人あたりの年間経費(歳費含む)は、
文書通信交通滞在費、立法事務費、賞与、交通機関の
無料クーポン公設秘書給与を含めると、年約7500万円
(2009年国会答弁より)
・各政党には、政党助成金として、総額319億4000万円/年が国から
支払われています。
・各国の議員数(共同通信社 世界年鑑より)
人口 議員数 1議員あたりの人口
-スウェーデン 886万人 、349人 、 2.5万人に1議員
-フィンランド 516万人 200人 2.6万人に1議員
-ノルウェー 444万人 165人 2.7万人に1議員
-デンマーク 531万人 179人 3.0万人に1議員
-スイス 716万人 246人 2.9万人に1議員
-イギリス 5950万人 1050人 5.7万人に1議員
-イタリア 5737万人 955人 6.0万人に1議員
-スペイン 3942万人 607人 6.5万人に1議員
-フランス 5952万人 898人 6.6万人に1議員
-オランダ 1576万人 225人 7.0万人に1議員
-カナダ 3075万人 405人 7.6万人に1議員
-ドイツ 8226 755 10.9万人に1議員
-日本 12000万人 722人 16.4万人に1議員
-アメリカ合州国 28142万人 535 52.6万人に1議員
8月27日、自民党、公明党は今週29日水曜日に野田首相への問責決議案を参議院に共同提出する方針を決めました。問責決議案の提出後は、審議拒否の構えを示しており、事実上、国会が空転したまま閉会予定の9月8日を迎える可能性が高まっています。
終盤国会を迎え、衆院選挙制度改革は、各党からさまざまな提案がありながらも8月27日、衆院政治倫理確立・公職選挙法改正特別委員会で野党欠席のまま民主党が、自らの案(主な内容は、
〈1〉5県で小選挙区を1減する「0増5減」〈2〉小選挙区比例代表連用制の一部導入〈3〉比例定数の40削減)を
単独で強行採決、可決しました。しかし、野党側の反対もあり、今国会での成立は困難な情勢です。
選挙制度改革法案は、2つの意味で極めて重要な法案となっています。ひとつは、社会保障・税一体改革を進めるにあたり、野田総理は議員定数削減を「身を切る改革」の目玉として位置づけているためで、この点については自民党、公明党は同調の姿勢を見せています。
もうひとつは、一票の格差の問題からです。
2009年の衆議院選挙は、一票の格差が最大2.3倍であったことから、最高裁が法の下の平等を保障した憲法に反するとして違憲状態と判断しており、この状況の改善がなされないまま次の選挙が行われた場合、最高裁が、選挙無効判決を出す可能性も指摘されています。
こうした国会の動きの一方で、8月26日、大阪維新の会代表の橋下徹大阪市長は、国は権限と財源を地方に移譲して外交や社会保障などに専念すべきという主張とともに、「国全体の仕事を絞り込めば480なんて数はいらない。維新として半減ということをしっかり出す」と述べ、次期衆院選の公約「維新八策」に衆院定数の半減を盛り込むことを明言しました。維新八策には、すでに参院の廃止も視野に入れた二院制の見直しも盛り込まれており、国会議員の人数を大きく削減する内容となる見通しです。
2:番組として(ouraim)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
国会議員の定数をどのように考えるかについての議論は、議席数が具体的でありながらもその論拠、論点については十分に整理されていないと思われます。
加えて、前述のように、定数是正の議論には、一票の格差問題、財政状況を踏まえた歳費削減や、国会議員の活動内容とそのための適正費用の問題などが混在しています。
そこで、今回、「ザ・コンパス」では、そもそも「日本に国会議員は何人必要か」についての考察から出発することで、国会議員の定数に関わるいくつかの論点を整理して考えることができればと思います。
(参考情報)
・国会議員の定数:衆議院480人 参議院242人
・国会議員一人あたりの歳費(議員給与):月129万4千円
(歳費法より、但し2012年5月から二年間は、年額270万円を
「身を切る改革」の一環として削減)
・国会議員一人あたりの年間経費(歳費含む)は、
文書通信交通滞在費、立法事務費、賞与、交通機関の
無料クーポン公設秘書給与を含めると、年約7500万円
(2009年国会答弁より)
・各政党には、政党助成金として、総額319億4000万円/年が国から
支払われています。
・各国の議員数(共同通信社 世界年鑑より)
人口 議員数 1議員あたりの人口
-スウェーデン 886万人 、349人 、 2.5万人に1議員
-フィンランド 516万人 200人 2.6万人に1議員
-ノルウェー 444万人 165人 2.7万人に1議員
-デンマーク 531万人 179人 3.0万人に1議員
-スイス 716万人 246人 2.9万人に1議員
-イギリス 5950万人 1050人 5.7万人に1議員
-イタリア 5737万人 955人 6.0万人に1議員
-スペイン 3942万人 607人 6.5万人に1議員
-フランス 5952万人 898人 6.6万人に1議員
-オランダ 1576万人 225人 7.0万人に1議員
-カナダ 3075万人 405人 7.6万人に1議員
-ドイツ 8226 755 10.9万人に1議員
-日本 12000万人 722人 16.4万人に1議員
-アメリカ合州国 28142万人 535 52.6万人に1議員
Q1:問1:国会議員の人数をどう思いますか?
| 1.多いと思う | |
| 2.適正範囲内であると思う | |
| 3.少ないと思う | |
| 4.その他(設問・選択肢以外の視点・考え方) |
Q2:問1の回答理由をお聞かせください。
適正と思われる人数について(できれば衆・参の別を踏まえ)
ご意見をお聞かせください。(参考情報では各国の議員数を紹介しております。)
適正と思われる人数について(できれば衆・参の別を踏まえ)
ご意見をお聞かせください。(参考情報では各国の議員数を紹介しております。)
Q3:現在の衆議院選挙制度は、最高裁によって違憲状態であるとされています。この違憲状態は、最高裁が示した期限を過ぎて尚、今国会でも解消されず、事実上放置されています。
この事態をどうお考えになりますか。可能であれば今後どうすべきかも合わせ、ご意見をお聞かせください。
この事態をどうお考えになりますか。可能であれば今後どうすべきかも合わせ、ご意見をお聞かせください。
Q4:現在の国会議員の活動内容と、歳費など国費から国会議員に支払われる活動費との関係についてどうお考えになりますか。ご意見をお聞かせください。
1. 多いと思う
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
地方にも議員がおり、国会議員については、多額の歳費をもらっていながら、めぼしい仕事をしていない議員も少なくない。今後、少子化による人口減少が進むことも考えると、人数については衆議院が300人くらい、参議院は200人くらいで運営していくことも可能
地方にも議員がおり、国会議員については、多額の歳費をもらっていながら、めぼしい仕事をしていない議員も少なくない。今後、少子化による人口減少が進むことも考えると、人数については衆議院が300人くらい、参議院は200人くらいで運営していくことも可能ではないか。
ただし、各議員が仕事のできる能力と技能を備えること、きちんと仕事ができる体力、人格識見が必要であるし、そういう議員を選ばなければならない。人数を減らすことで、国民からの監視もおよびやすくなるし、評価もしやすい(人数が多いと、目が届きにくい議員も出てくる)。また、かえって、もっと政策中心の政治もやりやすくなるのではないか。あまり大勢いても議論にならない。手分けをしていろいろな委員会で仕事をしてもらうにしても、できるはず。
そうした大変な仕事をしてもらう体力と、将来の日本のビジョンを考えてもらう知力・集中力が必要があることからすると、衆議院については65歳、参議院については75歳くらいの定年制を設けることも考える必要があるのではないか。何も議員として、国会で議決に参加しなくても、意見を述べたり、様々な活動はできるはずであって、歳費をもらいつづけながら、いつまでも国会議員としての職位を占拠している必要はないだろう。
なお、いろいろな専門分野はそれぞれの領域で議員以外の人材を使うこともできるので、何も国会議員である必要はないし、政治は国会議員だけでやるわけではない。
ただし、各議員が仕事のできる能力と技能を備えること、きちんと仕事ができる体力、人格識見が必要であるし、そういう議員を選ばなければならない。人数を減らすことで、国民からの監視もおよびやすくなるし、評価もしやすい(人数が多いと、目が届きにくい議員も出てくる)。また、かえって、もっと政策中心の政治もやりやすくなるのではないか。あまり大勢いても議論にならない。手分けをしていろいろな委員会で仕事をしてもらうにしても、できるはず。
そうした大変な仕事をしてもらう体力と、将来の日本のビジョンを考えてもらう知力・集中力が必要があることからすると、衆議院については65歳、参議院については75歳くらいの定年制を設けることも考える必要があるのではないか。何も議員として、国会で議決に参加しなくても、意見を述べたり、様々な活動はできるはずであって、歳費をもらいつづけながら、いつまでも国会議員としての職位を占拠している必要はないだろう。
なお、いろいろな専門分野はそれぞれの領域で議員以外の人材を使うこともできるので、何も国会議員である必要はないし、政治は国会議員だけでやるわけではない。
Q3. コメントする
国会の機能不全。政党の党利党略で、既存政党のこれまでの取り組みは、まったく評価に値しない。
こうした状況を打破できるような政治勢力による是正を望むし、真剣にこれに取り組む政治集団を支持したい。
もうそろそろ、あまりにも都会と比べて少数の票しかとらない議員については、当選無効の判決を出してもよいころではないか。
こうした状況を打破できるような政治勢力による是正を望むし、真剣にこれに取り組む政治集団を支持したい。
もうそろそろ、あまりにも都会と比べて少数の票しかとらない議員については、当選無効の判決を出してもよいころではないか。
Q4. コメントする
歳費が高いから、何もしないで遊んでいる議員も中にはいるという指摘があるが、もっともだろうと思う。逆に本当にやりたい政治目標があれば、歳費が安くても政治をやりたいという人はいくらでもいるだろう。また、海外と比べても日本の国会議員は無条件に高すぎる歳費をもらっている。
基本的な給与は500万円程度にして、立法等に必要な合理的な活動に実費ベースで支給するような制度にすべきではないか。その際に、政策秘書など、本当に役に立つスタッフを政党や政治家が合理的に使えるような体制を構築することは必要だろう。
基本的な給与は500万円程度にして、立法等に必要な合理的な活動に実費ベースで支給するような制度にすべきではないか。その際に、政策秘書など、本当に役に立つスタッフを政党や政治家が合理的に使えるような体制を構築することは必要だろう。
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
衆議院240名程度,参議院120名程度
まず,比例代表制(衆議院180名,参議院96名)をなくし,その上で憲法43条の「全国民を代表する選挙された議員」という趣旨をいっそう自由委任の要素を強く考えると,現状において,財政の逼迫した国政を運営するというためには,上記の程度での議員数で対応すべきと考える。
まず,比例代表制(衆議院180名,参議院96名)をなくし,その上で憲法43条の「全国民を代表する選挙された議員」という趣旨をいっそう自由委任の要素を強く考えると,現状において,財政の逼迫した国政を運営するというためには,上記の程度での議員数で対応すべきと考える。
Q3. コメントする
近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理を無視するものである。
判決で指摘されたことを解消しようとしないこと自体が議員としての自覚を欠いている。
判決で指摘されたことを解消しようとしないこと自体が議員としての自覚を欠いている。
Q4. コメントする
議員によっては,支払われる歳費に見合う活動をしていると評価できる者もいるであろうが,何をしているのかまったく分からない議員のほうが多い。ことに「チルドレン」と呼ばれる議員の中には,議員としての能力があるとはとても思えない者がいる。なぜなら議員としての活動がまったく伝わってこないからである。このような者に税金を歳費として支払うことはまったくない。
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
今の面子なら国会議員は一人でも多すぎる!元老院に習い、30人でしっかり議論すべきだ。道州制が前提だが今のままのでっかい議場でいったい何ができるのか?アホボンの原稿棒読みを議員どもが居眠りしながら聞いている醜態をいつまで曝すのか?
現状なら国会議員など一人でも多すぎる!全くの役立たずだからだ。
それに今回の定数是正の法案はいったいどこのバカが書いた筋書きか?国民をなめるのもほどほどにしろ!恥を知れ!何が「身を切る改革」だ!与党案なら湯葉の皮一枚切れないぞ!
定数是正の最低条件はまず参議院廃止!
アホのくせに偉そうに混雑する東京の街をでっかい公用車で走り回るな!従って公用車廃止!移動はすべてスズキの軽で!道州制が前提だが、そうなると定数はローマの元老院規模の30人程度でいいのでは。選び方もローマに習い、いろいろなパターンで選ぶべきだ。
30人である根拠は
①だいたいいろいろな道のまともに使える専門家ってこの国に30人ぐらいしかいないぞ。心臓外科医の数がその典型的な例だが、全国でまともにしっかり手術ができる(自分の親族を負かせてよい)心臓外科医は全国で30人程度だ。これは脳外科でも整形外科のある分野でもそうだろう。映画監督や脚本家、演出家でもトップレベルは30人程度ではないのか?(そう言えば平安時代も政権に関与できる藤原貴族は30人程度だったと言われている)。つまり「あらゆる業界のトップクラスは30人程度のリーグ戦である」(この書名でどっかから本を出す話はありませんか?)
②一つの部屋で議論できるのはせいぜい30人程度だ。
広い議場で議員どもは何をやっている?アホぼんの原稿棒読みを居眠りしながら議員どもが聞いているだけの茶番をあとどれぐらい、この国の国会は社会にさらし続けるのか?
それに今回の定数是正の法案はいったいどこのバカが書いた筋書きか?国民をなめるのもほどほどにしろ!恥を知れ!何が「身を切る改革」だ!与党案なら湯葉の皮一枚切れないぞ!
定数是正の最低条件はまず参議院廃止!
アホのくせに偉そうに混雑する東京の街をでっかい公用車で走り回るな!従って公用車廃止!移動はすべてスズキの軽で!道州制が前提だが、そうなると定数はローマの元老院規模の30人程度でいいのでは。選び方もローマに習い、いろいろなパターンで選ぶべきだ。
30人である根拠は
①だいたいいろいろな道のまともに使える専門家ってこの国に30人ぐらいしかいないぞ。心臓外科医の数がその典型的な例だが、全国でまともにしっかり手術ができる(自分の親族を負かせてよい)心臓外科医は全国で30人程度だ。これは脳外科でも整形外科のある分野でもそうだろう。映画監督や脚本家、演出家でもトップレベルは30人程度ではないのか?(そう言えば平安時代も政権に関与できる藤原貴族は30人程度だったと言われている)。つまり「あらゆる業界のトップクラスは30人程度のリーグ戦である」(この書名でどっかから本を出す話はありませんか?)
②一つの部屋で議論できるのはせいぜい30人程度だ。
広い議場で議員どもは何をやっている?アホぼんの原稿棒読みを居眠りしながら議員どもが聞いているだけの茶番をあとどれぐらい、この国の国会は社会にさらし続けるのか?
Q3. コメントする
今の政府にはガバナンスがないばかりかコンプライアンスもない。(統制もなく規律遵守の常識もない政府ってすごい!)法律でも何でも適当に理由をつけて国会でなんとでも捻じ曲げられるいい加減な法痴国家、あるいは放置国家だ。外交の問題でも今回の法解釈のせいで、パトカーにレンガを投げつける輩が全国で多発してしまうかも知れない。投げつけるだけならお咎めなしなのだから。あるいは「レンガ投げ」のような新たな私刑がはやってしまうかも知れない。何せ違法ではないのだから。
それにしても「絶対に逆らえない、そして誰も逆らわない」権威というか規範を頂くことは社会の枠組みの本態だ。それを国会議員が自ら率先して無視、あるいはあからさまなviolationを行ってきたことで、少なからず国家の相当部分がもうすでに瓦解してしまった。商鞅、韓非子までとは行かなくとも文明社会ならばある程度は法家国家を目指すべきで「もっとまじめにやれ!」
それにしても「絶対に逆らえない、そして誰も逆らわない」権威というか規範を頂くことは社会の枠組みの本態だ。それを国会議員が自ら率先して無視、あるいはあからさまなviolationを行ってきたことで、少なからず国家の相当部分がもうすでに瓦解してしまった。商鞅、韓非子までとは行かなくとも文明社会ならばある程度は法家国家を目指すべきで「もっとまじめにやれ!」
Q4. コメントする
国会議員が個人として使える歳費、つまり使える経費は全廃する。
ただし今でもそうなっているのかも知れないが、事務所単位で使える歳費は認める。確か年額2千万円程度だと思うが、一事務所当たり二億円程度にすべきだ(総数が30人だとしての話)。
秘書や情報収集、政策立案は有能な官吏をそのまま秘書に使えばよい。つまり公費で有能な秘書を一人の国会議員が20人程度使えるようにすればよい。
また、政党はうんざりだ。一人の国会議員の独自の考えが全く見えてこない、消し込まれる。こんなバカげた制度は戦前の遺物であり、外国がそうだからと言って形式だけ真似するのは愚かすぎる。各議員がおのおの行動し、一人で法律を立案し、それを個人が自由に投票して議決すべきだ。そのために国会議員になったのではないのか!? 一定期間中に一つの法律も立案できなかった役立たずはすぐにクビにすべきだ。
法律を一つも起案できない国会議員は、泳ぎを知らない魚であり、手術をしないペーパー心臓外科医、番組を作らない自称ディレクター、頼まれ取材(記事は書かない)で小銭を稼ぐインチキジャーナリストと同じだ。
ただし今でもそうなっているのかも知れないが、事務所単位で使える歳費は認める。確か年額2千万円程度だと思うが、一事務所当たり二億円程度にすべきだ(総数が30人だとしての話)。
秘書や情報収集、政策立案は有能な官吏をそのまま秘書に使えばよい。つまり公費で有能な秘書を一人の国会議員が20人程度使えるようにすればよい。
また、政党はうんざりだ。一人の国会議員の独自の考えが全く見えてこない、消し込まれる。こんなバカげた制度は戦前の遺物であり、外国がそうだからと言って形式だけ真似するのは愚かすぎる。各議員がおのおの行動し、一人で法律を立案し、それを個人が自由に投票して議決すべきだ。そのために国会議員になったのではないのか!? 一定期間中に一つの法律も立案できなかった役立たずはすぐにクビにすべきだ。
法律を一つも起案できない国会議員は、泳ぎを知らない魚であり、手術をしないペーパー心臓外科医、番組を作らない自称ディレクター、頼まれ取材(記事は書かない)で小銭を稼ぐインチキジャーナリストと同じだ。
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
国会議員は企業人の片手間でできる仕事。現状の半分で充分だ。これに伴って官僚の数も半減させねばならない。国の仕事など誰にでもできる。
筆者は従来から政府歳出を現状の半分の規模に圧縮することを訴えてきた。歳出半減の原則を国家の定数に当てはめると、当然、定数も半減するという主張となる。なお、平成維新の会も半減を主張しているが、これを後追いするものではない。従来から国会議員定数の半減を訴えてきている。もちろん、官僚の数も半減しなければならない。
Q3. コメントする
小選挙区制を撤廃し、比例代表制のみの1本にすればよい。
Q4. コメントする
一切不要。国会議員は時間を短縮して審議することだけを心がければよい。会議だけをする企業であれば倒産する。今の国会議員は倒産する企業の社員に成り下がっている。
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
小泉チルドレン、小沢ガールズ・ボーイズ、(橋下)ベイビーズ、といったネーミングが示すように、政治家として未熟な議員が多すぎる。
感覚的には多いと思う。チルドレンとかボーイズ・ガールズなど、ほとんど政策に貢献しない政治家が多くいることからそう感じる。
ただし、何が適正な数なのかについては、国ごとに事情が異なるので、アプリオリには言えないのではないか。
ただし、何が適正な数なのかについては、国ごとに事情が異なるので、アプリオリには言えないのではないか。
Q3. コメントする
放置されている背景には、「放置したまま解散・選挙をやっても、最高裁判所は解散・選挙が無効だとは言わないだろう」といった、司法をなめた感覚がある。その責任の一端は、違憲訴訟を最小限に抑えてきた最高裁にある。最高裁は、今回、一票の格差を是正せず選挙が行われた場合、「それは憲法違反で無効」と毅然とした対応を見せる必要がある。
Q4. コメントする
国会議員の歳費は、決して高くはないと思う。問題は、それを活用して政策を打ち出す政治家の資質にある。政治家が政策形成により多くの時間を使えるようにするためにも、総額一定の範囲で、定員削減により一人あたり歳費を増やすようにしてはどうか。
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
国家の戦略を論じることができ、少ない歳費でも仕事をしたいという使命感あふれた国会議員で構成される国会を実現するために、議員数の削減、歳費の削減を大胆にすすめるべし
「国会議員の適正人数」は、政治的イシューでもあるので、最初にお断りしておきたい。特定のグループや政党が、国会議員定数の削減に言及してきた。ここで削減数について具体的に言及すると、特定の政党や政治グループを支持するというニュアンスがどうしても出てしまうから、みんな慎重になる。「回答しない」としたほうが無難だから、今回のBSコンパスの有識者全体の回答数は減ると思う。しかし、私は過去、いかなる政治活動もしたことはないし、現在、どこかの政党を支援しているわけでもないので、国会議員の人数について、自分の考えていることを書く。その結果、どこかのグループの言っている数字と一緒であっても、それは結果として、そうなっただけであることを、お断りしたい。
スェーデンの人口が 886万人で国会議員が349人で、国民2.5万人に1人の議員。イギリスの人口が 5950万人、国会議員が 1050人で、 5.7万人に1議員。日本が人口 12000万人で国会議員が722人で 16.4万人に1議員。アメリカ合衆国の人口は 28142万人で議員が 535人、52.6万人に1議員。この数字から「日本の国会議員は多すぎることはない」と言うのは間違っている。各国の政治のありかたは多様であり、国会議員の仕事の内容が違うので、人口数をもとに国会議員の人数を決めるわけにはいかない。人口比というのは、あくまで参考の数字だ。
欧州各国の場合、人口比にすると国会議員の数が多いけれども、「減らせ」という声が大きくならないのは、欧州では国会議員にかかる経費が少ないからだ。「費用対効果比」の視点は不可欠だから、歳費についてもあわせて説明をすると、国会と国会議員を維持するために、日本人は高額のカネを支払っている。日本の総理大臣の年間報酬は4,022万円、アメリカ大統領3,600万円、イギリス首相3,100万円、フランス大統領2,900万円、インドネシア大統領240万円、フィリピン大統領52万円。イギリス、フランスは、人口比で日本よりも議員の数は多いけれど、議員の報酬が半分だ。イギリスの議員数は1,050人で報酬は年間8,900,000円、フランスが898人の議員で年間10,000,000円。日本はひとりの国会議員が年間24,000,000円を受け取っている。アメリカは年間18,000,000円だそうだ。地方議員になると、イギリスが年間730,000円、フランスが年間100,000円、アメリカが年間640,000円。日本の県会議員は、国会議員と同じで年間21,190,000円。フランスやスイスは、地方議員になると、ほとんど無報酬の名誉職らしい。議員数が多いか少ないかという話は、「国政を行なうのに、国民はいくらを支払うか」という問題と関連するので、議員定数削減と歳費削減の声が同時にでてくるのは当然だろう。日本で公務員給与を減額し続けていることに合わせて、歳費を減額してゆくことは可能であるはずだ。欧米なみの歳費を目標にして、議員報酬は半分にもってゆく。
では、議員定数はどうするか。「国会はどれだけの仕事をしているので、どれだけの人数が必要なのか」ということになる。問4で説明するように、国会議員は多忙だし、すべき仕事の量も多いが、仕事内容を整理すべきだ。国会は立法府であり、法律を作る仕事がある。現在の法律が妥当かを調べて、足りないものがあると立法する。ところが本来、議員が立法すべきであるところを過度に官僚に依存している。それを是正しつつ、議員の数を減らすには、国政に関係ない事項は地方に移管すること、そして、議員秘書には議員立法の能力がある有能な人を採用する。議員立法の青写真を自分でスラスラ書いてしまうような秘書を4人持てばよい。
また、衆参両院の役割は重複しているし、政党に属さない議員、議員立法をしない議員、委員会に属さない議員は、時間が余っているのではないか。日本では衆議院と参議院の役割があいまいだし、外国の上下両院の区別と比較したとき、よくわからない。衆議院1つにして良い。そうなると、自動的に242人が減る。衆議院でも、各地域からの代表としての国会議員は必要だが、各地域を細分化するから議員定数が増えてしまう。小選挙区の区分けをもっと大雑把にする。すると、国会議員数は半分くらいになるのではないか。議員数は350人にする。ただし、議員定数を半分にするのは、相当の混乱が生じるので、徐々に実施するとして、当面は、議員の数を現在の3分の2にする。
スェーデンの人口が 886万人で国会議員が349人で、国民2.5万人に1人の議員。イギリスの人口が 5950万人、国会議員が 1050人で、 5.7万人に1議員。日本が人口 12000万人で国会議員が722人で 16.4万人に1議員。アメリカ合衆国の人口は 28142万人で議員が 535人、52.6万人に1議員。この数字から「日本の国会議員は多すぎることはない」と言うのは間違っている。各国の政治のありかたは多様であり、国会議員の仕事の内容が違うので、人口数をもとに国会議員の人数を決めるわけにはいかない。人口比というのは、あくまで参考の数字だ。
欧州各国の場合、人口比にすると国会議員の数が多いけれども、「減らせ」という声が大きくならないのは、欧州では国会議員にかかる経費が少ないからだ。「費用対効果比」の視点は不可欠だから、歳費についてもあわせて説明をすると、国会と国会議員を維持するために、日本人は高額のカネを支払っている。日本の総理大臣の年間報酬は4,022万円、アメリカ大統領3,600万円、イギリス首相3,100万円、フランス大統領2,900万円、インドネシア大統領240万円、フィリピン大統領52万円。イギリス、フランスは、人口比で日本よりも議員の数は多いけれど、議員の報酬が半分だ。イギリスの議員数は1,050人で報酬は年間8,900,000円、フランスが898人の議員で年間10,000,000円。日本はひとりの国会議員が年間24,000,000円を受け取っている。アメリカは年間18,000,000円だそうだ。地方議員になると、イギリスが年間730,000円、フランスが年間100,000円、アメリカが年間640,000円。日本の県会議員は、国会議員と同じで年間21,190,000円。フランスやスイスは、地方議員になると、ほとんど無報酬の名誉職らしい。議員数が多いか少ないかという話は、「国政を行なうのに、国民はいくらを支払うか」という問題と関連するので、議員定数削減と歳費削減の声が同時にでてくるのは当然だろう。日本で公務員給与を減額し続けていることに合わせて、歳費を減額してゆくことは可能であるはずだ。欧米なみの歳費を目標にして、議員報酬は半分にもってゆく。
では、議員定数はどうするか。「国会はどれだけの仕事をしているので、どれだけの人数が必要なのか」ということになる。問4で説明するように、国会議員は多忙だし、すべき仕事の量も多いが、仕事内容を整理すべきだ。国会は立法府であり、法律を作る仕事がある。現在の法律が妥当かを調べて、足りないものがあると立法する。ところが本来、議員が立法すべきであるところを過度に官僚に依存している。それを是正しつつ、議員の数を減らすには、国政に関係ない事項は地方に移管すること、そして、議員秘書には議員立法の能力がある有能な人を採用する。議員立法の青写真を自分でスラスラ書いてしまうような秘書を4人持てばよい。
また、衆参両院の役割は重複しているし、政党に属さない議員、議員立法をしない議員、委員会に属さない議員は、時間が余っているのではないか。日本では衆議院と参議院の役割があいまいだし、外国の上下両院の区別と比較したとき、よくわからない。衆議院1つにして良い。そうなると、自動的に242人が減る。衆議院でも、各地域からの代表としての国会議員は必要だが、各地域を細分化するから議員定数が増えてしまう。小選挙区の区分けをもっと大雑把にする。すると、国会議員数は半分くらいになるのではないか。議員数は350人にする。ただし、議員定数を半分にするのは、相当の混乱が生じるので、徐々に実施するとして、当面は、議員の数を現在の3分の2にする。
Q3. コメントする
一票の格差をゼロにすることはできない。国会議員は、地域の代表という意味も兼ねているから、一票の格差がある程度あるのは当然だ。過疎地域でもその地域の代表を国会に送る権利がある。一票の格差をゼロにすると、北海道の広い地域から1人、神田神保町の電信柱3本分のブロックから国会議員1人というということになりかねない。これでは、政治が成り立たない。政治とは異なる利害を持つものの間の利害調整なのだから。2011年、最高裁が2009年の衆院選の「1票の格差」について、違憲状態と判断した。2011年9月の時点で、有権者数が最少の高知3区と比較したとき、格差2.30倍以上の選挙区は、野田首相の千葉4区、神奈川県10区など5つになったという。最高裁が法の下の平等を保障した憲法に反するとして違憲状態と判断したまま、国会はその判決を放置しておくことはできない。選挙制度を改革しないまま、次の選挙を迎えることはできないという危機感が国会議員のなかにあるのだろうか。次の選挙で最高裁が選挙無効判決を出したらどうするのだろうか。大混乱で尖閣諸島、竹島、北方領土どころではなくなってしまう。
Q4. コメントする
国会議員の歳費は高すぎる。国会議員一人あたりの年間経費(歳費含む)は、文書通信交通滞在費、立法事務費、賞与、交通機関の無料クーポン公設秘書給与を含めると、年約7500万円、各政党には、政党助成金として、総額319億4000万円/年が国から支払われている。日本経済がその歳費を負担し続けることができるときは、皆は黙っていたが、いまはそうはいかなくなった。歳費が高すぎるという結論に至る。
ただ、議員は忙しい。国会本会議に出席し、質問をする。質疑に参加する。委員会の報告を聞き法案の採決に参加する。法案の審議を各委員会で行うとき、委員長、理事、委員として国会議員が参加する。委員会によっては、多忙な委員会(予算委員会)とそうでない委員会がある。国会での出席記録は残るので、休むと何かとあとあとまで響く。委員会に所属しない議員は委員会出席の義務がないが、政党に所属していると、政党の仕事で多忙になる。大臣、副大臣、政務官、官房長官、官房副長官になると、さらに忙しい。自分は大臣への直接のブリーフィングを何度もしてきたが、大臣の仕事は5分刻みだった。そのほかに、政党の部会(外交部会、防衛部会など)や、議員らが作る政策勉強会がある。いろいろな政党の総会、部会と勉強会で講演したことがあるが、議員の予定が詰まっているため、議員が会場に出たりはいったり。冒頭の10分間だけ聞いて退出される方もおられる。議員会館で議員にブリーフィングをしたとき、講演の冒頭、「北朝鮮体制は長持ちしそうです。これが私の結論。ご多忙の議員は退出していただいても結構です」と言ったら、苦笑いされた。国会関係では、1990年代はじめ、参議院のいくつかの委員会に参考人として出席して、「金正日体制は崩壊する兆しはない。儒教文化をベースにした特殊な体制であり、耐久力があることを前提に情勢分析をしなければならないし、北朝鮮に対する外交と防衛力整備をしなければならない」と何度が報告したことがある。その説明に対して「崩壊秒読みの北朝鮮」と考える大臣、議員、官僚から袋叩きにされたのも、いまは良き思い出だ。金日成死去から20年近くがすぎた。いま「崩壊秒読み」の金正恩体制が日朝協議を始めている。政党の部会、勉強会は、専門家にとって政治の現場の人々の関心を知る良い機会だし、有識者の見解に国会議員が触れる良い機会であり、これは省略する必要はない。
話は戻って、比例区で当選した議員よりも小選挙区で当選した議員は、選挙区に戻って、地元に説明する必要があるから多忙だ。これらは、国会会期中は、国会に出席しながら週末は選挙区に戻るという日程になる。これらの仕事を抱えて、歳費は多すぎるのか、議員定数は多すぎるのかを考える。実態を考えると、議員立法が少なくて、官僚に立法の作業を指示してきた。官僚には過重の負担がかかり、夜中まで常に待機していなければならない。官僚も大変だが、議員の労力は軽減されてきた。ヒマな議員は誰か。政党に所属せず、政党の仕事がなく、議員立法の業績がない議員の一覧表を、わかりやすい形で国民が閲覧できるようにする。国会出席日数が少ない議員の一覧表も。そのとき、「こんなに国会議員の数は多かった」「この人が国会議員だった」と驚く人も多いのではないか。
このように考えているうちに、ヒマな国会議員の数の分は、ひとまず削減すること、多忙な国会議員の仕事の量を減らすことが先決であることがわかってきた。そうすれば、官僚への過度の依存も減る。ドイツ、フランス、スイスは、地方議員数が多く、国会議員の仕事を絞り込んでいる。日本のように、地方議会がすべきことを国会議員がしているということはない。地方議員は、ドイツ、フランス、スイスでは、無報酬であるか、あるいは最低限の必要経費のみを受け取る。
橋下市長が人気を得ているのは、国が権限と財源を地方に移譲して外交や社会保障などに専念すべきという主張が正論だからだろう。最近、とみに国会での天下国家の論議、国家戦略についての討論を聞く機会が減った。それなのに国会議員として以外の仕事の量がやたらと多い。そして時間に追われて議員立法の数が増えない。その結果、日本国のソフトパワーの力が低下してきたのである。
ただ、議員は忙しい。国会本会議に出席し、質問をする。質疑に参加する。委員会の報告を聞き法案の採決に参加する。法案の審議を各委員会で行うとき、委員長、理事、委員として国会議員が参加する。委員会によっては、多忙な委員会(予算委員会)とそうでない委員会がある。国会での出席記録は残るので、休むと何かとあとあとまで響く。委員会に所属しない議員は委員会出席の義務がないが、政党に所属していると、政党の仕事で多忙になる。大臣、副大臣、政務官、官房長官、官房副長官になると、さらに忙しい。自分は大臣への直接のブリーフィングを何度もしてきたが、大臣の仕事は5分刻みだった。そのほかに、政党の部会(外交部会、防衛部会など)や、議員らが作る政策勉強会がある。いろいろな政党の総会、部会と勉強会で講演したことがあるが、議員の予定が詰まっているため、議員が会場に出たりはいったり。冒頭の10分間だけ聞いて退出される方もおられる。議員会館で議員にブリーフィングをしたとき、講演の冒頭、「北朝鮮体制は長持ちしそうです。これが私の結論。ご多忙の議員は退出していただいても結構です」と言ったら、苦笑いされた。国会関係では、1990年代はじめ、参議院のいくつかの委員会に参考人として出席して、「金正日体制は崩壊する兆しはない。儒教文化をベースにした特殊な体制であり、耐久力があることを前提に情勢分析をしなければならないし、北朝鮮に対する外交と防衛力整備をしなければならない」と何度が報告したことがある。その説明に対して「崩壊秒読みの北朝鮮」と考える大臣、議員、官僚から袋叩きにされたのも、いまは良き思い出だ。金日成死去から20年近くがすぎた。いま「崩壊秒読み」の金正恩体制が日朝協議を始めている。政党の部会、勉強会は、専門家にとって政治の現場の人々の関心を知る良い機会だし、有識者の見解に国会議員が触れる良い機会であり、これは省略する必要はない。
話は戻って、比例区で当選した議員よりも小選挙区で当選した議員は、選挙区に戻って、地元に説明する必要があるから多忙だ。これらは、国会会期中は、国会に出席しながら週末は選挙区に戻るという日程になる。これらの仕事を抱えて、歳費は多すぎるのか、議員定数は多すぎるのかを考える。実態を考えると、議員立法が少なくて、官僚に立法の作業を指示してきた。官僚には過重の負担がかかり、夜中まで常に待機していなければならない。官僚も大変だが、議員の労力は軽減されてきた。ヒマな議員は誰か。政党に所属せず、政党の仕事がなく、議員立法の業績がない議員の一覧表を、わかりやすい形で国民が閲覧できるようにする。国会出席日数が少ない議員の一覧表も。そのとき、「こんなに国会議員の数は多かった」「この人が国会議員だった」と驚く人も多いのではないか。
このように考えているうちに、ヒマな国会議員の数の分は、ひとまず削減すること、多忙な国会議員の仕事の量を減らすことが先決であることがわかってきた。そうすれば、官僚への過度の依存も減る。ドイツ、フランス、スイスは、地方議員数が多く、国会議員の仕事を絞り込んでいる。日本のように、地方議会がすべきことを国会議員がしているということはない。地方議員は、ドイツ、フランス、スイスでは、無報酬であるか、あるいは最低限の必要経費のみを受け取る。
橋下市長が人気を得ているのは、国が権限と財源を地方に移譲して外交や社会保障などに専念すべきという主張が正論だからだろう。最近、とみに国会での天下国家の論議、国家戦略についての討論を聞く機会が減った。それなのに国会議員として以外の仕事の量がやたらと多い。そして時間に追われて議員立法の数が増えない。その結果、日本国のソフトパワーの力が低下してきたのである。
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
国会議員は国民の代表であることを前提に、同質性の高い日本においては定数を抑え気味にすることは可能である。また、異なる代表から構成される2院制をとっているので、衆院300、参院100程度で十分ではないか。
原則として、日本国憲法の前文にも書かれているように、国会議員は国民の代表であることを押さえなくてはならない。その上で国会議員の定数を考える必要がある。したがって、同質性の高い国家と低い国家では規模が同じであっても、定数は異なるべきである。日本は多民族であったり、多文化、多言語などの異質性の高い国家ではないので、その意味では多くの国会議員を必要とはしない。
また、現行の憲法のままであると仮定すると、2院制であり、それぞれの院で異なる代表を選ぶのであるから、1院の定数は押さえられてしかるべきである。両院併せて何人という議論は意味を持たない。
まず衆院は、下院的要素が高くより国民の意見を反映する場であるので、現行の小選挙区300人程度で十分なのではないか。参院は衆院とは異なる代表を選ぶべきであるので、たとえば比例代表だけの大選挙区で100人もいれば十分だろう。この数に大きな根拠はない。選挙制度はどのような代表を選ぶのかという手段なので、単純なものの方が代表を強く意識できる。複数の制度を混合するのは代表制の意義を踏みにじることになりかねない。
ただし、現行制度のままで、やみくもに定数を削減するのは反対である。「身を切る}の中身は、トカゲのしっぽ切りと言わんばかりで、ただでさえ民意が反映されている国会とは言えないのに、代表を減らしたらより国民の声が国会に届かなくなる恐れがある。
また、現行の憲法のままであると仮定すると、2院制であり、それぞれの院で異なる代表を選ぶのであるから、1院の定数は押さえられてしかるべきである。両院併せて何人という議論は意味を持たない。
まず衆院は、下院的要素が高くより国民の意見を反映する場であるので、現行の小選挙区300人程度で十分なのではないか。参院は衆院とは異なる代表を選ぶべきであるので、たとえば比例代表だけの大選挙区で100人もいれば十分だろう。この数に大きな根拠はない。選挙制度はどのような代表を選ぶのかという手段なので、単純なものの方が代表を強く意識できる。複数の制度を混合するのは代表制の意義を踏みにじることになりかねない。
ただし、現行制度のままで、やみくもに定数を削減するのは反対である。「身を切る}の中身は、トカゲのしっぽ切りと言わんばかりで、ただでさえ民意が反映されている国会とは言えないのに、代表を減らしたらより国民の声が国会に届かなくなる恐れがある。
Q3. コメントする
この状態で選挙を行うことは識者でも意見が分かれることではあるが、選挙無効の判決が出る可能性も以前より高いことは間違いない。したがって、常識的に考えれば、格差を是正してから選挙を行うべきであり、それをしないことは選挙をしたくないと言われても仕方がない。また、選挙を「近いうちに」行うのであれば、最低限の改正にとどめ、国民の信を得た新政権で議論するべきである。
民主党、自民党ともに党利党略が透けて見える行いを国民が気が付かないとでも思っているのであろうか?きわめて愚かな対応ではないだろうか。次の選挙、最長でもライ夏には行わなくてはならないのであるから、ここは格差是正だけにとどめて選挙ができるようにすべきである。自らのマニフェストに今回だけ固執して、強行採決をするのは腑に落ちない。
自民党などの野党案を軸にできるだけ早く違憲状態を脱する手当てをすべきである。
一方自民党も粛々と民主党案を廃案とすればいいものを、増税理由の問責に賛成し、反対理由に乗ることが「小異」と言わんばかりの発言も呆れるばかりである。
民主党、自民党ともに党利党略が透けて見える行いを国民が気が付かないとでも思っているのであろうか?きわめて愚かな対応ではないだろうか。次の選挙、最長でもライ夏には行わなくてはならないのであるから、ここは格差是正だけにとどめて選挙ができるようにすべきである。自らのマニフェストに今回だけ固執して、強行採決をするのは腑に落ちない。
自民党などの野党案を軸にできるだけ早く違憲状態を脱する手当てをすべきである。
一方自民党も粛々と民主党案を廃案とすればいいものを、増税理由の問責に賛成し、反対理由に乗ることが「小異」と言わんばかりの発言も呆れるばかりである。
Q4. コメントする
まず国会議員の生活費の意味合いを持つ歳費(約2200万円)、政治活動をするために支給されるさまざまな特典(現金を含む)は分けて考えなくてはならない。国会議員の政治活動はカネがかかるので、歳費からも負担しているなどの発言や思い込みが両者を混同する原因となっている。
歳費については、現在の景気などを考えればもらいすぎではないのか。議員定数削減を身を切るというが、一部切られる議員がいる代わりに大半の議員はどこも変わらない生活を続けるのは身を切るとは言えない。たとえば生活費なのだから半額の1000万円にしても高給である。そうすることで、歳費だけでいえば半数の定数削減効果がある。
政治活動については、政党助成金が認められるようになってからも、政治家の歳費はもちろん活動費の支給は減額されていない。たとえば、月額100万円の使途自由、非課税の文書交通費などは必要ない。どうしても必要だというのであれば、使用額については報告を義務付けるべきである。会派所属議員に支給される月額65万円の立法事務費についても、政党によって党の運営資金にしたり、議員に支給したり対応はまちまちであり、存続するのであれば使途を明確化すべきで、文書交通費を併せて、説明がつかない場合は、変換ないしは歳費として課税対象とする必要がある。その他の手当てなどについても、同様の処置を必要とする。
歳費については、現在の景気などを考えればもらいすぎではないのか。議員定数削減を身を切るというが、一部切られる議員がいる代わりに大半の議員はどこも変わらない生活を続けるのは身を切るとは言えない。たとえば生活費なのだから半額の1000万円にしても高給である。そうすることで、歳費だけでいえば半数の定数削減効果がある。
政治活動については、政党助成金が認められるようになってからも、政治家の歳費はもちろん活動費の支給は減額されていない。たとえば、月額100万円の使途自由、非課税の文書交通費などは必要ない。どうしても必要だというのであれば、使用額については報告を義務付けるべきである。会派所属議員に支給される月額65万円の立法事務費についても、政党によって党の運営資金にしたり、議員に支給したり対応はまちまちであり、存続するのであれば使途を明確化すべきで、文書交通費を併せて、説明がつかない場合は、変換ないしは歳費として課税対象とする必要がある。その他の手当てなどについても、同様の処置を必要とする。
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
欧州諸国と比べれば、適正範囲内に見えるが、単純比較はできない。たとえはイギリスの貴族院と日本の参議院を人口比だけで議論するのは乱暴に過ぎる。参院で言えば、米上院や戦前の貴族院より多い。衆院も増員が繰り返される以前は300定数だった。今後、比例区を中心に定数を削減すべき。現行の半数(衆院240、参院121)でよい。
Q3. コメントする
このまま解散となるなら、今度こそ最高裁は違憲無効判決を下すべき。そうでないと憲法が空文化してしまう。問責は野田総理に対する決議であり、本来、議員立法は別問題。「0増5減」を軸に与野党間で協議し、速やかに「違憲状態」を解消すべき。それもできないなら、もはや立法府に値しない。
Q4. コメントする
諸外国と比べれば高いが、財布を分けて議論すべき。公設秘書給与まで議員の収入に含める一部のマスコミ世論は実態に即さない。問題は、金額の多寡より、立法事務費その他が、再選のための活動資金に充てられている現状にある。アメリカなどと違い、日本に個人献金の風土はなく、選挙運動も手伝わない。だから政治・選挙にカネがかかる。ネットを活用した個人献金など実効的な対策を検討すべき。
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
教科書で昔、習ったのは現在の人数ですが、、、何人、必要なのか?といわれて理由が分からない。
Q3. コメントを控える
Q4. コメントを控える
Q2. 「1 - 多いと思う」の回答理由
多すぎる。
国会議員は、国民の代表者である。代表者である以上、国民にとって、その議員がどのようなことを発信し、どのようなことを考えているかをチェックする必要がある。白紙委任ではないはず。そのためには、議員のいわゆる顔が見えることが大事。現況は見たことがない議員が多すぎる。
衆議院は今の定数の半分、参議院は100名名程度でよい。
現況を見ていて、現在の議員数がいて良かったと思ったことはこれまでない。
国会議員は、国民の代表者である。代表者である以上、国民にとって、その議員がどのようなことを発信し、どのようなことを考えているかをチェックする必要がある。白紙委任ではないはず。そのためには、議員のいわゆる顔が見えることが大事。現況は見たことがない議員が多すぎる。
衆議院は今の定数の半分、参議院は100名名程度でよい。
現況を見ていて、現在の議員数がいて良かったと思ったことはこれまでない。
Q3. コメントする
国会の怠慢であることは明らか。そして、議員定数にも手を付けられない政治情勢になっているのであれば、即刻総選挙を行うべき。このまま選挙をすれば選挙無効になるという人がいる。しかし、一票の格差が是正されないと総選挙ができないなどと考える必要はない。というのは、今後、最高裁が総選挙をすべて無効にすることはあり得ない。少なくとも格差が激しい選挙区だけに限って無効にすることがある程度にすぎないからである。定数是正をできない、ていたらくの国会であればあるほど、総選挙をして国民にどこが問題の政党なのかの信を問えないという論理矛盾はあり得ない。政界をガラガラポンすべき時期になっている。
ところで、一票の格差を問題にする最高裁の見解は法律家としては一つの見識であるが、法律家である私は、法律を離れた視点として、過疎地域の人にはむしろ一票により重い価値があるとしても構わないと思っている。地方は首都圏のように住環境が恵まれていない。首都圏には、税金が住環境の整備に向けて直接的・間接的にも使われている。地方は福島を始め、首都圏のために電力供給をするなど、首都圏生活を援助していた。その土地その土地でいろいろな事情がある。一律に一票ということを比較することだけが正義だとは思わない。地方活性化の観点でも、地方の声を反映させるため、地方に居住する人の一票を重くして良いように思う。一票の格差を嘆く人は地方に引っ越せば良い。一票の格差があることを理由として地方に引っ越しする人はまず聞かない。
ところで、一票の格差を問題にする最高裁の見解は法律家としては一つの見識であるが、法律家である私は、法律を離れた視点として、過疎地域の人にはむしろ一票により重い価値があるとしても構わないと思っている。地方は首都圏のように住環境が恵まれていない。首都圏には、税金が住環境の整備に向けて直接的・間接的にも使われている。地方は福島を始め、首都圏のために電力供給をするなど、首都圏生活を援助していた。その土地その土地でいろいろな事情がある。一律に一票ということを比較することだけが正義だとは思わない。地方活性化の観点でも、地方の声を反映させるため、地方に居住する人の一票を重くして良いように思う。一票の格差を嘆く人は地方に引っ越せば良い。一票の格差があることを理由として地方に引っ越しする人はまず聞かない。
Q4. コメントする
現状では、少なくとも議員全員の総額としては多すぎる。将来は、定数を半分に減らす。その上で、本当に議員がその職責を果たすために必要なお金は必要とすべき。それが現状の一人あたりの金額を維持することになったとしても。その意味では、議員を半分にした場合の議員活動に真に必要な金額を第三者(議員OBで公正中立を保てる人など)で判断してもらいたい。
2. 適正範囲内であると思う
Q2. 「2 - 適正範囲内であると思う」の回答理由
はっきりいって、何人でもいい。それよりも重要なのは政治家の質である。
はっきりいって、何人でもいい。
日本は実は大国である。人口が多い。経済規模も大きい。だから、国会議員が1000人でも250人でも大勢に影響はない。
それよりも重要なのは、政治家の質である。
数を減らせば質が上がるかというとそうでもない。
人気投票で100人選べば、著名人が100人になるが、1000人選べば、下のほうには、割と実力で選ばれる人も入ってくる可能性がある。それは有権者の質による。
これまで失望ばかりの政治家だったということは、自分たちの選択が浅はかだった、ということだ。
しかも、これだけ繰り返している。
したがって、今後国会議員が何人になろうとも、質は低いままで、国民は失望するだろう。本当は、それは自分たちの質に失望していることに他ならないのであるが。
数だけを言うなら、県会議員、市町村議会議員を減らすべきだ。
日本は実は大国である。人口が多い。経済規模も大きい。だから、国会議員が1000人でも250人でも大勢に影響はない。
それよりも重要なのは、政治家の質である。
数を減らせば質が上がるかというとそうでもない。
人気投票で100人選べば、著名人が100人になるが、1000人選べば、下のほうには、割と実力で選ばれる人も入ってくる可能性がある。それは有権者の質による。
これまで失望ばかりの政治家だったということは、自分たちの選択が浅はかだった、ということだ。
しかも、これだけ繰り返している。
したがって、今後国会議員が何人になろうとも、質は低いままで、国民は失望するだろう。本当は、それは自分たちの質に失望していることに他ならないのであるが。
数だけを言うなら、県会議員、市町村議会議員を減らすべきだ。
Q3. コメントする
是正すべきであるが、何よりも優先されるわけではない。
Q4. コメントする
金額は、現在の質から言えば多すぎるが、質の高い議員となるなら増やしてもいいと思う。
しかし、個人で活動するには限界があり、やはり 政党の組織化にお金もエネルギーも使うべきだと思う。
しかし、個人で活動するには限界があり、やはり 政党の組織化にお金もエネルギーも使うべきだと思う。
Q2. 「2 - 適正範囲内であると思う」の回答理由
国会議員の数が多いという意見はよく聞かれるが、上記の各国比較のデータでも明らかのようにアメリカをのぞけば、人口比で見た場合に日本の国会議員の数は決して多いものではない。
衆議院は完全に小選挙区制度とするならば400人くらいが適正かもしれない。選挙区の規模が30万人程度であれば、大体選挙区のことに精通できるのではないか。
参議院については参議院議員選挙の際の有権者の一票の価値を平等にしようとすれば現在の県単位の選挙区の区割りには無理があり、いずれ選挙制度の抜本的改革が必要となる。衆議院の選挙制度と違うものにし、かつ無所属議員の当選の可能性も残すのであれば、適当と考えられるのは地方ブロック毎に大選挙区を設けることである。その場合、地方毎にわりふる際には改選ごとに少なくとも100万人あたり一人とするならば改選毎に120人、あわせて240人程度くらいが適当ではないかと考え、結果としてこれは現在の参議院議員の総数とほぼ一致する。
衆議院は完全に小選挙区制度とするならば400人くらいが適正かもしれない。選挙区の規模が30万人程度であれば、大体選挙区のことに精通できるのではないか。
参議院については参議院議員選挙の際の有権者の一票の価値を平等にしようとすれば現在の県単位の選挙区の区割りには無理があり、いずれ選挙制度の抜本的改革が必要となる。衆議院の選挙制度と違うものにし、かつ無所属議員の当選の可能性も残すのであれば、適当と考えられるのは地方ブロック毎に大選挙区を設けることである。その場合、地方毎にわりふる際には改選ごとに少なくとも100万人あたり一人とするならば改選毎に120人、あわせて240人程度くらいが適当ではないかと考え、結果としてこれは現在の参議院議員の総数とほぼ一致する。
Q3. コメントする
この状態は民主主義の基本原則をゆるがしかねない由々しき事態である。
民主主義の原則は国民一人一人が平等に一票を与えられ、それを行使できることである。しかるに現在は最大で一票の価値に2.3倍の格差がある。一人一人が平等に扱われていないということであり、選挙の正統性を損ないかねない状態にある。
一票の価値に2.3倍の格差というと視聴者の方に訴える力を欠く恐れがあるので別のいい方をしてみよう。
まず、倍数で示すことがわかりにくい。2.3倍というのはいいかえると一部の地域の住民の一票の価値が他の地域の住民の一票の価値の半分以下、43%程度しかないということである。
また一票の価値というのもわかりにくい。ほとんどの人が政治に参加する手段というのは選挙で一票を投じるしかない以上、選挙における一票というのは参政権にほかならない。従って一票の価値に2.3倍の格差があるということは一部の地域の国民の参政権は他の地域の国民の半分以下しかないということである。
一部の視聴者の皆様、あなたの参政権がほかの地域に住んでいる視聴者の方に比べ50%以下ということをお許しになれますか???(ちなみに参議院はもっとひどくて一部の視聴者の参政権は他の視聴者の方の20%程度のことがあるのでご注意ください。)
このような状況は到底放置されることが許されるものではなく、全国民の持つ一票の価値=参政権を平等にするために選挙区に対する議員定数の配分を抜本的に見直すべきである。
不平等が放置されたままで行われる選挙の正統性に疑問がつく以上、議員定数の配分の是正が行われるまで選挙は行われるべきではない。
民主主義の原則は国民一人一人が平等に一票を与えられ、それを行使できることである。しかるに現在は最大で一票の価値に2.3倍の格差がある。一人一人が平等に扱われていないということであり、選挙の正統性を損ないかねない状態にある。
一票の価値に2.3倍の格差というと視聴者の方に訴える力を欠く恐れがあるので別のいい方をしてみよう。
まず、倍数で示すことがわかりにくい。2.3倍というのはいいかえると一部の地域の住民の一票の価値が他の地域の住民の一票の価値の半分以下、43%程度しかないということである。
また一票の価値というのもわかりにくい。ほとんどの人が政治に参加する手段というのは選挙で一票を投じるしかない以上、選挙における一票というのは参政権にほかならない。従って一票の価値に2.3倍の格差があるということは一部の地域の国民の参政権は他の地域の国民の半分以下しかないということである。
一部の視聴者の皆様、あなたの参政権がほかの地域に住んでいる視聴者の方に比べ50%以下ということをお許しになれますか???(ちなみに参議院はもっとひどくて一部の視聴者の参政権は他の視聴者の方の20%程度のことがあるのでご注意ください。)
このような状況は到底放置されることが許されるものではなく、全国民の持つ一票の価値=参政権を平等にするために選挙区に対する議員定数の配分を抜本的に見直すべきである。
不平等が放置されたままで行われる選挙の正統性に疑問がつく以上、議員定数の配分の是正が行われるまで選挙は行われるべきではない。
Q4. コメントする
歳費はともかくとして秘書を雇うための活動費などは増額するべきでしょう。
国会議員も一人で政策をすべて勉強できる訳ではなく補助スタッフがある程度必要です。現在の3人はすくなすぎるので、もう少し増やすべきですし、優秀なスタッフをやとおうとすれば一定の給料は支払う必要があるはずで、これに対する補助は増やすことが我が国の政策の質を向上させることにつながるのではないでしょうか。
国会議員も一人で政策をすべて勉強できる訳ではなく補助スタッフがある程度必要です。現在の3人はすくなすぎるので、もう少し増やすべきですし、優秀なスタッフをやとおうとすれば一定の給料は支払う必要があるはずで、これに対する補助は増やすことが我が国の政策の質を向上させることにつながるのではないでしょうか。
Q2. 「2 - 適正範囲内であると思う」の回答理由
問題はここにはない
問題はここにはない
一人あたり有権者数で見て日本の国会議員は少ない
なぜ人数を減らす必要があるのかわからない
一人あたり有権者数で見て日本の国会議員は少ない
なぜ人数を減らす必要があるのかわからない
Q3. コメントする
問題は総数では無く一票の格差にある
定数の多少の増減をみとめつつ,
議席数調整のためのルールを設け毎回の選挙の度に定数是正を講じるべき.
問題が生じてから泥縄に(そしてあまりにも遅遅と)対策をしていることが大きな問題.
定数の多少の増減をみとめつつ,
議席数調整のためのルールを設け毎回の選挙の度に定数是正を講じるべき.
問題が生じてから泥縄に(そしてあまりにも遅遅と)対策をしていることが大きな問題.
Q4. コメントする
各政党が十分な政策シンクタンク機能を持ち,
官僚と党シンクタンク研究員の間を行き来できる制度が必要.
そのためには,たとえば,衆参合計で150以上の議席を有する政党に限定し(これによって通常2,特別な場合でも3の政党が大規模シンクタンクを持つことになる)てシンクタンク運営と雇用のための追加の政党助成金を交付する必要がある.
官僚批判はさかんだが,金を掛けずに官僚と対峙できる政策立案能力を持つことなどできようもない...
官僚と党シンクタンク研究員の間を行き来できる制度が必要.
そのためには,たとえば,衆参合計で150以上の議席を有する政党に限定し(これによって通常2,特別な場合でも3の政党が大規模シンクタンクを持つことになる)てシンクタンク運営と雇用のための追加の政党助成金を交付する必要がある.
官僚批判はさかんだが,金を掛けずに官僚と対峙できる政策立案能力を持つことなどできようもない...
Q2. 「2 - 適正範囲内であると思う」の回答理由
国民一人当たり議員数から見れば多すぎることはないだろうが、イギリス、ドイツなどの議員歳費は日本より
はるかに安く、日本は議員が特権階級化している点に国民の不満があるのかもしれない
はるかに安く、日本は議員が特権階級化している点に国民の不満があるのかもしれない
国民一人当たり議員数から見れば多すぎることはないだろうが、イギリス、ドイツなどの議員歳費は日本より
はるかに安く、日本は議員が特権階級化している点に国民の不満があるのかもしれない。かつて、医者が特権階級化して不興を買い、感情的に「医師過剰」を煽り、あげくに医学部の定員を抑制した結果、現在の医師不足が生じたことを考えると、定数問題は、理性的に判断しないと、将来に禍根を残すことになるだろう。
ちなみに、現時点で維新の会の半減案はあまりに暴論だが、おそらくは、道州制などで、地方に権限を委譲して、国の役割がスリムになることが前提なのだろう。
はるかに安く、日本は議員が特権階級化している点に国民の不満があるのかもしれない。かつて、医者が特権階級化して不興を買い、感情的に「医師過剰」を煽り、あげくに医学部の定員を抑制した結果、現在の医師不足が生じたことを考えると、定数問題は、理性的に判断しないと、将来に禍根を残すことになるだろう。
ちなみに、現時点で維新の会の半減案はあまりに暴論だが、おそらくは、道州制などで、地方に権限を委譲して、国の役割がスリムになることが前提なのだろう。
Q3. コメントする
違憲状態を放置していること自体に問題があることは間違いないが、小手先の調整で帳尻合わせをしている限り、何年かで再び違憲状態になることは目に見えており、根本的解決にはほど遠い。とりあえずは、毎年の国勢調査のデータから自動的に定数が是正されるルールなどが導入できたらいいのだが・・
Q4. コメントする
当然のことだが、議員活動に限界はなく、本当に必要なら現行の活動費で足りるわけもない。一方で、たいした活動もせずに、形式的に処理している議員もいるだろう。それを防止するためにも、領収書など、活動費の中身をネットで全面的に公開し、国民がチェックできる体制を確立すべきである。
Q2. 「2 - 適正範囲内であると思う」の回答理由
「0増5減」や「比例定数40削減」まではまだ、理解は出来る。しかし「議員半減」の話は、政治家はしない。政局家が言うことである。
そもそも政治家の数の多い、少ないかは、本質抜きの議論になってしまう。議論すべきは、政策であり、政治家の質である。
そもそも政治家の数の多い、少ないかは、本質抜きの議論になってしまう。議論すべきは、政策であり、政治家の質である。
「0増5減」や「比例定数40減」まではまだ理解はできる。しかし「議員半減」までくるとそれは、それは政治家がいうことでは無い。政局を好む政局家が言うことである、(政局好きという点、今までのマスコミとも相性が良い。さては、今回はメディアが便乗するかどうか!?国民に政治=政局という価値を誤認させるか?)しかし、そもそも政治家の数の多い、少ないかは、本質抜きの議論になってしまう。議論すべきは、政策であり、政治家の質である。
1億2500万人のこの国では、超過密都市と超過疎地域を抱える日本では、50年後の姿が絶望的にしか想像できないこの国では、国会議員の数も現行程度は必要だろうし、報酬も多少は減らすべきだが目くじら立てるほどの高額ではない。国家の骨格を決める、政策立案には(現地調査なども含め)相当な数の秘書・ブレーンも必要だろうし、むしろ、議員1人当たりの年間経費で言えば、現行(7500万円)を上回っても納得する。
ただし条件がある。国会議員が崇高な理念・哲学・理想・志を持ち、国民の生活を第一と考え、そのためには国家の安全と外交のあり方を日夜熟考し、そこから生まれた政策を分かりやすく国民に説明し、責任を持って国民を引っ張っていく覚悟を示し、生命を賭けて実現に向けて努力・邁進し、その過程も国民に説明し、中でわずかでも間違い・過ちがあれば潔く辞任し、決して地位・報酬・名誉を望まず、もちろん『先生』などと呼ばれるのを自ら断り、もちろん家業などではなく・・・・であれば。だから、多いか少ないか、などと論じるのは本質抜きの議論になってしまう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう一つ、現在国会で成立すべき法案である「0増5減」や「比例40減」と橋本氏の「国会議員半減」は別のものとして考える必要がある。後者は、議員すべてが選挙区情勢の下でのエゴイズムに陥り、国民が求める「身を切る決断」=定数削減=ができないときに、橋下氏は一般大衆受けのする、こういうメッセージを発していることに気づくべきである。自らの欲求不満をすべて橋下にゆだねている日本国民の無関心層=無知レベル=考えることを放棄した層は、国会議員が減ったらそれだけで拍手喝采=万歳する。こんなポピュリズムが今の日本で、爆発しようとしている。『全てを彼に委ねる』ような、ヒットラー的人間を無条件に支持する層が、日本に猛烈に増えていると感じており、これを強く心配しており、警戒している。
橋本氏の「議員半減」で何か起きるかを考えて見よう。小選挙区が半分になると、過疎地域を抱える地方はさらに地元選出の国会議員定数が減る。橋下人気が低いところ(地方)は、一層議員が減る。現状は国政にまったく反映されない。橋下人気の高い過密地帯の首都圏・大阪圏周辺では、無関心層が多いから、不満分子が多いから、そこからの選出議員は全体の中でさらに%を増して発言権が強まる。都会の不満分子に支えられた議員が増える。気が付いたら、国会の定数の40%が橋下グループ、10%が安倍グループ、20%が自民党保守層になりかねない(割合までは予想出来ないが・・・)。日本は憲法9条を破棄し、再軍備し、アジアの緊張は極限に達し、そして日本は国際社会の中で孤立する。それでもネット族を中心とした不満分子は拍手喝采を叫ぶのだろうか。そんな危険性をはらんでいることを知っていて放っておいて良い訳がない。
1億2500万人のこの国では、超過密都市と超過疎地域を抱える日本では、50年後の姿が絶望的にしか想像できないこの国では、国会議員の数も現行程度は必要だろうし、報酬も多少は減らすべきだが目くじら立てるほどの高額ではない。国家の骨格を決める、政策立案には(現地調査なども含め)相当な数の秘書・ブレーンも必要だろうし、むしろ、議員1人当たりの年間経費で言えば、現行(7500万円)を上回っても納得する。
ただし条件がある。国会議員が崇高な理念・哲学・理想・志を持ち、国民の生活を第一と考え、そのためには国家の安全と外交のあり方を日夜熟考し、そこから生まれた政策を分かりやすく国民に説明し、責任を持って国民を引っ張っていく覚悟を示し、生命を賭けて実現に向けて努力・邁進し、その過程も国民に説明し、中でわずかでも間違い・過ちがあれば潔く辞任し、決して地位・報酬・名誉を望まず、もちろん『先生』などと呼ばれるのを自ら断り、もちろん家業などではなく・・・・であれば。だから、多いか少ないか、などと論じるのは本質抜きの議論になってしまう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう一つ、現在国会で成立すべき法案である「0増5減」や「比例40減」と橋本氏の「国会議員半減」は別のものとして考える必要がある。後者は、議員すべてが選挙区情勢の下でのエゴイズムに陥り、国民が求める「身を切る決断」=定数削減=ができないときに、橋下氏は一般大衆受けのする、こういうメッセージを発していることに気づくべきである。自らの欲求不満をすべて橋下にゆだねている日本国民の無関心層=無知レベル=考えることを放棄した層は、国会議員が減ったらそれだけで拍手喝采=万歳する。こんなポピュリズムが今の日本で、爆発しようとしている。『全てを彼に委ねる』ような、ヒットラー的人間を無条件に支持する層が、日本に猛烈に増えていると感じており、これを強く心配しており、警戒している。
橋本氏の「議員半減」で何か起きるかを考えて見よう。小選挙区が半分になると、過疎地域を抱える地方はさらに地元選出の国会議員定数が減る。橋下人気が低いところ(地方)は、一層議員が減る。現状は国政にまったく反映されない。橋下人気の高い過密地帯の首都圏・大阪圏周辺では、無関心層が多いから、不満分子が多いから、そこからの選出議員は全体の中でさらに%を増して発言権が強まる。都会の不満分子に支えられた議員が増える。気が付いたら、国会の定数の40%が橋下グループ、10%が安倍グループ、20%が自民党保守層になりかねない(割合までは予想出来ないが・・・)。日本は憲法9条を破棄し、再軍備し、アジアの緊張は極限に達し、そして日本は国際社会の中で孤立する。それでもネット族を中心とした不満分子は拍手喝采を叫ぶのだろうか。そんな危険性をはらんでいることを知っていて放っておいて良い訳がない。
Q3. コメントする
現制度が、最高裁で違憲状態であり、今後の選挙結果が無効であるという可能性があるなら、いうまでもなく最優先に今国会で是正すべきである。民主党案(主な内容は、〈1〉5県で小選挙区を1減する「0増5減」〈2〉小選挙区比例代表連用制の一部導入〈3〉比例定数の40削減)で良い。ましてや自民党と公明党も賛同しているのだから、先送りする必要性が全く見当たらない。昨日の自民党党首の演説をたまたまテレビで見た。「解散総選挙、私達の手によって・・・」など声を張り上げている。御手柄がほしいのか、何がしたいのか?国民をバカにするにも程がある。大変残念だが『醜い!』としか言葉が見つからない。国民にとって何の意味成さず、ただただ党利党略のためだけに、血税で懐を肥やして、国会をボイコットするような言動は我々国民をバカしている。なるほど、そういう話だったのか。それなら話が早い。この類の国会議員なら確かに『全員削減』で良い。
Q4. コメントする
国会議員に払われている費用を総額として見たら異論は無いが、名目については議論が必要かもしれない。
しかし、国家議員の活動内容については確かに問題を抱いてしまう。特に『金帰月来(きんきげつらい)』文化が、そうである。週末帰っては、地元では後援会という名の組織の集まりに顔を出し、機嫌をとり、酒を振舞う。集まる人は、もちろんタダ酒・タダ飯。地元には政策秘書は必要なく、地元の雑用をやるための秘書を何人か雇っている。もちろん事務所も必要で、その地元秘書は、どこかで亡くなった人がいると知ると、どこの誰かは知らなくても、議員の名前で弔電を出す。葬式には花を供える、もちろん、議員の名前が大きく書いてある供花だ。場合によっては議員が日帰りで帰ってきて葬儀に顔を出す。議員が無理なら秘書が参列して議員の名刺を置いてかえる。政治とはそういうものだ、政治化はそう使うべきやという、文化が長い自民党政権化で出来上がり、謳歌された。それまでして作り上げた地盤、看板、鞄は簡単には手放したくないでしょね。政治も、三世、四世まで継ぎたくもなる。この構造では、地元の主権者に媚を売るような、売らないと成立しないような、今の日本の政治文化は、政治家も国民を一丸となって腐っているとしか見えない。自民党の与党時代があまりにも長引かせたことが、改めて反省すべき点である。
戦争などを好んで誘発させない、まっとうな値観のある政治政党の、コンスタントな権交交代(8年周期)の中で政治家の活動内容の浄化もはかって行くべきである。
しかし、国家議員の活動内容については確かに問題を抱いてしまう。特に『金帰月来(きんきげつらい)』文化が、そうである。週末帰っては、地元では後援会という名の組織の集まりに顔を出し、機嫌をとり、酒を振舞う。集まる人は、もちろんタダ酒・タダ飯。地元には政策秘書は必要なく、地元の雑用をやるための秘書を何人か雇っている。もちろん事務所も必要で、その地元秘書は、どこかで亡くなった人がいると知ると、どこの誰かは知らなくても、議員の名前で弔電を出す。葬式には花を供える、もちろん、議員の名前が大きく書いてある供花だ。場合によっては議員が日帰りで帰ってきて葬儀に顔を出す。議員が無理なら秘書が参列して議員の名刺を置いてかえる。政治とはそういうものだ、政治化はそう使うべきやという、文化が長い自民党政権化で出来上がり、謳歌された。それまでして作り上げた地盤、看板、鞄は簡単には手放したくないでしょね。政治も、三世、四世まで継ぎたくもなる。この構造では、地元の主権者に媚を売るような、売らないと成立しないような、今の日本の政治文化は、政治家も国民を一丸となって腐っているとしか見えない。自民党の与党時代があまりにも長引かせたことが、改めて反省すべき点である。
戦争などを好んで誘発させない、まっとうな値観のある政治政党の、コンスタントな権交交代(8年周期)の中で政治家の活動内容の浄化もはかって行くべきである。
3. 少ないと思う
Q2. 「3 - 少ないと思う」の回答理由
1.将来の国政を担う人間をプールしておくという意味で、国会議員は多い方がよい。2.今でさえ、二世議員、高齢議員、男性議員が多い。削減してしまえば、本当に議員が二世と高齢の男性ばかりになってしまう。
1.国会議員は、単に立法し、国政を調査するという人ではない。議院内閣制においては、平の国会議員の中から、将来の首相、閣僚がでる確率が高い。だから、将来の国政を担う人間をプールし、勉強するという意味で、国会議員は多めの方がよい。日本は人口比にして少なすぎる。
2.今でさえ、二世議員、高齢議員、男性議員が多い。地盤がない人、若い人、女性の声を国政に反映させるために、数は多少多めでもよい。それが、将来の国政を担う人材の多様化にもつながる。
今、削減してしまえば、本当に議員が二世と高齢の男性ばかりになってしまうことを憂う。
2.今でさえ、二世議員、高齢議員、男性議員が多い。地盤がない人、若い人、女性の声を国政に反映させるために、数は多少多めでもよい。それが、将来の国政を担う人材の多様化にもつながる。
今、削減してしまえば、本当に議員が二世と高齢の男性ばかりになってしまうことを憂う。
Q3. コメントする
人口比に従って今の制度のまま、直ちに是正すべき。それよりも、人口比により、自動的に選挙区を是正する中立機関を作るようにした方がよい。
根本的な選挙制度の改変とセットするから議論がややこしくなる。
根本的な選挙制度の改変とセットするから議論がややこしくなる。
Q4. コメントする
公私混同を廃すべき。私の知り合いのある国会議員は、プライベートの旅行に普通車で自費で行っていた。このような清潔な人はまれなのではないだろうか。
活動分だけ払い、監査して、後で返すと言うことにすればよい。つまり、国会議員の活動を監査する中立機関を作って、公私混同していないかをきちんと監査すればよい。
活動分だけ払い、監査して、後で返すと言うことにすればよい。つまり、国会議員の活動を監査する中立機関を作って、公私混同していないかをきちんと監査すればよい。
Q2. 「3 - 少ないと思う」の回答理由
増収効果が少ない。また、これ以上減らすと、過疎地域の県からは国会議員が選出されなくなる。効果的な施策はまだまだあるのに、国民のガス抜き目的で国会議員削減にこだわるべきではない。地方議員の削減、地方公務員給与の削減、消費税のインボイス化による補足率アップ等などの方が実効性は高い。
隗より始めよ、とは言うが、私には効果のないことはやるべきではないと思う。
国会議員の歳費と政党助成金を合わせても、たかが知れている。こうした「目くらまし」の実効の少ない話で国民のガス抜きをしても何もならないだろう。
実際、現状の選挙制度では、鳥取県や島根県などは、各自治体への強制配分の1議席を除くと、その他にはもう1議席しかない。このままでは、過疎地域から国会議員は選出できなくなってしまう。そのことに気づいているのだろうか。
こうした「国民に人気の」施策ではなく、もっと実効性の高い財政再建策はいくらでもある。
・3万7000名もいる地方議員の削減⇒国会議員の50倍近いから、効果覿面のはず。
・地方公務員の給与削減。地域物価に合わせた給与設計ではないため、地方公務員の生活レベルが高くなっている。現状が、ラスパイレス指数(国家公務員対比)97%の給与が地方公務員に支払われているが、これを1割下げるだけで、年間2兆5000億円もの増収効果がある。
・消費税のインボイス化。本来、GDPが約450兆円あり、政府支出を除いても350兆円を超えているので、税率1%当たりの増収額は3.5兆円となる。ところが現実的には税率1%当たり2.5兆円にしかならない。これはひとえに、税の補足率が低いためといえるだろう。この補足率を上げるために、消費税をインボイス化すること。これにより、増税なしでも消費税収は4割伸びる。
国会議員の歳費と政党助成金を合わせても、たかが知れている。こうした「目くらまし」の実効の少ない話で国民のガス抜きをしても何もならないだろう。
実際、現状の選挙制度では、鳥取県や島根県などは、各自治体への強制配分の1議席を除くと、その他にはもう1議席しかない。このままでは、過疎地域から国会議員は選出できなくなってしまう。そのことに気づいているのだろうか。
こうした「国民に人気の」施策ではなく、もっと実効性の高い財政再建策はいくらでもある。
・3万7000名もいる地方議員の削減⇒国会議員の50倍近いから、効果覿面のはず。
・地方公務員の給与削減。地域物価に合わせた給与設計ではないため、地方公務員の生活レベルが高くなっている。現状が、ラスパイレス指数(国家公務員対比)97%の給与が地方公務員に支払われているが、これを1割下げるだけで、年間2兆5000億円もの増収効果がある。
・消費税のインボイス化。本来、GDPが約450兆円あり、政府支出を除いても350兆円を超えているので、税率1%当たりの増収額は3.5兆円となる。ところが現実的には税率1%当たり2.5兆円にしかならない。これはひとえに、税の補足率が低いためといえるだろう。この補足率を上げるために、消費税をインボイス化すること。これにより、増税なしでも消費税収は4割伸びる。
Q3. コメントを控える
Q4. コメントを控える
Q2. 「3 - 少ないと思う」の回答理由
議員は多いほど政治に民意を反映できるはず
少なくとも1200人、つまりは人口10万人に一人ぐらいは必要。
ただし、二院は必要ないので衆議院だけでよい。
また、歳費も総額を現状のまま据え置き、一人当たりの歳費は減額する。
ただし、二院は必要ないので衆議院だけでよい。
また、歳費も総額を現状のまま据え置き、一人当たりの歳費は減額する。
Q3. コメントする
国勢調査の結果、自動的に選挙区区割りを変更するよう選挙法を変えればよい。
Q4. コメントする
活動費や調査費は増額してもよい。
議員宿舎を廃止せよ。
議員宿舎を廃止せよ。
4. その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)
Q2. 「4 - その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)」の回答理由
国会議員の数の多寡を問う前に、どこまで国政で審議をするのかを考えることが重要だ。米国の議員が人口当り世界で一番少ないのは、各州の自治の範囲が広いから。今後日本がどこまで地方分権を進めるつもりかによって、自ずと適正な国会議員定数が決まるはずだ。
国会議員の数の多寡を問う前に、どこまで国政で審議をするのかを考えることが重要だ。米国の議員が人口当り世界で一番少ないのは、各州の自治の範囲が広いから。今後日本がどこまで地方分権を進めるつもりかによって、自ずと適正な国会議員定数が決まるはずだ。
Q3. コメントする
国民の権利の差を放置することは許されない。個人的には地方分権を思い切って進め、国会議員は比例代表制を中心に選抜することが公平を保ちやすいと考える。
Q4. コメントする
「カバン、看板、コネ、金、時間」という言葉を聞いたことがあるが、多くの国会議員は(もちろんすべてではないが)、世襲や官僚出身者、さらに一定の団体の応援によって議員になっているように見える。
国会議員という役割がその人物の「生活の糧を稼ぐ職業」となって国政が影響されることは、長期的に見て好ましくない。それは自身の「生活」を保つための議員活動や、政治判断(≒国会での投票行動)に繋がる危険性が高いからだ。
また十分な経費がないと議員活動ができないという論理も良く聞くが、ある意味十分な経費があるために国政に対する高い志や考えが乏しくても国会議員という職業になりたがる、一度なってしまうと辞めたくなくなるという弊害もあるのではないか。
以上現在の支払われている「経費 vs 活動内容」という意味では現在の経費(政党助成金を含めて)おおいに疑問が残る。
今までのように金がかかる政治を放置すれば、金を出せる団体(経済界や種々の既得権益)が思うままの政治に陥りやすい。せっかくSNS等が発達してきた現在、ネットを利用した情報発信や政治活動を広く認めるべきだ。さもなければ国民はいつまでも大手メディアの報道する政治ショー(政局中心)に右往左往して、政治に対する失望感が高まり、政治に関する関心が薄れるばかりではないかと心配だ。
国会議員という役割がその人物の「生活の糧を稼ぐ職業」となって国政が影響されることは、長期的に見て好ましくない。それは自身の「生活」を保つための議員活動や、政治判断(≒国会での投票行動)に繋がる危険性が高いからだ。
また十分な経費がないと議員活動ができないという論理も良く聞くが、ある意味十分な経費があるために国政に対する高い志や考えが乏しくても国会議員という職業になりたがる、一度なってしまうと辞めたくなくなるという弊害もあるのではないか。
以上現在の支払われている「経費 vs 活動内容」という意味では現在の経費(政党助成金を含めて)おおいに疑問が残る。
今までのように金がかかる政治を放置すれば、金を出せる団体(経済界や種々の既得権益)が思うままの政治に陥りやすい。せっかくSNS等が発達してきた現在、ネットを利用した情報発信や政治活動を広く認めるべきだ。さもなければ国民はいつまでも大手メディアの報道する政治ショー(政局中心)に右往左往して、政治に対する失望感が高まり、政治に関する関心が薄れるばかりではないかと心配だ。
Q2. 「4 - その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)」の回答理由
格差の是正は当然必要だが、「量」ではなく「質」の問題。国際的に見ても日本はそれほど多くない。それ以上に問題なのは現行の選挙制度の問題点、参議院との役割分担の見直しなどをきちんと整理すべき。そのうえで、初めて適正規模が見えてくる。仮に定数を半減しても「質」の悪い議員ばかりが多数を占めるようでは、かえって政治全体の質の低下を招く。人気取りのための「削減」から約束はいい加減にしたほうがいい。
Q3. コメントする
選挙制度の抜本改革と切り離し、当面は格差是正を実現すべき。なお、選挙制度改革は、当事者である国会議員に任せるべきではない。社会保障改革国民会議にならって、強い権限を持った第三者機関に委ねなければ、改革は実現しない。
Q4. コメントする
国会議員1人当たりの年間経費は、公設秘書給与、政党交付金などを含めると約1億円。多いか少ないかは個々の議員の活動内容と評価によってきまるが、他の国にはない議員宿舎等を含めて考えると、多い気もする。使途を明確化し、政策活動に特化するような資金投入なら、むしろ増額を認めてもいいのでは。
Q2. 「4 - その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)」の回答理由
多いかすくないかというはんだんはできない。
ただ、半分ぐらいの議員が役に立たないということは、言えると思う。
ただ、原稿の選挙制度での人材選びが十分ではないことも含め、
政党の意見に従うことが議員の役目になってしまった。
国会というところは、議論の場であるから皆がいろいろな立場で学んだことを国身にはんえいさせようと考えれば、
その議論に時間は足りないほど。
今の人数で何をやるか。その時に不足か与文化という判断をすべきだが、
決められない、何もしない政治で人数が余っているとは活用しきれていないから。
・
働いてないから削減ではないと思う。
今の選挙制度は長年の経験から落ち着いた制度。人数も。
一人当たり1憶円でまかなうと、240億円浮くが、議員がもっと全員が目配りすれば
もっと国民の役に立てるはず。
何の根拠で半分かがわからない。
選挙向けのアドバルーン的な要素が強く、
どういう国をつくるのに今より半分でもすむということになるのか。
長年の流れで、今の定数に落ち着いている。
ということは、現時点では適正ということから出発してもっと政治家の役割を担ってもらう。
政府三役でだいたい60名、官邸に10名が入ると120名の過半数の政権だと
動ける議員が限られる。
ただ、半分ぐらいの議員が役に立たないということは、言えると思う。
ただ、原稿の選挙制度での人材選びが十分ではないことも含め、
政党の意見に従うことが議員の役目になってしまった。
国会というところは、議論の場であるから皆がいろいろな立場で学んだことを国身にはんえいさせようと考えれば、
その議論に時間は足りないほど。
今の人数で何をやるか。その時に不足か与文化という判断をすべきだが、
決められない、何もしない政治で人数が余っているとは活用しきれていないから。
・
働いてないから削減ではないと思う。
今の選挙制度は長年の経験から落ち着いた制度。人数も。
一人当たり1憶円でまかなうと、240億円浮くが、議員がもっと全員が目配りすれば
もっと国民の役に立てるはず。
何の根拠で半分かがわからない。
選挙向けのアドバルーン的な要素が強く、
どういう国をつくるのに今より半分でもすむということになるのか。
長年の流れで、今の定数に落ち着いている。
ということは、現時点では適正ということから出発してもっと政治家の役割を担ってもらう。
政府三役でだいたい60名、官邸に10名が入ると120名の過半数の政権だと
動ける議員が限られる。
Q3. コメントする
違憲状態のままは政治家の怠慢。
酷い話だ。選挙をしたくないために、物事を決めずにとぼけて先送りしようとしているのか。
この程度のことも決められず放置する議員には失望している。
最低限のルールだ。
最高裁からの違憲状態という判断を舐めてるとしか言いようがない。
国民の中で誰より先に、政治家は立法府として法に従い法の下で活動しなければいけない立場だ。
酷い話だ。選挙をしたくないために、物事を決めずにとぼけて先送りしようとしているのか。
この程度のことも決められず放置する議員には失望している。
最低限のルールだ。
最高裁からの違憲状態という判断を舐めてるとしか言いようがない。
国民の中で誰より先に、政治家は立法府として法に従い法の下で活動しなければいけない立場だ。
Q4. コメントする
歳費が貰い過ぎかどうか。
政治家は国民とは違う。国民がこの国の将来を委ね、国民が選んだ特別な存在だ。
一般国民に比べてはおかしい。
ところがそれだけの働き、国民にはできない国の大事業など、
大きい将来を描く仕事だから、
きちんと仕事をしてもらわなければならない。
員数合わせ、過半数要因ではないが、それだけのために議員をやっているレベルが多くいることも間違いない。
政治家は国民とは違う。国民がこの国の将来を委ね、国民が選んだ特別な存在だ。
一般国民に比べてはおかしい。
ところがそれだけの働き、国民にはできない国の大事業など、
大きい将来を描く仕事だから、
きちんと仕事をしてもらわなければならない。
員数合わせ、過半数要因ではないが、それだけのために議員をやっているレベルが多くいることも間違いない。
Q2. 「4 - その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)」の回答理由
今、問題なのは量(人数)より質(資質)。定数は衆議院議員240人でも480人でも良いと思う。国政を議論するに足る人材を選び、民意が反映される仕組みが大切。現在の小選挙区制では、多様な人材を選べず、民意も反映されていないように思う。また、4年間は総理大臣が変わらない国家運営の仕組み、決められる民主主義の仕組みを作ることが先決。
Q3. コメントする
違憲状態ではあっても、現在は違憲ではない。選挙制度などと一緒に定数配分の是正を論議すべき。
Q4. コメントする
尊敬できる国会議員であれば一定の歳費、活動費を払うべき。しかし、現状では歳費、活動費等は半額でもよいと思う。
Q2. 「4 - その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)」の回答理由
適正な人数は、国会議員の質に応じて決まるので、一概には言えない。しかし、近年、国会議員の質の低下は目を覆うばかりの状況だと、多くの国民が感じている。ただし、国会議員の質は国民の「民度」を映す鏡なので、最終的には国民に責任がある。最終的な解決方法は、教育制度改革などを通じて、国民の「民度」を上げて行くしかないだろう。
Q3. コメントする
違憲状態を早急に解消すべきであるという点は言うまでもない。現状は、あえて単純化して言えば、プレイヤー(国会議員)が審判を兼ねている状態とも言える。今後は、基本的に第三者機関が選挙制度改革を主導すべきであろう。
Q4. コメントする
政治にお金がかかるのは紛れもない現実なので、国会議員にはある程度の活動費を公的に補助する必要がある。ただし、資金の使途は従来以上に透明性を高めるべきだ。他方で、政党助成金の給付水準は、国際比較などから見ると高すぎる。政党法による規制などが不十分な現状では、大幅に削減すべきであろう。
Q2. 「4 - その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)」の回答理由
国会議員の人数を云々する前に、国会議員がその役割を十分に果たすにはどのような条件が必要なのかを具体的に議論する必要がある。その上で人数の削減や、必要な経費問題について国会議員以外の第3者機関が見直すべきだ。現在の人数が多いから半分で十分だというのはあまりにも荒っぽい議論といえる。
ただ、衆参がねじれを起こすことによる弊害を考えた場合、一院制にする「案」は検討すべきと思う。そうすれば自動的に人数の削減は行なわれるだろう。
ただ、衆参がねじれを起こすことによる弊害を考えた場合、一院制にする「案」は検討すべきと思う。そうすれば自動的に人数の削減は行なわれるだろう。
Q3. コメントする
国民を代表する国権の最高機関である国会が憲法違反状態では話にならない。そこで制定された「法律」の正当性にもら疑問符が付き、それはそのまま民主主義の根幹である「法治主義」をも危うくする。なぜこの問題が早急に解決されないのかが不思議だ。
こうした危機意識のなさにも国会議員の劣化が現れているといえるのではないか。国会議員の人数問題も重要だが、まずは目先の違憲状態を解消することが先決だ。
こうした危機意識のなさにも国会議員の劣化が現れているといえるのではないか。国会議員の人数問題も重要だが、まずは目先の違憲状態を解消することが先決だ。
Q4. コメントを控える
Q2. 「4 - その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)」の回答理由
国会議員は、政策の利害対立を調整し最終的に意思決定する存在である。地域や世代等によって政策の利害が異なるなら、その利害を代表する議員が選出される必要があり、利害対立の仕方により小選挙区制の下で選挙区を分ける必要がある。したがって、国会議員の数は、利害対立の仕方に即した選挙区の数と等しくすべきである。
国会議員の数は、人口が多いほど多くする必要はないし、面積が広いほど多くする必要もない。あくまで、有権者間における政策に関する利害対立の程度に応じて決めればよい。
この原則を、例示してみよう。もし仮に、日本を、北日本、中日本、南日本と3つの地域に分けられて、国政の全ての政策において、各地域内では全ての有権者の利害が一致していて、地域間だけで利害が異なっていたとする。そして、この3つの地域の有権者数は、全て同じであると仮定する(定数格差の問題を捨象するためのものである)。
このとき、国会議員は、各地域を1つの選挙区として、各地域からその利害を代表して議員が1人選出されて、3地域から選出された国会議員の間で政策の利害調整を行い、意思決定すればよい。地域内で利害が対立しない状況では、(定数格差はないから)その選挙区から1人だけ代表者を出せば事が足りる。
この例示は極端としても、ここから示唆されることは、政策の利害が対立する場合には、それぞれの利害を代表する国会議員が必要となるが、利害が対立しない有権者の間では、国会議員を(定数格差の問題が生じない範囲で)過度に多く選出する必要はない、ということである。したがって、原則として、小選挙区制(※)の下で、選挙区は利害対立の仕方に即して分けられ、そこから(定数格差を是正した下で)各選挙区1人の国会議員が選出されればよい。これに基づき、国会議員の数は、選挙区の数と同じだけであればよい。
※小選挙区制が望ましい理由は、決定性(勝者を必ず選ぶ)があるところにある。その選挙区内での代表者を1人選出することにより、小選挙区制で選ばれた国会議員は、その選挙区の利害を代表することになり、他の選挙区から選出された国会議員との間で代表制を持って利害調整し、意思決定ができる。他方、比例代表制のように、総体的に異なる意見を比例的に代表させる形で国会議員を選出すれば、国会において決定性の保証がない。
これまで、民主主義が世界で育まれて以来、政策の利害は、産業構造や地政学的な差異から、地域を単位として選挙区が分けられてきた。しかし、少子高齢化が進む日本において、政策に関する利害対立は、必ずしも地域を単位としていない可能性がある。むしろ、世代を単位とした利害の差異が生じているともいえる。したがって、今後は、井堀利宏・東京大学教授と私が最初に提唱した「年齢別(世代別)選挙区」(初出は、井堀利宏・土居丈朗『日本政治の経済分析』木鐸社、1998年)も踏まえた選挙区の見直しが必要であろう。
そう考えると、現在の衆議院の定数480は、地域別という観点から言えば多すぎるが、世代別という観点から言えば全く考慮されていない(年齢階層別に議員を選出する観点では議員数を増やす必要がある)といえる。
この原則を、例示してみよう。もし仮に、日本を、北日本、中日本、南日本と3つの地域に分けられて、国政の全ての政策において、各地域内では全ての有権者の利害が一致していて、地域間だけで利害が異なっていたとする。そして、この3つの地域の有権者数は、全て同じであると仮定する(定数格差の問題を捨象するためのものである)。
このとき、国会議員は、各地域を1つの選挙区として、各地域からその利害を代表して議員が1人選出されて、3地域から選出された国会議員の間で政策の利害調整を行い、意思決定すればよい。地域内で利害が対立しない状況では、(定数格差はないから)その選挙区から1人だけ代表者を出せば事が足りる。
この例示は極端としても、ここから示唆されることは、政策の利害が対立する場合には、それぞれの利害を代表する国会議員が必要となるが、利害が対立しない有権者の間では、国会議員を(定数格差の問題が生じない範囲で)過度に多く選出する必要はない、ということである。したがって、原則として、小選挙区制(※)の下で、選挙区は利害対立の仕方に即して分けられ、そこから(定数格差を是正した下で)各選挙区1人の国会議員が選出されればよい。これに基づき、国会議員の数は、選挙区の数と同じだけであればよい。
※小選挙区制が望ましい理由は、決定性(勝者を必ず選ぶ)があるところにある。その選挙区内での代表者を1人選出することにより、小選挙区制で選ばれた国会議員は、その選挙区の利害を代表することになり、他の選挙区から選出された国会議員との間で代表制を持って利害調整し、意思決定ができる。他方、比例代表制のように、総体的に異なる意見を比例的に代表させる形で国会議員を選出すれば、国会において決定性の保証がない。
これまで、民主主義が世界で育まれて以来、政策の利害は、産業構造や地政学的な差異から、地域を単位として選挙区が分けられてきた。しかし、少子高齢化が進む日本において、政策に関する利害対立は、必ずしも地域を単位としていない可能性がある。むしろ、世代を単位とした利害の差異が生じているともいえる。したがって、今後は、井堀利宏・東京大学教授と私が最初に提唱した「年齢別(世代別)選挙区」(初出は、井堀利宏・土居丈朗『日本政治の経済分析』木鐸社、1998年)も踏まえた選挙区の見直しが必要であろう。
そう考えると、現在の衆議院の定数480は、地域別という観点から言えば多すぎるが、世代別という観点から言えば全く考慮されていない(年齢階層別に議員を選出する観点では議員数を増やす必要がある)といえる。
Q3. コメントする
定数格差是正は、当然改められなければならない。次期衆議院総選挙の前に定数格差を是正せずして次期選挙を行うべきではない。与野党は、早急に定数格差を是正して、次期総選挙が行える制度的前提を確立すべきである。
国会議員の定数の問題と、定数格差の問題は、切り離して議論すべきである。定数が定められた上で、それを前提に定数格差のない選挙区割りを行うという手順に従えば、(さらには現在衆参ねじれ状態で法改正を行うには両院で可決されなければならないことを踏まえれば)次期衆議院総選挙は定数を変えずに、定数格差是正を先に行うという方法を取らざるを得ないだろう。
国会議員の定数は、次期衆議院総選挙の後で変更することもやむを得ない。
国会議員の定数の問題と、定数格差の問題は、切り離して議論すべきである。定数が定められた上で、それを前提に定数格差のない選挙区割りを行うという手順に従えば、(さらには現在衆参ねじれ状態で法改正を行うには両院で可決されなければならないことを踏まえれば)次期衆議院総選挙は定数を変えずに、定数格差是正を先に行うという方法を取らざるを得ないだろう。
国会議員の定数は、次期衆議院総選挙の後で変更することもやむを得ない。
Q4. コメントする
現在の国会議員の多くは、各政党内での人材育成が制度的に不十分にしか行われていないことから、政策知識の面で、官僚よりも劣るところが多い。したがって、立法技術も政策運営能力も、残念ながら現在のところ歳費に見合うだけのものがある議員はかなり少ないと言わざるを得ない。
歳費は、能力に相応するだけのものが与えられてしかるべきだが、願わくば、現在の歳費を支払うにふさわしい立法技術や政策運営能力を、各国会議員が身につける(ように各政党が人材育成する)ようにしてもらいたい。
歳費は、能力に相応するだけのものが与えられてしかるべきだが、願わくば、現在の歳費を支払うにふさわしい立法技術や政策運営能力を、各国会議員が身につける(ように各政党が人材育成する)ようにしてもらいたい。
Q2. 「4 - その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)」の回答理由
現状の国民生活の状況、たとえば福祉、環境、経済、財政、エネルギー等々満足心を与えてくれるように議員活動をしてくれたとは思えない。すなわち立法府としての機能を果たしてくれたとは思えない。
故に現状の数が必要とはいえない。
故に現状の数が必要とはいえない。
1.必要人数は、議員が国民に対してどのような役割、すなわちパブリックアカウンタビリティを履行してくれているのかによる。
2.現状の国民生活の状況、たとえば福祉、環境、経済、財政、エネルギー等々をみれば、過去の立法府の活動が国民に満足心を与えてくれるように議員活動をしてくれたとは思えない。すなわち立法府としての機能を果たしてくれたとは思えない。
3.故に現状の数が必要とはいえない。
4.議員が2.の諸活動を真剣に一人ひとり専門性をもって行うとすれば一定の人数は必要となるかもしれない。
5.立法府の役割と国民の負託を実施できる体制・システムを再構築すべきで、それらを根拠に人数を算出すべきである。
6.故にいったん現状は何もしていないと思われる3分の1程度は削減すべきことになる。
2.現状の国民生活の状況、たとえば福祉、環境、経済、財政、エネルギー等々をみれば、過去の立法府の活動が国民に満足心を与えてくれるように議員活動をしてくれたとは思えない。すなわち立法府としての機能を果たしてくれたとは思えない。
3.故に現状の数が必要とはいえない。
4.議員が2.の諸活動を真剣に一人ひとり専門性をもって行うとすれば一定の人数は必要となるかもしれない。
5.立法府の役割と国民の負託を実施できる体制・システムを再構築すべきで、それらを根拠に人数を算出すべきである。
6.故にいったん現状は何もしていないと思われる3分の1程度は削減すべきことになる。
Q3. コメントする
1.放置することは違法状態であり、議員に自らがパブリックアカウンタビリティ違反であること認識させるべきである。
2.本来は、国会が自ら解消のための活動をおこさせるべきであるが、それをやらないのであるから国民的議論をおこさせ早急に改善すべきである。
3.民間の国民がこのようなことをすれば即法的処置をとられるのであるから、最高裁(憲法裁判所のような)、会計検査院(司法機関としての)等の中立機関が強制執行できるような体制を構築すべきである。
2.本来は、国会が自ら解消のための活動をおこさせるべきであるが、それをやらないのであるから国民的議論をおこさせ早急に改善すべきである。
3.民間の国民がこのようなことをすれば即法的処置をとられるのであるから、最高裁(憲法裁判所のような)、会計検査院(司法機関としての)等の中立機関が強制執行できるような体制を構築すべきである。
Q4. コメントする
1.議員のうちには、ただ参加しているに過ぎないものがかなり見受けられるのであるから、活動費の経済性・有効性の公監査を実施し、国会の成果になっていない部分は削減すべきことになる。
2.民間の国民の場合は、そのような金銭をもらっている場合には違法所得、課税所得等を構成することになるのであるから会計検査院等の中立機関が厳格に処分すべきであるが、そうならないであろうから国民的活動をおこさせるべきである。
2.民間の国民の場合は、そのような金銭をもらっている場合には違法所得、課税所得等を構成することになるのであるから会計検査院等の中立機関が厳格に処分すべきであるが、そうならないであろうから国民的活動をおこさせるべきである。
Q2. 「4 - その他(設問・選択肢以外の視点・考え方)」の回答理由
他国と比べるのはナンセンス。
選挙の手段や方法、政党の在り方、国家元首と行政の最高責任者の位置づけや権限等々、国により政治、議会運営はまちまちであり、日本を他国と比べるのには抵抗がある。日本で現在の定員の多少は選挙民独自で適正数を判断すべきである。議員数で勝るものが行政を司る仕組みの中で、議員の資質を持たない輩が数合わせの為に議員となっている体質が問題だ。事業での成功、二世議員によく有る先祖や親からの遺産等の収入、支持者からの寄付をもとに、給与や手当を返上してでも議員活動をすると云う政治家は皆無なのでは。そういった気概を持った議員たちが増えれば、今の定員数でも、又多くなっても構わない。
いっその事、議員在任中であっても、選挙民自らが、パフォーマンスや行動に問題ある議員の手当を減額したり、罷免できる制度を導入してはどうか。国民の注視する中で、本当の議員活動をさせれば良い。
維新の会が主張する国会議員半減も、自治体での地方議員数増加を、更に促すだけでは。手始めに、地元大阪市・府の議員を減らす試みは無いのだろうか。
いっその事、議員在任中であっても、選挙民自らが、パフォーマンスや行動に問題ある議員の手当を減額したり、罷免できる制度を導入してはどうか。国民の注視する中で、本当の議員活動をさせれば良い。
維新の会が主張する国会議員半減も、自治体での地方議員数増加を、更に促すだけでは。手始めに、地元大阪市・府の議員を減らす試みは無いのだろうか。
Q3. コメントを控える
Q4. コメントする
一律では無く、前述したように、議員活動の優劣を、歳費や活動費の金額査定基準に盛り込んでみたら良い。国会・地方議員を問わず、当選後、私生活での不祥事、税金未納、不正な歳費/活動費の使用を含めたスキャンダル、ゴシップでしか名前を聞かない議員は、税金の浪費でしかない。

※ご入力いただいた情報の取り扱いについては、『利用目的』をご覧下さい。
また、メッセージを送信される前には『フジテレビホームページをご利用される方へ』を必ずお読み下さい。
※送信内容に個人情報は記載しないようお願いします。
※投稿する際は、件名を編集しないでください。
また、メッセージを送信される前には『フジテレビホームページをご利用される方へ』を必ずお読み下さい。
※送信内容に個人情報は記載しないようお願いします。
※投稿する際は、件名を編集しないでください。

コメントはありません