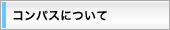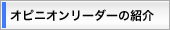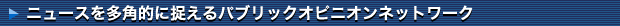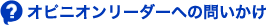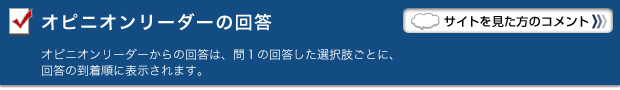その他
アルジェリア人質事件から何を学ぶか?
1:設問テーマの背景 (facts)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1月16日、アルジェリア東部イナメナス近郊の石油ガスプラントが、イスラム武装勢力に襲撃され、アルジェリア人のほか、イギリス人、アメリカ人、フランス人、ノルウェー人、アイルランド人、そして日本人など外国人多数が人質として拘束されました。
・
犯人グループの目的にはっきりとした情報がないなか、17日深夜、アルジェリア軍は人質救出作戦を決行。その結果、人質も含め多数の死亡者が出たと伝えられています。
・
襲撃された石油ガスプラントは、アルジェリアの国営企業、イギリスのBP社、ノルウェーのスタトイル社による合弁企業による運営であり、この中に、プラント建造に関わる仕事で、日本のプラントメーカー「日揮」の関係者も勤務していました。
・
日本政府の対応としては、16日、岸田外相が、アルジェリアのメデルチ外相と電話で会談。
岸田外相は、「日本政府として極めて憂慮している。人命最優先で対応してほしい」と安全確保を要請し、メデルチ外相は「最大限配慮する」と述べました。
・
17日からアルジェリアに城内外務政務官が派遣され、現地での情報収集を開始しました。
安倍首相は東南アジア諸国の歴訪中でしたが、突入作戦開始後の18日未明にアルジェリアのセラル首相と電話会談を行い、安倍首相から、「アルジェリア軍が軍事作戦を開始し、人質に死傷者が出ているという情報に接している。人命最優先での対応を申し入れているが、人質の生命を危険にさらす行動を強く懸念しており、厳に控えてほしい」と軍事作戦の即時中止を要請したのに対し、セラル首相は「相手は危険なテロ集団で、これが最善の方法だ。作戦は続いている」
と述べました。
・
作戦は19日に終了し、多くの人質が救出された一方で、人質にも多数の死者が出ました。
20日未明、アルジェリア政府は、一連の制圧作戦で武装勢力32人を殺害、人質23人の死亡を発表しました。
アルジェリア政府の対応について、フランスのオランド大統領は、「最も適切な対応だった」
と評価しましたが、イギリスのキャメロン首相は、「事前に知らせてもらった方が望ましかった」
と失望感を示しています。
・
18日夜までに7人の生存が確認されましたが、アルジェリアのセラス首相は、21日の時点で、死亡した人質が37人に上ると発表。同日夜の時点で、7人の日本人が犠牲となったことが判明し、3人の安否については依然不明の状態となっています。政府は邦人の帰国に向けて近く政府専用機の派遣を行うとしています。
2:番組として (our aim)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
今回の事件で日本政府はアルジェリア政府に人命最優先を何度も要請しましたが、アルジェリア軍は突入作戦を決行し、人質にも多数の死者が出ました。
事件報道の中では、各国と比較する形で日本の対応の課題について指摘がありました。
邦人保護の体制や情報収集などが挙げられ、その中で、自衛隊法や情報収集に関する組織の問題などが指摘されました。
世界経済のグローバル化が進み、日本企業がこれまで以上に世界各地で仕事を行うことが予想されるなか、確認されてはいないものの複数の日本人が犠牲になったと見られることは、日本社会に衝撃を与えています。
中東のみならず、今後も同様の事態が予想されます。また、さまざまなカントリーリスクがつきまとうことも考えられます。
番組として、今回の事件を多角的に捉え学ぶことは、今後の日本の在り方を考える上で、有意義であると考えました。
コンパス・オピニオンリーダーの皆さまから、是非ともご意見をお寄せいただけますようお願い申しあげます。
1月16日、アルジェリア東部イナメナス近郊の石油ガスプラントが、イスラム武装勢力に襲撃され、アルジェリア人のほか、イギリス人、アメリカ人、フランス人、ノルウェー人、アイルランド人、そして日本人など外国人多数が人質として拘束されました。
・
犯人グループの目的にはっきりとした情報がないなか、17日深夜、アルジェリア軍は人質救出作戦を決行。その結果、人質も含め多数の死亡者が出たと伝えられています。
・
襲撃された石油ガスプラントは、アルジェリアの国営企業、イギリスのBP社、ノルウェーのスタトイル社による合弁企業による運営であり、この中に、プラント建造に関わる仕事で、日本のプラントメーカー「日揮」の関係者も勤務していました。
・
日本政府の対応としては、16日、岸田外相が、アルジェリアのメデルチ外相と電話で会談。
岸田外相は、「日本政府として極めて憂慮している。人命最優先で対応してほしい」と安全確保を要請し、メデルチ外相は「最大限配慮する」と述べました。
・
17日からアルジェリアに城内外務政務官が派遣され、現地での情報収集を開始しました。
安倍首相は東南アジア諸国の歴訪中でしたが、突入作戦開始後の18日未明にアルジェリアのセラル首相と電話会談を行い、安倍首相から、「アルジェリア軍が軍事作戦を開始し、人質に死傷者が出ているという情報に接している。人命最優先での対応を申し入れているが、人質の生命を危険にさらす行動を強く懸念しており、厳に控えてほしい」と軍事作戦の即時中止を要請したのに対し、セラル首相は「相手は危険なテロ集団で、これが最善の方法だ。作戦は続いている」
と述べました。
・
作戦は19日に終了し、多くの人質が救出された一方で、人質にも多数の死者が出ました。
20日未明、アルジェリア政府は、一連の制圧作戦で武装勢力32人を殺害、人質23人の死亡を発表しました。
アルジェリア政府の対応について、フランスのオランド大統領は、「最も適切な対応だった」
と評価しましたが、イギリスのキャメロン首相は、「事前に知らせてもらった方が望ましかった」
と失望感を示しています。
・
18日夜までに7人の生存が確認されましたが、アルジェリアのセラス首相は、21日の時点で、死亡した人質が37人に上ると発表。同日夜の時点で、7人の日本人が犠牲となったことが判明し、3人の安否については依然不明の状態となっています。政府は邦人の帰国に向けて近く政府専用機の派遣を行うとしています。
2:番組として (our aim)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
今回の事件で日本政府はアルジェリア政府に人命最優先を何度も要請しましたが、アルジェリア軍は突入作戦を決行し、人質にも多数の死者が出ました。
事件報道の中では、各国と比較する形で日本の対応の課題について指摘がありました。
邦人保護の体制や情報収集などが挙げられ、その中で、自衛隊法や情報収集に関する組織の問題などが指摘されました。
世界経済のグローバル化が進み、日本企業がこれまで以上に世界各地で仕事を行うことが予想されるなか、確認されてはいないものの複数の日本人が犠牲になったと見られることは、日本社会に衝撃を与えています。
中東のみならず、今後も同様の事態が予想されます。また、さまざまなカントリーリスクがつきまとうことも考えられます。
番組として、今回の事件を多角的に捉え学ぶことは、今後の日本の在り方を考える上で、有意義であると考えました。
コンパス・オピニオンリーダーの皆さまから、是非ともご意見をお寄せいただけますようお願い申しあげます。
Q1:今回のアルジェリア人質事件で、日本が学ぶべき課題は何だと思いますか?
| 1.回答する(問2にお答えください。) | |
| 2.回答を控える |
Q2:(問1つづき)日本が学ぶべき課題についてお聞かせください。
Q3:(上記で挙げられた)その課題を解決するために必要なことは何だと思いますか?
Q4:今回のアルジェリア事件にとどまらず、グローバル化で日本の企業などの一層の海外進出が進むとされています。日本や日本の企業などは、カントリー・リスクにどう対処していけばいいとお考えですか?
(どの地域の、どんなリスクに、どう対処すべきかなど具体的なお考えがあれば、合わせてお聞かせください。)
(どの地域の、どんなリスクに、どう対処すべきかなど具体的なお考えがあれば、合わせてお聞かせください。)
1. 回答する(問2にお答えください。)
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
今回の事件が「イスラム原理主義」勢力による実質的な「フランス~英米以外の先進国」への武力行使である点を冷静に考える必要がある。
今回の事件が「イスラム原理主義」勢力による実質的な「フランス~英米以外の先進国」への武力行使である点を冷静に考える必要がある。事件で失われた命は戻らず、このようなテロ行為は許されてはならない事だ。であると同時に、マリ内戦以来の新たな動乱とイスラム・テロとの結びつきに、日本は慎重な姿勢で対処してゆくべきと思う。
Q3. コメントする
米国・欧州とイスラム勢力、あるいはアフリカとの間には積年の様々に複雑な問題があるが、日本はそうした来歴と一定の距離がある。今回のような犠牲を再び出すことなく、中長期的にグローバルな協調的発展が進むよう、被害者の立場となった日本は、とみに冷静に事態を把握し、適切なイニシアティヴを発揮する必要があると考える。
Q4. コメントする
丸腰で紛争地域に入ればアクシデントは避けられない。個別の事案に即して検討しければならないが、グローバルな趨勢を念頭に無用のリスクは徹底して軽減しなければならないだろう。大きく見るならドルとユーロの行方が流れを作っているように思っている。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
人口縮小による国内経済規模の縮小停滞が確実視される日本経済は、海外市場で稼ぐ道を取らなければ成長の余地は大きくない。海外市場と言っても、治安がよく安全な市場は競争も厳しく利幅も小さい。となると、ある程度の危険は覚悟の上で新興市場や資源国へ進出することは不可避であろう。企業はますます海外市場に成長を求め、国民はますます海外へ出て行く時代。そういうニッポンを前提とした仕組みや社会制度を整備する必要がある。
①政府の海外情報収集能力の大幅強化
国際情報機関を整備し、世界のあらゆる国へ日本人が進出することを前提とした情報収集能力を整備する。現地大使館の機能を充実させ、いざという際には日本国民の安全を確保するための最大限の方策が打てるようにする。
②国としての補償制度の整備
外国での経済活動に際するテロ、政変や天災による犠牲については、政府としての補償制度を整備すべき。民間企業や保険でカバーするにはコストが高すぎる。
③各国政府との協調によるテロ対策機関の設立
作家のトム・クランシー氏が提唱するような、国際的なテロ対策のための精鋭部隊を整備することも検討すべき。
①政府の海外情報収集能力の大幅強化
国際情報機関を整備し、世界のあらゆる国へ日本人が進出することを前提とした情報収集能力を整備する。現地大使館の機能を充実させ、いざという際には日本国民の安全を確保するための最大限の方策が打てるようにする。
②国としての補償制度の整備
外国での経済活動に際するテロ、政変や天災による犠牲については、政府としての補償制度を整備すべき。民間企業や保険でカバーするにはコストが高すぎる。
③各国政府との協調によるテロ対策機関の設立
作家のトム・クランシー氏が提唱するような、国際的なテロ対策のための精鋭部隊を整備することも検討すべき。
Q3. コメントする
国民意識の現実主義への転換が必要と考える。人命優先、武力行使反対を叫ぶのは聞こえはいいが、テロや暴力を助長し、より多くの犠牲者を生み出す可能性もある。国民一人一人が安易に政府の責任を追及するのではなく、テロや政変が起こる可能性がある国々が存在することを現実として理解し、現実的な政策や対策に理解を示すべき。今後、日本が新興市場や資源国に進出すればするほど、日本人がテロや暴力のターゲットになる可能性が高まるのだから。
Q4. コメントする
個別の企業の対策の充実も当然必要であるが、日本全体としての対策を具体化するべき。
特に補償制度や海外駐在の手当はより厚くしないと、リスクの高い海外勤務を日本人や企業が避けることになる。リスクを取らなければリターンはない。そしてリスクをゼロにすることはできない。
特に補償制度や海外駐在の手当はより厚くしないと、リスクの高い海外勤務を日本人や企業が避けることになる。リスクを取らなければリターンはない。そしてリスクをゼロにすることはできない。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
海外での活動は最悪のリスクを常に想定しなければならない時代になった。
だが「撃ちてしやまん!」サムライ精神で世界をリードして人類に幸福をもたらす民族を目指してこの菩薩の行はさらに勢いを増して欲しい!
だが「撃ちてしやまん!」サムライ精神で世界をリードして人類に幸福をもたらす民族を目指してこの菩薩の行はさらに勢いを増して欲しい!
非常に残念だ。会社のため、国益のため、文字通り企業戦士として散った7柱の英霊に全国民が哀悼の意を示している。ところで日本人であるというのがわかった(認識された)上で殺害されているようなので、これは今後も世界の各地で「お前日本人だろう!」ということで理不尽に殺害されてしまう可能性があると言うことだ。これを防ぐためには日本の現在のプレゼンスを変えるか、あるいは海外では360度、どっから見ても日本人には見えないようにするしかない。
今後は海外での企業活動が相当に制限されるのだろうか。
何かを行うには相当なリスクを覚悟しなければならない時代になった。
今回の対応や結末については情報がないので誰にも論評は難しいのではないか。
カントの推奨する人間の行動様式の第一条、我々は何を知ることができるのか?
という観点からすると、まず報道されている「事実」が本当なのかどうか?全て疑ってかかる必要がある。いろいろな国の人が力を合わせて推進している超大型プロジェクトのようだが、「天然ガス」とあるだけで、本当にそうなのか?その点も疑問だ。そうだとしても、その仲間に入れてもらえなかった別の国の勢力の攻撃であったのではないか、などとも邪推してしまう。もちろん当局はそのことを知っているのだろう。単なる直感だが、テレビで映し出される「使用された武器」の映像には定番のAK47またはAK100が写っていない。報道をうのみにしない!これがまず今回の第一番の教訓だろう。
また、あ戦闘地域の現場の指揮について結果だけであれこれ言うのは簡単だ。先に挙げた「本当に天然ガスのプラント?」など、いろいろな事情があって今回の結末となったと理解すべきではないか。
孫濱の兵法に「兵は拙速を貴ぶ」=「兵は拙速を聞くも、未だ巧、久しきを睹ざるなり。」
「敗軍の将、は兵を語らず」etc.戦争と言う事態においては起こってしまった事、を後からごちゃごちゃ言っても何も得るものはない。それに繰り返すが、我々は事態にかかわる事実については一方的で偏狭そうな視野から造られたニュースを観ているだけで、他に何も知らない。
ところで、今回の当事国以外の政府の対応としてはalternativeな判断や行動は成し得なかったように想像する。
今後は海外での企業活動が相当に制限されるのだろうか。
何かを行うには相当なリスクを覚悟しなければならない時代になった。
今回の対応や結末については情報がないので誰にも論評は難しいのではないか。
カントの推奨する人間の行動様式の第一条、我々は何を知ることができるのか?
という観点からすると、まず報道されている「事実」が本当なのかどうか?全て疑ってかかる必要がある。いろいろな国の人が力を合わせて推進している超大型プロジェクトのようだが、「天然ガス」とあるだけで、本当にそうなのか?その点も疑問だ。そうだとしても、その仲間に入れてもらえなかった別の国の勢力の攻撃であったのではないか、などとも邪推してしまう。もちろん当局はそのことを知っているのだろう。単なる直感だが、テレビで映し出される「使用された武器」の映像には定番のAK47またはAK100が写っていない。報道をうのみにしない!これがまず今回の第一番の教訓だろう。
また、あ戦闘地域の現場の指揮について結果だけであれこれ言うのは簡単だ。先に挙げた「本当に天然ガスのプラント?」など、いろいろな事情があって今回の結末となったと理解すべきではないか。
孫濱の兵法に「兵は拙速を貴ぶ」=「兵は拙速を聞くも、未だ巧、久しきを睹ざるなり。」
「敗軍の将、は兵を語らず」etc.戦争と言う事態においては起こってしまった事、を後からごちゃごちゃ言っても何も得るものはない。それに繰り返すが、我々は事態にかかわる事実については一方的で偏狭そうな視野から造られたニュースを観ているだけで、他に何も知らない。
ところで、今回の当事国以外の政府の対応としてはalternativeな判断や行動は成し得なかったように想像する。
Q3. コメントする
日本人はずうっと日本人であるので、どこに行ってもその地に溶け込むことはない。組織的行動ではなおさらである。そして交渉もド下手で人を疑うことを知らず、すぐ騙される。それは美徳に他ならないのだが、その点をわきまえて、つねにお客さんと言う立場で、今後も海外では多くを望まないことが肝要なのではないか。
Q4. コメントする
圧倒的な技術力と知識、そして勤勉さと忍耐力でただひたすら寡黙に、粛々と目的の実現に邁進する、そんなチョー日本人らしさを際立たせて物事にあたる姿勢を絶対に崩さないよう、事業を展開するべきだ。東京を出た新幹線の「のぞみ」は京都に定刻から20秒と遅れない。そんな世界中では有りえない仕事をこれからも続けて世界を呆れさせ、驚かせ、そしてさらなる信頼と尊敬を勝ち得るよう、努力すべきだ。日本人にしかできないことはいっぱいある!
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
被害者の安否情報に加え、制圧作戦に関する情報収集にも大きな課題を残した。情報の分析評価や公表のあり方についても疑問が残る。英仏首脳はじめ関係国が制圧作戦に一定の理解を示すなか、日本政府による作戦への批判が際立つ結果となった。政府だけの課題ではない、マスコミ世論も同様である。「人命尊重」を唱えるだけでは代替策、解決策にならない。
Q3. コメントする
情報収集および分析体制の強化。政府与党は日本版NSC(国家安全保障会議)の創設を検討しているが、今回の教訓に即して言えば、創設すべきは日本版SIS(MI6・秘密情報局)である。その諜報要員による人的情報に加え、情報収集衛星の基数を増やし精度を向上させ、高精度の無人偵察機を導入するなどの施策が必要かつ効果的である。制圧作戦を含む軍事情報収集には「ミリミリ」(軍と軍)の関係構築が望ましい。それを目指した政府が「防衛駐在官」の配置を増員するのはよいが、諸外国と違い、彼らは「駐在武官」ではない。そうした戦後日本独自の縛りを解くことが先決ではないか。今後、邦人の保護、救出を可能とすべく自衛隊法を早急に改正すべきことは言うまでもない。海外での武力行使を禁じた憲法解釈の見直しも必要である。
Q4. コメントする
憲法(解釈)の制約から、自衛隊を含め政府の支援を当てにできない以上、企業としては今後とも、民間の専門機関に頼らざるをえない。ところが日本は、民間にも専門機関が育っていない。他方、英米などでは、軍の特殊部隊などで勤務した経験を持つ要員を多数、雇用する民間軍事会社(PMSC)が活躍している。日本の在外公館も(自衛隊ではなく)外国のPMSCに警護を依頼している。日本にも、本格的なPMSCが誕生することが望ましい。陸自の特殊作戦群OBなどが高い能力を持て余している現状は国家的な損失でもある。企業も、日本のPMSCに警護を依頼できれば、より安心・安全が望めるのではないだろうか。ちなみに、あくまで民間企業なので、日本国憲法の縛りも受けない。政府としても、日本版PMSCの育成を支援すべきと考える。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
国際的に見て日本が、極端に「経済」に偏重して、「安全保障」の意識と情報が欠如
外務省・大使館のミッションとして「邦人の保護」の重要度、特定地域の情報に詳しい専門人材の欠如、駐在武官の配置なども課題。
民間企業も地域ごとの実情に合わせた、きめ細かな危機管理体制には程遠い。
外務省・大使館のミッションとして「邦人の保護」の重要度、特定地域の情報に詳しい専門人材の欠如、駐在武官の配置なども課題。
民間企業も地域ごとの実情に合わせた、きめ細かな危機管理体制には程遠い。
1今後の成長市場としての新興国市場についてメディアを含めて、そのチャンスばかりが喧伝されて「バスに乗り遅れるな」との風潮が蔓延している中で、リスクと隣り合わせであることを具体的に考えてきたかの検証が必要。ただし、今後の日本のあり方として新興国への進出がこの事件で躊躇されることは避けるべき.]
国も日本企業を全面的に守る姿勢を明確にして、海外展開を支援すべき。
2まず「経済」と「安全保障」のバランスにおいて、国際的に見て日本が、極端に「経済」に偏重して、「安全保障」の意識と情報が欠如していることに気づくべき
その結果、例えば「アラブの春」を契機としたイスラム武装勢力の拡大など、国際的な安全保障環境の急激な変化に多くは無関心であった。インテリジェンスの世界ではマリが最も危険視されていたことにもあまり関心払われず。
3国もインテリジェンス情報を英米のアングロサクソンからだけに依存していることの限界がある。特に北西アフリカは旧宗主国フランスがポイント。
また情報収集はギブ・アンド・テイクの世界。独自情報を持たなければ、国際連携をしても情報を取れない。
4日本企業の海外展開が進展する中で、外務省・大使館のミッションとして「邦人の保護」がこれまで人的、組織的にも重視されてこなかった。
現地大使館の構造的問題もある。出身省庁ごとの縦割り構造。
特定地域の情報に詳しい専門人材の欠如。大使館にいる現地情報収集のための「専門調査員」の地位も低く、任期も2年と短い。
今回のような軍事行動に関しては軍事情報であり、駐在武官など軍のネットワークでなければ情報は取れない。駐在武官の配置不足、語学も備えた人材不足、大使館の他の部署との情報共有不足も指摘される。
5自衛隊の任務としても「邦人の保護、救出」を重視した制度整備を行ってこなかった。「安全でなければ活動できない」といった矛盾を抱えたままでいる。
6多くの日本企業においても、標準装備である、①危機管理マニュアルの作成 ②保険会社系のリスク管理会社との契約 をしていれば一安心との風潮がある。地域ごとの実情に合わせた、きめ細かな危機管理体制には程遠い。危機発生時の対外広報のあり方として、今回の日揮の対応は評価すべきで、他の日本企業も参考にすべき。
国も日本企業を全面的に守る姿勢を明確にして、海外展開を支援すべき。
2まず「経済」と「安全保障」のバランスにおいて、国際的に見て日本が、極端に「経済」に偏重して、「安全保障」の意識と情報が欠如していることに気づくべき
その結果、例えば「アラブの春」を契機としたイスラム武装勢力の拡大など、国際的な安全保障環境の急激な変化に多くは無関心であった。インテリジェンスの世界ではマリが最も危険視されていたことにもあまり関心払われず。
3国もインテリジェンス情報を英米のアングロサクソンからだけに依存していることの限界がある。特に北西アフリカは旧宗主国フランスがポイント。
また情報収集はギブ・アンド・テイクの世界。独自情報を持たなければ、国際連携をしても情報を取れない。
4日本企業の海外展開が進展する中で、外務省・大使館のミッションとして「邦人の保護」がこれまで人的、組織的にも重視されてこなかった。
現地大使館の構造的問題もある。出身省庁ごとの縦割り構造。
特定地域の情報に詳しい専門人材の欠如。大使館にいる現地情報収集のための「専門調査員」の地位も低く、任期も2年と短い。
今回のような軍事行動に関しては軍事情報であり、駐在武官など軍のネットワークでなければ情報は取れない。駐在武官の配置不足、語学も備えた人材不足、大使館の他の部署との情報共有不足も指摘される。
5自衛隊の任務としても「邦人の保護、救出」を重視した制度整備を行ってこなかった。「安全でなければ活動できない」といった矛盾を抱えたままでいる。
6多くの日本企業においても、標準装備である、①危機管理マニュアルの作成 ②保険会社系のリスク管理会社との契約 をしていれば一安心との風潮がある。地域ごとの実情に合わせた、きめ細かな危機管理体制には程遠い。危機発生時の対外広報のあり方として、今回の日揮の対応は評価すべきで、他の日本企業も参考にすべき。
Q3. コメントする
1日本の情報収集体制の整備・・・以下のハードとソフト、官と民の複合的な整備が不可欠
① 偵察衛星の数を早急に増やすべき
② 駐在武官の拡充(ただしアフリカ・フランス語圏ではフランス語必須)
③ 特定地域の専門家を養成するために、大使館の専門調査員の任期5年にしたうえで、外交官としての地位向上を。
④ 大使館(駐在武官を含む)と現地民間企業トップによる形骸化しない定期情報交換の場を作るなど、国ごとに現地での官民一体での複合的情報収集体制を
⑤ 日本企業においても、欧米のインテリジェンス情報に強い危機管理専門会社をリテインするなど、コストベネフィットを精査して検討する
⑥ IISS(国際戦略研究所)のレポート、FT(フィナンシャル・タイムズ)の記事など、安全保障情報として最低限押さえておくべき情報をフォローする体制を社内で整備する。
そのうえで、日本単独では限界があることから、国際的連携・ネットワークを強化。そのためには日常的な人脈を地道に形成。
2自衛隊のよる邦人保護、救出を現実的に行えるよう、自衛隊法の改正を早急に行うべき。前提は民間だけにリスクを負わせないのが基本。
3中東、アフリカなどリスクの高い地域においては、民間企業も欧米の軍隊経験者からなる国際的な民間警備会社に依頼することも普及しており、こういう手段も視野に入れるべき。
① 偵察衛星の数を早急に増やすべき
② 駐在武官の拡充(ただしアフリカ・フランス語圏ではフランス語必須)
③ 特定地域の専門家を養成するために、大使館の専門調査員の任期5年にしたうえで、外交官としての地位向上を。
④ 大使館(駐在武官を含む)と現地民間企業トップによる形骸化しない定期情報交換の場を作るなど、国ごとに現地での官民一体での複合的情報収集体制を
⑤ 日本企業においても、欧米のインテリジェンス情報に強い危機管理専門会社をリテインするなど、コストベネフィットを精査して検討する
⑥ IISS(国際戦略研究所)のレポート、FT(フィナンシャル・タイムズ)の記事など、安全保障情報として最低限押さえておくべき情報をフォローする体制を社内で整備する。
そのうえで、日本単独では限界があることから、国際的連携・ネットワークを強化。そのためには日常的な人脈を地道に形成。
2自衛隊のよる邦人保護、救出を現実的に行えるよう、自衛隊法の改正を早急に行うべき。前提は民間だけにリスクを負わせないのが基本。
3中東、アフリカなどリスクの高い地域においては、民間企業も欧米の軍隊経験者からなる国際的な民間警備会社に依頼することも普及しており、こういう手段も視野に入れるべき。
Q4. コメントする
カントリーリスクに対しては、最終的には、国が貿易保険制度で投資リスクをカバーする制度を強化することが基本。
そのうえで、上記3は中国の反日暴動、タイの洪水、インドの労働争議などさまざまなカントリーリスクに共通する。企業においては国ごとに事情が異なることから、重点地域ごとに社内体制をチェックしたうえで、現地大使館、ジェトロだけでなく当該地域の鍵になる他社との連携も図る。
いずれにしても個別企業では限界があるので、官民一体としての取り組みが不可欠。
そのうえで、上記3は中国の反日暴動、タイの洪水、インドの労働争議などさまざまなカントリーリスクに共通する。企業においては国ごとに事情が異なることから、重点地域ごとに社内体制をチェックしたうえで、現地大使館、ジェトロだけでなく当該地域の鍵になる他社との連携も図る。
いずれにしても個別企業では限界があるので、官民一体としての取り組みが不可欠。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
まず今回は犠牲者の方々に深く哀悼の意を表するとともに、今後、こういった惨事
が繰り返されないことを願って止みません。
その上で、今回、日本が学ぶべきは「日本の常識、世界の非常識」ということのよ
うに思います。
フランス大統領のオランド氏が、今回のアルジェリア政府の行動に支持を表明した
ように、必ずしも人命よりも今後のテロ対策に重点を置く国も世界には数多くあり
ます。
かつて山本七平が「日本人は水と安全を無料だと思っている」と言いましたが、ま
さに我々は世界で最も安全な恵まれている国で生活している、ということを認識す
べきだと思います。
が繰り返されないことを願って止みません。
その上で、今回、日本が学ぶべきは「日本の常識、世界の非常識」ということのよ
うに思います。
フランス大統領のオランド氏が、今回のアルジェリア政府の行動に支持を表明した
ように、必ずしも人命よりも今後のテロ対策に重点を置く国も世界には数多くあり
ます。
かつて山本七平が「日本人は水と安全を無料だと思っている」と言いましたが、ま
さに我々は世界で最も安全な恵まれている国で生活している、ということを認識す
べきだと思います。
Q3. コメントする
コストはかかりますが、国も企業も安全を守るための費用を組み込み、その上でビ
ジネスしていくことしかないと思います。
費用を組み込むことで利益が出ないのであれば、そのビジネスは成立しない、と考
えるべきだと思います。
ジネスしていくことしかないと思います。
費用を組み込むことで利益が出ないのであれば、そのビジネスは成立しない、と考
えるべきだと思います。
Q4. コメントする
私もアジア各国を周ってマーケティングをしているので、大変危ない目にも遭った
ことが何度もあります。
ここ数年、定期的に起きている中国の暴動で、日本企業の工場などが壊され、それ
が政府に補償されるわけでもなく、多くの日本企業は初めてカントリーリスクを意
識し始めた段階だと思います。
個人で危機を乗り越えねばならない状況に陥ることもあり、多くの企業のこれまで
のリスク管理が充分とは言えない状況だと思います。
前述したように、これからはリスク対策費用も必要経費と考えられる時代に突入し
ていると思います。
ことが何度もあります。
ここ数年、定期的に起きている中国の暴動で、日本企業の工場などが壊され、それ
が政府に補償されるわけでもなく、多くの日本企業は初めてカントリーリスクを意
識し始めた段階だと思います。
個人で危機を乗り越えねばならない状況に陥ることもあり、多くの企業のこれまで
のリスク管理が充分とは言えない状況だと思います。
前述したように、これからはリスク対策費用も必要経費と考えられる時代に突入し
ていると思います。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
先ず、今回の事件で被害に遭われた方々とその御遺族の皆様に対し、心よりお悔やみ申し上げます。
テロの可能性が高い地域や政情不安定な地域であっても、我が国のエネルギー資源の確保のためにどのような事業が行われているのか、そのような場所で誰が働いているのか、我々日本国民は改めてしっかりと知る必要があると思う。
その上で、そうした危険な地域での日本国民の安全確保のための経済的方策、軍事的方策等の在り方について、国際的な常識に照らして何が必要か、今後早期に洗い出して具体策を実施すべきである。
また、特にエネルギー資源安全保障の観点からは、我が国において、石油・ガス火力発電や原子力発電を含めたエネルギーベストミックスとはどのような形か、偏重した感情論を抜きにして冷静な視点で打ち立てていくべきである。
カントリーリスクへの対応としては、地域にもよるが、国家ないし国際協調による保険・保証システムを強化する方向で検討すべきであろう。
テロの可能性が高い地域や政情不安定な地域であっても、我が国のエネルギー資源の確保のためにどのような事業が行われているのか、そのような場所で誰が働いているのか、我々日本国民は改めてしっかりと知る必要があると思う。
その上で、そうした危険な地域での日本国民の安全確保のための経済的方策、軍事的方策等の在り方について、国際的な常識に照らして何が必要か、今後早期に洗い出して具体策を実施すべきである。
また、特にエネルギー資源安全保障の観点からは、我が国において、石油・ガス火力発電や原子力発電を含めたエネルギーベストミックスとはどのような形か、偏重した感情論を抜きにして冷静な視点で打ち立てていくべきである。
カントリーリスクへの対応としては、地域にもよるが、国家ないし国際協調による保険・保証システムを強化する方向で検討すべきであろう。
Q3. コメントを控える
問2にて回答
Q4. コメントを控える
問2にて回答
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
日本は安全ということで、ともすれば世界も安全と思いがちですが、アメリカなど銃社会があるということ。
かつてフレーズといわれて英語がわからず、動いたらうたれて死亡するという日本人もいました。
ただ、今回の場合は、防ぎようがないような状況です。
安倍首相は、強行突破を避けるようお願したというが、それも聞き入れてもらえなかった。
正直、どうすればいいのかいい考えは浮かばない。
かつてフレーズといわれて英語がわからず、動いたらうたれて死亡するという日本人もいました。
ただ、今回の場合は、防ぎようがないような状況です。
安倍首相は、強行突破を避けるようお願したというが、それも聞き入れてもらえなかった。
正直、どうすればいいのかいい考えは浮かばない。
Q3. コメントする
自分が総理ならと思っても、手の打ちようはあったのだろうか。
外交による日本のメッセージ、危険な国にはいかないということぐらいだが、
中々その判断も難しいかったのではないか。
外交による日本のメッセージ、危険な国にはいかないということぐらいだが、
中々その判断も難しいかったのではないか。
Q4. コメントを控える
問3に回答
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
一回の人質事件で日本人が9人も尊い命が奪われたのはあまり前例がない。何も罪がない日本人の企業戦士が殺されたのは、痛恨の極みであり、テロリストに対し、言葉で表現できない怒りを感じています。
今回の人質事件で日本政府の現地情報の乏しさに驚いた。国際テロリストに対する警戒が緩んでいるのではないかと思う。確かに国際テロ組織アルカイダのリーダーであるビンラディンがアメリカの攻撃で死亡した。しかし、テロ活動は無くなるのではなく、むしろ世界各地で増殖している。反テロは依然として、各国の重要課題となっている。しかし、いまの安倍政権は「中国けん制」に偏っているので、テロへの警戒を緩んでいる。このツケは後、必ず回ってくる。
従いまして、日本が学ぶ課題として、次の3つがあげられる。
①反テロの持続的な努力
②問われる日本の情報収集の能力
③国際連携の強化
今回の人質事件で日本政府の現地情報の乏しさに驚いた。国際テロリストに対する警戒が緩んでいるのではないかと思う。確かに国際テロ組織アルカイダのリーダーであるビンラディンがアメリカの攻撃で死亡した。しかし、テロ活動は無くなるのではなく、むしろ世界各地で増殖している。反テロは依然として、各国の重要課題となっている。しかし、いまの安倍政権は「中国けん制」に偏っているので、テロへの警戒を緩んでいる。このツケは後、必ず回ってくる。
従いまして、日本が学ぶ課題として、次の3つがあげられる。
①反テロの持続的な努力
②問われる日本の情報収集の能力
③国際連携の強化
Q3. コメントする
上記の課題を解決するために
①テロ危険性に対する再認識を要する。
現実の脅威は本当に中国なのかそれともテロなのか。きちんと理路整然の現状認識を整理しなければなら ない。
②諜報活動の強化。特に日本企業の石油輸入依存度が高い地域、大型案件が展開中の地域に大幅に増強する
必要がある
③政府一本化組織の創設で、危機対応能力を強化する。今の政府対応は無力感を感じさせざるを得ない。
④日本独自の情報力が弱く、欧米諸国との国際連携を強化することが必要である。
①テロ危険性に対する再認識を要する。
現実の脅威は本当に中国なのかそれともテロなのか。きちんと理路整然の現状認識を整理しなければなら ない。
②諜報活動の強化。特に日本企業の石油輸入依存度が高い地域、大型案件が展開中の地域に大幅に増強する
必要がある
③政府一本化組織の創設で、危機対応能力を強化する。今の政府対応は無力感を感じさせざるを得ない。
④日本独自の情報力が弱く、欧米諸国との国際連携を強化することが必要である。
Q4. コメントする
当面、中東・アフリカ地域は不安定さをましているので、これらの地域への進出やビジネス展開は慎重にしたほうがいいと思う。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
外国において人質が取られたら、もう対応できることは少ない。したがって、日本がなすべきことは、いかにして、こうした事態に至らないようにできるかを、総合的に考えていくことが必要。
外国において人質が取られたら、もう対応できることは少ない。したがって、日本がなすべきことは、いかにして、こうした事態に至らないようにできるかを、総合的に考えていくことが必要。
第一に、国際的なさまざまな対立に対して、外交政策を戦略的に見直していくことが必要ではないか。テロに対しては対決する姿勢は必要であるが、中近東における軍事的な介入のあり方については是々非々で中立的な姿勢は取れないだろうか。
第二に、テロが起きる原因となる貧困等の構造的な問題に対して、人道的な取り組みを推進しながら、その事実を、しっかりと国際社会にアピールして、十分に理解してもらうことが必要ではないか。すなわち、テロ組織から日本が標的になりにくい国となるための努力はできないか。
第三に、テロを実行する人々への資金・武器の流れを断絶するための法的規制を、より実効性のあるものとするべく、国際的な連携をさらに強めていくことが必要。マネーロンダリング防止や情報収集活動などの安全保障強化は必要。
このほか、海外における邦人の保護に関する条約を充実強化する取り組みを推進するとともに、現状において、相手国で人命尊重の理念がどの程度実現できるかについてを明らかにし、その程度に応じた対策を、各企業において可能な限り検討すること、それを国家と連携して推進することも必要だろう。
第一に、国際的なさまざまな対立に対して、外交政策を戦略的に見直していくことが必要ではないか。テロに対しては対決する姿勢は必要であるが、中近東における軍事的な介入のあり方については是々非々で中立的な姿勢は取れないだろうか。
第二に、テロが起きる原因となる貧困等の構造的な問題に対して、人道的な取り組みを推進しながら、その事実を、しっかりと国際社会にアピールして、十分に理解してもらうことが必要ではないか。すなわち、テロ組織から日本が標的になりにくい国となるための努力はできないか。
第三に、テロを実行する人々への資金・武器の流れを断絶するための法的規制を、より実効性のあるものとするべく、国際的な連携をさらに強めていくことが必要。マネーロンダリング防止や情報収集活動などの安全保障強化は必要。
このほか、海外における邦人の保護に関する条約を充実強化する取り組みを推進するとともに、現状において、相手国で人命尊重の理念がどの程度実現できるかについてを明らかにし、その程度に応じた対策を、各企業において可能な限り検討すること、それを国家と連携して推進することも必要だろう。
Q3. コメントする
上記課題を実現するために必要な人材の登用。さらに、将来的にそうした課題を担う人材の育成が必要。
また、それらの課題を検討するための英知を結集する組織も必要。
資金・武器の流れを断絶するための法的規制の強化については、国際的な連携を担う法律専門家を強化する必要がある。日本は、マネーロンダリング防止の規律について、まだ不十分であるとの厳しい指摘も受けており、改善の余地があろう。
また、それらの課題を検討するための英知を結集する組織も必要。
資金・武器の流れを断絶するための法的規制の強化については、国際的な連携を担う法律専門家を強化する必要がある。日本は、マネーロンダリング防止の規律について、まだ不十分であるとの厳しい指摘も受けており、改善の余地があろう。
Q4. コメントする
まず、前提として、その対象となる国と、日本との間で、どのような条約が締結されていて、国家間における信頼関係がどのレベルであるのかをチェックすることが必要。
日本国としては、それぞれの国との条約の水準をレベルアップしていくこと、人権尊重、人命尊重の価値観を推進する努力が必要であることは当然である。
そのうえで、危険性の高い国においては、企業として、そのリスクを軽減するための情報管理、防衛体制を構築する必要がある。それには相当なコストもかかることになるので、その辺のリスクが十分に管理できない企業は危険なエリアからは撤退するほかないだろう。
逆に、そうしたリスクに挑戦する企業は、危険に直面した場合の対応方法、防衛体制、人事管理、情報管理、危機対応の訓練、万一の場合の保険に至るまで、広範な対応をするとともに、国としてもバックアップしていくことが求められる。
一方、そうした危険な国家においてはビジネスを行わないというポリシーも、一つの見識だと思われ、そうした危険な国から、安全な国家に脱皮するためのインセンティブを強く働かせるように仕向けていくという考え方も必要ではないだろうか。
日本国としては、それぞれの国との条約の水準をレベルアップしていくこと、人権尊重、人命尊重の価値観を推進する努力が必要であることは当然である。
そのうえで、危険性の高い国においては、企業として、そのリスクを軽減するための情報管理、防衛体制を構築する必要がある。それには相当なコストもかかることになるので、その辺のリスクが十分に管理できない企業は危険なエリアからは撤退するほかないだろう。
逆に、そうしたリスクに挑戦する企業は、危険に直面した場合の対応方法、防衛体制、人事管理、情報管理、危機対応の訓練、万一の場合の保険に至るまで、広範な対応をするとともに、国としてもバックアップしていくことが求められる。
一方、そうした危険な国家においてはビジネスを行わないというポリシーも、一つの見識だと思われ、そうした危険な国から、安全な国家に脱皮するためのインセンティブを強く働かせるように仕向けていくという考え方も必要ではないだろうか。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
今回の事件では、アルジェリア政府にとって、人質の人命よりもアルカイダ系のイスラム武装勢力を殲滅することの方が重要だったことが明らかになった。アルジェリアに限らず、政情が不安定化した中東やアフリカの国々では、政府と反政府勢力の力が拮抗し、多少の人命を犠牲にしても、政府が自らの存続のために武力を行使することは大いに起こりうることである。そいうった外国政府に対して、日本政府が人命優先を主張しても、必ずしも聞き入れられるとは限らないのが国際社会の現実である。今回の事件は、我々にそのことを改めて認識させたくれたと言えよう。
Q3. コメントする
日本政府が上記のような事態に対処するためには、的確な情報を迅速に収集し、それを現地の企業や邦人に迅速に提供することが第一であり、それに尽きるのではないか。特に、アルカイダ系や反政府組織の動きを重点に、ある国の政情がどのように変化しつつあるのか、それによって、一般人や現地の企業活動に対する危険性がどの程度変化するのかを分析し、速やかに関係の現地企業や邦人に提供するシステムを確立することが重要である。この情報の収集分析については、日本政府だけでは限界があるので、アメリカやフランス、イギリスなどの情報機関と緊密な連携が取れる体制を日常的に確立しておくことが必要となる。
そういったカントリー・リスクの高い国で活動する企業がリスク管理を強化・徹底するのは当然だが、企業努力だけでは上記のような情報の収集分析には対応できない。やはり、政府の情報提供が基本とならざるを得ないと思われる。
ちなみに、研究のため、一昨年チュニジアに、昨年はアルジェリアとモロッコに行ったが、今回の事件のような雰囲気は感じなかった。どこかの国がアプリオリに危険ということではなく、危険な動きがいつどこで起きるのかであり、そういった動きをいかに迅速かつ正確に察知できるかが鍵になると思う。
そういったカントリー・リスクの高い国で活動する企業がリスク管理を強化・徹底するのは当然だが、企業努力だけでは上記のような情報の収集分析には対応できない。やはり、政府の情報提供が基本とならざるを得ないと思われる。
ちなみに、研究のため、一昨年チュニジアに、昨年はアルジェリアとモロッコに行ったが、今回の事件のような雰囲気は感じなかった。どこかの国がアプリオリに危険ということではなく、危険な動きがいつどこで起きるのかであり、そういった動きをいかに迅速かつ正確に察知できるかが鍵になると思う。
Q4. コメントする
問3の回答と同じ。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
「テロとの戦い」と「人命尊重」の二兎を追うことは極めて困難だということをわれわれに再認識させた。
「国境なき技術団」を標榜してきた日揮(JGC)。日揮の外国受注比率は実に9割、売り上げの8割を外国で稼ぐ。有能な技術者を数多く抱える日揮は自他共に認める世界屈指のプラント大手である。最先端技術力とそれをコーディネートする技術は他社の追随を許さない。日本が世界に誇る日揮のスタッフがいまいましいテロの犠牲になったことは日揮のみならず日本産業界の損失である。
今回のイスラム武装勢力によるテロはいわゆる「アラブの春」の副産物である。フランス軍のマリ軍事介入はイスラム武装勢力の肩を押したに過ぎない。「アラブの春」を通じて北アフリカ独裁国の独裁者の息の根が止められた。特に、リビアのカダフィ大佐が殺害されたことで無数の近代武器・兵器が大量に流出。その多くがイスラム武装勢力の手に渡ったとされる。イスラム武装勢力の兵力は確実に強化されている。
われわれが今回のテロを通じて再認識したことは「テロリストとの交渉には応じない」とする大原則と「人命尊重」の二兎を追うことは極めて困難だということである。しかもイスラム武装勢力によるテロの手口は一種類ではない。多様な手口に対応していかなければならないということも再認識させられた。
もう一つ。アルジェリアのような独裁国で事業展開することにともなう課題である。独裁国では武装勢力掃討作戦の際、現地情報に関しては統制が敷かれる。被害者、犠牲者の情報提供は限定的だという現実だ。ただ、日揮は独裁国であるからこそ継続的に事業を受注できてきた面もある。なかなか悩ましいところだ。
日本政府は「人命は地球よりも重い」という原則を貫く。しかし、非情だが、アルジェリア大統領にとって人命よりも天然ガスプラントの安全のほうが重いのである。であるがゆえに、強行突破した。アルジェリアの天然ガス生産量は年間780億立方メートル。このうちテロの舞台となったイナメナス天然ガス田の生産量は90億立方メートルで12%を占有する。アルジェリアからイタリアを筆頭とする欧州諸国に天然ガスが輸出される。資源エネルギー関連の輸出がアルジェリア輸出総額の95%を占めると同時に、同産業が同国国内総生産(GDP)の3割を稼ぐ。
資源エネルギーの生産国と消費国、それに進出企業の事業展開。非常に難しいバランスの上に日揮の事業が成立している。
今回のイスラム武装勢力によるテロはいわゆる「アラブの春」の副産物である。フランス軍のマリ軍事介入はイスラム武装勢力の肩を押したに過ぎない。「アラブの春」を通じて北アフリカ独裁国の独裁者の息の根が止められた。特に、リビアのカダフィ大佐が殺害されたことで無数の近代武器・兵器が大量に流出。その多くがイスラム武装勢力の手に渡ったとされる。イスラム武装勢力の兵力は確実に強化されている。
われわれが今回のテロを通じて再認識したことは「テロリストとの交渉には応じない」とする大原則と「人命尊重」の二兎を追うことは極めて困難だということである。しかもイスラム武装勢力によるテロの手口は一種類ではない。多様な手口に対応していかなければならないということも再認識させられた。
もう一つ。アルジェリアのような独裁国で事業展開することにともなう課題である。独裁国では武装勢力掃討作戦の際、現地情報に関しては統制が敷かれる。被害者、犠牲者の情報提供は限定的だという現実だ。ただ、日揮は独裁国であるからこそ継続的に事業を受注できてきた面もある。なかなか悩ましいところだ。
日本政府は「人命は地球よりも重い」という原則を貫く。しかし、非情だが、アルジェリア大統領にとって人命よりも天然ガスプラントの安全のほうが重いのである。であるがゆえに、強行突破した。アルジェリアの天然ガス生産量は年間780億立方メートル。このうちテロの舞台となったイナメナス天然ガス田の生産量は90億立方メートルで12%を占有する。アルジェリアからイタリアを筆頭とする欧州諸国に天然ガスが輸出される。資源エネルギー関連の輸出がアルジェリア輸出総額の95%を占めると同時に、同産業が同国国内総生産(GDP)の3割を稼ぐ。
資源エネルギーの生産国と消費国、それに進出企業の事業展開。非常に難しいバランスの上に日揮の事業が成立している。
Q3. コメントする
唐突だが、米国ではシェール革命で原油と天然ガスの生産量が急上昇している。早晩、輸入に依存しない日が到来する。そうなると、米国の納税者は米軍が中東地域に駐留することに反発するようになるだろう。米軍が撤退した後の空白をどの国が埋めるのか。日本は永続的に中東産の原油に依存しなくてはならない。ワシントンは北・西アフリカに軍事介入することを極度に嫌う。リビアでもマリでも欧州諸国のリーダーシップに丸投げした。今回のアルジェリアでの事件では欧米各国の介入を嫌う同国大統領が単独でイスラム武装勢力の掃討作戦を強行した。
日本政府は従来、安全保障に関しては米国重視一辺倒で、勢い、欧州諸国との軍事的連携には消極的だった。この姿勢が今回のテロ事件では裏目に出た。米国との関係強化を図る一方、表現的に重複するが、欧州諸国、北大西洋条約機構(NATO)加盟国との連携強化も図っていかなければならない。場合によってはロシアとの関係強化も必要だろう。
イスラム武装勢力がイスラム教を悪用し、武装闘争を繰り返す限り、地球上からテロは消滅しない。特に、資源大国では今後も同様のテロが頻発することだろう。しかしそれでも、資源エネルギー関連企業には完全撤退の選択肢はない。アルジェリアでも軍による警戒は充分だったと思われる。それでも事件が発生した。テロ事件発生後にどのように対処すればいいのかをあらためて主要国で検討すべきではないか。民間企業にはこのような対策を講じる手立ては限られる。政府間の連携が重要だと思う。
日本政府は従来、安全保障に関しては米国重視一辺倒で、勢い、欧州諸国との軍事的連携には消極的だった。この姿勢が今回のテロ事件では裏目に出た。米国との関係強化を図る一方、表現的に重複するが、欧州諸国、北大西洋条約機構(NATO)加盟国との連携強化も図っていかなければならない。場合によってはロシアとの関係強化も必要だろう。
イスラム武装勢力がイスラム教を悪用し、武装闘争を繰り返す限り、地球上からテロは消滅しない。特に、資源大国では今後も同様のテロが頻発することだろう。しかしそれでも、資源エネルギー関連企業には完全撤退の選択肢はない。アルジェリアでも軍による警戒は充分だったと思われる。それでも事件が発生した。テロ事件発生後にどのように対処すればいいのかをあらためて主要国で検討すべきではないか。民間企業にはこのような対策を講じる手立ては限られる。政府間の連携が重要だと思う。
Q4. コメントする
カントリーリスクにはさまざまな側面があるが、テロに限定すると、特殊情報機関を設置して、テロリスト集団への潜入捜査を本気で考える必要があるかもしれない。いわばスパイをスパイするわけである。特に、北・西アフリカ一帯ではイスラム武装勢力が国境に関係なく自由に往来している。国境警備の強化を関係国に要請するとともに、日本政府としてはそのための資金を拠出しなければならないだろう。進出企業に一任するのではなく、政府間で連携強化を図ることが重要だろう。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
世界は広い、人種はもちろん、国の経済発展や民主化の程度も、さらに何といっても宗教も異なる。
日本や先進国の常識が、発展途上国で通じるという考えは捨ててかからなければならない。
日本や先進国の常識が、発展途上国で通じるという考えは捨ててかからなければならない。
世界は広い、人種はもちろん、国の経済発展や民主化の程度も、さらに何といっても宗教も異なる。
日本や先進国の常識が、発展途上国で通じるという考えは完全に捨ててかからなければならない。
日本や先進国の常識が、発展途上国で通じるという考えは完全に捨ててかからなければならない。
Q3. コメントする
相手国の、人種や宗教、さらに歴史や周囲国との関係等について、詳しい情報収集と分析が必要。世界情勢の変化に瞬時に対応して、今後起こりうる紛争等を察知する能力の向上が重要。もちろん加えて日頃からの国民レベルでの交流による相互理解の促進も積極的に行うべき。
Q4. コメントする
経済最優先で進出を決めることは多くのリスクを伴うことを今回の事件は教えてくれた。政府と民間ともに協調しながら相手国の十分な情報をえて対応することしかないのでは。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
私たちが住んでいる所や交流をもっている国のものの考え方や文化とは
全く異なる人々が生きている国や社会背景をもっと理解しておかなくては
ならないということだと思います。
全く異なる感覚をもつ人々についての理解を深める。
正直、人命がこんなに軽いとは思わなかったので、、、、、、
全く異なる人々が生きている国や社会背景をもっと理解しておかなくては
ならないということだと思います。
全く異なる感覚をもつ人々についての理解を深める。
正直、人命がこんなに軽いとは思わなかったので、、、、、、
Q3. コメントする
仕事のために出かけてゆく国について民間も含めて、まず相互理解を深める必要を思う。
今回も手を打っていたと思われるが、スキをつかれた感がある。
もっともっと慎重に国外へ出かけていかないと重ねてテロの餌食になってしまいそうな気がする。
日本人に対しての誤解も諸外国には少なくないのではないか。
今回も手を打っていたと思われるが、スキをつかれた感がある。
もっともっと慎重に国外へ出かけていかないと重ねてテロの餌食になってしまいそうな気がする。
日本人に対しての誤解も諸外国には少なくないのではないか。
Q4. コメントする
極めて難しい問題。
セキュリティー強化だけでは済まない気もします。
セキュリティー強化だけでは済まない気もします。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
9・11米国同時多発テロをきっかけに米国主導で始まった「対テロ戦争」はいまも続いており、一部の地域では文字どおり戦争なのだという事実。そしてそれが「戦争」である以上、敵からの攻撃は当たり前、当事国が人質の命を軽視した軍事行動を取る可能性も十分にあるという、国際社会の冷酷な現実を直視すること。
2001年の9・11米国同時多発テロ事件をきっかけに米国主導で始まった「対テロ戦争」はいまなお広い範囲で続いており、一部の地域では文字どおり「戦争」なのだという事実。
にもかかわらず、日本人は官民あげて、「対テロ戦争」という表現を一種の比喩としか受け止めて来なかったために、敵(テロリスト)の反撃にあって、海外に居住する日本人や日本企業の安全が脅かされる危険について真面目に対策を練って来なかったし、現に事件が起こった後も、テロリストと交渉するなかで人質が解放されることを期待した。テロを犯罪と見なしているがゆえに、国内の通常の立籠り事件と同様の発想で臨んだと言っていいだろう。
けれどもアルジェリアでは、イスラム武装組織も政府軍もともに20年に及ぶ内戦を戦ってきた経緯があり、これが「戦争」である以上、他の状況では認められないような、あらゆる戦術の使用が正当化されるとテロリストの側が考えていたと思われる一方で、アルジェリア軍も、戦争に犠牲はつきものであり、将来に禍根を残さない(より大きな損害を被らない)ためには人質を犠牲にしてでも敵であるテロリストを殲滅しなくてはならないといった、まさに現に戦争を戦っている者たちの論理が優先された。アルジェリア軍の作戦を「最も適切な対応だった」と評価するフランス政府もまた、現に戦争を戦っており、戦争当事者の論理に立っている。また、欧米諸国政府の対応がおおむね沈静化しつつあるのも、同じく「これは戦争なのだ」という認識がある程度まで共有されているがゆえのことであろう。
よって、アルジェリア人質事件から日本が学ぶべき教訓は何より、「対テロ戦争」はまさに戦争に他ならず、戦争である以上、敵からの攻撃があるのは当然で、当事国の軍が人質の人命を軽視した作戦行動を取る可能性も十分にあるという、今日の国際社会の冷酷な現実であろうと思われる。人命が軽視されてしまうのは極めて遺憾なことではあるが、それもまた現実であることに疑いはない。
にもかかわらず、日本人は官民あげて、「対テロ戦争」という表現を一種の比喩としか受け止めて来なかったために、敵(テロリスト)の反撃にあって、海外に居住する日本人や日本企業の安全が脅かされる危険について真面目に対策を練って来なかったし、現に事件が起こった後も、テロリストと交渉するなかで人質が解放されることを期待した。テロを犯罪と見なしているがゆえに、国内の通常の立籠り事件と同様の発想で臨んだと言っていいだろう。
けれどもアルジェリアでは、イスラム武装組織も政府軍もともに20年に及ぶ内戦を戦ってきた経緯があり、これが「戦争」である以上、他の状況では認められないような、あらゆる戦術の使用が正当化されるとテロリストの側が考えていたと思われる一方で、アルジェリア軍も、戦争に犠牲はつきものであり、将来に禍根を残さない(より大きな損害を被らない)ためには人質を犠牲にしてでも敵であるテロリストを殲滅しなくてはならないといった、まさに現に戦争を戦っている者たちの論理が優先された。アルジェリア軍の作戦を「最も適切な対応だった」と評価するフランス政府もまた、現に戦争を戦っており、戦争当事者の論理に立っている。また、欧米諸国政府の対応がおおむね沈静化しつつあるのも、同じく「これは戦争なのだ」という認識がある程度まで共有されているがゆえのことであろう。
よって、アルジェリア人質事件から日本が学ぶべき教訓は何より、「対テロ戦争」はまさに戦争に他ならず、戦争である以上、敵からの攻撃があるのは当然で、当事国の軍が人質の人命を軽視した作戦行動を取る可能性も十分にあるという、今日の国際社会の冷酷な現実であろうと思われる。人命が軽視されてしまうのは極めて遺憾なことではあるが、それもまた現実であることに疑いはない。
Q3. コメントする
「対テロ戦争」が文字どおり「戦争」であることをきちんと認識したうえで、まずは敵であるテロリストについてきちんと研究し、その戦力と戦術を分析して、味方の損害を可能な限り小さなものに留める努力をすること。
9・11米国同時多発テロ事件の直後に刊行した拙監著『よくわかるイスラム原理主義のしくみ』(中経出版)の冒頭で、あえて私は「戦争を始めるにあたって、「敵」を知る努力すら放棄するというのは、果たして正しい態度なのだろうか。ふつう戦争を始めるときには、敵がなぜ戦うのかを研究して情報戦を有利に進めるとか、敵の戦力を分析してできるだけ味方の損害を少なく留めるとか、不必要に敵の数を増やさないなどの政治的な努力が不可欠なはずである。「テロリストとの戦争」を強く支持する論者の中には、反対派を「平和ボケ」と罵った輩もいたが、敵の研究もせず「テロリスト憎むべし」という信条だけで戦争に加わろうとする人々こそ、「超平和ボケ」なのではあるまいか」と挑発的なことを書き、そのうえで「これは「戦争」なのだ。宣戦布告した相手に反撃されないと信じていい理由などどこにもない。日本国内はともかく、今後の展開によっては、海外に居住する日本人や日本企業の安全が脅かされる危険を当然考慮しておくべきだろう。日本政府にその準備は出来ているか。…アメリカ人は等しく自分たちが海外で狙われる可能性を考慮してきたし、米国政府も海外に居住するアメリカ人の安全を守るために最善の努力をしてきた。日本政府が海外に住む日本人の安全を確保するために何をできるのかが、これからは問われて行くのである」と警鐘を鳴らし、「しかし、いずれにしても海外に居住する日本人の安全対策は、ほとんど手つかずの状態といえる。「敵」の反撃からどうやって国民を守るのか。「敵」の研究もせずに戦争に突入し、国民を守るための目立った方策もとらず、反撃を受けて初めてことの重大さに気づき、責任逃れに走るような間の抜けた日本政府ではないことを祈りたい」と同書をしめくくったが、以来10年あまり、幸いにして外国で働く日本企業の方々がテロの犠牲になった例はなく、そうであったがゆえに、海外に居住する日本人の安全対策は相変わらずあまり重視されないまま、今日に至ってしまった観がある。しかしながら、海外で暮らす日本人の安全を守るためにも、まずは敵であるテロリストについてきちんと研究し、その戦力と戦術を分析する体制を整える必要があろう。
9・11米国同時多発テロ事件の直後に刊行した拙監著『よくわかるイスラム原理主義のしくみ』(中経出版)の冒頭で、あえて私は「戦争を始めるにあたって、「敵」を知る努力すら放棄するというのは、果たして正しい態度なのだろうか。ふつう戦争を始めるときには、敵がなぜ戦うのかを研究して情報戦を有利に進めるとか、敵の戦力を分析してできるだけ味方の損害を少なく留めるとか、不必要に敵の数を増やさないなどの政治的な努力が不可欠なはずである。「テロリストとの戦争」を強く支持する論者の中には、反対派を「平和ボケ」と罵った輩もいたが、敵の研究もせず「テロリスト憎むべし」という信条だけで戦争に加わろうとする人々こそ、「超平和ボケ」なのではあるまいか」と挑発的なことを書き、そのうえで「これは「戦争」なのだ。宣戦布告した相手に反撃されないと信じていい理由などどこにもない。日本国内はともかく、今後の展開によっては、海外に居住する日本人や日本企業の安全が脅かされる危険を当然考慮しておくべきだろう。日本政府にその準備は出来ているか。…アメリカ人は等しく自分たちが海外で狙われる可能性を考慮してきたし、米国政府も海外に居住するアメリカ人の安全を守るために最善の努力をしてきた。日本政府が海外に住む日本人の安全を確保するために何をできるのかが、これからは問われて行くのである」と警鐘を鳴らし、「しかし、いずれにしても海外に居住する日本人の安全対策は、ほとんど手つかずの状態といえる。「敵」の反撃からどうやって国民を守るのか。「敵」の研究もせずに戦争に突入し、国民を守るための目立った方策もとらず、反撃を受けて初めてことの重大さに気づき、責任逃れに走るような間の抜けた日本政府ではないことを祈りたい」と同書をしめくくったが、以来10年あまり、幸いにして外国で働く日本企業の方々がテロの犠牲になった例はなく、そうであったがゆえに、海外に居住する日本人の安全対策は相変わらずあまり重視されないまま、今日に至ってしまった観がある。しかしながら、海外で暮らす日本人の安全を守るためにも、まずは敵であるテロリストについてきちんと研究し、その戦力と戦術を分析する体制を整える必要があろう。
Q4. コメントする
中東・北アフリカをはじめとするイスラーム世界にあって、最も警戒すべき安全上のリスクは、都市に住む日本企業の社員が通勤途中に攻撃され、拉致・誘拐されるというケースかと思われるが、これについては現地の武装ガードマン、とりわけ退役軍人や警察OBを雇用して警護させることで、かなりの程度までリスクを回避できるだろう。
一方、今回の人質事件の舞台になった砂漠のプラントなどの場合、軍が警備していることから、武装ガードマンを雇うことすら軍に認めてはもらえず、軍の警備能力を信頼するしかないというのが実情ではないかと思われる。
自衛隊を海外派遣できるように法改正するとか、人質救出のための特殊部隊を強化するといった案も耳にするが、残念ながら各国には主権というものがあり、現に世界有数の特殊部隊を持つ米英仏も、他国で勝手気ままに作戦行動を取ることはできないのが実情で、特殊部隊の海外派遣によって問題が解決するわけではない。
このためもあって、正直なところ、人里離れたプラントなどで働いておられる日本企業の方々のリスクを抜本的に解消できる方策は見当たらず、現地の軍や警察に警備のいっそうの強化を要望することくらいしかできないようにも思われる。
一方、今回の人質事件の舞台になった砂漠のプラントなどの場合、軍が警備していることから、武装ガードマンを雇うことすら軍に認めてはもらえず、軍の警備能力を信頼するしかないというのが実情ではないかと思われる。
自衛隊を海外派遣できるように法改正するとか、人質救出のための特殊部隊を強化するといった案も耳にするが、残念ながら各国には主権というものがあり、現に世界有数の特殊部隊を持つ米英仏も、他国で勝手気ままに作戦行動を取ることはできないのが実情で、特殊部隊の海外派遣によって問題が解決するわけではない。
このためもあって、正直なところ、人里離れたプラントなどで働いておられる日本企業の方々のリスクを抜本的に解消できる方策は見当たらず、現地の軍や警察に警備のいっそうの強化を要望することくらいしかできないようにも思われる。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
日本政府は今回の人質テロを人命第一の危機管理として理解し、警察が対処した。しかしながら、アルジェリア政府は政権転覆をめぐるテロリストからの戦争だととらえて、安全保障問題として対処した。このアルジェリア政府の対応をフランス政府はいち早く評価している。また、米国のオバマ政権もいち早く、パネッタ国防長官が陣頭指揮をとり、国防総省が対処し、無人飛行機をとばし空軍のC130輸送機を現地に派遣した。イギリスも特殊部隊を待機させた。すなわち、日本人救出のみを考えて動いた日本。それとテロとの闘いとして対処した、米英仏をはじめとする国際的な意識の違いが歴然としたケースであった。
Q3. コメントする
したがって、日本政府は自衛隊を活用しmili-miliのコンタクトをしてはじめて情報収集が可能となる。また、アルカイダをはじめとするテロリストはアフガニスタンやイラクからアフリカに移動しつつあり、今後とも同じような事件は起こる可能性が高い。
早い段階から日本政府は自衛隊に任務をあたえ米軍とのすり合わせが必要である。自衛隊ができることは、給油、輸送、あるいはc130輸送機の活用など積極的に後方支援をすることが必要となろう。
早い段階から日本政府は自衛隊に任務をあたえ米軍とのすり合わせが必要である。自衛隊ができることは、給油、輸送、あるいはc130輸送機の活用など積極的に後方支援をすることが必要となろう。
Q4. コメントする
企業自身の対策はブラックウオーター等の民兵会社にsecurityを依頼することが必要だと思われる。また、情報収集のために独自のnetworkを拡充する必要がある。特に、フランス、イギリスの軍事関連機構、情報組織などとの接触が必要となろう。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
日本は、再生可能エネルギーの普及推進を加速するべきだ。これにより、脱原発依存、CO2削減、および、エネルギー安全保障の推進にも貢献できる。
中東の場合もそうだが、特に、エネルギー資源地帯=危険地帯であることを認識するべき。
Q3. コメントする
今回の事件をエネルギー問題の観点から考えてみる。日本は、2030年の原発比率決定の一環として、水力発電を含む再生可能エネルギーの比率を30%程度まで増やすという案が検討された。ドイツはもっと積極的であり、2030年までに50%まで引き上げる計画を持っている。現在の日本では、再生可能エネルギーの推進は、主として脱原発依存の観点から議論されることが多いが、同時に脱化石燃料も重視すべき。これによりCO2削減のみならず、エネルギー安全保障の推進にも貢献できる。
Q4. コメントする
海外進出企業は、国際的な危機に当って、日本政府の情報収集能力、対応能力は当てにならないことも認識するべき。その上で、
・地元政府との連携強化など企業レベルでの危機対応能力を高めるべきであり、
・従業員に対しては、勤務地を選ぶ権利を尊重すべき。つまり、危険地帯への赴任を強要しない
などの対策が必要。
・地元政府との連携強化など企業レベルでの危機対応能力を高めるべきであり、
・従業員に対しては、勤務地を選ぶ権利を尊重すべき。つまり、危険地帯への赴任を強要しない
などの対策が必要。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
今回の事件を受けて「アフリカは危ない」「途上国は危ない」かのような印象が広まるかもしれないが、
本来必要なリスク管理を行っていくうえではそういうステレオタイプ的な認識が一番危ないのではないかと思う。アフリカでも地域によってこうした進出企業にとってのリスクは全く異なり(当たり前ですが)、アフリカに進出する日本企業の半数以上が集中する南アフリカではイスラム過激派勢力によるテロ事件等のリスクははるかに少ないし、ケニア、タンザニアなど発展が著しいインド洋沿岸の東アフリカ地域もかつてのようなアルカイダ系勢力の影響はほとんどみられない。
いわゆる「アラブの春」が北アフリカ地域で起きたこと、リビアから流出した武器が北西エリアの政情不安定国に流れ込んでいること、今回の犯行の背景に実行グループのイスラム武装勢力内でのある種の「内紛」 があるとみられること、首謀者の中に西欧の白人が含まれていたことなど、こうした人質テロ事件が発生する背景が複雑化していることもある。
「アフリカが危ない」「イスラム原理主義の武装勢力が危ない」という一面的な認識ではなく、リスク要素を多面的、複層的にとらえて考える、備えるという思考と行動の習慣を身につけることが政府としても、個々の企業としても、一人ひとりの日本人としても必要なのではないかとおもいます。
本来必要なリスク管理を行っていくうえではそういうステレオタイプ的な認識が一番危ないのではないかと思う。アフリカでも地域によってこうした進出企業にとってのリスクは全く異なり(当たり前ですが)、アフリカに進出する日本企業の半数以上が集中する南アフリカではイスラム過激派勢力によるテロ事件等のリスクははるかに少ないし、ケニア、タンザニアなど発展が著しいインド洋沿岸の東アフリカ地域もかつてのようなアルカイダ系勢力の影響はほとんどみられない。
いわゆる「アラブの春」が北アフリカ地域で起きたこと、リビアから流出した武器が北西エリアの政情不安定国に流れ込んでいること、今回の犯行の背景に実行グループのイスラム武装勢力内でのある種の「内紛」 があるとみられること、首謀者の中に西欧の白人が含まれていたことなど、こうした人質テロ事件が発生する背景が複雑化していることもある。
「アフリカが危ない」「イスラム原理主義の武装勢力が危ない」という一面的な認識ではなく、リスク要素を多面的、複層的にとらえて考える、備えるという思考と行動の習慣を身につけることが政府としても、個々の企業としても、一人ひとりの日本人としても必要なのではないかとおもいます。
Q3. コメントする
インフラ輸出を国策として推進する方針を政府が示している以上、コストがかかるとはいえ、大使館の駐在武官を増やす、欧米のあまり関係性が深くない国々より日系企業が多く進出する国々の情報収集やセキュリティー体制構築するなどの大使館機能を強化する、などが求められると思います。
あと、日常ベースの態勢では、日本は米英等と異なり情報機関を実質的にもたないため、情報の収集・解読・分析がアメリカとイギリス頼りになっているが、これに問題があることは言うまでもない(解決策はないけど)。
欧米メジャーのBPやスタトイルさえ今回の事件を予期できなかった以上、日本政府や日本企業がこうした事件を予期するのは極めて困難という説明はまったくその通りだが、ならば仕方ないというわけにもいかない。しかし、正直言って対処できる問題でもない。
あと、日常ベースの態勢では、日本は米英等と異なり情報機関を実質的にもたないため、情報の収集・解読・分析がアメリカとイギリス頼りになっているが、これに問題があることは言うまでもない(解決策はないけど)。
欧米メジャーのBPやスタトイルさえ今回の事件を予期できなかった以上、日本政府や日本企業がこうした事件を予期するのは極めて困難という説明はまったくその通りだが、ならば仕方ないというわけにもいかない。しかし、正直言って対処できる問題でもない。
Q4. コメントを控える
おおむね上記の2つの設問への回答に含まれている通りです。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
今回の事件で日本政府は迅速に的確に対応したが、課題も明らかになった。今回の事件の教訓をもとに、与野党、政府と国民が協力して危機管理に強い国家作りに向けて協力しよう。亡くなった方々の死を無駄にしないためにも。
日本政府と日本国民に多くの教訓を与えた事件であった。
第1に、日本政府は極めて迅速に対応した。アルジェリアが情報を十分に開示しないまま、何が起きているのか不明な点が多いという状況で、1月17日に欧州滞在中の城内外務大臣政務官をアルジェリアに入れた。日本人の安全を確認するための任務を遂行すべく、「対テロ緊急展開チーム(TRT-2)」は、1月18日にアルジェに到着した。迅速な対応だった。このような事態に直面したとき、迅速に判断する能力がいかに大事かを我々は知った。
第2に、テロリズムに関する発想の転換が課題となっている。これだけ経済がグローバル化し、テロリズムが拡散し、凶悪になっていることから、日本人が直接にテロに遭遇して、被害を受けることがあることを教えてくれた。これまでの会社と国家と個人のテロ対策が不十分であることを教えてくれた。相互の連携、情報の共有や、迅速な国際社会の情報入手が重要であることがわかった。プラント建設の事業にかかわっているというだけで、一瞬にして仕事熱心な夫、息子、兄弟、友人、同僚が、むごい殺されかたをして、人生を終えるということが起きた。テロ対策の前提を全面的に見直すことが必要になっている。
第3に、テロが起きやすい地域で危険が高まりつつあるというテロ情報を出すとき、想定の幅を広げながら、国際政治の分析をして、テロ関連情報を出すことが課題になっている。今回、「フランス軍がアルジェリア上空を経由して、マリを攻撃したところ、テログループがアルジェリア上空通過を許したアルジェリア政府への非難を始めて、アルジェリア内の天然ガスプラントを攻撃の対象にした」という話が事実なら、国際政治の現実は想定の域を超えていたことになる。フランス、マリ、イスラム原理主義、アルジェリア、日本企業、テロ被害という展開を誰が予想しただろうか。アルジェリアのプラント建設事業に関わる欧米と日本の企業の幹部の会議開催日を事前に知って狙った襲撃であるならば、会議開催場所の選定もテロ対策では重要になってくる。
第4に、テロに対処し、人命の被害を最小に食い止めるべく、実力行使をする軍事力は日本にはない。外国で邦人の命をテロ集団から守るための軍事能力はない。まずは危機に際して、邦人を安全に避難させる法律、安全に輸送する装備を点検して、不足するものは導入を検討することから始めたい。テロに起因する危機を管理するための法律、装備、情報収集の国際ネットワーク作りを、政府主導で行う。国民のひとりとして、邦人の安全確保のために何が必要かを考えたい。「外国で自衛隊が武器を使用することには反対」と言うだけでは、邦人の安全を確保することはできない。
第1に、日本政府は極めて迅速に対応した。アルジェリアが情報を十分に開示しないまま、何が起きているのか不明な点が多いという状況で、1月17日に欧州滞在中の城内外務大臣政務官をアルジェリアに入れた。日本人の安全を確認するための任務を遂行すべく、「対テロ緊急展開チーム(TRT-2)」は、1月18日にアルジェに到着した。迅速な対応だった。このような事態に直面したとき、迅速に判断する能力がいかに大事かを我々は知った。
第2に、テロリズムに関する発想の転換が課題となっている。これだけ経済がグローバル化し、テロリズムが拡散し、凶悪になっていることから、日本人が直接にテロに遭遇して、被害を受けることがあることを教えてくれた。これまでの会社と国家と個人のテロ対策が不十分であることを教えてくれた。相互の連携、情報の共有や、迅速な国際社会の情報入手が重要であることがわかった。プラント建設の事業にかかわっているというだけで、一瞬にして仕事熱心な夫、息子、兄弟、友人、同僚が、むごい殺されかたをして、人生を終えるということが起きた。テロ対策の前提を全面的に見直すことが必要になっている。
第3に、テロが起きやすい地域で危険が高まりつつあるというテロ情報を出すとき、想定の幅を広げながら、国際政治の分析をして、テロ関連情報を出すことが課題になっている。今回、「フランス軍がアルジェリア上空を経由して、マリを攻撃したところ、テログループがアルジェリア上空通過を許したアルジェリア政府への非難を始めて、アルジェリア内の天然ガスプラントを攻撃の対象にした」という話が事実なら、国際政治の現実は想定の域を超えていたことになる。フランス、マリ、イスラム原理主義、アルジェリア、日本企業、テロ被害という展開を誰が予想しただろうか。アルジェリアのプラント建設事業に関わる欧米と日本の企業の幹部の会議開催日を事前に知って狙った襲撃であるならば、会議開催場所の選定もテロ対策では重要になってくる。
第4に、テロに対処し、人命の被害を最小に食い止めるべく、実力行使をする軍事力は日本にはない。外国で邦人の命をテロ集団から守るための軍事能力はない。まずは危機に際して、邦人を安全に避難させる法律、安全に輸送する装備を点検して、不足するものは導入を検討することから始めたい。テロに起因する危機を管理するための法律、装備、情報収集の国際ネットワーク作りを、政府主導で行う。国民のひとりとして、邦人の安全確保のために何が必要かを考えたい。「外国で自衛隊が武器を使用することには反対」と言うだけでは、邦人の安全を確保することはできない。
Q3. コメントする
第1に、会社のみでは安全対策、危機管理は困難であることが判明した。アルジェリア政府の治安維持安全対策の強化が必要だ。天然ガスプラントの建設は、日本のエネルギー事情の改善に貢献するものだった。日本の国益に合致する事業にかかわっていた人々が命を落とした。だから、アルジェリア政府に対して安全対策を日本政府がリーダーシップをとり、強力に申し入れる。アルジェリア人はテロリストから「兄弟だ」といわれて釈放され、外国人が標的となった。そして、アルジェリア政府は無事に解放されたアルジェリア人の数を含めながら「多数の人が解放されたのだから、アルジェリア政府の作戦は間違っていなかった」という説明しているが、何か割り切れないものが残る。
第2に、的確な国際テロ情報を国家的規模で収集し分析をするために、外務省職員として情勢分析にあたる防衛省出身の防衛駐在官の数を増やす。いま世界の43カ国にしか防衛駐在官がいない状態であり、もちろんアルジェリアには駐在していない。エジプトには防衛駐在官がいるが、アフリカには最低5名の駐在官がほしい。アフリカでの情報収集に関しては、日本のメデイアも今回の報道にあたって独自の取材を開始するまでに時間がかかった。BBC、CNNの映像ばかりだった。日本人の間で、北アフリカの政治を日本の安全保障との関連で分析する視点が不足にしていたことを反映していた。この地域の情勢分析をする体制を強化したいものだ。アラビア語を駆使しながら通訳を介さないで、現地の報道をリアルタイムで入手して、分析できる人材を政府部内と民間会社で養成し、その情報と分析結果は「テロ対策情報」として、即刻、官民で共有するシステムを作る。
第3に、今回の事件の教訓であるが、日本だけの力では、国際的な規模のテロには対処できない。日本政府は米国、英国などと協力しながら迅速に対処した。今後も過激派のテロに対しては、国際協力が重要であることがわかった。米国、英国、フランスなどと国際的な対テロ対策の協力網を構築する。
第4に、このような危機管理という事態は今後増えるだろう。日本政府は指揮統制の面で、一元化した指揮体制をとる体制を強化する。今回、日本政府の対応には不手際はなかったと思うが、危機管理体制をさらに強化するために、米国なみの国家安保会議を創設する。
第5に、テロ発生国の許可を得て、日本人の脱出を支援しながら、日本に無事帰国させることができるのは自衛隊になる。火器を装備した陸上自衛官も派遣できるように、法律面を改正する。テロリストとの交戦を覚悟の上で、邦人を輸送するような事態も今後は想定して、武器使用基準の見直しに着手する。
第2に、的確な国際テロ情報を国家的規模で収集し分析をするために、外務省職員として情勢分析にあたる防衛省出身の防衛駐在官の数を増やす。いま世界の43カ国にしか防衛駐在官がいない状態であり、もちろんアルジェリアには駐在していない。エジプトには防衛駐在官がいるが、アフリカには最低5名の駐在官がほしい。アフリカでの情報収集に関しては、日本のメデイアも今回の報道にあたって独自の取材を開始するまでに時間がかかった。BBC、CNNの映像ばかりだった。日本人の間で、北アフリカの政治を日本の安全保障との関連で分析する視点が不足にしていたことを反映していた。この地域の情勢分析をする体制を強化したいものだ。アラビア語を駆使しながら通訳を介さないで、現地の報道をリアルタイムで入手して、分析できる人材を政府部内と民間会社で養成し、その情報と分析結果は「テロ対策情報」として、即刻、官民で共有するシステムを作る。
第3に、今回の事件の教訓であるが、日本だけの力では、国際的な規模のテロには対処できない。日本政府は米国、英国などと協力しながら迅速に対処した。今後も過激派のテロに対しては、国際協力が重要であることがわかった。米国、英国、フランスなどと国際的な対テロ対策の協力網を構築する。
第4に、このような危機管理という事態は今後増えるだろう。日本政府は指揮統制の面で、一元化した指揮体制をとる体制を強化する。今回、日本政府の対応には不手際はなかったと思うが、危機管理体制をさらに強化するために、米国なみの国家安保会議を創設する。
第5に、テロ発生国の許可を得て、日本人の脱出を支援しながら、日本に無事帰国させることができるのは自衛隊になる。火器を装備した陸上自衛官も派遣できるように、法律面を改正する。テロリストとの交戦を覚悟の上で、邦人を輸送するような事態も今後は想定して、武器使用基準の見直しに着手する。
Q4. コメントする
経済のグローバル化で日本の企業は一層、海外に進出してゆくだろう。日本の企業は、様々なカントリー・リスクに対処してゆく必要がある。資源争奪に起因する地域情勢の不安定化や、宗教的理由による対立の激化、米国、中国、ロシアの思惑が絡み合い、地域紛争やテロの原因が多様になっていることに着目する必要がある。国際戦略情報の分析力を強化したい。具体的には、
1 アフリカ、中東、東南アジア(とくにインドネシア)での民間企業の経済活動の安全確保が必要。産業基盤建設にかかわる民間企業がイスラム過激派に襲撃される場合、大きな被害が発生する。国家的事業に関わっている企業の安全確保には、国家の一層の支援が必要だ。世界でテロが発生したとき、米国や英国などの特殊部隊が緊急に対処できるような国際的協議を事前に行っておくことも一案だろう。日本は邦人の救出のために、武器を携行した陸上自衛隊員が、海上、航空自衛隊の装備を活用して緊急輸送を行うことができるよう、自衛隊を改正する。装備の改善をしておく。
2 朝鮮半島の有事という危機では、韓国にいる邦人を緊急に救出するための準備が必要。韓国には観光客と在住者を合わせると、常時3万人の邦人がいるが、有事にどう救出するかが確立していない。日韓の事前取り決めもない。邦人が韓国から出国できないままで、韓国内の空港は破壊されて使用できない。海上自衛隊の艦船は、韓国に寄港して邦人輸送をすることを試みるが、港湾も破壊された港湾が多くて接岸できないまま、長崎港、舞鶴港で足止めという事態になる。自衛隊が邦人輸送に向おうとしても、韓国政府の承諾が確認できないまま、時間がすぎてゆくという展開は大いにありうる。緊急時どうするかを、いまから日韓で話し合っておくことは大事だ。
対策として、日本は邦人救出を想定して、接岸する桟橋がなくとも輸送ができる揚陸艦の機能を持った艦船を20隻に増やす。
また緊急事態発生の時、もっとも重要なものは、本人の「自助努力」だろう。今回のアルジェリアのテロ事件でも、拘束されそうになったとき、息をひそめながら潜伏して脱出し、鉄条網を切断して1キロを走って逃げた英国人が助かった。このような場合、自分で工夫して脱出する智慧と勇気と体力が決め手となることが多い。朝鮮半島有事で韓国に残された人は、自力で自転車でもお借りしながら、自分の力でできるだけ南下して、釜山にたどり着いて船で対馬に向かうのがよいのかもしれない。
1 アフリカ、中東、東南アジア(とくにインドネシア)での民間企業の経済活動の安全確保が必要。産業基盤建設にかかわる民間企業がイスラム過激派に襲撃される場合、大きな被害が発生する。国家的事業に関わっている企業の安全確保には、国家の一層の支援が必要だ。世界でテロが発生したとき、米国や英国などの特殊部隊が緊急に対処できるような国際的協議を事前に行っておくことも一案だろう。日本は邦人の救出のために、武器を携行した陸上自衛隊員が、海上、航空自衛隊の装備を活用して緊急輸送を行うことができるよう、自衛隊を改正する。装備の改善をしておく。
2 朝鮮半島の有事という危機では、韓国にいる邦人を緊急に救出するための準備が必要。韓国には観光客と在住者を合わせると、常時3万人の邦人がいるが、有事にどう救出するかが確立していない。日韓の事前取り決めもない。邦人が韓国から出国できないままで、韓国内の空港は破壊されて使用できない。海上自衛隊の艦船は、韓国に寄港して邦人輸送をすることを試みるが、港湾も破壊された港湾が多くて接岸できないまま、長崎港、舞鶴港で足止めという事態になる。自衛隊が邦人輸送に向おうとしても、韓国政府の承諾が確認できないまま、時間がすぎてゆくという展開は大いにありうる。緊急時どうするかを、いまから日韓で話し合っておくことは大事だ。
対策として、日本は邦人救出を想定して、接岸する桟橋がなくとも輸送ができる揚陸艦の機能を持った艦船を20隻に増やす。
また緊急事態発生の時、もっとも重要なものは、本人の「自助努力」だろう。今回のアルジェリアのテロ事件でも、拘束されそうになったとき、息をひそめながら潜伏して脱出し、鉄条網を切断して1キロを走って逃げた英国人が助かった。このような場合、自分で工夫して脱出する智慧と勇気と体力が決め手となることが多い。朝鮮半島有事で韓国に残された人は、自力で自転車でもお借りしながら、自分の力でできるだけ南下して、釜山にたどり着いて船で対馬に向かうのがよいのかもしれない。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
学ぶべき課題ではなく、すべき事は、当該国と敵対せず、友好的で平和主義を尊ぶ日本、日本人だから安全であると云う認識を改めるべき。犯罪者やテロリストには人道上のモラルや道徳感は無い。特にテロリストにとっての正義は、彼らの主義や行動のみであり、その為には手段を選ばない。一部報道に有る様に、もし今回の事件に、日揮の雇用した現地従業員が、内部からの手引きに関わっていたとしたら、日本人の人柄を逆手に取った愚行だ。
Q3. コメントする
日本企業は、職場に於いての人間関係を大切にし、身内や家族の様に必要以上に扱うところが有る。残念な事だが、雇用に際して、職歴や身辺などのバックグラウンドを念入りにチェックするのが必須。
又、派遣されている日本人社員が技術者やビジネスの関係者ばかりでなく、安全保障や危機管理の専門家はいるのだろうか。欧米企業では、軍や公安などの経験者が、安全管理の専門家として入っているのが多々ある。当該国の軍や警察組織が100パーセント信頼できないゆえ、それを監視する為にも不可欠なファンクション・人員だ。
又、派遣されている日本人社員が技術者やビジネスの関係者ばかりでなく、安全保障や危機管理の専門家はいるのだろうか。欧米企業では、軍や公安などの経験者が、安全管理の専門家として入っているのが多々ある。当該国の軍や警察組織が100パーセント信頼できないゆえ、それを監視する為にも不可欠なファンクション・人員だ。
Q4. コメントする
アジア、アフリカ諸国で、日本企業は、プラント、ダム、交通インフラ、土木等の事業に現在関わり、今後一層成長する産業と思われる。日本政府は、政情が安定せず、内乱、宗教対立が続く、危険と認定される地域、国で事業を行う日本企業を守るために、安全・防御対策を自ら行う仕組みを構築しなければならない。日本企業への被害を防ぐのは、国益の損出を防ぎ、生命を守るのは日本人の人権を国際社会での紛争から守ることであり、企業だけがする事では無い。自衛権は日本人、日本企業がいる地域全てに該当する。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
リスクは存在する
リスクは必ずある。
Q3. コメントする
絶対安全はあり得ない。リスクを減らすということしかない、という認識を持つこと。
Q4. コメントする
普通に現地の人々と同じように行動する。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
世界には日本国内より安全な場所はないという自覚をもって、原則として自分の身は自分で守るという方針で外国での活動に臨むべきことを、改めて痛感させられた。
日本人が外国に行けば、日本政府の主権が及ばないのは当然である。だから、日本政府の主権が及ぶ日本国内で政府が日本国民の安全を守るのと同じように、外国政府が自らを守ってくれるかどうかはわからないという不確実性がある。それは、日本政府の怠慢ということではなく、むしろ外国での活動ではこれが当たり前であることを改めて肝に銘じて臨むべきと考える。
Q3. コメントする
グローバル化が進む今日、外国で活動する日本人は増えている。そのためにも、日本の主権が及ばない外国において自らの身をどう守るかについて、外国に出る前に日本人にきちんと認識させるような取組みが求められる。
Q4. コメントする
極言して言えば、赴いた先々で日本人がアメリカ人の仲間と同一視されているか否かをきちんと踏まえた上で適切な対処が求められる。日本人は、西洋人ではなく東洋人であるという認識が当然ながら強くあるが、赴く先(特にアメリカと敵対している勢力がいる国)によっては、日本人は東洋人であるというよりアメリカと同様の先進国の人という認識が先立つ場合がある。そうした現地の認識と日本人の認識にギャップがある場合、日本人や日本企業にとってリスクが高まる可能性がある。特に、日本人や日本企業にとって自覚がなかなか出てこないだけに、日本人や日本企業自身がこれを「リスク」と認識できないかもしれない。その間隙を狙って、日本人や日本企業の活動に支障をきたす恐れが出てくる。こうしたことのないように、現地の日本人に対する認識について、感度を高くして情報収集することが重要と考える。
Q2. 「1 - 回答する(問2にお答えください。)」の回答理由
「テロリストとは交渉しない」というアルジェリア政府の姿勢は欧米各国が基本的に支持していた。多少の犠牲はやむなし、というのが世界の常識になってきている。「人命尊重の立場から人質の釈放を求める」とテロリストに呼びかけることの無意味さを日本政府以外の世界は知っている。かつて日本で、福田首相が「人命は地球よりも重い」と言って、ハイジャック犯の要求を飲んだことがある。身柄拘束しているハイジャック犯の仲間を釈放し、身代金を支払い、テロリストグループからも各国政府の双方から「日本は甘い」と見られた歴史もある。
日本はキリスト教の国ではなく、アメリカとか西ヨーロッパの国でもなく、国民が勤勉で経済復興を遂げた国として、日本国も日本人もイスラム社会から「敵」と見られたことはなかった。しかし、2003年のイラク戦争で小泉政権がとった「米ブッシュ政権支持」と「自衛隊派遣」でイスラム社会からは「アメリカの属国」と見られるようになった。
小泉氏の後継色強い安倍政権が「日米関係を最重視する」とか、「集団的自衛権の行使を認めるべき」とか、さらには「憲法改訂」や「自衛隊でなく軍隊に」などと言えば言うほど、イスラムから見れば日本は「敵」になっていく。そして世界に羽ばたく日本の企業戦士も「敵」になっていく。日本人が安倍政権の政策を支持するか支持しないかはともかく、安倍政権の発言はイスラムの世界にも伝わるだろうし、伝わればイスラム社会の対日本観は厳しいものになっていくだろう。旅行者も狙われて人質となり、日本政府に身代金を要求する、という事態もありうる。人質になっても、必ずしも救出されるとは限らない。「テロリストとは交渉しない」のが世界の常識だから、日本人旅行者が多数、命を落とす、ということもあるだろうことを、今回の事件は我々に教えてくれた。
日本はキリスト教の国ではなく、アメリカとか西ヨーロッパの国でもなく、国民が勤勉で経済復興を遂げた国として、日本国も日本人もイスラム社会から「敵」と見られたことはなかった。しかし、2003年のイラク戦争で小泉政権がとった「米ブッシュ政権支持」と「自衛隊派遣」でイスラム社会からは「アメリカの属国」と見られるようになった。
小泉氏の後継色強い安倍政権が「日米関係を最重視する」とか、「集団的自衛権の行使を認めるべき」とか、さらには「憲法改訂」や「自衛隊でなく軍隊に」などと言えば言うほど、イスラムから見れば日本は「敵」になっていく。そして世界に羽ばたく日本の企業戦士も「敵」になっていく。日本人が安倍政権の政策を支持するか支持しないかはともかく、安倍政権の発言はイスラムの世界にも伝わるだろうし、伝わればイスラム社会の対日本観は厳しいものになっていくだろう。旅行者も狙われて人質となり、日本政府に身代金を要求する、という事態もありうる。人質になっても、必ずしも救出されるとは限らない。「テロリストとは交渉しない」のが世界の常識だから、日本人旅行者が多数、命を落とす、ということもあるだろうことを、今回の事件は我々に教えてくれた。
Q3. コメントする
日本政府の危機管理については、情報の収集も、危機対応も、全てアメリカ頼みである。アメリカしか見ない。どこを見るにしてもアメリカというフィルターを通してしか見ない。これでは日本、というより、日本人は、何もイスラム世界だけに限らず、世界で一層危機にさらされる。なにも「反米」をいうのではない。しかし、アメリカにも言うべきは言う、その主権を持ちたい。
自民党政権がしばらく続き、維新もみんなも民主も、同じ種族だとすれば、外交に変化など起こらないだろう。では、民間外交、特に若者のエネルギーに期待するしかないだろうか。
自民党政権がしばらく続き、維新もみんなも民主も、同じ種族だとすれば、外交に変化など起こらないだろう。では、民間外交、特に若者のエネルギーに期待するしかないだろうか。
Q4. コメントを控える
2. 回答を控える
該当する回答がありません

※ご入力いただいた情報の取り扱いについては、『利用目的』をご覧下さい。
また、メッセージを送信される前には『フジテレビホームページをご利用される方へ』を必ずお読み下さい。
※送信内容に個人情報は記載しないようお願いします。
※投稿する際は、件名を編集しないでください。
また、メッセージを送信される前には『フジテレビホームページをご利用される方へ』を必ずお読み下さい。
※送信内容に個人情報は記載しないようお願いします。
※投稿する際は、件名を編集しないでください。

コメントはありません