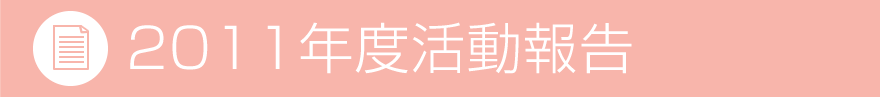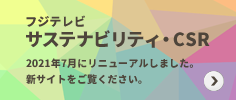こどもおうえんプロジェクト活動報告(3)
岩手県医師会を通じて医療現場にも・・・
[2011年5月17日更新分]
 5月6日、お台場フジテレビから段ボールに詰められたおもちゃ、ぬいぐるみ、絵本などが運び出されました。向かった先は岩手県盛岡市。「こどもおうえんプロジェクト」に賛同していただいた岩手県医師会に届けるためです。
5月6日、お台場フジテレビから段ボールに詰められたおもちゃ、ぬいぐるみ、絵本などが運び出されました。向かった先は岩手県盛岡市。「こどもおうえんプロジェクト」に賛同していただいた岩手県医師会に届けるためです。
 岩手県では今回の東日本大震災で2名の医師が死亡、未だに6名が行方不明となっています。また16の医療施設が全壊、診療不可能な医療機関は35施設にものぼり深刻な被害を受けました。(5月12日現在)
岩手県では今回の東日本大震災で2名の医師が死亡、未だに6名が行方不明となっています。また16の医療施設が全壊、診療不可能な医療機関は35施設にものぼり深刻な被害を受けました。(5月12日現在)
震災発生から2か月以上が経ち、被災者の身体だけでなく心のケアの必要性も高まっており、医療の使命が今問われているところです。そのような状況で、今回岩手県医師会として「こどもおうえんプロジェクト」の意思をご理解いただき快く受け入れて頂きました。
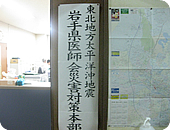

右2人が事務局のお二人。
一番右が藤村さん。
岩手県医師会としては、今後は、被災地の仮設病院を含む医療施設の整備正常化をさらに進めなければならず、また被災した子どもたちの今だけでなく、将来、親になって子どもを産み育てる時に悪い影響が最小限になるよう見据えて医療活動を行って行きたいとのこと。
そこで今回お届けしたおもちゃやぬいぐるみ、絵本などを、被災地の医療施設や子どもたちに直接渡し、心のケアに少しでも役立たせることができればと考えています。
フジテレビでは、今後も、この「東日本大震災・こどもおうえんプロジェクト」を、被災地のニーズに応じて継続して展開していきます。
なお、岩手県医師会よりお礼状を頂きましたので掲載させていただきます。
この度のご好意に感謝いたします。
この度の震災は、神戸の時のような瓦礫に閉じ込められる外傷性のものはほとんど無く、津波により生きる方と亡くなられる方のどちらかに生死が分かれるはっきりした災害であります。
震災後、救命救急のレスキュー期間はそれ程無く、普段通院されている方がお薬も受診券も流されて、被災前からいただいていたお薬を、どこでどのように受け取れるかが医療活動のポイントであります。
その対応も軌道に乗りつつある中で、心の問題、とりわけ大人たちの自殺対応に取組んでおりますが、子どもたちの心の傷がどのくらい傷つき、そして癒せるかも大きな課題です。
私どもの医師会長も、今回の災害で津波が人を飲み込む、親や家族、お友達などの身近な人が目の前でなくなって迎えに来ないなど、子どもの心にトラウマとして刻まれたことをどのようにして癒してゆくか?この子達が、大人になってからもこのことは大きく影響するし、この子達が親になって子どもを生み育てるときにも影響が必ず残ることを大きな課題だと苦慮しています。
地域により習慣、文化は異なりますが子どもたちの心には国境はありません。今回のご支援の効果は必ず子どもの心には届くと考えておりますので、ありがたくお受けさせていただきます。
![]() 文:藤村広栄さん(岩手県医師会事務局)
文:藤村広栄さん(岩手県医師会事務局)