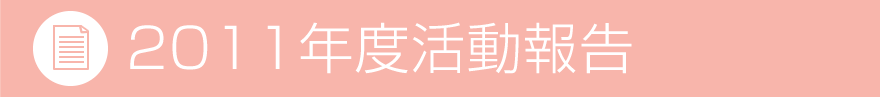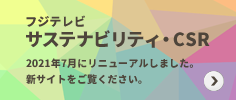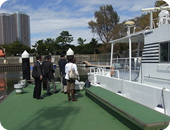東京海洋大学海洋工学部・刑部真弘先生に会いに行きました!
~コンバインドサイクルってなに?洋上発電って?~
[2011年10月26日更新分]
 10月初旬の朝、CSR推進室&プロジェクトチームのメンバーは、月島駅(東京都・中央区)から墨田川にかかる相生橋を渡り・・・・
10月初旬の朝、CSR推進室&プロジェクトチームのメンバーは、月島駅(東京都・中央区)から墨田川にかかる相生橋を渡り・・・・
東京海洋大学の越中島キャンパスへと向かいました。
秋晴れの空が広がる気持ちのいい日でした。
東京海洋大学を訪れた目的は、今、注目されている「コンバインドサイクル」と「船による洋上発電」を研究されている【海洋工学部 海洋電子機械工学科 刑部真弘(おさかべ・まさひろ)教授】に、会いに行くためです。
東日本大震災後、刑部教授のもとには、「電気はないけど、船ならある」「船で発電してそれを使えないか」という問い合わせが被災地から多く寄せられたそうです。
周囲を海に囲まれている台場でもいざという時に役に立つのではと、「洋上での発電」や「賢い電気の使い方」を教えていただきました。
見学ポイントその1
≪研究室にドーン!と設置された手作りの世界最小の複合サイクル発電装置≫
広々としたキャンパスを入り、少し歩くとターボ動力実験棟という文字が見えてきました。
2種類のタービンを組み合わせることで、熱エネルギーをより効率的に利用でき、同じ量の電気を作るのに、CO2排出量も少なくできるすぐれた発電方法なのです!
もっと小型すれば、自宅の庭や屋上において活用することも可能だそうです。
見学ポイントその2
≪船の発電能力を地上に有効利用~やよい丸~≫
船は自家発電なので、予備を含め2つの発電機を備えています。
発電機は船底にある。やよい丸の発電能力は20kW。ただ、この電気は60ヘルツなので(関東エリアの周波数は50ヘルツ)、陸にある変換機で50ヘルツに変換。
・同大学は、勝どきに中型船 :汐路丸(しおじまる:船体長48m、幅10mの中型船)を保有。
こちらは、最大出力500kW(60ヘルツ)もあるそうです。
※ちなみにクイーンメリーII 号は、11万4000kW=一般家庭の電力28万軒分の発電能力をもつ。
見学ポイントその3
≪※スマートグリッド≫

実際の電力使用状況を表す
パソコン画面※電力の流れを供給側、需要側の両方から制御し、
最適化できる送電網のこと。
⇒ 例:みんなが時間をずらしてお風呂に入れば電力は少なくて済む、
といった考え方。
東京海洋大学でも、この夏 電力の使用状況をリアルタイムでウェブ上で公開したそうです。
その結果、15%の節電目標をみごとにクリア。
「寮の学生がどの時間帯に朝食を食べているか、などの行動パターンがわかりました。何度か(目標値を)超えそうになったことはあったが、日本人はマジメだからか、危なくなるとみんなが協力して自然と調整されたんですね。」
(刑部)
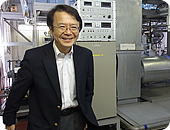 この試みにより"見える化"の効果を実感したそうです。
この試みにより"見える化"の効果を実感したそうです。
素人の私たちに、穏やかな口調で時折ユーモアも交えながら丁寧に説明してくれた刑部先生。
この日得た知識が、お台場の(フジテレビの)いざという時の対応策として活用できるのか、今後検討していきたいと思います。
 |
刑部先生、本当にどうもありがとうございました!