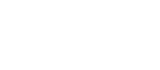これは「あるもの」を誕生させた者たちの挑戦の物語。 それは今や47都道府県、全てに存在し、誰もが利用したことがあると言っても過言ではない。 そんな我々の生活に欠かせないものを誕生させたのは、全く異なる畑出身の素人集団。 しかも…それを海外から持ちもこうとした時、周囲の誰もが猛反対。 立ちはだかるいくつもの壁、それを乗り越えるために考えられた驚愕の秘策の数々。 そして彼らは、戦後最大とも言われる大偉業を成し遂げる。 これは今では当たり前にあるものを、当たり前の存在にするために素人集団が繰り広げた挑戦の物語である。
それは今から52年前の東京で始まった。
鈴木敏文、清水秀雄の2人は、当時業界では17位という、とある中堅企業に勤めていた。
2人は海外研修に参加し、アメリカを訪れた時に偶然知った「あるもの」」の存在が妙に気になり、記録を詳しく調べてみることにした。
すると、2人が見つけた「あるもの」は、アメリカで徐々に増え続け、この時 実に4000も存在していた。
そのことが2人には不思議でならなかった。
そして、アメリカで増え続けているには何か理由があるはず、それを見つけて日本に持ち込めば、新しいビジネスモデルになるのでは。
そう思った鈴木と清水は、アメリカで見つけた「あるもの」を日本に持ち込めないかと、上層部に掛け合った。
すると…猛反発を受けたのだ!
いくらアメリカに4000もあるとはいえ、日本とは文化も社会背景も全く異なる国でのこと。
同じものを持ち込んでも、日本人に受け入れられると思う者は1人もいなかった。
そう、鈴木と清水を除いては。
どうしても諦めきれなかった鈴木と清水は、ある行動に出る。
それは、上司をなんとか説得し、アメリカで「あるもの」を展開している会社、サウスランド社に直談判に出向いたのだ。
そして…8年で1200件展開することを条件にOKをもらった。そして、その売り上げのうち0.6%をロイヤリティーとして支払う契約を結んだ。
上司も渋々了承したものの、2人が勤める会社にとってもこれまで手がけたことがないプロジェクト。 そのため、子会社を設立し、新たな事業として始めることになった。 資本金は親会社が出資してくれたものの、到底足りず。 残りは2人が銀行からの借入や貯金を崩すなどして賄った。
しかも、社の幹部たちは成功する見込みのない事業に人は出せないと、人材の提供をも渋った。 こうした事情もあり、親会社から鈴木たちの新会社に異動してきたのは…当時、労働組合の仕事に専念していた岩國修一、たまたま中途採用で入社したばかりの鎌田誠皓、この2人だけだった。
実は鈴木たちが始めようとしている事業には販売経験が必須。 そこで新聞の求人広告で人材を募集した。 その結果、なんとか11人が集まったのだが、誰も販売経験がなかった。 さらに、鈴木と清水も販売経験はなかった。 こうして、販売経験がないまさに素人集団によって新事業はスタートすることとなった。
アメリカ・サウスランド社から27冊にも及ぶマニュアルが送られてきた。 鈴木たちは、この中に成功の秘訣が書かれているはずと考え、その到着を待ち望んでいた。 それを英語が堪能な鎌田が翻訳していったのだが…そこに書かれていたのは、レジの打ち方や、釣り銭の渡し方など、販売に携わる初心者向けの手引きのようなものばかり。 アメリカで大成功を収めた秘訣のようなことは全く書かれていなかった。
相手に怒りをぶつけようにも、もはや手遅れと感じた鈴木。 こうして15人の素人集団は自分たちでマニュアルを作ることを決意。 たとえ一歩ずつでも前進することを選んだ。
そんな矢先であった。
鈴木に手紙が届いたのだ。
差出人は山本憲司、当時23歳。
彼は東京都江東区で山本茂商店という酒店を経営していた。
鈴木と清水が山本を訪ねると「そちらが始めようとしているお店のフランチャイズ店にしていただきたいんです」という申し出だった。
山本は数年前に亡くなった父親の酒店を継ぐことになったのだが…その時は、まだ大学生だった。 妹はまだ高校2年生、弟が中学2年生という状況で、酒を中心としてしか商品を扱えないことに、店の将来性がないかもしれないと感じた。 そんな時、新聞の募集欄に目が止まった。 8年で1200店舗の展開、その数字を実現すべく、鈴木たちはフランチャイズという形で同じ商売をしてくれる仲間を募っていた。
当時アメリカでは、フランチャイズ店は基本的に夫婦で経営することが望ましく、さらにどちらかが30歳以上の方がより社会的信頼をおけると考えられていた。 だが、鈴木と清水は、新しい道に進みたいと考えている山本と自分たちの思いは同じだと感じ、契約を結ぶことを決意。 こうして、第1号店は山本の店に決定したのである。
半年後に迫るオープンに向け、素人なりにマニュアルを作成しながら、着々と準備が進められた。 その間にも世間からは、成功できる見込みはないと見られていた。 だが、鈴木たちの新会社の社員たちはそんな世間を見返してやろうと一致団結して闘志を燃やしていた。
そんな最中、山本から連絡があった。
なんと結婚したという報告だった!
というのも、「アメリカではフランチャイズ店は基本、夫婦で経営してもらうのが好ましいと考えられています。」という鈴木の言葉を聞いて…山本はどう頑張っても年齢は変えられないが結婚はできると思った。
そしてすぐに学生時代の友人に相談。 小中高の同級生で地元に残っている独身女性を見つけると、「結婚してください」は唐突すぎるので、「一緒にフランチャイズ店をやってくれませんか?」と言ってみた。 すると…あれよあれよと恋仲になり、結婚の運びとなった。
オープン時が近づくにつれ、メンバーたちはさらに活気づいていった。 みんなで1号店オープンを知らせるチラシを作り、近所に配って回った。
そして今から49年前、1974年5月。 鈴木や清水ら、15人の素人集団から始まり、今や我々の生活に欠かせないほど日常に根付いた店、それこそが…日本初の本格的なコンビニ、セブン-イレブンだった。 そして、セブン-イレブン日本第1号店のオーナーこそが山本だった
こうして、東京都江東区に完成した日本初のセブン-イレブン。
開店時間となり、店頭には山本と彼の妻が立つ。
鈴木たちは前日から泊まり込み、その様子を見つめていた。
そして、最初の客が来店。
記念すべきお買い上げ商品第1号は、サングラスであった。
その後もチラシを見た客が次々と訪れ、オープン初日は大盛況!
その日の売り上げは、酒店時代の約2倍であった。
2日目以降も長時間の営業が多くの人に重宝され、日に日に売り上げは上昇、順調な船出を切った。
だが、1号店の開店から1ヶ月後、ある問題が浮かび上がった。
当時は酒店の3倍近い2000品目以上取り扱っていたため、在庫も大量にあった。
その上、1つの商品につき、カップ麺だと10ケースから、缶詰の場合、48個入り1ケースからと大量配送する決まりとなっていた。
さらにその商品を欲しい数だけ配送してもらうという、現在では当たり前の小分け配送ができなかった。
品切れする人気商品は各ジャンルでいくつも出てきた。
つまり、いくつもの品切れ商品を頼むと全て必要以上の数が配送され、置き場がなくなってしまう。
結果、品切れになっているものがあっても、売れ残っている商品の在庫が山積みになっているため、注文できずにいたのだ。
問屋に小分け配送をお願いしたものの、1店舗だけ特別扱いできないと、すげなく断られてしまった。
そこで鈴木は、1号店の周辺に集中して店舗を増やすことを考えた。
そして周辺の増やした店舗に小分け配送をしてもらえば、問屋的にもまとまった数になるため、OKしてもらえるかもしれない。
これを実現すべく、メンバーたちは新たにフランチャイズに加盟してくれる酒店や小型小売店を探し、毎日走り回った。
1号店が話題になっているとはいえ、コンビニの存在自体が理解されていない時代、まだ認知されていないセブン-イレブンに対し警戒する店も多く、加盟してくれる店は、なかなか見つからない。 その気がないと言われても、何度も訪れ、一日中 店の手伝いをするなど、どうにかフランチャイズ店になってもらえるよう、奮闘。 すると、その姿に心を打たれ、承諾してくれる店が現れるように。 そして、1号店の周辺に新たに11店舗のセブン-イレブンをオープンすることに成功したのだ。
この結果を受け、岩國は問屋を説得。
ついに問屋も承諾してくれた。
そして店舗数の増加がより一層の相乗効果を生む。
看板が多くの人の目に触れることで、どの店舗でも客足が伸びていったのだ。
さらに店舗を集中させる方式を用いることで、日本各地で徐々に店舗を増やすことに成功。
まさに素人集団が作り上げた独自マニュアルの一つとなった。
そんな中、鈴木は誰もが考えなかった一手を打とうとしていた。
当時 店頭で販売していたファストフードは、アメリカで販売していたものばかりだったが、鈴木は日本独自のファストフードを生み出すべきだと考えていた。
何かを閃いた鈴木はメンバーに報告したのだが、他の社員たちからは猛反発を受けた。
しかし、「家庭のものと差別化すれば必ず支持される」と押し切り、販売にふみきったもの…それは、おにぎり!
家庭のものと差別化するため、フィルムを抜き去るとパリパリした海苔が巻けるという活気的なスタイルを考案。
販売当初は1日3個程度しか売れなかったが、次第にこのパリパリ食感が話題となり、大ヒット!
見事、コンビニの定番商品となった。
おにぎりのみならず、バリエーション豊かなお弁当や、冬の定番・おでん、本格的な味が楽しめるとセブンプレミアムの商品も当初は大反対されたものであった。
しかし、コンビニのおにぎりやお弁当の登場は、毎日食事の準備をする主婦たちを助け、女性が社会進出するきっかけのひとつとなったという。
他にも、24時間、365日営業など、今のコンビニの常識を次々生み出していったことで、さらに多くの人が利用。
その後も鈴木たちは多くの試行錯誤を繰り返しながら、独自に生み出した経営ノウハウをマニュアルとして蓄積。
セブン-イレブンは着実に店舗数を増やしていった。
そして…ついにサウスランド社と契約する際の条件、8年で1200店舗出店という課題も1年遅れはしたが、クリアすることができたのである。
当初、コンビニエンスストアを始めることに反対していた親会社もこの事実には驚きを隠せなかったという。
親会社は、事業が進むうち、鈴木や清水たちを理解してくれるようになっていた。
その親会社こそ、イトーヨーカ堂である。
こうして鈴木たちの存在がコンビニの存在を当たり前のものに変えていった。
そして彼らはもう一つ、とてつもないことを成し遂げる。
1990年、アメリカでセブン-イレブンを経営していたあのサウスランド社が経営難に陥った。
原因は同業他社との安売り競争など、複合的なものだった。
その中でも大きかったのが、各店舗の売れ筋商品とは関係なく、本社の都合で商品を発送していたこと。
その結果、在庫が山積みになる問題が発生していた。
そんな中、サウスランド社に鈴木と清水が訪れ、日本で培ったノウハウで会社を救ってみせると言った。
鈴木たちは店舗の従業員が自分たちの意思で品薄になった売れ筋の商品を発注、配送してもらうという日本独自のノウハウで、アメリカのセブン-イレブンの既成概念を壊していった。
怒涛の如く常識を打ち破る鈴木についた異名は、ハリケーン・スズキ。
そして、鈴木たちが介入してわずか3年で、サウスランド社は、およそ36億円の利益を上げるまでに復活。
これは、アメリカ戦後最大の再建劇として語り継がれている。
その後も、鈴木たちの挑戦が終わることはなかった。
当時、代表取締役だった鈴木は、取材でこう語っている。
「文字通り『コンビニエンス(便利)』ですから、その時代時代によって便利な商品というのは非常に変わってくるわけです。便利という事になりますと必ずしも食べ物などじゃなくて、他の生活の上においても店で便利さが買えるという様なものに変えていきたいと考えております。」
「大きく変化させていかないと一般の消費者の皆様方に、いわゆる便利な店として利用していただけなくなってしまうと考えています。」
この言葉を体現するかのように、時代のニーズに合った『便利さ』を追求。
品揃えを見直しながら、商品を増やしていった。
1号店の時は2000だった商品数も、現在では3000品目も扱う様になった。
さらに、便利さの追求は商品に留まらない。
コンビニで初の挑戦にも次々に挑戦していった。
例えば、2001年に始めたコンビニのATM。
これにより24時間、いつでもお金を下ろせるようになった。
この他にも、電気・ガス代などの支払いがコンビニでできる収納代行サービスも始めた。
また、小売店舗の少ない地域のために、移動販売サービス『セブンあんしんお届け便』も開始。
実はこのサービス、2011年3月に起きた東日本大震災時に力を発揮した。
鈴木の指揮により、地震発生4分後に対策本部を設置。
宮城・岩手の自治体にトラックで大量に物資を輸送。
その際、『セブンあんしんお届け便』も出向き、被災者に物資を届けてまわった。
日本になかったコンビニという存在。 今では当たり前となった商品の数々、生活を支えるサービスなど、次々と新たなサービスに挑戦した結果、セブン-イレブンは小型小売店の枠を超え、現在、国内 約21,400店舗にまで店舗数を増やし、私たちにとってなくてはならない存在となった。
挑戦することで多くの当たり前を実現していった鈴木は、今から7年前、経営から退いた。
しかし、その火は消える事なく、次の世代が未来に向かい新たな挑戦に挑んでいでいる。
今挑んでいる課題は環境への配慮。
例えば、プラスチック削減のため、丼物の器を紙製にしたり、サンドウィッチの包材も半分は紙製にしたりと、既存の形の見直しを進めている。
さらに、こんな取り組みも。
こちらはセブン-イレブンで使用する野菜を育てている熊本県の農家。
収穫されたブロッコリーはサラダなどの材料になっているが、実はこの茎の部分もあるものに使用されている。
それは、スムージー!
ブロッコリー以外にも従来は見た目の問題だけで規格外となり、破棄されていた傷のついた果物なども使用し、環境にやさしいスムージーを完成させた。
今年で50周年を迎えたセブン-イレブン。
先日、記念すべき節目を祝す式典が行われた。
その中で、この式典に合わせて撮影した鈴木のインタビュー映像が流れ、創業当時について語られていた。
「たまたま運が良くてタイミングが合った。みんなの協力を得たこと、すぐに共鳴してくれたこと。そういう人がいないと広がらない。私は(セブン-イレブンが成功した)大きな要素だと思う。常に新しい事に挑戦する。それにはなんといっても質。質というのはいくら挑戦してもこれでいいってことはない。逆にゴールがないから挑戦できる。」