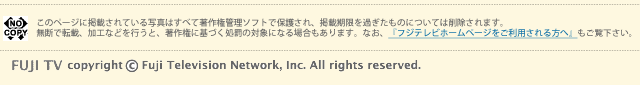今年で45回目の「Inter BEE 2009」。11月18日-20日、千葉市・幕張メッセで開催され、延べ3万人超の来場者を集めた。注目されたのは3D。来年にも発売予定の3Dテレビや、小型化された撮影用3Dカメラが登場。またテレビの新しい視聴スタイルを提案する展示も。携帯電話でテレビに無線通信し、誰が見ているかをテレビが把握、それにあった情報を表示する技術は一般家庭に導入可能な段階という。稲増教授は「テレビ受像器としてだけでなく、いろんな形で応用されていく可能性がある」と語った。
意見書は、バラエティー番組を「人々を新しい感受性に目覚めさせてきた」と評価する一方、視聴者が不快感・嫌悪感を持ち、反発するような問題点があることは否定できない事実と指摘。その上で、シンポジウム開催など放送界全体で議論する場が必要だと訴えた。民放連会長は「制作者レベルまで範囲を広げ、議論を深めていきたい」とコメント。バラエティーをモチーフにした文体で、挿絵も描かれたユニークな意見書で、松野教授は「現場の人間に読んでもらって議論してもらい、良い番組を作ってほしいという叱咤激励の意味がある」と語った。
10月から30分番組を1時間に拡大し、生放送になった『新・週刊フジテレビ批評』。委員から「ニュースと天気予報を無理にあわせた感じ(八木秀次氏)」「批評ではなく番組紹介・解説のレベルで批判的対峙が少ない(毛利衛氏)」「視聴者の声に答える担当プロデューサーが生出演すべき(大石静氏)」「生にした意気込みを感じた(石井英夫氏)」「番組制作の内輪話は今後も入れていくべき(酒井真喜子氏)」などの意見が出た。稲増教授は、「フジテレビ批評」と番組審議会がフジテレビの内と外からの批評として両輪でやっていくことが大事と述べた。
10月時点の調査で、地デジ対応受信機の世帯普及率は69.5%(目標72%)。都道府県別では1位(奈良78.4%)と最下位(岩手55.2%)の差が前回よりも縮まった。一方、アナログ放送終了時期(2011年7月)の認知度は89.6%と高かった。また地デジ対応した人のうち77%が満足と答え、理由として約93%が「画質の良さ」を挙げた。地デジ対応していない理由では「アナログ放送終了まで時間的余裕がある(78.7%)」「経済的余裕がない(40.9%)」が上位だった。稲増教授は、エコポイントなどで普及率が改善してきていると指摘した。
BPO(放送倫理・番組向上機構)の「放送と青少年に関する委員会」は、一連の芸能人薬物事件の報道について青少年への影響を考慮するよう求める要望をまとめた。①薬物が個人の健康や社会に与える深刻な被害の実態を正確に伝え、青少年が手を染めないようにする②薬物への興味を起こさせないよう表現に配慮する③逮捕された個人に焦点をあてるだけでなく、背景や影響などを多角的に報道するよう各放送局に求めた。コメンテーターの砂川氏は今回視聴者からの声が多かった点を挙げ、結果的にバランスを欠いて映ったのでは、と指摘した。