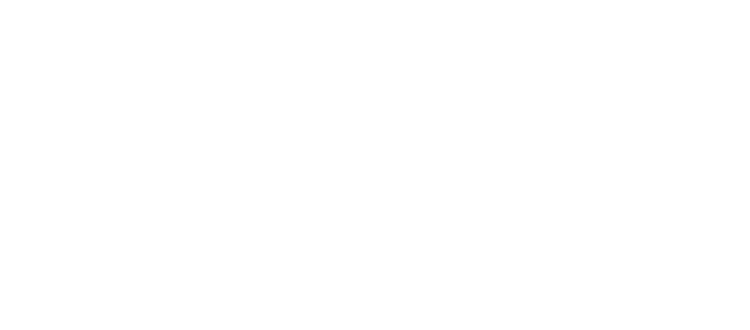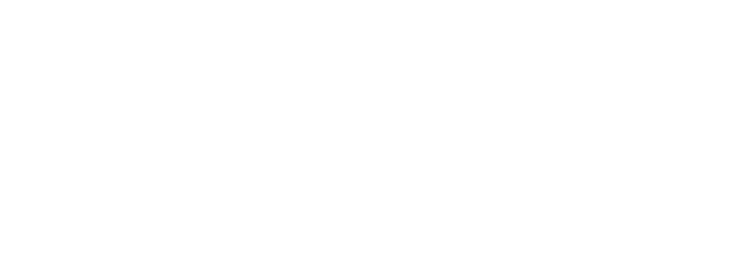2025.09.08
NEWS 14
こども家庭庁の皆さまが
撮影現場を訪問!
宮﨑暖プロデューサーと座談会も実施!
2023年4月に政府が新設した行政機関で、「こどもがまんなかの社会」をつくることを目的に、子どもと家庭の支援を一元化し、児童虐待の防止や 子育て支援(保育・教育・経済的支援など)、少子化対策などに取り組んでいるこども家庭庁。『明日はもっと、いい日になる』が児童相談所を舞台にしたドラマということで、こども家庭庁の職員の方々がドラマの現場を訪問し、実際の撮影の様子を見学するとともに、プロデューサーとの意見交換を行った。今回、こども家庭庁から参加された中には、実際に児童相談所で勤務した経験がある方も。
こども家庭庁職員さま
「撮影現場を拝見して、丁寧なドラマ作りに感動しました。スタジオセットの作り込み、たくさんのスタッフが関わっていること、同じシーンを何度も撮っていく撮影の仕方など、リアルな現場を体験させていただきました」
本作を企画した意図について質問を受けた宮﨑暖プロデューサー
「このドラマをやろうと思ったのは、元々児童相談所というものにすごく興味があったのですが、ニュースになる度に、悪いニュースばかり取り沙汰されている現状を見ていて、『果たしてこれだけが児童相談所の姿なのだろうか?』と疑問に思っていました。実際に取材を重ねると本当の児童相談所の姿が見えてきて、これはドラマになる題材ですし、伝えるべきことだと思いました。ですので、こうしてこども家庭庁の皆さんからお声がけをいただいたときは、自分が頑張ってきたことが報われたような気持ちになりました」と話す。
「児童相談所は、家庭と対立するような存在だと思われている方も多く居ると思いますが、実際は家庭に寄り添いながらこどものためにどうするべきかをともに考えるところなんです。そういうこともドラマの中ですごく丁寧に描かれているなと感じています。そこに込められた思いは?またそのために、どんな工夫をされていますか?」という職員の方からの質問に対しては
「僕自身が個人的に抱いていた印象は、やっぱり虐待に対応する場所。だからこそ、児童相談所の方が訪問すると虐待を疑われるんじゃないか、と考えてしまうという印象がありました。第1話のセリフの中に『招かれざる客』という言葉が出てきますが、それも取材させていただいた児相の方がおっしゃっていた言葉で、『僕らが来ると親や近隣の方が警戒するんです。だから、児童相談所の者だと名乗らないようにして、○○市から来た者です』と言うと伺いました。虐待を扱う場所、というイメージが強過ぎますが、本当は“親子に関することだったら何でも相談していい場所”であるということを打ち出さなければいけないなと思い、ドラマの中に登場する浜瀬市児童相談所は“そこにある児童相談所”みたいなイメージを意識して作りました」と答える宮﨑プロデューサー。
それに対して職員の方は、「虐待対応の大変さのひとつは、ドラマでも描かれていたように、児童相談所職員による家庭訪問は親から歓迎されない場合もあるということです。でも、我々児童相談所が関わったきっかけは望まない形だったかもしれないけど、終わるときに児童相談所に関わってもらって良かったな、ちゃんと話を聞いてもらえて良かったな、と思ってもらえるようにと思いながら、自分も仕事をしてきました。受け入れられるのは中々難しいですけど、段々信頼関係が出来てきて、親の意識が変わっていくと、家庭も変わっていくんです。最後に『ありがとう』で終わることは少ないのですが、ごく稀にそう言ってもらえることもありますし、そういうときはやりがいを実感します。そういうことがひとつあると、それまでの苦労は全部吹っ飛んでしまうんです」と話す。
意見交換会では、ドラマの中でさまざまなテーマが描かれていることも話題に。
「虐待は決して許されるものではないですけど、その裏にはさまざまな事情もあるということをこのドラマではしっかりと描いていただいています。虐待と聞くと、ひどい部分にだけフォーカスされてしまいますが、その背景にある事情に対処していくことが重要なんだということを、ドラマという形で取り扱っていただけるからこそ多くの方に知っていただける。親子のあり方、こどもへの接し方、こども家庭庁として『こどもまんなか社会』を実現していきたいと思っている中で、その芯の部分を見せていただいていると感じています。目を向けていただきたいテーマを毎回取り上げていただいていますが、どうしてそこに焦点を当てられたのか、と思いました。『面前DV』は、『よくある夫婦ゲンカがなぜこどもに対する虐待になるのか?』という方も多い中では、虐待になり得ることを知っていただきたいものです。それから新しいエピソードの『きょうだい児』などもそうですね」と職員の方が話す。
それに対して宮﨑プロデューサーは「最初の狙いとしては、ドラマの中で描かれていることが、自分たちとは関係が無い話だと視聴者に思われたくなかったんです。面前DVは僕自身も取材するまで知りませんでした。こどもの目の前で繰り広げられる夫婦ゲンカはこどもへの心理的な虐待になってしまうというのは本当に驚きでした。ですからドラマを見て、ドキッとするご家庭もあったかと思います。きょうだい児に関しては、僕自身がきょうだい児で、弟が障がいを持っているんです。児童相談所のドラマを作るとなったときには、どこかで取り上げようと思っていました」と語る。
また職員の方々からは、「南野丞(柳葉敏郎)さんのセリフも素晴らしいと思いました。丞さんが一時保護所にきたこどもに必ず言う『なんにも話さなくてもいいし、なんでも話してもいいんだよ』という言葉はどういう経緯で生まれたんでしょうか?」という質問もあった。宮﨑プロデューサーは「実は丞さんのモデルになった方がいるんです。その方とは結構密接にいろいろなやり取りをさせていただいているんですけど、その中で『あ、そうなのか!』と思ったことがあったんです。それは児童相談所が、こどもの意思に対して何かをこうしようと決めることはない、という言葉です。あくまでもこどもの意思があって、どうしたいかを聞く。そして、答えたければ答えて、答えたくなければ答えなくてもいい、ということを必ず最初に言うようにしている、と伺って。それってすごいことだなと思ったんです。だから、ドラマの中でも丞さんが最初にそれを言うことで、こどもの意思を確認する意味を印象づけられたらいいなと思って。脚本の谷碧仁さんに意識して作っていただいたセリフなんです」と明かした。
参加した職員の方々以外にも、ドラマの今後の展開について興味を持ってくれている方が多いという。「翼(福原遥)が警察に戻るのか戻らないのか、というのは周りの人たちとの間で話題になっています」と職員の方から言われた宮﨑プロデューサーは、「そこは最終回でひとつの答えを出します。翼は『助ける』という言葉をよく口にしますが、翼にとって『助ける』とはどういう意味なのか。『私にとって”助ける”は”助ける”なんです』――1話で提示したものへの答えにもなっていると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらうれしいです」と話し、終始和やかな雰囲気のまま座談会を終えた。
ラストへと繋がる第10話は本日9月8日(月)、よる9時スタート。ぜひご期待いただきたい。
こども家庭庁公式note
https://kodomo-gov.note.jp/