CLAMP TALK Vol.32
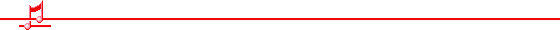
NAKAI in talking with MOTOHARU SANO.
- 佐野:
- また、学習というと、自分から学ぶという要素もあるけ
れども、誰か僕の知らないことを知っている誰かから教えてもらうということも
あるよね。僕が小学校に通っていた頃、あるいは中学校に通っていた頃いつも
思っていたのは、先生たちはいろんなことを教えてくれるんだけども、いつも教
えてもらうことが、すぐに古臭くなってしまうなと思ってた。
- 中居:
- え?たとえばどういう点ですか?
- 佐野:
- どういうことだろうな?
- 中居:
- 古臭くなってしまう?
- 佐野:
- どんどん新しいことを教えてもらうんだけど、現実のほ
うがスピードが早くって、先生から教えてもらったことが現実に役に立たないと
いうかね。
- 中居:
- それは学校の勉学っていうことですか?
- 佐野:
- うん。いわゆる学習ってこと。学校の中の学習。だか
ら、これは自分でどうにかね、何か学習していかなくちゃいけないなってことを
なんか思ってた。
- 中居:
- 学校の勉強以上にもっと大事な?
- 佐野:
- ことがあるんじゃないかと毎日思ってた。
- 中居:
- もっとやらなければならないことがあるんじゃないかっ
てことですか?
- 佐野:
- 焦ってた。それでたまたま15歳ぐらいだったかな?14歳
ぐらいだったかな?僕の好きなソングライターの一人に、ボブ・ディランというソ
ングライターがいるんだけれども。彼のレコードを何かのきっかけで聴いて、そ
こでは英語で歌われていたから、歌詞の意味はその時にはわかんなかったけれど
も、レコードを買って聴いてみたら、非常に共感を覚えたんだね。
- 中居:
- それは音で共感を覚えたっていうことですか?
- 佐野:
- うん、音。それから歌い方。それから詞の内容。ギター
の弾き方。そしてまたボブ・ディランというアーティストの雰囲気かな。それが
何か言葉では言えないんだけれども…うーん?
- 中居:
- その当時っていうのは、佐野さんは音楽は?
- 佐野:
- もう何かやり始めてた。ギターを持って曲を書きはじめ
てたり、詞を書き始めてたかもしれない。
- 中居:
- その共感ていうのは、尊敬であったり、憧れであったり
とか?
- 佐野:
- あ、憧れっていうのはあったかもしれない。それからむ
しろ、さっきの学習の話でもないけれども、学校の社会科で学ぶよりも、そのボ
ブ・ディランというソングライターの曲、詞を通して社会や世界を見たほうが現
実感があったんだね。
- 中居:
- 自分だけのためには、その彼の学習をしたほうが?
- 佐野:
- っていうか、彼の音楽のほうが、学校で勉強しているより役
に立つような、そんな感じを受けた。そのくらい彼の詞は何というか、僕にとっ
て現実味を持って迫ってきた。
- 中居:
- その詞っていうのは、悲しい詞でしたか?
- 佐野:
- 悲しい詞でもなかった。一言で言えばね、とても難解な
詞だった。それから、言いたいことが10も20も30もあるので、ただそれをスケッ
チして書いただけでは言い足りないといったような様子。それから、右からも見
て左からも見て、上からも下からも立体的に見て、一つの詞が出来てくる。だか
ら、ものすごく立体的な詞であるし。言葉もなんか僕は難解だと思う。難解な詞
だった。だけども、なんかわかったような気がしちゃうんだな。また、10代の時
は何か難しいものに憧れてしまうという部分もあるじゃない。
- 中居:
- うんうん、わかります。自分の未知の世界のものにね。
- 佐野:
- そう、未知の世界のものに、憧れも含めてね。そういう
気持ちも相まっていたのかもしれない。
- 中居:
- それがきっかけで音楽に対する姿勢っていうのも、執着
心みたいなのも深くなって。
- 佐野:
- とにかく、それ以来もうギターを持って毎晩毎晩詞を書
き、曲を書き始めたよ。
- 中居:
- 佐野さんの詞っていうのは、自分の言いたいことだった
り、物事をいろんな角度から見て結果が今に繋がってます?
- 佐野:
- 繋がってます。10代の時に僕が経験したこと。それから
感じたこと。それらは今でも僕の役に立ってる。
- 中居:
- 佐野さんの作ってる作品、音楽っていうのは、常に自信
のあるものと考えていいんですね?聴く側としては。
- 佐野:
- 自信があるもの?そうだな、今、僕が歌いたい曲。それ
と、僕が今、自分で聴きたい曲。
- 中居:
- 聴きたい曲?
- 佐野:
- 自分で聴きたい曲を自分で作るんだ。
- 中居:
- まあ、歌いたい曲っていうのはわかりますけどね。自分
で作った作品を、聴きたい曲を出すっていうことですか?
- 佐野:
- っていうかね、街にはいっぱい音楽があるよね。世界中
にいっぱい音楽がある。でも、どれも聴いてピンと来ないとしたら、自分が本当
に聴きたい音楽を自分で作るしかないと思っちゃうの。そういう意味。
- 中居:
- はいはい、はいはい。
- 佐野:
- だから、 「フルーツ」アルバムに収録されてるのは、
今、自分が聴きたい曲だし。また、今、心から歌いたい曲を収録しました。
- 中居:
- その「フルーツ」のなかで、いちばん最後に“死”とい
う言葉が。“そして、死”と最後にありましたけど。死というのは、やっぱり生
きている我々にとって、誰もが経験のないことで、誰もがやっぱり未知の世界で
あって。で、空想するわけですよね。佐野さんにとってその“死”に対するこだ
わりじゃないですけど、どういうふうに考えてらっしゃるのかな?
- 佐野:
- 僕は小さい頃、死ぬことが恐かった。いろいろと想像し
てみて、「死ってどういうことだろう?」「自分がこの世の中からになくなってし
まうって、どんなことだろう?」。そんなことを想い巡らせてると、死っていうの
はすごく恐く感じて。ただ、少し成長して、映画や小説や、いろいろな他の作家
たちが書いた作品を通してね、その死というものは、それほど恐くない。そんな
に恐れることではない。誰もが経験することだし、何も自分だけに起こる出来事
ではないんだなっていうふうに、少し、昔ほど死を恐れないようになったの。そ
して、さらに成長して、これは1年前、僕の母が亡くなった。で、僕は母が亡くな
る時ずっと一緒にいたんだ。2ヶ月間ぐらいずっと一緒にいた。で、彼女がコトッ
と息を止めて天国に行く瞬間まで、僕はずっと彼女のことを看てたんだ。その時
に「死はちっとも恐くない」「死はとても厳かで、感動的なものだ」って思っ
た。でも、100%そう思ったかどうかわからない。悲しみのほうが先に立つから
ね。そう思い込もうとしたのかもしれない。でも、これから何年僕が生きるかわ
からないけども、きっと自分が死ぬ時に、死についてもっと本当のことがわかる
だろうなって思う。難しいテーマだけどね。
- 中居:
- そうですよね。これは断定できないですからね、「死と
いうのはこういうものなんだ」って。でも、その五つの要素が「フルーツ」に。
だから、「フルーツ」っていう言葉を聞いた時に、すごく甘いアルバムなのかな
と。すごい甘い香のするアルバムかと思ったんです。でも、その「フルーツ」と
いうタイトルに対する五つの要素が、あまりにも僕にとって疑問じゃないですけ
ど、ちょっと衝撃があったんで。どういう感性で、どういう物の捉え方でこうい
うふうに付けられたのかな?って思ったんですけどね。あの五つっていうのは、僕
にとってちょっと衝撃的だったですね。
で、その前に組んでらっしゃったグルー
プから、今の。
- 佐野:
- ええ、インターナショナル・ホーボー・キング・バン
ド。
- 中居:
- その昔やってたバンドと今やってるバンドっていうの
は、やっぱり捉え方っていうのはちがうと思うんですけども。佐野さんにとって
どうなんでしょうかね?音楽に対する接し方が変わったのか、それとも逆にただメ
ンバーが変わっただけなのか。そのへんはどうなんでしょうかね?
- 佐野:
- 多分、テレビみている方たちもね、バンドというものが
どういう関係で成り立っているのか、多分、ウマく想像できない方が多いと思う
んだ。で、それぞれのバンドによって成り立ち方も違いますしね。僕がレコー
ディングアーティストとしてデビューしてから、ずっと長い間組んでいたバンド
がありました。それはザ・ハートランドという名前だった。僕らがまだ22歳ぐら
いの時に結成したバンドで。そして、ザ・ハートランドは当初、「頑張れベアー
ズ」だった。
- 中居:
- なかなか売れないじゃないですけど。
- 佐野:
- まあ僕も含めて下手クソだし、お客さんの前で歌っても
投げやりな拍手って感じだし。でも、「今に見てろ」っていう気持ちはいつも
あったのね。いつか本物のでっかい球場で、たくさんの人たちを前に、彼等の熱
狂するようなコンサートをやりたい。それは幸せなことに8年後か9年後に実現す
るんだけどね。とにかくバンドを組んだ時、僕ら「頑張れベアーズ」だった。そ
して、みんな22〜3歳。まだ多感といえば多感の頃だよね。で、僕ら出会った。そ
して僕らは15年間、一緒にライヴをするためにいろいろな街に行き、また、レ
コーディングもした。で、その間、僕らはお互いの成長を見続けた。それは例え
ばレコーディングスタジオの中で。あるいはそれぞれライヴに行った公演先の楽
屋の中で。感じからいったら、ザ・ハートランドというのは僕にとっては兄弟の
ような感じだった。中居君も一つのグループの中にいるわけでしょ?
- 中居:
- ええ。
- 佐野:
- もうどれぐらい経つの?
- 中居:
- 我々はもう8年。9年目です。
- 佐野:
- あ、そんなに経つんだ?
- 中居:
- ええ。
- 佐野:
- そうするとやっぱり、長男の役割とか次男の役割とか出
てくる?
- 中居:
- そうですね。役割分担じゃないですけど、そういうキャ
ラクターももちろんありますし。それはやっぱり兄弟に近いものはありますよ
ね。
- 佐野:
- そうするとやっぱり、お互いの成長を「あ、あいつ少し
成長したな」とか。
- 中居:
- でも、兄弟っていうのは、ちょっと捉え方違いますけど
も、我々にとってはある意味ではライバルでもあるんですよね。
- 佐野:
- ああ、なるほど。
- 中居:
- たとえば他のメンバーが活動であったり発言でもそうな
んですけど。すごい刺激になるわけですよ。
- 佐野:
- なるほど。
- 中居:
- でも兄弟っていうと、例えば弟がいたら「ほら、何やっ
てんだよ。ついてこいよ、おまえ」って。弟は「お兄ちゃん、お兄ちゃん」て。
最初の結成当時はそうだったんですけど、やっぱり年が経つにつれて、一人で自
分が人に頼らずに自分でやってく。それは兄弟でもそうでしょうけども、ある意
味ではもうライバル。いつも一番でいたい。常に一番でいたいっていうライバル
意識が我々にはありますから。だから、兄弟とはまたちょっと違うんじゃ
ないかなと思うんですけどもね。
- 佐野:
- その集まりはでも、すごく前進を目指す集まりだと思う
な。僕らがやってたザ・ハートランドの場合には、僕はなんとなく長男の役割を
してたんだけども、みんななんか次男坊みたいに優しくてボーッとしてるんだ。
いい意味でだよ。優しくてボーッとしてる。ピースフルなんだ。戦闘的ではな
い。
- 中居:
- 平和ですよね、でも。
- 佐野:
- そうだね 。まあ、バンドによっては、やはり自己主張
がたいへん強いメンバーが一人二人いると、彼らがエゴでぶつかってしまって急
にバンドが解散とかいうことはよくある。けども、かつて僕が組んでいたザ・
ハートランドというバンドに属していたメンバーは、みんなすごくピースフルな
連中だった。音楽をすごく愛していて、争いを好まない。そういう連中たちが集
まっていた。だから、何かいい意味でずっと仲良しでいられたんだな。
- 中居:
- でも、ぶつからないっていうことは、その次男坊たち、
自分たちのやりたい音楽が密かに自分の中であったかもしれないって。
- 佐野:
- 僕もそう思う。だから、ちょうど解散した時に彼らは自
分の音楽を作り出した。そして自分のレコードを作り始めた。だから、なんか仲
間として見ていて、僕も含めて、彼らも含めてバンドから一人一人が自立してい
く様子っていうのかな。それがちょっとだけ見えて、なんとも仲間として嬉し
かったんだ。そして僕もデビューしてから、もうだいぶ経つけれども。またバン
ドを結成してもう長い時間経ったけれども、バンドを解散した時に初めて「あ
あ、これで僕は本当に自立したのかな?」「バンド解散の日は、僕にとって独立記
念日だったのかな?」そんなことを思いました。あんな感じは、僕、初めてだっ
た。そして今、また新しい仲間たちと一緒にやってるけどね。
[CONTENTS] |
[CLAMP] |
[FACTORY] |
[REPRODUCT] |
[CIRCUS] |
[INFO]
[TKMC TOP PAGE]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.