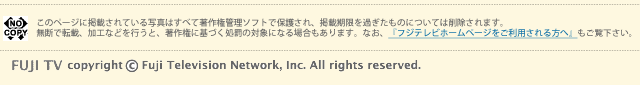メディア論の立場から政治を見ている須藤春夫氏は、半年経った鳩山政権に対する報道について、「初めての本格的な政権交代で登場した民主党政権に対し、メディアの見方はかなり混乱している。選挙前から『政権交代』や『政権選択』という言葉が踊っていた。これがその後の政治のあり方をどうするのかを狭めてしまった。ワンフレーズ化で、メディアの側も一色になってしまうと問題の本質が見えなくなってしまう。これだけ価値観が多様な社会なのだから、その多様な意見を拾い上げ、検証し、有権者が判断できる材料を出してくれるのがメディア。八ッ場ダム問題、普天間基地移設問題、郵政民営化見直しと、いずれも自民党政権時に決められたことで、民主党政権は違う選択肢を出したのに、メディアはこれまでの路線を崩さない批判をする。それでは有権者の政権交代させた判断に沿うものではない。政権が55年体制から変わったのに、メディアがまだ木鐸(ぼくたく)意識を持って、こうすべきという報道になっている。」と語った。松野教授は、「メディアがどこに議題があるのかを視聴者に設定をして問題提起すべき。」と語った。 番組内で募集したアンケートでは「政治を考える上で最も参考にするメディアは?」の質問に、テレビと答えた人が53%、インターネットが28%、新聞15%、ラジオ2%、雑誌1%だった。この結果に須藤氏は、「テレビが政治報道の重要な情報源だという認識が問われている。テレビの役割として『政権とテレビ』と『政治とテレビ』は分けて考えるべき。前者は、時の政権の監視役という役割を強く出すべき。後者は、民主党が記者会見をオープン化しているが、会見よりも目に見えない政策決定の過程の部分こそ追究して、積極的に国民に知らせることが期待されているということ。両方のバランスが必要で、自分たちが寄って立つべき視点を持つことが大事。映像で見えるテレビの良さを視聴者は十分に知っている。それだけメディアの見方も厳しくなっているので、テレビの側がジャーナリストとしての能力を高めていくための教育が重要だ。ますますテレビの役割が需要になってくる。テレビの持つ信頼性をもっと発揮できる能力を蓄積すべき。」と語った。


地下鉄サリン事件から丸15年となるこの日、オウム事件を追い続けたジャーナリストの江川紹子氏は「最初に関わった坂本弁護士一家殺害事件から20年の去年の方が感慨深い。ずっと報道されない期間があって、地下鉄サリン事件で怒濤のように報道され、その後パタッと報道されなくなってしまった感じがする。裁判が始まった当初は教祖と事件の関わりに興味が集中して、なぜ多くの若者が惹きつけられたのか、なぜ教祖の指示に唯々諾々と従って殺人まで起こしてしまったのか、という“なぜ"の部分が置き去りにされた感があって、そういう報道が少なかった。」と話した。報道されない点については「事件そのものに対する考察がもう少しあって良かった。事件そのものは記憶に残っても、事件の教訓が果たしてどの程度共有化されたのか。普通の人がああいう事件に巻き込まれる、あるいは犯してしまうというのがオウムの一番の怖さだった。そこが伝わらないと、特異な人たちがやった特異な事件ということで、自分は絶対巻き込まれないと自信を持ってしまう人も多い。でもそれが一番危ないと感じる。」と語った。オウム裁判については、「同じ実行犯でも、自分のやったことの重みに苦しんだり、そうでない人も、いまだに教祖に心酔している人もいる。」砂川准教授は、「不可解な初めての事件では、メディア自身が過熱してしまい、見ている側も過熱し、すごく印象論的な伝え方になってしまう。もし今オウムのような事件があった時に、教訓として生かして報道出来るかが問われている。」と話した。多くの若者がオウムに惹かれていくことについて「悩みがあって行った人や、生き甲斐を探して行った人もいる。麻原は常に力強い答えを出してくれる。自分たちは真理で、それ以外は悪だという二元論的考え。二元論的発想は一般の社会でも幅をきかせてきた。テレビもわかりやすくシンプルにという方向になってきている。複雑な部分を、わからないものはわからないなりにどうやって伝えていくかが大事。」と語った。


最も古いアニメ雑誌「月刊アニメージュ」編集長の松下俊也氏は、「本来テレビアニメは、提供スポンサーがついて番組を作っていて、キャラクター商品を売れるようにするのが番組の使命だった。それが90年代半ば、特に『新世紀エヴァンゲリオン』からスキームが変わってきて、アニメそのものに商品価値が出てきて、ソフト化され売れるようになってきた。」とアニメの歴史を話した。テレビ番組の役割の変化については、「アニメのコストを回収できるのは、視聴率1%の視聴者数よりもずっと少ない人数だが、それでも5〜6000円のお金を出して購入してくれる人にきっちり届く作品を作っていかなければならないから、今までと同じではいけない。お金を払ってくれるユーザーに向けた作品になってきている。テレビは、そういうユーザーに向けたショーケースになってきている。そして『製作委員会方式』をとり、それぞれが儲かるようなスキームで作るものが深夜枠に多くなっている。」と語った。稲増教授は、「これはビジネスモデルの変化。映画でもDVD化され初めて採算が取れるようになっている。テレビアニメも、ソフト、コンテンツの時代になっている。」と語った。だが、松下氏は、「DVDは2006年をピークに売れなくなってきている。テレビアニメの制作本数も減少傾向にある。」と話した。稲増氏は、「『宇宙戦艦ヤマト』や『機動戦士ガンダム』などは本放送の時の視聴率は良くなくて、後のシリーズ化や劇場版などで話題になってヒットした。だから、先取りする部分と多くの人に見てもらう部分のバランスの問題だ。」と話した。番組内で募集したアンケート結果は、「週に何本テレビアニメを見ますか?」の質問に、5本以上が35%、1本が30%が多かった。次の「テレビアニメに期待するものは?」の質問には、感動が42%、冒険・アクションが17%だった。松下氏は、「一番多かった『感動』を追い求めるのは理想的で重要。ソフトとしての優良なものの中に、テレビの番組作りのノウハウがうまく注入されて<ノイタミナ>のような形が両者にとっていい形になっていくと思う。」とテレビ局への期待を語った。


去年11月にBPO放送倫理検証委員会が民放連に出した「バラエティー番組に関する意見書」について、作った一人である委員の里中満智子氏は、「委員会に様々に寄せられた視聴者の意見をまとめて最初に作った意見書はあまりにもバラエティーらしくないものになり、もっとバラエティーにふさわしい意見書にしよう、ということで話し合い、今の形になった。」と語った。 この意見書を受けて、2月27日放送の「めちゃ×2イケてるッ!」でフジテレビとしての姿勢を示したが、その番組については里中氏は、「バラエティーらしくおちょくる姿勢があって、手の内をばらして実験的にやっていながら、実はばかばかしいところを見せている。何度も通用する手ではないが、安心して見ていられた。バッカだなぁと安心して見ていられるものは面白いが、ひどいなぁと思ってしまうものは引いてしまう。」と話した。 音教授は、「放送局の側からBPOの提起したことに対して打ち返してる、キャッチボールしていると思えた。ここからが議論するスタートだと思う。」と語った。また、今月1日には「私たちのフジテレビバラエティ宣言」を発表したが、これについて里中氏は、「キャッチフレーズを作るのはいいこと。制作者一人一人が意識するし、バラエティーの未来があると思う。私たちはバラエティー番組にはある節度を守りながら、萎縮してほしくない。」と語った。委員の一人である吉岡忍氏から「めちゃイケ」に対する感想を文書でもらい、「岡村隆史さんが今の何に注目し、何を笑おうとしているのかが分からなかった」というコメントを紹介した。最後にバラエティー制作者への提言で、里中氏は、「とにかく萎縮しないでほしい。バラエティーが元気がないとテレビの魅力が小さくなる。どんどん新しい驚かせ方、演出の手法を見せてほしい。」と語った。