Muscat~フジテレビの番組情報
2018.09.04更新
ことさらに人権めいたことを主張する気はないけれど、ギャップは埋めたい
『ケンカツ』実写化で最も意識したこと
吉岡里帆さん主演で放送中のドラマ『健康で文化的な最低限度の生活』。「生活保護」というナイーブなテーマを取り扱い、決して白と黒では割り切れない人間ドラマを描いている作品です。
同名タイトルの原作マンガは、現在も「ビッグコミックスピリッツ」にて連載中の人気作。そんな作品を実写化するにあたって、どんな点を意識しているのか。ドラマの担当プロデューサーである米田 孝さんに、お話を伺いました。
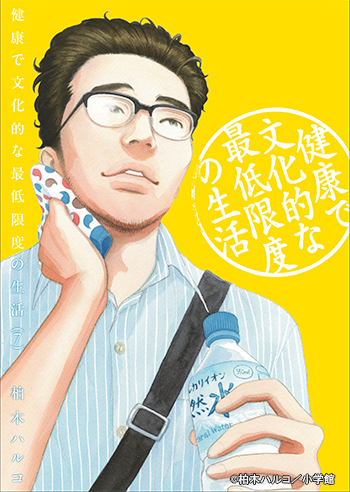
人権ばかりを主張する気はないんだけど、ギャップは埋めたい
――7月31日に放送された欣也くん(吉村界人)の回でいうと、「不正受給」がひとつのキーワードになっていました。生活保護をテーマに扱う時点で、どうしてもナイーブな問題をドラマの中で扱わなければならないと思うのですが、そういった点で注意していることやこだわっている点はありますか。
まず、原作ありきの話になりますが、とにかく言いたいのは、この作品は柏木先生の努力の賜物、ということです。彼女がどれだけの量の取材をして、どれだけの事実をつぶさに自分の目で見て、これを描いているか、という。だからこそ一辺倒の答えではない、絶妙なところを描くことができる。
ドラマ化が決まった際に、柏木先生からは、ドラマはまた別の作品だから自由にやってください、と言われていました。ただひとつ、原作の監修をしている方の話をしっかり参考にしてください、とも言われていて、脚本もすべて監修していただき、何度も認識のすり合わせを行っています。
もちろん、僕自身も知識を入れないといけないと思って、独学で本を買って勉強したり、監修者の方が働く現場に同行したり、セミナーに通ったりして、ケースワーカーという仕事に対しての理解を深める努力はしています。それでも全然足りてないとは思うんですけど、できることはすべてやるようにしていますね。
――実際にこのドラマの制作を通して、ケースワーカーや生活保護に対する印象は変わりましたか。
変わったというか、なかったものが形になった、という感じですね。それまでは、ケースワーカーってなんですか?と聞かれても、答えることができなかった。その上で感じたのは、世間でみんなが思っているようなイメージと、実際の現場や制度のあり方が、いかにかけ離れているか、ということです。社会派ドラマにしたいわけではないんだけど、現状を知ってしまったら、どうしてもギャップは埋めたくなりますよね。

米田 孝プロデューサー
――たとえばどういうところでギャップを感じたんですか。
これは監修の方が働いている現場でのことなので、他の現場とはまた違うかもしれないですが、ケースワーカーの方々が働いている職場がとても明るい雰囲気だったんですよ。みんなすごく大変な思いをしているはずなのに、とても生き生きとしている。これはドラマでも表現したいな、と思っていて。
――確かにドラマでえみるが働く現場は、みんな元気で明るい印象がありますね。
ただ、だからといって「生活保護は権利なんだ! 受け取っていいんだ!」といった人権ばかりを主張するようなドラマにはしたくないんです。世間と現実のギャップを埋めながらも、いろんな意見があるんだということを表現したい。白黒はっきりとした、勧善懲悪の世界の方が見やすいかもしれないけど、そこはあくまでグレーゾーンとして描ききりたい。

――ひとつの強いメッセージを押し出したいわけではない、と。
そうですね、それはたとえばキャラクターひとつとってもそうで、いろいろな人間模様があることに恐れずに立ち向かうえみるのような存在もいれば、そこまでやる必要ないんちゃいます?という石橋さんみたいな存在もいる。そのどちらも間違っていない、と思うし、そういう風に見せたい。
――なるほど。
石橋さんを嫌な人だとか冷たい人だという風には見せたくないんです。だからこそ内場(勝則)さんに演じてもらっているというのもあります。ああいった、ちょっと人間味の部分で人物に魅力を感じてもらっておかないと、ただ悪者をやっつけるような取られ方をしてしまう。それこそ見やすいから数字にはつながりやすいかもしれないですけどね、この作品はそういう作品ではないので、そこは大事にしたいなって思っています。
――原作もそういったグレーゾーンや答えの出ない問いを、真摯に描いた作品ですよね。
そうですね、それはこの作品を作る上でも自分の中の根っことしてあると思います。やっぱり、原作をドラマ化する上で大切なのはリスペクトだと思うので、映像化をする上で、どうしても変えたり加えたりしなければならないのですが、本質だけは見誤らないようにしたい。そもそも、これは生活保護がテーマではありますが、あくまでこの作品の舞台なだけであって、そこにあるのは、生きている人間のドラマです。生活保護をかかげて社会に一石を投じたいとかではなくて、そういうところを描きたいだけなんです。
受給者がどう見るかという視点は絶対に欠かしてはいけない
――ドラマ化する上で「どうしても変えたり加えたりしないといけない」というお話がありましたが、それはどうして必要になってくるんですか。
やはり、ドラマの1時間というサイズ感に合わせて、伏線や展開などは新たにオリジナルで加えていかないといけない。それは原作ドラマ化の醍醐味でもあり難しいところでもありますよね。ファンや原作の先生の想いをふいにしては絶対にいけない。でも、すでに面白い作品がある上で、さらに何を加えようか、と考えるのは楽しいです。ここにこんな人物がいたら、面白い展開が起きそうだな、とか。
――オリジナルな部分でいうと、たとえば欣也くんの回では、妹さんにお小遣いをあげるシーンがありましたよね。原作にはない展開でしたが、欣也くんの兄としての姿も垣間見えてまた少し印象が変わりました。
あれはぴーんと閃きましたね、「妹に小遣いや!」って。ドラマとしてはやっぱり、キャラクターにどう感情移入してもらえるか、そのために要素として何を足していけるか、というのが大事なんです。あのシーンを前半に入れておくことで、欣也のキャラクターがさらに深く掘り下げられていく。
――確かに欣也というキャラクターにより複雑性が増す場面でした。
もうちょっと欣也を理解してほしい、とは思っていたんですよね。僕はもともと原作で欣也が叫ぶ「バカで貧乏な人間は夢見んなってことかよ」というセリフが、この作品の中でも特に大きな問いだな、と思っていて。すごく難しい問題なんだけど、欣也の立場に感情移入して考えてもらいたい。
だからこそ、ただの元ヤンの変な奴ではなくて、自分の夢をもって自分でお金を稼いで、妹にもそのお金をあげるような側面もあって、という面を描きたかった。もちろん、その上で「でもダメでしょ」と思う人がいたっていいんです。

――逆に、ドラマを制作する上で、これだけはやらないと決めていることなどはありますか。
それはやはり、原作が本質的に大事にしていることを見誤らないことですね。あとは、やはりナイーブなテーマを扱っているドラマではあるので、できる限り誰かを傷つけるようなことはないようにと思っています。限界はあると思うんですけど。
それは実際に働いているケースワーカーの方々に対してはもちろんですが、やっぱり受給者の方々が見てどう思うのか、というのは常に考えているつもりです。そのことを忘れたら絶対にダメだ、と思っているので。もちろん、それでも嫌な思いをさせている側面はあると思うんですけどね。やっぱりそこの意識をなくしたら、この作品やっちゃダメだな、って思います。
取材・文=園田菜々
番組情報
- 『健康で文化的な最低限度の生活』
- <放送>
- 毎週火曜21時~21時54分
- <出演>
- 吉岡里帆 井浦新 川栄李奈 山田裕貴/田中圭 遠藤憲一 他
掲載情報は発行時のものです。放送日時や出演者等変更になる場合がありますので当日の番組表でご確認ください。