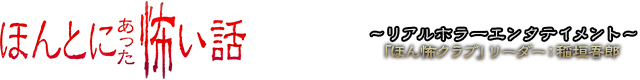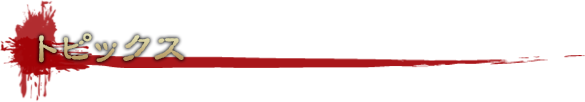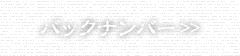プロデューサー×監督×編集者 SPトーク!

10月12日(土)に、稲垣吾郎が出演するフジテレビ『ほんとにあった怖い話 20周年スペシャル』が放送される。

本作は、一般の人の身に実際に起こった心霊体験を基に、豪華俳優陣によって心底怖いゾッとする恐怖と、その恐怖や不安に翻弄(ほんろう)されつつも立ち向かっていく人々の姿を描くリアルホラーエンターテインメント。
今回、フジテレビュー!!では、“ほん怖”20周年を記念して、原作となった漫画誌『ほんとにあった怖い話』を手掛けた朝日新聞出版の長谷川まち子氏、「Jホラーの父」と呼ばれる映画監督でシリーズ開始から120話以上の“ほん怖”作品を演出してきた鶴田法男氏、番組のチーフプロデューサー・後藤博幸の鼎談が実現した。
番組の成り立ちから、こだわりや苦労、制作秘話まで、前後編でたっぷりと聞いた。
番組スタートのきっかけとなったビデオ映画版『ほん怖』
きっかけは、後藤プロデューサーがレンタルビデオ店で見つけた、とある作品だったという。
後藤:幼い頃からハリウッド映画の『ハロウィン』とか『ジョーズ』とか『エイリアン』などがすごく好きで、それがフジテレビに入社してからも続いていて。どうして日本にはこういう面白くて怖い作品がないのだろう、と。

そんな中、レンタルビデオ店で「ほんとにあった怖い話」(’91~’92)のビデオを見つけて、「これだ!」と思ったんです。気が付いたら、パッケージに書いてある電話番号に電話して「鶴田監督お願いします」って言った気がします(笑)もちろんそこにはいらっしゃらなくて、原作の編集部経由でご連絡先を教えていただきましたね。
鶴田:あれは1998年の12月でしたね。当時僕はいろいろな事情が重なって、映画監督を引退していて会社員をしていたんです。そんな中、後藤さんからお電話をいただいたのですが、「監督は引退したので、ちょっと…」とお伝えしたんです。
時を同じくして、当時大ヒットしていた『リング』(’98)の中田秀夫監督が、「『リング』はビデオ映画『ほん怖』が存在しなかったらできていなかった」というようなことをインタビューで言ってくれてびっくりしていたこともあって。そこにきて後藤さんからお電話をいただき、なんか“風向きが変わってきたな”と感じることがいくつかありまして。「これは監督に復帰しろということかな」と思っていたのです。 後藤さんは思い込むとあきらめない人なので、年明けに再度電話がかかってきて(笑)。 渋谷で 後藤さんにお会いすることにしたのですが、名刺をいただくまで信じられなかったです(笑)。
長谷川:鶴田監督は『ほんとにあった怖い話』の漫画雑誌の存在はいつからご存知だったんですか?
鶴田:初めて読んだときに、過去に出版されたものまで全部買ったから記憶は曖昧ですが…。ビデオ映画が発売された’91年から逆算すると’89年にはビデオ化の企画書に手を付けていたはずなので、その頃でしょうね。
長谷川:まだ季刊で出していた頃ですね。初めて「テレビ番組になる」と聞いた時は、ビデオ映画がとても面白かったので驚きませんでしたが、深夜番組向きだろうな、と思っていました(笑)。
後藤:僕が最初に提出した企画書も、深夜帯で、無名のキャストで、徹底的に怖いものをやろうというものでした。でも、当時のドラマの企画担当部長(亀山千広・元フジテレビ社長/現BSフジ社長)に見せたら、「馬鹿野郎!」と企画書を投げつけられまして。
鶴田:当時、後藤さんは企画書を出すのも初めてだとおっしゃっていましたよね。
後藤:だから「やっぱりダメか…」と思ったら、「ゴールデンでやるから企画書を書き直してこい」と言われたんですよ。これには僕の方が驚きました。当時は、テレビドラマ『学校の怪談』(’94~)を関西ローカルで放送していたくらいで、こういう番組は少なかったんですよ。
鶴田:当時ホラーというと、それこそ『13日の金曜日』シリーズとか、斧でパコンとやって血が吹き出すようなスプラッターホラーですよね。それがみんなのイメージで。でも、後藤さんが作りたいホラーは、血は出ないし、内臓も飛び出さないし、残酷な描写は何もない。人間が斧を振り回して人を襲うタイプの怖さではなくて、“得体のしれない何か”の怖さ。僕もまさに同じところに“怖さ”を感じるタイプだったので、「感覚が合うな」と(笑)。だから、とんとん拍子に企画が決まっていきました。
日本人の誰かが体験した話がすべてのベース “オチのない怖さ”にこだわり
長谷川:そもそも『ほんとにあった怖い話』は、『ハロウィン』という女性向けのホラー・オカルト漫画誌の増刊号だったんです。『ハロウィン』創刊号に「子どもの霊が現れる踏切は事故が起こりやすい」みたいなフィクションの心霊漫画を載せたら反響が良くて、次第に読者から実際の霊体験を綴った手紙が届くようになりました。「私も幽霊見たことがあります」みたいな。これが面白いんですよ(笑)。
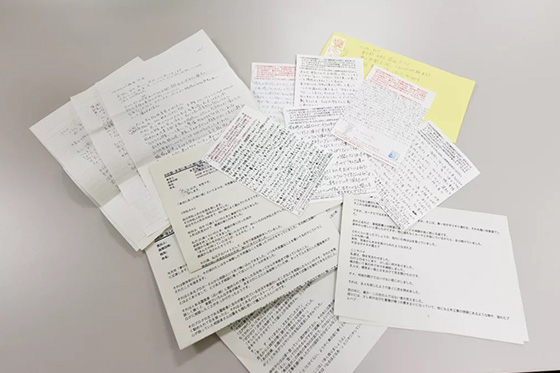
だから、その実体験の話を漫画化したものを集めて、増刊号を出そうという企画を通しました。全部実話です。それで、キャッチコピーを考えようということになったのですが、ピッタリくるものがなかなか思い浮かばなくて…。
表紙のデザインを決めるギリギリのタイミングで、「ほんとにあった怖い話」という、後にタイトルとなるコピーが“降りて”きたんです。あれは、編集部に数人残っているくらいの夕暮れ時だったと思います。あの瞬間のことは一生忘れないと思います(笑)。

後藤:番組の放送が始まると、フジテレビにも体験談が届くようになりました。
鶴田:視聴者の投稿や、知り合いの体験談から生まれた脚本もたくさんありますね。ちなみに、乃木坂46が主演した『もう一人のエレベーター』(夏の特別編2016)は、僕の行きつけの地元の中華屋さんのご主人の体験談がベースです。
長谷川:「説明のつかない“何か”に出会いました」という話って、興味を持って聞いてくれる人と、はなから受け付けない人がいるわけじゃないですか。『ほん怖』は、そういう話を誰かに聞いてほしい人たちの受け皿になったんだと思います。
後藤:最近はネット上で、起承転結がしっかりと構成された“ネタ”のような話を見つけることもありますが、『ほん怖』は“日本人の誰かが実際に体験した話”であることにこだわり続けました。起承転結なんかなくても、“これは体験した人じゃないと絶対思いつかない”というものが詰まっているほうが面白いですからね。
長谷川:オチのない怖さ、とでも言うのでしょうか。
鶴田:映画の作り手としては、どうしても物語に“起承転結”を作りたくなる。でも僕は、オチなんてなくても、そこにある“怖さ”を“怖く感じさせる”映像を作ることに特化しようと振り切っていた。しかも、普通のプロデューサーならオチをつけたくなるものですが、後藤さんは「ここで終わったほうがいい!」と確信をもって言ってくれた。それが評価されたのは幸運でしたよね。
後藤:「これは何なんだ?」という状態で終わったほうが、面白いし怖いじゃないですか。だから、『ほん怖』はかなりの確率で「これは一体何なのかいまだにわかりません」というナレーションが入る(笑)。でも解明できないからこそ、面白いんだと思っています。