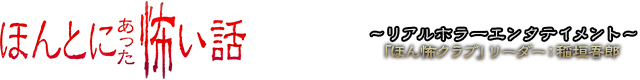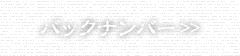第1シーズン #10
- 墓地の女

- 脚本:佐藤太喜
- 演出:鶴田法男
- 出演:神崎智子 … 竹田侑美
- 関根千尋 … 松田けいか
- 磯部江里 … 川口真理恵
- 歩く女 … 鍋田カホル
部活を終えた智子(竹田)と千尋(松田)は、自転車で帰路についた。が、墓地の前に差しかかると、突然千尋が自転車を止めた。智子も慌てて止まるが、千尋は何かに怯えたような表情を見せると、何も言わずにすぐさま自転車を走らせた。しばらく走ると、前方にクラスメートの江里(川口)の姿があった。智子と千尋の姿を見つけて安心したのか、江里はいまにも泣き出しそうだった。「どこ通ってきた?」とふたりに問いかける江里。彼女は、墓地の前で女の姿を見たのだという。智子は、自分たちが通った時は誰もいなかった、と江里に答えた。ところが千尋が「私も見た…」と言いだす。その女性は、髪の毛で顔は見えなかったが、黒い服を着て墓地の前に佇んでいた。しかもその背中には巨大な目玉があり、こちらを見つめていたのだという…。
- 京子ちゃん

- 脚本:高木登
- 演出:三宅隆太
- 出演:西田美由紀 … 三浦理恵子
- 西田忍 … 工藤あかり
夫と離婚したばかりの美由紀(三浦)は、ひとり娘の忍(工藤)を引き取り、とある団地で新しい生活を始めた。が、美由紀は、生活のために、幼い忍を残して、パートに出なければならない状態だった。美由紀は、忍がどこからか拾ってきたおもちゃで遊んでいる姿を見て、心を痛めていた。
そんなある日、美由紀が帰宅すると、忍が拾ってきた人形に話しかけながら楽しそうに遊んでいた。忍が話しかけていたのは、薄汚れた市松人形だった。
その夜、忍は市松人形を抱いて床についた。その人形が不気味で、忍に背を向けて横になる美由紀。が、どうしても背後が気になって仕方ない。そっと後ろを振り返ると、人形がじっと美由紀を見つめていた。
あくる朝も、忍は、人形と楽しそうに会話していた。忍は、人形に「京子」という名前をつけていた。そんな娘の姿に言いようのない不安を感じ始めた美由紀は、その夜遅く、人形をゴミ捨て場に捨ててしまう。が、美由紀が部屋に戻ると、テーブルの上には捨てたはずのあの人形が…。言いようのない恐怖を感じた美由紀は、人形を箱に入れ、ガムテープでぐるぐる巻きにし、もう一度ゴミ捨て場に捨てに行く。 あくる日、美由紀は、忍のために新しいおもちゃを買って帰宅した。すると、部屋にはまたあの人形が! 美由紀は、人形をある寺院に持っていき、供養を頼んだ。その帰り道、ふいに忍が寺の方を向いて手を振った。「京子ちゃんがね、“さよなら”って」。忍はそう美由紀に告げた。
- 注文の多い幽霊

- 脚本:清水達也
- 演出:鶴田法男
- 出演:宇佐見要 … 金子貴俊
- 宇佐見裕子 … 菊池麻衣子
要(金子)と裕子(菊池)は、とあるアパートで新婚生活を始めた。ある夜、裕子は、要が接待で遅くなったため、先にベッドに入った。すると、キッチンのある場所から物音が聞こえ、目を覚ます裕子。裕子が寝ぼけながらそちらに目をやると、冷蔵庫の前に人影があった。裕子は、要が帰ってきたのだと思い、再び眠りについた。
あくる朝、裕子が目を覚ますと、隣には要の姿があった。しかし、冷蔵庫の扉が開いており、中に入れてあったお茶が異常に減っていた。裕子は、要に文句を言うが、要は「冷蔵庫なんか開けていない」と反論した。しかも、彼が帰ってきたのは明け方近くだという。
その夜、眠っていた裕子は、髪の毛を引っ張られるような感覚で目を覚ました。すると、冷蔵庫の前にまたもや人影があった。が、隣を見ると要は寝ていた。裕子は、慌てて要を起こすが、彼はその話を信じようとはしなかった。
そんな折、裕子が友人の家に泊まりに行ったため、久しぶりにひとりの夜を過ごし、床につく要。が、ただならぬ気配を感じ、目を覚ますと、キッチンの方から人影が近づいてきた。金縛りにあったように動くことも出来ず、その人影を凝視する要。すると、その人影は突然、要の髪の毛を掴んだ。
あくる朝、戻ってきた裕子は、要から昨夜の話を聞いた。その時、冷蔵庫の中にあったお茶がからっぽであることに気づく裕子。要が全部飲んでしまったのだという。その時、裕子たちは気づいた。ふたりが起こされるのは、決まって冷蔵庫の中のお茶が切れている時だったことを…。
- 夜の再会

- 脚本:清水達也
- 演出:加藤裕将
- 出演:中田悦子 … 山本道子
- 中田章平 … 冨田翔
- 医師 … 遠藤たつお
深夜、車を走らせていた悦子(山本)は、遠くで鳴り響くバイクの音を聞き、他界した息子・章平(冨田)のことを思い出していた。章平はバイクが好きで、夜遅くに出かけては悦子を心配させていたのだ。
しかし、章平が死んだのはバイクの事故などではなく、急性白血病によるものだった。悦子はその時、病に苦しむ息子を目の前にしながら、何も出来ないでいた自分の無力さを嫌というほど味わっていた。
やがて悦子の車は、先が見えないほどの霧の中に包まれる。すると、悦子の車の後方から、バイクが近づいてきた。バイクの男は、次第にスピードを上げ、悦子の車を追い抜いていった。その時、悦子はそのバイクが章平と同じものであることに気づく。深い霧の中、バイクに先導されるように走っていく悦子の車。やがて霧が晴れ、道が見えてきた。ふと気づくと、バイクの姿はなくなっていた。が、しばらくすると、反対車線からあのバイクが現れ、運転していた男が悦子に手を振った。
悦子は、自分が章平を心配していたように、彼もまた、夜中に車を運転している自分のことを心配していたのを思い出していた。