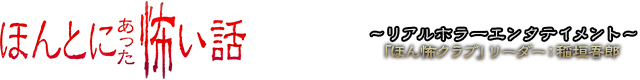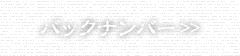第1シーズン #07
- 夜話の窓

- 脚本:清水達也
- 演出:大木綾子
- 出演:宮脇あや … 塚本雛子
- 冨田真帆 … 寉岡萌希
- 宮脇良子 … 小関可奈
小学四年生のあや(塚本)は、泊まりにきた友人の真帆(寉岡)と、夜遅くまで怖い話をして盛り上がった。母親の良子(小関)に注意されたあやは、寝る前にトイレに行こうと部屋を出た。すると、背後に何か気配を感じるあや。しかし、鏡に映った背後には何も見えなかった。部屋に戻ったあやは、「怖い話をしてると(幽霊が)集まってくるってほんとなのかな?」などと真帆に話しかけた。その時、窓のカーテンが開いていることに気づくあや。そして、真帆の様子がどこかおかしいことにも…。その瞬間、真帆がまるで男のような低い声で「本当だよ…」とつぶやいた。「だって、いまだってほら?」と言うと、突然、前のめりに倒れる真帆。そして、真帆の背後の窓には不気味な顔が浮かんでいて…。
- 近づく足音

- 脚本:田村孝裕
- 演出:三宅隆太
- 出演:麻里 … 香椎由宇
- 直樹 … 藤間宇宙
麻里(香椎)は、ノートを忘れた、という直樹(藤間)に付き合って、彼の通っている男子校にもぐり込んだ。なんとなく後ろめたかった麻里は、壁の下部にある戸をあけて顔を出し、見回りの用務員が通り過ぎたのを確認すると、教室を出ようとした。すると、廊下を赤いハイヒールを履いた女性が通り過ぎるのが見えた。不審に思ったふたりが下の戸から様子をうかがうと、ハイヒールを履いた下半身だけの女性の姿が廊下を歩いていた。驚きのあまり、「あっ!」と声を出してしまう麻里。すると、下半身だけの女は、向きを変えてこちらに向かってきた。麻里と直樹は、慌てて頭を引っ込めた。ほどなく、開いている戸から赤いハイヒールが見えた。とっさに戸を閉める麻里。足音が遠ざかったことを確認した麻里は、ふたたび戸を開いて廊下のようすをうかがった。やはり下半身だけの女性の姿はなかった。安心して、ふたりが立ち上がった瞬間、廊下に面した高窓から、今度は女性の上半身が!ジッとふたりを見つめるその顔は、この世のものとは思えなかった。教室内に、麻里と直樹の悲鳴が響いて…。
- 二時四十五分の泣き声

- 脚本:長津晴子
- 演出:鶴田法男
- 出演:小林真美 … 山口香緒里
- 小林康雄 … 福本伸一
- 小林奈々美 … 諸頭未優
東京郊外のマンションに引っ越したばかり真美(山口)は、1歳になった長男・翔太の泣き声を聞き、ベッドが置いてあるリビングにかけつけた。すると、翔太の顔には切り傷があり、爪には血がついていた。伸びた爪で顔を傷つけたのだろうと思い、翔太の爪を切る真美。ところがその数日後、再び翔太が顔に切り傷をつけ、泣き出すという騒ぎがあった。今度は、翔太の爪には血はついていなかった。様子がおかしいと思った真美は、時計に目をやり、躊躇しながらも夫の康雄(福本)に連絡する。仕事中だった康雄は、真美の動揺ぶりに困惑するが、「帰ったらゆっくり話そう」と言うと電話を切った。
医師に相談した真美は、手袋をした方がいい、と助言される。不安げな真美の表情に気づいた康雄は、「あまり考えすぎるな」と声をかけた。あくる日、再び翔太が泣き出した。翔太の顔には、生々しい傷がついていた。その時、ふと時計を見た真美は、翔太がいつも同じ時刻に泣き出すことに気づいた。翔太は、午後2時45分になると顔を傷つけて泣いていたのだ。
あくる日、真美は、友達の誕生日会に招かれた長女の奈々美(諸頭)をその家まで送り、慌てて家に戻ろうとしていた。翔太のことは康雄に任せていたが、心配で仕方なかったのだ。時計の針は、まもなく2時45分になろうとしていた。
真美が家につくと、すでに2時46分になっていた。一目散にベビーベッドのところに駆け込んだ真美は、叫び声を上げた。そこには、顔が真っ二つにさけた人形が横たわっていた。真美の話が気になっていた康雄が、翔太の代わりに人形を置いたのだった。それからまもなく、一家は引っ越した。が、何故2時45分に翔太が泣き出したのかは、いまでも謎のままだった。
- 二階が怖い

- 脚本:清水達也
- 演出:大木綾子
- 出演:草野亜矢子 … 碇由貴子
- 草野芳江 … 喜多道枝
喘息を患っていた亜矢子(碇)は、親の離婚や学校でのいじめをきっかけに、心因性の発作を起こすようになっていた。そんな亜矢子が、医師の勧めで田舎に住む祖母の家で暮らすことになったのは、彼女が中学生の時だった。
祖母の芳江(喜多)は、亜矢子を温かく迎えた。が、亜矢子は何もしゃべろうとはしなかった。そんなある日、芳江から探し物をしてほしいと頼まれた亜矢子は、物置代わりに使っているという2階の部屋で何者かの視線を感じる。その部屋には、布に覆われた鏡があった。そこにやってきた芳江は、鏡の前にいる亜矢子に気づき、鏡を覆っていた布を取った。ごく普通の鏡だった。亜矢子がその鏡に背を向けて部屋を出ようとすると、突然の発作が亜矢子を襲った。そのとき亜矢子は、鏡の中に白い着物を着た女性が写っていることに気づく。
その夜、トイレに立った亜矢子は、電話で話している芳江の声に気づいた。相手は、亜矢子の母親のようだった。「あの子があんな風にならなければ、あんたたちだって別れるなんて事にならなかったんじゃないのかい?」。芳江の言葉に、亜矢子は、いままで気づかないフリをしてきた現実と向き合わざるを得なくなっていた。両親に必要以上の負担をかけたのも、喘息を理由に自分の殻に閉じこもっていた私のせいなのだ、と…。その時、亜矢子は再び激しい発作に襲われた。直感的に、あの女性に会わなければ、と思った亜矢子は、2階の鏡の前に立った。すると、あの女性が再び鏡の中に現れた。ゆっくりと顔を上げる白い着物の女性。その顔は、自分とまったく同じだった。亜矢子は、とっさに近くにあるものをつかみ、鏡を叩き割った。その音に驚いて、芳江も2階に駆け上がってきた。亜矢子は、芳江にしがみつき、声を上げて泣いた。
数日後、亜矢子は芳江の家を後にした。それ以来、亜矢子の発作は回復の兆しをみせ、少しずつ友達もできるようになっていた。