『罪の壁 危険運転致死傷罪の23年』
2024.09.25更新
報道・情報
第33回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品(制作:福井テレビ)
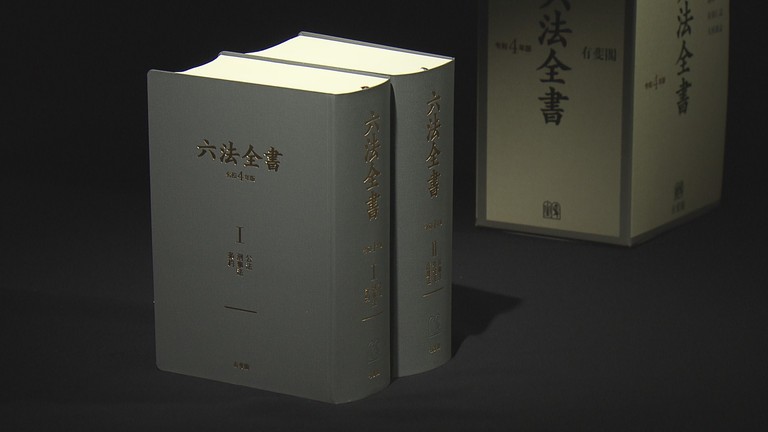
六法全書(罪の壁をイメージ)
『罪の壁 危険運転致死傷罪の23年』
<10月2日(水) 26時25分~27時25分>
危険運転致死傷罪23年
危険運転致死傷罪は、1999年に東名高速で発生した追突死傷事故がきっかけで制定された法律。2年にわたる被害者遺族の署名活動が実り、2001年に悲願ともいえる制定となった。ところが、一般感覚では「危険」と思われる速度や飲酒運転で人をあやめても、危険運転致死傷罪が適用されないケースが全国で相次ぎ遺族を苦しめている。4年前、福井市内で発生した事故の検証から、法の運用の不可解な現状に迫る。
飲酒運転や異常な速度でも危険運転と判断されず苦しむ被害者遺族たち。法の専門家の見解は・・・不可解な罪の壁に迫る
2020年11月27日深夜、福井市内で飲酒運転していた加害者が、パトカーの追跡を振り切ろうと住宅街に逃げ込み、時速105㎞まで加速し交差点に進入。優先道路を走行していた軽乗用車に激突し、軽乗用車の助手席に乗っていた18歳の女子大学生が死亡した。事故から約1年後に開かれた裁判で下されたのは、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪による懲役5年6カ月の判決。裁判長は「危険運転が認められないからと言って、危険な運転でなかったとは言えない」と異例の言葉を残して・・・。遺族は強く反発したが検察は控訴を断念。刑が確定した。
なぜ、裁判所は危険運転ではなく過失運転と判断したのか?なぜ、検察は控訴を断念したのか?

マスコミの取材に初めて答えてくれた、福井の事故の被害者・渡辺さん
同様の判決を受け苦しむ全国の被害者遺族を取材して見えてきたのは、危険運転致死傷罪の適用をめぐる法解釈の曖昧さだった。アルコールを大量に摂取していても、また住宅街の狭い道を時速100km以上で暴走していても「事故が発生する直前まで真っすぐ車を走行していれば、車を制御できている」と解釈され、危険運転致死傷罪が適用されないという判例が続いていた。
全国で市民感覚とずれた司法判断が繰り返されるのは、なぜか。

大分県の一般道を時速194キロで走行した車に衝突された被害者の車
そんな中、大分では一石を投じる動きが。遺族や支援者たちが「危険運転致死罪」での起訴を求めて約3万筆の署名を地検に提出。地検側も「過失運転致死罪」での起訴を取り下げ「危険運転致死罪」に訴因変更。検察が起訴内容を変えるという異例の事態に・・・。元最高検検事、交通犯罪に詳しい弁護士、さらには元法務省刑事局長などの専門家を訪ね、不可解な「壁」の正体に迫った。

危険運転致死傷罪制定時、法務省刑事局長だった古田佑紀氏にインタビュー
左から)武澤貴之記者、古田佑紀氏
ディレクター・武澤貴之(福井テレビ 報道番組部)
「3年前、福井地裁で傍聴していた私は懲役5年6カ月の判決に耳を疑いました。飲酒をして住宅街の狭い道を時速100km超で暴走し、人をあやめた加害者は“危険運転”ではなく“過失運転”として裁かれたのです。遺族は控訴を強く求めましたが、検察が控訴しませんでした。国の犯罪白書には、警察が“危険運転”で検挙しても、同罪で起訴されるのは約4割にとどまると紹介していました。この不可解な現状に強い違和感を抱き取材を始めました。取材を重ねていくと、危険運転罪を適用しにくい状況が全国で相次いでいました。取材を通して見えてきたのは、判例主義や法曹関係者の威信が作り出したともいえる“壁”でした。きっと法律は施行されて終わりではなく、“生活道具”のように私たちが使い勝手をよくするために“手入れ”をする必要があるのだと痛感しました。被害者を救うはずの司法に2次被害を受けるような現状は一刻も早く変えるべきです」
【番組概要】
- 第33回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『罪の壁 危険運転致死傷罪の23年』(制作:福井テレビ)
- ≪放送日時≫
- 10月2日(水) 26時25分~27時25分 ※関東ローカル
- ≪スタッフ≫
-
プロデューサー:横山康浩(福井テレビ)
ディレクター:武澤貴之(福井テレビ)
ディレクター:青園大亮(福井テレビ)
取材:菅野佑斗(福井テレビ)
カメラ・選曲:加藤英一(福井テレビ)
構成:塩野千景(フリー)
ナレーター:中村優子
法律監修:吉川奈奈(杉原・きっかわ法律事務所)
掲載情報は発行時のものです。放送日時や出演者等変更になる場合がありますので当日の番組表でご確認ください。