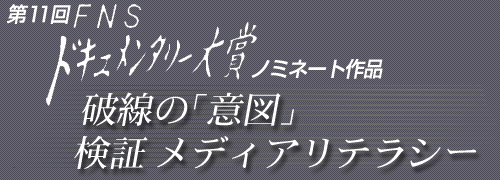 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
|
■ intoroduction 「情報とは何か」 「正しく伝えるとはどういうことなのか」 「情報を誰に伝えるのか」 「何のために伝えるのか」 今、メディアの在り方が問われている。過熱する取材合戦、相次ぐ報道被害、そして、いわゆる「やらせ」を巡る問題・・・。そういう状況の中、「個人情報保護法案」や「人権救済機関」設置構想、「青少年有害社会環境対策基本法案」など、メディアを規制しようという動きが出てきて、大きな議論を巻き起こしている。 「メディアリテラシー」という言葉がある。あふれ出る情報の洪水の中で「メディアを読み解く力」が視聴者にも求められている。9月17日(火)深夜27:13〜28:08放送の第11回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『破線の「意図」検証 メディアリテラシー』(制作:フジテレビ)では今、必要とされている「メディアリテラシー」をテーマにフジテレビの若きドキュメンタリスト二人が意欲的な作品に挑戦した。 今年の春、東京・八王子市立楢原中学校のディベート部の生徒たちが「メディアリテラシー」の向上を目的としたNHKと民放連の共同企画番組に参加した。課題は「我が街の未来」。彼らの作った3分間の番組が全国に放送された。シャキシャキした玉ねぎが特徴の八王子ラーメンのルーツをたどることにより見えてきたラーメン屋さんたちの熱意、そして、八王子の明るい未来。 中学生たちは初めての番組制作の中で、番組には「制作者の意図」があることを知った。自分たちが作る側になって初めてわかった「情報を切り取る」という行為。普段何気なく見ていたテレビが、作り手の意図によって構成され編集されているという事実。 この番組では、中学生たちの番組制作過程の徹底検証を中心に、メディアを読み解く上でもっとも重要である「メディアには送り手の意図が存在する」という事実を国内・海外の事例を交えながら考えていく。 ■ 番組内容
■ ディレクターからのコメント 西村陽次郎ディレクター(フジテレビ情報2部) 「5月に放送した『テレビの鉄人になろう!!〜つくるとわかる「TVの気持ち」〜』という番組の中で、八王子と愛知の中学生が3分間の番組作りに挑戦した姿をお伝えしました。中学生たちは情報を切り取る作業過程の中で、プロと変わらない悩みを持ち、壁を乗り越えていきました。彼らの行動の中で見えてきたものをもう一度、切り口を変えて取り上げてみたいなと思ったのです。中学生たちは“自分たちが伝えたいことを伝えるために、テレビは意図的に作ることができる。ナレーションや編集で全く印象の違うものができる。これまで何気なくテレビを見ていたのだけれど、ちょっと待てよ”と思ったと言います。私自身も作り手によって情報が切り取られているとことに改めて気づかされました。中学生たちがやっていることは、本質的に私たちプロと同じで、テクニックが違うだけなんですよね。情報の送り手は見せたいように見せたり、意図のある切り方ができるんですよね。八王子の新名物のラーメン店がいかにブームかを表現するために行列のシーンを重ねたり、遠くから来ている人たちだけのインタビューを使うこともできますから。プロである我々が無意識にやっていることが子供たちを通して見え、ディレクターとして新鮮な驚きを感じました」 吉野敏彦ディレクター(フジテレビ情報2部) 「切り取られた情報を我々は日々、受け取っているという自覚を持つべきだと思います。人間が表現する上で情報を切り取るというのは当たり前の行為ですが、自分が送り手になって初めて実感しました。カナダでは“メディアリテラシー教育”がしっかりされており、カナダ人はテレビをうのみにせずに、高校生でも、一歩ひいてみることさえできれば、テレビがいい情報ツールの一つだとわかっています。テレビをまずクリティカルにみるように教育されているんです。メディア不信の時代の中、情報の送り手であるテレビ局も情報を送り出す責任を自覚するとともに、受け手もメディアの意図やメッセージを読みとる力を身につけることが必要だと思います。語弊のある言い方かもしれませんが、日本の視聴者はテレビを見る姿勢が“うのみ”か“全否定”のどちらかに向かいがちです。日本ではメディアリテラシーの議論があまりなされていないのが現状ではないでしょうか。送り手と受け手が新しい関係を築くべきではないでしょうか。今回の番組では情報の送り手自らが“番組に込められた意図”をテーマに取り上げるというある種“タブー”とされてきたことに挑戦したいと思います」 |
※当番組の放送日時については各地方の放送局により異なりますのでお近くの放送局にてお問い合わせください。

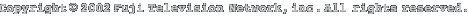
|