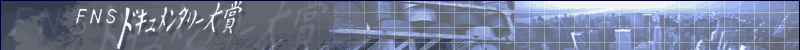2008.11.12
第17回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品
『戦後は終らない 〜硫黄島・日米元兵士たちの証言〜』
(制作:長野放送)
太平洋戦争最大の激戦地のひとつとなった硫黄島。
昭和20年3月…。この島の日本軍守備隊は、援軍や補給を断たれ、水も食料もない中、生還の望みもない戦いを最期まで続けていた。そして、一ヶ月間におよぶ日米の激しい戦いの末、約2万人の日本軍守備隊はほぼ全滅。その戦いは、今もなお多くの人々の心に、癒やすことのできない悲しみを刻んでいる。
番組は、この戦いで生き残った日米の元兵士たちの証言を元に「戦争」が勝ち負けを問わず「人間」にもたらす悲惨さ、むごさを描く。
<2008年11月15日(土)深夜2時5分〜3時放送>
太平洋戦争最大の激戦地のひとつとなった硫黄島。
昭和20年3月…。この島の日本軍守備隊は、援軍や補給を断たれ、水も食料もない中、生還の望みもない戦いを最期まで続けていた。そして、一ヶ月間におよぶ日米の激しい戦いの末、約2万人の日本軍守備隊はほぼ全滅。
その戦いは、今もなお多くの人々の心に、癒やすことのできない悲しみを刻んでいる。この戦いの日本軍指揮官だった男が、長野市松代町出身の栗林忠道陸軍中将だった。若い頃のアメリカ留学で、その国力を知り尽くしていた栗林はアメリカとの戦いに反対していたが、その思いが上層部に伝わることはなかった。死を覚悟して島に赴いた栗林は島の防御に独特な戦法を取った。地下トンネルを掘って敵を迎え撃つ準備を進めたのだ。こうした戦術はその後の日米の兵士たちの命に大きな影響を与えた。
当時、硫黄島戦から奇跡的に生き残った日本人兵士は守備隊のわずか5%にあたる、およそ1,000名。その中現在でも存命の兵士は20名前後と言われている。番組ではその20名の中から数名の兵士をピンポイントで探し出し、インタビューをお願いすべくスタートした。しかし、元兵士が誰で、どこに住んでいるのか全く当てが無い、探しようがない…、戦友名簿は個人情報保護の壁で教えてもらえない…、やっと探し当てても名簿に載っている方々すべてがお亡くなりになっていた…等々、年月の壁が取材の前に大きく立ちはだかった。こうした中、手探りで探しあてた5名の元兵士の皆さんに、番組の趣旨をお話しし、「後世に残す記録としたい」と取材をお願いすると「今しか残された時間は無いでしょう」と、快く取材に答えてくれた。中には、硫黄島で体験したことを戦後初めて口にした方もいた。
一方、元米軍兵士の皆さんにもインタビューをするため、私たちはアメリカを縦横断する2週間の取材も行った。日米相互の視点でひとつの戦争を見つめたかったのだ。
取材を終え、日米元兵士のインタビューを比較した時、元日本兵に特異的に強かった思いは「自分一人が生き残った負い目」であり「亡くなった戦友への負い目」だった。過酷な戦場を一緒に戦った戦友への思い…。それは日本人独特の感情なのかも知れない。
元日本兵5人の中に、弱冠17歳で戦いに加わり、奇跡的に生還した秋草鶴次さんがいた。秋草さんはこれまで現地での慰霊祭や遺骨収集を固く拒み続けてきた。その秋草さんが、取材中、初めて硫黄島を訪れる機会があった。彼はそこで何を回想し、何を思うのか…。そしてこの島で何があったのか…。
一方、取材班は小笠原村の計らいで硫黄島への上陸撮影が許された。そこは暑い暑い灼熱の島だった。日本兵が潜んだ壕内に入ると、サウナのような熱気で汗が滴り落ちる。草むらには朽ち果てた機関銃や砲台が今も残っていた。岩肌には猛烈な艦砲射撃の跡。そして遺骨収集のために掘り返された壕の入り口には古びた日本兵のヘルメットが数個、置かれていた…。取材を忘れ、おもわず手を合わせた瞬間だった。
番組は、秋草さんはじめ、生き残ったわずかな元兵士たちの証言を元に、勝ち負けを問わず、戦争が「人間」にもたらす悲惨さ、むごさを描く。
今年、硫黄島はアメリカから日本に返還されて40周年を迎えた。
制作担当者のコメント
長野放送 制作部長 春原晴久(当番組プロデューサー兼ディレクター)
硫黄島で戦った日米元兵士たちの思いは、番組の思いと同じです。それは「二度と人間を殺すことはできない、殺してはいけない」決意と「テレビやゲーム等でリセットすれば、人間を簡単に生き返らせることができる現代社会に対して、戦争は人間の命の尊さを教えてくれる。しかし、その戦争だけは二度と繰り返してはならない」というメッセージを視聴者に伝えることです。戦後生まれが国民の半数を超えた今、メディアが戦争の実相を伝えない限り、私たち一人一人がリアリティーある戦争の追体験・共有体験・疑似体験をすることはできません。そのうち「映像と音声」という強い武器を持つテレビに課せられた役割はとても大きいと思うのです。
日米元兵士にとっても、私たちメディアにとっても、そして、日本人にとっても、戦後はまだまだ終わっていないのです。いえ、終わらせてはいけないと思っています。
<番組概要>
◆番組タイトル
第17回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品
『戦後は終らない 〜硫黄島・日米元兵士たちの証言〜』
◆放送日時
2008年11月15日(土)深夜2時5分〜3時放送
◆スタッフ
- プロデューサー・ディレクター・構成
- 春原晴久(長野放送制作部長)
- ナレーター
- 寺瀬今日子(青二プロ)
- 撮影・編集
- 高橋 慶(長野放送管財)ほか
- MA
- 矢島善紀(長野トップ)
2008年11月12日発行「パブペパNo.08-317」 フジテレビ広報部
※掲載情報は発行時のものです。放送日時や出演者等変更になる場合がありますので当日の番組表でご確認ください。