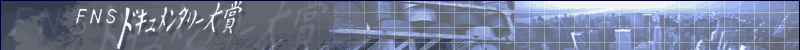2008.8.15
第17回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品
『“幸齢者”からのバトン
〜隠岐・看取りの家より〜』
(制作:山陰中央テレビ)
療養病床の大幅な削減。後期高齢者医療制度。私たちの身の回りでも介護が必要になったら施設へ、死の間際は病院まかせという現実がある。高齢者の終末期は幸せといえるのだろうか。柴田久美子さんはその原因を家族の喪失にみつけ、島根県隠岐・知夫里島に「なごみの里」を開設した。高齢者を最期まで介護する看取りの家だ。柴田さんの活動や波乱万丈の半生を通し、家族のつながり、そして世代間のつながりの大切さを問いかける。
<2008年8月16日(土)深夜2時35分〜3時30分放送>
【高齢化率43%の島】
島根県の隠岐諸島にある人口700人の小さな島、知夫里島(知夫村)。知夫で生まれた人は知夫で死んでいく。何百年も当たり前だったこの島の光景に近年変化が起きていた。介護が必要になったお年寄りの多くが島を離れ、本土の病院で最期を迎えるようになったのだ。高齢化率43%。財政状況の厳しい村は特別養護老人ホームを作る余裕はない。過疎高齢化の進んだ離島の現実だった。
【なごみの里開設】
「生まれ育った島で最期の日を迎えてもらいたい」2002年5月、NPO法人が運営する「なごみの里」が開設された。介護が必要なお年寄りに入所してもらい、臨終まで世話をする「看取りの家」だ。開設したのは島根県出雲市出身の柴田久美子さん(55)。これまでに5人のお年寄りが望みどおり島で人生の幕を下ろした。現在は90歳以上のお年寄り4人が、若い職員やボランティアたち15人のスタッフの介護を受けながら静かにのんびりと暮す。
収入は入所者からの食費と介護保険料、そして柴田さんの本の印税や講演料など月100万円ほどで、運営はギリギリ。活動に共鳴する全国800の団体や個人の支援者からの物品の寄付のみ。金銭は一切受け取らない。
お年寄りは食事も昼寝も時間に縛られることはなく自由。柴田さんはお母さん、そしてスタッフは家族、そしてお年寄り。まるで「家」の延長だ。そこには柴田さんの波乱万丈の半生からくるある思いがあった。
【大切なのは「家族」】
柴田さんの半生は波乱万丈だ。若き日は大手ハンバーガーチェーンの企業戦士。年収は数千万円もあったという。しかし夫と3人の子どもたちとの暮らしはうまくいかず、自殺未遂そして離婚と挫折を経験した。そこから見えてきたものは「家族の大切さ」。
大家族で育ち、臨終の際には自宅で家族が看取るのが当たり前だった柴田さん。その経験からその後、介護職に就いた。しかし本土の老人保健施設でみた高齢者の現実は…。入所者の意向にかかわらず、終末期には病院に送られ、死ぬ間際も病院まかせという現実。ここで感じたことはやはり「家族の大切さ」。家族とは一緒に住むだけの存在ではない、最期まで共に過ごし、送り送られという「命のバトンタッチ」をすることが大切なのだと。
【看取りの現場から】
後期高齢者医療制度、療養病床の削減、老老介護の現実…高齢化社会を迎え高齢者を取り巻く環境は急激に変化した。看取りの現場からみえる「今」を、静かに流れる島の情景を織り交ぜながら切り取っていく。
制作担当:澤田陽ディレクター(山陰中央テレビ)のコメント
日本海の小さな離島で、静かにゆっくりと時間が流れていくなごみの里。生き生きと暮らすお年寄りと介護をする若いスタッフ、そして柴田さんがいます。それは、かつての日本に当たり前にあった大家族の姿。そして、大家族にあったであろう、互いに学びあう何かを感じます。
もしかしたら、それは私たちが忘れてしまった姿かもしれません。離島からのメッセージはそのまま私たち自身への問いかけでもあるのです。
<番組概要>
◆番組タイトル
第17回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品
『“幸齢者”からのバトン 〜隠岐・看取りの家より〜』
◆放送日時
2008年8月16日(土)深夜2時35分〜3時30分
◆スタッフ
- プロデューサー
- 野津富士男(山陰中央テレビ)
- アシスタントプロデューサー
- 奥村亜希(山陰中央テレビ)
- ディレクター
- 澤田 陽(山陰中央テレビ)
- カメラ
- 野田 貴(フリー)
- CG
- 三島聡子(山陰中央テレビ)
- 構成
- 関 盛秀(フリー)
- 音響効果
- 相田恵美子(sound RING)
村松勝弘(スタジオ ヴェルト) - ナレーター
- 松尾佳子(シグマ・セブン)
2008年8月15日発行「パブペパNo.08-215」 フジテレビ広報部
※掲載情報は発行時のものです。放送日時や出演者等変更になる場合がありますので当日の番組表でご確認ください。