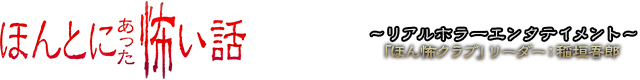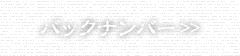第1シーズン #11
- 幽霊アパート

- 脚本:清水達也
- 演出:加藤裕将
- 出演:矢崎修一 … 山崎樹範
- 三崎景子 … 木内晶子
- 大家さん … 明日香まゆ美
修一(山崎)は、家賃の安さにひかれて古いアパートの一室に引っ越した。修一が、引っ越しを手伝ってくれた景子(木内)と見送ろうとすると、その時、天井あたりで「ガシャン」という妙な音が…。部屋が2階だったこともあり、修一も景子も、ネズミでもいるのか、とその時は全く気にも留めなかった。
ある夜、布団で寝ていた修一は、「ガシャン」という不気味な音で目を覚ます。誰かが部屋の中を歩いている音のようだった。その音が押し入れの中から聞こえてくるような気がした修一は、襖を開けてみるが、中には誰もいなかった。
数日後、修一のもとに景子が遊びにきた。景子が洗い物をしている時、修一は再びあの音を耳にした。やはり、音は押し入れの中から聞こえてくるようだった。修一は、押し入れを開けるが、やはり変わったところはない。が、何気なく押し入れの天井を見ると、そこには足跡が…。あくる日、修一は、大家(明日香)に事情を話すが、結局何の解決にもならなかったため、引っ越しを決意する。
その夜、家に帰る気になれなかった修一は、友人の家に向かっていた。すると、景子から電話が入った。景子は、修一のために料理を作ろうと思い、すでに彼のアパートの下にきているのだという。修一は、景子が部屋に入るのを止めようとしたが、何故か電話が切れてしまったため、慌ててアパートへと向かった。
修一が恐る恐る部屋に入ると、室内には誰もいなかった。とその時、修一の携帯電話が鳴った。景子からだった。「…ごめんね…修一の言うこと聞いておけばよかった…」と言う景子。そして再び電話は切れてしまう。
その瞬間、部屋の電気が消え、押し入れの中からあの足音が聞こえてきた。修一は、覚悟を決めて襖に手をかけ、一気に開けた。が、やはりそこには何もなかった。思わずその場にへたり込む修一。すると、押し入れの下段には落ち武者のような男の上半身があり…。
- 誰かが囁いている

- 脚本:長津晴子
- 演出:鶴田法男
- 出演:原田さやか … 上原美佐
- 鈴木透 … 山本康平
- 原田芳子 … 三谷侑未
- 60歳前半の女性 … 志水恵実子
その年、さやか(上原)の周りでは、よくない出来事ばかり続いていた。母親の芳子(三谷)は、先週から原因不明の病気で入院していた。母を見舞った後、病院を出たさやかは、突然耳鳴りに襲われる。そして、その音に混じって女性の囁くような声が…。このころ、さやかは度々起こる耳鳴りに苦しんでいたのだ。すると、さやかの携帯に父親から連絡が入った。階段から落ちて複雑骨折したのだという。
その夜、さやかは恋人の透(山本)と電話で話をしていた。が、電話を切った途端、また耳鳴りが…。女性の囁く声も以前よりはっきりと聞こえていた。
あくる日、さやかは伯母の家が火事で全焼したという知らせを受ける。ちょうどそこに、透がやってきた。その際、透は、知り合いにお祓いをしてもらったらどうか、とさやかに持ちかける。
深夜、再び耳鳴りに襲われたさやかは、透に電話し、知り合いを紹介してもらうことにした。あくる日、さやかがその人物に会うためにタクシーに乗ると、隣には初老の女性(志水)の姿が…。それを見たさやかは、直感的に、祖父母の墓に行かなければ、と思い、とある墓地へと向かった。
さやかは、母親から、祖母と祖父の折り合いが悪かったことを聞かされていた。祖母は、祖父とは別の墓に入りたい、と切望していたのだという。さやかがその墓の前に立つと、墓石には不気味なひびが入っていた。その後、祖母の願いどおり墓を移すと、母親の病気は快方に向かい、さやかの耳鳴りもおさまったという。
- 訪う人々

- 脚本:小川智子
- 演出:鶴田法男
- 出演:篠崎清美 … 雛形あきこ
- 篠崎敬介 … 武井証
- 母 … 南風佳子
- 幸田 … リットン藤原(リットン調査団)
- 安井 … リットン水野(リットン調査団)
- パート主婦 … 萩原利映
- 保育士 … 江澤規子
- 父 … 田山涼成
清美(雛形)は、18歳で結婚したものの、夫とは1年ほどで別れ、5歳になるひとり息子・敬介(武井)を抱えながら、昼は弁当店、夜はスナックで働いていた。ある夜、スナックでサラリーマンの幸田(藤原)や安井(水野)の相手をしていた清美は、奥の席に中年の男女が座っていることに気づく。それは、死んだはずの父(田山)と母(南風)だった。
それから数日後、仕事を終えて、酔って帰ってきた清美は、「お前に子どもなんか育てられるのか!?」という父の声を聞く。幼いころに母を失った清美は、父とふたりきりの生活の窮屈さからすさんだ生活を送っていた。聞こえたのは、その当時、妊娠した清美に向かって父が言った言葉だった。
そんな折、弁当店で働く清美のもとに、保育園から連絡が入った。敬介が熱を出したのだという。清美は、父と母はこんな自分のことを怒って現れたのではないか、と思い始めていた。
清美は、敬介の具合を心配しながらも、夜の仕事に出かけていった。が、やはり敬介のことが気になって、仕事が手につかない。両親が敬介を連れて行こうとしているのではないか、という不安に襲われた清美は、仕事を終えると急ぎ足で帰宅した。清美が部屋に入ると、眠っている敬介の枕元には父と母の姿があった。両親に向かって、敬介を連れて行かないで、と哀願する清美。すると、ふたりはゆっくりと清美の方に顔を向けた。慈愛と悲しみをたたえたふたりの顔を見た清美は、ようやくすべてを悟った。ふたりは、清美のことを心配していたのだ。泣きながら、父と母に謝る清美。するとふたりは、微笑みをうかべてゆっくりとうなずき、姿を消した。
その時、敬介が目を覚ました。その手には、清美が家を出たときに捨ててしまったお守りが握られていた…。