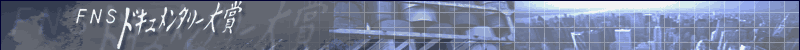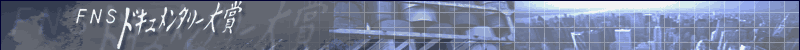東北大学病院の前にある手向花がある。
1999年、女子高生がこの場所で交通事故に遭ったが、目の前の大病院に運ばれることなく、
別の病院に搬送され、3時間後に亡くなった。以来、花は絶えることなく手向けられてきた。
女子高生はなぜ大学病院に運ばれなかったのか、東北大病院の救急医療はどう変わろうとしているのか。
第13回ドキュメンタリー大賞ノミネート作品
『手向花の伝言〜東北大学病院と救急医療〜』
(制作:仙台放送)
<2004年10月31日(日)4時〜4時55分放送>
【10月30日(土)28時〜28時55分放送】
|
|
東北大学病院の前にある手向花がある。1999年、女子高生がこの場所で交通事故に遭ったが、目の前の大病院に運ばれることなく、別の病院に搬送され、3時間後に亡くなった。以来、花は絶えることなく手向けられてきた。そして、この花が大学病院の医療を変え始めた。
女子高生はなぜ大学病院に運ばれなかったのか、東北大病院の救急医療はどう変わろうとしているのか。10月31日放送の第13回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『手向花の伝言〜東北大学病院と救急医療〜』(仙台放送)<4時〜4時55分>では「手向花の伝言」をつづってゆく。
(内容)
路傍に手向けられた花の背後には、多くのドラマがある。
東北大学病院の入り口に、絶えることなく手向けられた花にも…。
その花をきっかけに大学病院の医療が変わろうとしている。
この花にまつわる事故を教訓に「救命救急の碑」を建立し、救急医療の充実に乗り出すというのである。その事故とは5年前にさかのぼる。
1999年6月23日午後6時30分ごろ、一人の女子高生が自転車で東北大学病院前の横断歩道を渡ろうとしたところ、前から来た歩行者とぶつかり、車道側に転倒、走りかかった市バスにひかれてしまった。出血はなかったが女子高生の腰のあたりにはくっきりとタイヤ痕がついていた。救急車はその3分後に到着した。
東北大学病院は医師数1000人、ベッド数1300、最先端医療を担う日本有数の大病院である。居合わせた誰もが目の前の大学病院に運ばれるものと思った。不幸中の幸いというべきか。しかし、女子高生を乗せた救急車は大学病院に背を向け、別の病院へ向かった。
そして、彼女は事故から3時間後、息を引き取った。16歳だった。大学病院前の手向花は以来、絶えることなくずっと供えられ続けてきた。
当然誰もが持つ疑問、『なぜ彼女は目の前の大学病院に運ばれなかったのか?』
そこには大学病院の驚くべき医療の実態と同時に、一方で救急医療の充実に取り組む真摯な医師たちの姿があった。
倒れた人に手を差し伸べる、このことは医の原点である。このために医師は学び、働いているはずだ。それゆえに医師という仕事はとても重要な役割を社会的にも担っている。
しかし、現実の大学病院の医師たちの多くは、目の前で苦しむ人を診ることが出来ないのだという。大学病院の患者の70%以上は、他の医療機関からの紹介患者、端的に言えば
すでに診断がついている患者であり、なおかつ大学病院の医師たちの専門分野の研究対象にふさわしい珍しい病気の患者なのである。
苦しいと訴える目の前の患者は、どこが悪いのか診断しなければならない。それは全身をよく診て判断しなければならない。しかし臓器別、疾患別に細分化した大学病院の医師たちは、専門分野を診ることができても、全身を診て判断する能力が退化してしまっているのである。それゆえ、大学病院での救急医療は、これまで、ほとんどまともに行われてこなかったのだ。
実は女子高生の事故の時、たった一人だけ、救助に駆けつけた大学病院の医師がいた。
救急部の医師であった。彼は彼女を診て、骨盤骨折の疑いが強いと診断した。骨盤骨折は骨折の中ではもっとも致死的な病態である。腹部の動脈が破裂し、体内で大出血が起きている恐れがあるのだ。一刻を争う事態である。その救急部の医師は大学病院への搬送は無理と判断し、別の病院への搬送を選んだ。「もし彼女を連れて行っても、なぜこんな患者を連れてきたのかと非難の誹りを浴びることになっただろう」とその医師は答えている。つまり、そうした救急患者を診る体制がまったく皆無だったのだ。
インタビューで山田章吾病院長は、大学病院は研究志向で、これまで救急についてなんら対策をとってこなかったことを明らかにし、2年後の救命救急センター立ち上げなど、救急医療充実の病院の方針について異議や反対の声が少なくないと答えている。救急とはまさに第一線の診療であるが、そうした診療に力を入れると、それぞれの研究の時間が割かれてしまうというのが多くの反対意見の論拠のようだ。
そうした研究志向の医師たちがいる一方で、東北大学病院には、救急医療の充実に取り組む医師たちがわずかながらいる。救急部の4人の医師たちである。東北大学病院には19年前に救急部はできたのだが、実態は学生教育担当部門で、診療はしてこなかった。しかし6年前、篠沢洋太郎教授を慶応大学救急部から招いたことにより、慶応大から救急医がやってくるようになり、少しずつ救急建て直しの動きが強まり始めた。それまで昼間はほとんど使われていなかった救急処置室を開放、またまったくなかった救急部のベッドを4床確保、さらに救急部の医師には使用が認められなかったカルテを獲得した。こうして、改革の内容を列挙するだけでも、それまでがいかにひどい状況だったかがうかがい知れる。
そして今年、東北大学病院は現在建設中の病棟の1階に大規模な救命救急センターを作ることを決めた。ベッド数20、医師28人、看護師56人、CTや手術室も完備した、本格的な救急医療の拠点である。
取材を始めた3月1日から4ヶ月間、小さなカメラを抱え、ほとんど居つく形で大学病院の医療、とくに救急医療の実態を見つめ、記録してきた。救急の取材に予定は立てられないからだ。そうした中で全身の96%をやけどした4歳の子どもが運ばれた。風呂の湯加減を見に行って誤って熱い湯船に落ちてしまったのである。救命の可能性は限りなくゼロに近かったが、救急医たちは形成外科、麻酔科などの専門科と連携し、命をつなぐ治療に乗り出した。その中心になったのが救急部の田熊清継医師である。
田熊医師は去年、慶応大救急部から東北大にやってきたばかりの医師で、やけど治療のスペシャリストでもある。この治療では東北大で初めて死体皮膚を使った皮膚移植手術が行われた。全身やけどのため、自分の皮膚が使えないからだ。手術は形成外科医が担当、3度行われ、ほぼ全身に移植された。拒絶反応もなく手術は成功した。しかしそれだけでは重度のやけど患者は救えない、多くのやけど患者が細菌感染によって命を落とすのだ。救急医たちは泊り込みで治療にあたった。その甲斐あって、患者は奇跡的に回復した。救命が成功したのである。
田熊医師はいう。
「命を失う危険性の高い患者の命が助かることはみんなの心をよくする」と。
女子高生が命を落とした現場には、その見えないが確実にある命をつなぐために、同級生や家族、事故のことを知った人々が絶えることなく花を手向けている。そして、その営みそのものが命をつなぐ救急医療と重なるように思われた。
岩田弘史ディレクターのコメント
私が東北大学病院の入り口に、絶えることなく手向けられた花に目を留めたことから、この取材は始まった。ありふれた日常の隙間に、ぽっかりできた時間の止まった空間、手向花のあるそこだけがそんなふうに見えた。
なにかがあると直感した私は、知り合いの大学病院の関係者から、その花をきっかけに
大学病院の医療を変えようとしている動きがあることを聞いた。そして、“なぜ女子高校生は大学病院に運ばれなかったのか?”という素朴な疑問。
この番組は、手向けの花に導かれ、その花ごしに、大学病院の医療を見つめた4ヶ月の記録であり、手向花の伝言でもある、と願う。
そして、真剣に命と向き合う医師たちの姿に心底敬服する。
| エグゼクティブプロデューサー |
: |
山並秀昭 |
| プロデューサー |
: |
大沼浩一 |
| ディレクター・構成・撮影・取材・編集 |
: |
岩田弘史 |
| ナレーター |
: |
丹野久美子(劇団IQ150主宰) |
| 撮影 |
: |
渡辺勝見 |
| 音声 |
: |
小峰義央 |
| 編集 |
: |
上池隆宏 |
2004年10月28日発行「パブペパNo.04-343」 フジテレビ広報部
|