CLAMP TALK Vol.42
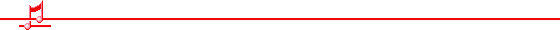
NAKAI in talking with RYUDOH UZAKI.
- 宇崎:
- うん。だから、一生バンドマンでいたいわけね。
- 中居:
- ああ、やっぱりでも、最後に辿り着くところはバンドマ
ンであると。
- 宇崎:
- うん、そうだね。
- 中居:
- ふーん。
- 宇崎:
- だって、楽しいんだもん。
- 中居:
- 昔はもちろんやっぱり、闘争心を剥き出しにしてたん
じゃないですか?
- 宇崎:
- うん、もう剥き出しにしてたと思うね。
- 中居:
- やっぱ、それを経て、経験を経て、キャリアを積んで、
今の宇崎さんだから。で、あるところで、あるいい評価を得たうえでの宇崎さん
であるから言えることであったり考えられることじゃないかと思うんですけど
ね。
- 宇崎:
- だから、評価はもちろん、いろんな評価をいただいてる
けど、支えてくれた人たちがいるわけでね。そういう人たちがいて僕がいる
なぁってね、もうそれはね、それに気付くのがすごく遅かったわけ。「俺がいる
からみんな食えてるんだろう」とかさ、ね。だって、俺たちステージ立った時
に、売れた時にね、売れない時期もあったから。売れない時は、なぜ売れないの
か不思議でしょうがなかったのね、自分の中で。ビアガーデンでやってることも
あってね、2年ぐらい、ね。そういうダウンタウン時代なんてさ、「何で売れねぇ
のかなぁ?」って思ってたんだ。で、売れたらさ、「ほら見ろ。当たり前じゃねぇ
か」って思ったから、もう天狗になってたわけで。で、客が満杯になってさ、
「ギャァー!!」とかいってるとさ、「うるせぇなぁ」とかさ。ステージの上から
「騒ぐんじゃねぇよ」なんてね。それ普通さ、感謝じゃない。本当は感謝するべ
きことだよね。俺たちはもちろんカッコいいよ。ただ、じゃあ、SMAPに置き換え
た時ね、みんなが並んだら「ギャァーッ!!」って言ってるのはさ、その個々に対
してファンの人たちがいて、そのチームに対して「ワァーッ」と声援を送ってる
やつらに対してさ、やっぱり「どうもありがとう」って気持ちだよね、素直に
どっかきっと。で、それと同時に、やっぱりどっかプライドもあったりね、「俺
がいるから盛り上がってんだろ」とかっていうのもあるけどさ、俺はもう、それ
しかなかったからさ。だから、客は集まって当然だし。
- 中居:
- 当時の宇崎さんは嫌な奴ですよねぇ。
- 宇崎:
- そう、その時の俺はね、最低だと思うよ。
- 中居:
- 嫌な奴ですねぇ。
- 宇崎:
- だって、俺だってさ、本当にさ、あの、売れてから歌番
組いっぱいあったでしょ、その頃。
- 中居:
- ええ、ええ。
- 宇崎:
- でさ、「向こうが挨拶するまですんなよ」って言ってた
んだよ。
- 中居:
- ……そんなの、ヤクザの出入りじゃないんですからね。
- 宇崎:
- 本当に。メンバーたちに、ね。うん、俺たちはキャリア
は少ないけど、その時まだだって、デビューとか3年目ぐらいだよね。で、キャリ
アからいけば森進一さんとか、五木ひろしさんとか、そういう人たちのがぜんぜ
んね、歳は下でも上だよね。「挨拶すんなよ。向こうからするまで」って。
- 中居:
- 向こうが頭下げるまで、こっちすんじゃないよと。
- 宇崎:
- そんなのくだらないエネルギーだよね。でも、そうやっ
てないと自信持てなかったんだよ。要するに、歌がウマいわけじゃない、演奏が
ウマいわけじゃない、何がいいわけじゃねぇよっていうさ、何か拠り所ないわけ
さ。その時あったのは、歌が売れたっていう。でも、これだって2発目は売れるの
か3発目も売れるのか、何の自信もないわけ。裏付けはね。そうすると、なんか
さ、どっかで突っ張ってねぇと、「ちわーっス」ってなっちゃうような気がする
のね、自分は。いわゆる芸能界って中で。「どうも、こんちわス」、あっちも
こっちも、右も左も「こんにちは」みたいになっちゃうと、俺たちなんか勝てな
いなって。みんなさ、芸があるんだよ。
- 中居:
- まあ、それは歌唱力であったり。
- 宇崎:
- そうでしょ。踊れるとかさ、喋りがウマいとかさ。
- 中居:
- ええ、ええ。
- 宇崎:
- なんか必ず芸があるの。僕が自信持てたのは、「なんか
面白い曲は書けるだろう」っていう自信は多少あったかもしんないし、でも、バ
ンド全体の音楽性とかさ、ルックスとかね、歌とかってのはさ、何にも自信がな
かったんだね、そういう意味の。
- 中居:
- それでも、あっちが頭下げるまでは。それ、何だったん
でしょうかね?「ナメられたくない」ってのがあったんですかね?それはね。
- 宇崎:
- あ、そうそう、そうそう。
- 中居:
- ね。
- 宇崎:
- うん。わけもなく「ナメられねぇぞ」っていうね。で、
訳はあるわけだよ、だからさ。「歌ヘタだな」って。例えばね、僕らが歌ってる
とこを後ろで見てる人たちはさ、モニターで聴いてたら「歌、ウマくねぇなぁ、
宇崎は」って思われることは思われちゃうわけだから、ね。勝手に評価できるわ
けだから。でも、それでもってなんか態度変えられちゃうのは嫌だなとかって
思ったし。だから要は、自分に自信がないからそういうことやって。やっぱり自
分の目がもうちょっと鋭くていい男だったら、サングラスしてないだろうし。
ね、そういうのあるわけよ。
- 中居:
- へぇー。え?でも、いつその、まあ先ほどね、感謝の気
持ちっておっしゃったじゃないですか、ね。感謝の気持ちは、最初に売れた頃に
はなかったって。「俺がいるからおまえら」逆に「おまえら俺に感謝しろよ」っ
ていう立場だったんですよ。
- 宇崎:
- それはね、やっぱりね、ドツボにはまったからだね。
- 中居:
- ドツボにはまった?
- 宇崎:
- だから、25年やったんだよね。それでさ、ダウンタウン
て8年半ぐらいやってたんだよね。で、後半のね、1年半ね、今まで自分たちの
ヒット曲っていうのがいくつかあって、みんなに愛された曲がたくさんあったん
だよ。それを一回ね、しまっちゃおうって宣言しちゃったわけ。「やんねぇ
よ」って言ったの。これ、傲慢だよな。
- 中居:
- なぜ?何がそう?
- 宇崎:
- うーん?
- 中居:
- それはやっぱり、その時代の自分がカッコいいって思っ
たんですかね?何が?
- 宇崎:
- あのね、うーん?まあ、だから、あ
る種の自分に対する挑戦でもあったのね。だから、いっぱい作品を持ってる、
ヒット曲を持ってるってことは、すごい財産だ。だけど、俺はやっぱり、その時
は若気の至りだと思うけどね、例えば僕はプレスリーが好きだったりビートルズ
が好きだったり、いろんなバンドが、いろんなアーティストが好きだ。と、ぜん
ぜん違う方向性出しても「でも好きなんだよ」っていうことに変わりはない。
「どの歌を歌ったから好き」じゃなくて、歌にくっ付いてるんじゃなくて、「俺
はその人にくっ付いてんだ」って自分は思ってた。だから、ヒット曲捨てても、
俺たちがとんでもない歌を歌っても、ファンは来るってタカくくってたわけ。
- 中居:
- ああ。
- 宇崎:
- それの挑戦だった。そしたら1万人コンサートに20人し
か来なかったりとかいうことがあって。
- 中居:
- ……カッコ悪いですねぇ。
- 宇崎:
- 最低だよな。「あら?いないわ」って。で、後ろにタレ
幕「1万人コンサート」って書いてあんだ。入れる会場なの、1万人ぐらい。それ
が20人しかいないんだ。俺、ビール配っちゃった、お客さんに。「すいません、
飲んで下さい」って。
- 中居:
- それ見た時、もうショックだったでしょ。
- 宇崎:
- まあ、でも、これは自分で選んでね、自分でやっちゃっ
た傲慢なやり口だったから、しょうがねぇやって思った。で、そこで20人来てく
れた人にものすごく感謝したわけ。これがあと100人いたり、200人いたりってい
うことじゃん。それが積もり積もって1万人になっていくわけだし、積もり積もっ
て何十万枚のレコードが売れるわけだから。だから、僕はたくさん今まで25年の
あいだに、たくさんファンの人を裏切ってるな、と今でも思う。だから、今は
ファンを裏切らないということではなく、奇麗な裏切り方かな。
- 中居:
- え?どういうことです?奇麗な裏切り?裏切りは、奇麗な
裏切り方っていいますと?
- 宇崎:
- なんか「こうきたのか!?ウワァーッ!」ってみんなが膝
を打ってくれるようなさ、そういう。
- 中居:
- 期待に応えた意外性っていのかな?
- 宇崎:
- だから、期待っていうのはさ、不特定多数でさ、最大公
約数、ね。ただじゃあ、「宇崎さんに歌って欲しい歌は、こういう歌」っていう
のをアンケートとったとするじゃん。すっと大体こういうのが出ると、「バラー
ド」。で、出せばある程度の人が買ってくれるかもしれない。「バラードをみん
な望んでんのか、……やめよう」っていって、で、「とんでもない歌を歌ったら
面白いじゃん」っていうふうに意識が変わるっていうことかな、向こう側の。そ
ういうものを作っていく楽しみっていうのは、作家としての自分の中にあるわけ
だよね。そうやって、なんかだから、そういう裏切り方だったらまだいいけど。
例えば、やっぱりダウンタウンてのは、ブルースだロックンロールだっていう。
白いつなぎ着てさ、バァーン!てやって。裏街の話、路地裏の話をテーマにして
さ、で「俺ぁよぉ」っていうような歌を歌ってたわけ。そして、次に作ったバン
ドは竜童組。
- 中居:
- はいはい、はい。
- 宇崎:
- そうすっと和太鼓叩いちゃう。と、「ええ?ロックン
ロールじゃないの?」って思ってた奴は、「なんであれがドンツク叩くんだよ、こ
の野郎!」っつって離れていく人がいた。だけど、新しいファンが付く。「面白
い。なんだかこのグループ、お祭バンドみたい」とかいって。そして、それもま
た6年やって、また店終いしちゃう。それで次作ったグループは井上さんとシンプ
ルなロックね。やると、「ドンツクどこ行っちゃったの?」っいう話になるわけで
しょ。
- 中居:
- ええ、ええ。ある意味では、すごい挑戦ていうか。で
も、ある意味ではすごく決意がいることだと思いますよ。それを持続することだ
けがいいものなのか、切り替えていくのがいいものなのか、正解はないと思うん
ですけども。
- 宇崎:
- うん、でも、飽きちゃうんだよ。
- 中居:
- あ、宇崎さん本人がもう?
- 宇崎:
- うん。
- 中居:
- 今まで自分のやってて、先に飽きがきちゃうんですか?
- 宇崎:
- うん、そうそう。飽きちゃったら、そのまま続けていく
のは失礼だなと。そのチームの人たちに対して。で、なんか「休もうかな」とか
さ。
- 中居:
- でも、自分の作ってきた作品、音楽には後悔は?
- 宇崎:
- ないない。
- 中居:
- それがいいですね。後悔ないから多分いえると思うんで
すよ。
- 宇崎:
- うん。で、やっぱ財産だし、そんだけの曲はね。だか
ら、支えてくれた人たちは。だから今度は、出来上がった曲だってね、みんなが
育ててくれたわけだから、作って自分で育てるっていうことは出来ないわけね、
曲はね。やっぱりだから、やっと、やっとここ本当に10年ぐらいかな。一生懸命
なんかひたむきに作品を書いて、ひたむきにバンドをやり続けていくのが自分の
本望っていうかね。だから、そのためだったら、それをよくするために、もしも
お誘いがあって映画の話やドラマの話があって、自分がやれそうな「やれっか
な?」って。それも半歩ぐらい先いけることね。だったらある種の挑戦だし、そこ
で栄養もらえるかもしんないなぁとかね。そんなつもりで引き受けてるから。
きっと音楽捨て俳優になっちゃうとかってことはないからなぁと思って。
- 中居:
- 常にベースは音楽、バンドマンであり。で、いろんな寄
り道をして。
- 宇崎:
- そうだね。
- 中居:
- いろんな道草をして。で、得たものを逆に自分にとって
は「これは違うんなじゃないか?」っていうものをやっぱり、いいものだけを吸収
して。自分にとって、自分の基準で悪いものは捨てて。で、バンドに帰って。一
つ成長してバンドに帰ってくるわけですよね。
- 宇崎:
- うん。そうなればいいなと思ってるけど、成長してるか
どうかはわかんねえんだよ。
うん。だって僕、歌い手になろうって思ってなかったもん。だから、何
になるかなんて、本人が望んでいたり望んでいなかったりって、望んでいてもな
れない人もいれば、望んでないのにその場でなっちゃう人もいるでしょ。僕は作
曲家にはなりたいなぁって思ってたけど、学生時代から曲書いてて。マネー
ジャー時代も曲書いてて。で、人の営業ぜんぜん取れなくて。でも、それで曲は
書いてたんだけど、「自分は歌は、これを自分で歌うだろう」と。例えば井上陽
水さんとか吉田拓郎さんみたいに、シンガーソングライターになれると思ってな
かったから。「曲を提供してくだけだろう」と。「いつかは作曲家になりたい」
と思ってた。
- 中居:
- 作曲家として?ああ、はいはい。
- 宇崎:
- そしたらある日、「おまえレコード出さないか?」って
いう人出てきたの。レコード会社が。「ウウーッ!?」って。
- 中居:
- え?それは宇崎さんの声とか歌ってる姿ってのも?
- 宇崎:
- 自分でだからオリジナルを歌ってた時があるのね。あ
る、ちっちゃいコンサートで歌った、2曲ぐらい。そしたらパパパッてきて、
「レコード出そうよ」
「ええ!?」って。
「こういう顔でいいの?こういう声で」
「いいじゃん」
「あ、本当に?」
そして、「いや、僕は歌わない」ってどっかで思って
たわけじゃん、ずっと。で、「待てよ?この顔で、この声でいいって?周りにこ
んなルックスの悪くて声も悪い奴いるかな?」って思ったら「あ、泉谷しげるがい
るわ」と思って。「あ、あいつが歌ってんだったらいいだろう」。泉谷がいたか
ら、僕、デビューできたんだ。
- 中居:
- ああ、泉谷さんは宇崎さんにとって、もう計り知れない
自信になったわけですね。
- 宇崎:
- 恩人だよね、あいつは。
- 中居:
- へぇー。
[CONTENTS] |
[CLAMP] |
[FACTORY] |
[REPRODUCT] |
[CIRCUS] |
[INFO]
[TKMC TOP PAGE]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.